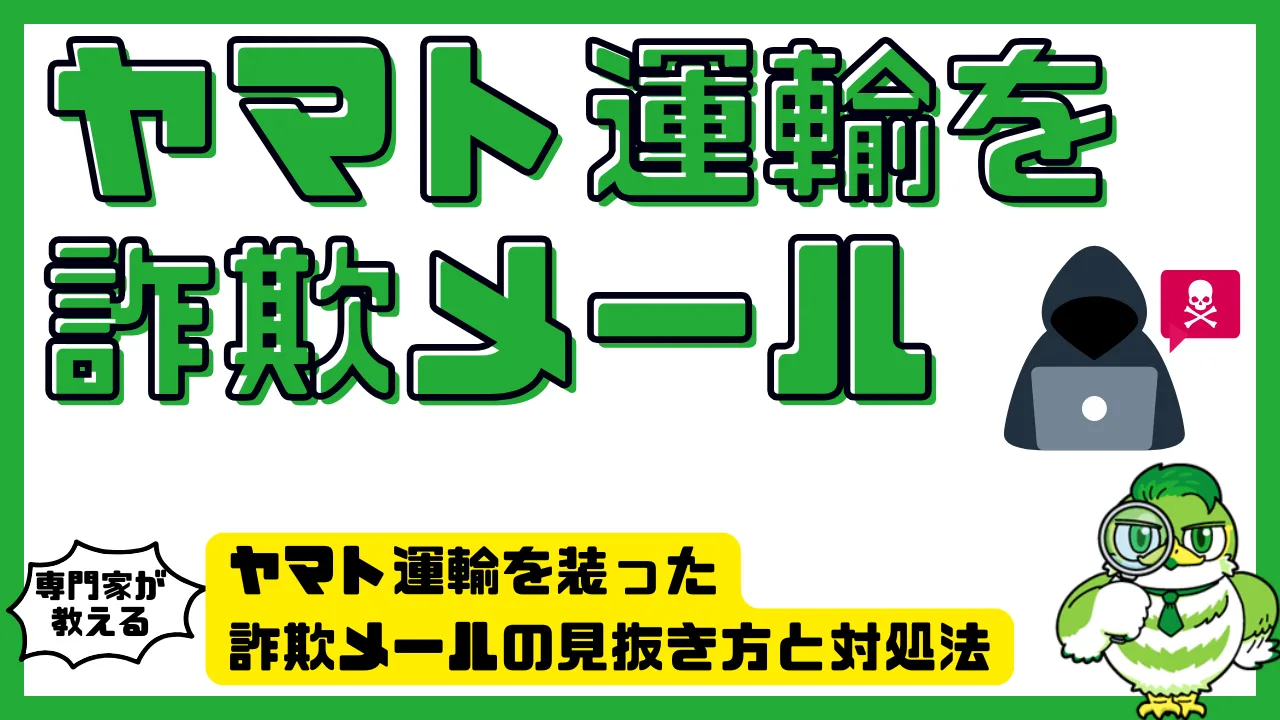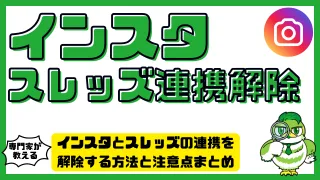本ページはプロモーションが含まれています。
ヤマト運輸を装った詐欺メールとは
ヤマト運輸を装った詐欺メールは、実在する宅配サービスの信頼を悪用し、個人情報の窃取や不正アクセスを狙う手口です。メールやSMSで届く通知を装い、「荷物の配達に失敗した」「配送先住所に誤りがある」などの不安をあおる文言が多く使われています。
詐欺メールがヤマト運輸を装う理由は、利用者数の多さと、荷物通知という日常的な連絡手段への信頼があるからです。受取人が違和感を覚えにくく、反射的にリンクを開いてしまうケースが少なくありません。
最近の手口としては、以下のような特徴が見られます。
- 宛名がメールアドレスになっており、個人名の記載がない
- メール内に不自然な日本語や誤字脱字がある
- QRコードやリンク付きで、再配達や情報更新を促す
- 伝票番号が存在しているように見えるが、公式サイトで確認すると動きが不自然
- 「再配達の手続きはこちら」として、偽サイトへ誘導される
また、公式と似たメールアドレス(例:@kuronekoyamato.co.jp)を装ってくるケースもあり、送信元のドメインだけで信頼するのは危険です。
ヤマト運輸では、公式メール以外からの連絡に注意喚起を行っており、特にSMSでの連絡は行っていないと明言しています。そのため、SMSで届いた通知は原則削除し、公式アプリやマイページを使って荷物情報を確認することが安全です。

詐欺メールの多くは一見すると本物と見分けがつかないほど巧妙ですが、少しでも違和感を覚えたら、記載されたリンクやQRコードには絶対にアクセスせず、ヤマト運輸の公式チャネルで真偽を確認することが重要です。
実際に届く詐欺メールの文面例
ヤマト運輸を装った詐欺メールは、見た目が本物そっくりに作られており、内容も巧妙です。特に件名・本文・差出人情報・リンク先などに巧みに偽装が施されているため、少しの違和感でも注意が必要です。ここでは実際に確認された詐欺メールの文面例と特徴的なフレーズを紹介します。
よく使われる件名の例
- 配送先住所が誤っています。再配達の手続きをお願いします
- 荷物のお届けに失敗しました。ご確認ください
- お荷物が保留されています。詳細はこちら
- 配送情報に不備があり、配達できませんでした
- 【ヤマト運輸】再配達のご依頼について
これらの件名はいずれも「急ぎ対応が必要」と思わせる内容で、不安を煽る文言が多く使われています。
本文の文面例(抜粋)
お客様のお荷物につきまして、配送先の情報に誤りがあったため、現在配送が保留されております。
以下のリンクより、正しい受取情報の入力をお願いいたします。https://yamato○○○.com/redirect/xxxxx
※本メールは自動送信されています。ご返信いただいてもお答えできません。
ヤマト運輸よりご連絡です。
配達員がお届けに伺いましたが、ご不在でした。再配達をご希望の場合は、以下のQRコードを読み取ってください。[QRコード画像]
※手続きが行われない場合、荷物は廃棄される可能性がございます。
いずれの文面にも共通するのは、「リンクやQRコードの誘導」「強い不安を与える表現」「返信不可の記載」です。こうした特徴は詐欺の典型です。
公式メールとの違い
| 項目 | 詐欺メールの特徴 | 公式メールの特徴 |
|---|---|---|
| 差出人名 | ヤマト運輸株式会社(偽装) | ヤマト運輸(正規) |
| メールアドレス | 例:noreply@yamato-tracking-jp.com(偽) | @kuronekoyamato.co.jp など正規ドメイン |
| 宛名 | メールアドレスや空白 | 登録氏名が明記される |
| 文面 | 日本語が不自然・改行が多い | 丁寧で整った日本語 |
| リンク先 | 不自然なURL・短縮URL | 公式ドメインへのリンクのみ |
実在するように見えるが偽物と判明した文面
「配送状況を確認したが、伝票番号が存在しない」「クロネコメンバーズに荷物情報が表示されない」といったケースも多く報告されています。
また、実際に存在するメールドメイン(@kuronekoyamato.co.jp)を使った偽メールも確認されており、見た目だけでの判断は非常に危険です。
注意点
- 本文に「荷物が廃棄される可能性がある」と書かれている場合、それ自体が脅迫的で不自然です
- QRコードの使用はヤマト運輸の正規メールでは確認されていません
- リンク先のURLがhttps://から始まっていても安全とは限りません。必ずドメイン全体を確認しましょう
このような文面を見かけた場合は、リンクを開かず、ヤマト運輸の公式サイトやアプリから配送状況を確認するようにしてください。
本物か見分ける5つのチェックポイント
1. 送信元メールアドレスを確認する
ヤマト運輸を装った詐欺メールは、見た目上の差出人名が「ヤマト運輸株式会社」となっていても、実際のメールアドレスはまったく異なるドメインを使用していることがあります。
公式で使用されているドメインは以下の通りです。
- @kuronekoyamato.co.jp
- @ml.kuronekoyamato.co.jp
- @ml2.kuronekoyamato.co.jp
- @shop.rakuten.co.jp(楽天市場関連)
これら以外のアドレスや、アドレスが異常に長い・不自然な文字列を含む場合は詐欺の可能性が高いため、開かずに削除してください。
2. 宛名や表現の不自然さに注意する
正規のヤマト運輸の通知メールでは、利用者の本名が明記されています。一方、詐欺メールでは「お客様」「メールアドレス+様」など、個人名がなく曖昧な表現が多く見られます。
また、文面に以下のような不自然な日本語が含まれていれば、詐欺の疑いがあります。
- 「配送に失敗しました」
- 「ご住所が正しくありません」
- 「荷物の受け取りに失敗しました」
文法ミスや違和感のある丁寧語なども見逃さないようにしましょう。
3. メール内のリンクやQRコードは触れない
ヤマト運輸の公式メールでは、不審なQRコードの使用は基本的にありません。「再配達の予約には以下のQRコードを長押ししてください」などと記載されたメールは、リンク先が偽サイトである可能性があります。
リンクをクリックせず、公式サイトやアプリから直接確認するようにしてください。
4. 不自然な日本語・誤字脱字の有無
詐欺メールには、機械翻訳のような日本語や、意味の通らない表現、誤字脱字が頻繁に見られます。
特に以下のような例には注意が必要です。
- 「お届けに伺いましたが、失敗した」
- 「配送できないお荷物あります」
- 「状態異常により荷物停止」
自然なビジネス文書とは言えない場合、詐欺の可能性を疑ってください。
5. 荷物番号や内容を公式で照合する
メールに記載された伝票番号が本物に見えても油断は禁物です。ヤマト運輸の公式サイトで伝票番号を入力し、以下のような不審な表示が出た場合は注意が必要です。
- 「依頼受付」の履歴のみが表示される
- 配送履歴が実際の荷物と異なる
- クロネコメンバーズの「My荷物一覧」に該当がない

本物であれば「発送」「輸送中」「配達完了」などの詳細な履歴が確認できます。公式サイトでの確認を習慣にしてください。
詐欺メールに騙されないための対策
ヤマト運輸を装った詐欺メールは、日々その手口が巧妙になっており、メールの見た目だけでは判別が難しくなっています。しかし、日常的にいくつかの基本対策を意識することで、被害を未然に防ぐことが可能です。
メール内リンクや添付ファイルは安易に開かない
詐欺メールの多くは、URLリンクやQRコードをクリックさせ、偽サイトに誘導する手口を取っています。たとえそれが本物のように見えても、絶対に安易にクリックしないようにしてください。とくに「住所不備」「再配達依頼」などの文言があるメールは要注意です。
荷物の状況は公式サイトやアプリで確認する
不審なメールを受け取った場合、まずはヤマト運輸の公式サイトや「クロネコメンバーズ」のマイページで該当の荷物情報を確認しましょう。本物の荷物が存在していれば、正確な配送状況が表示されます。情報がない、または「依頼受付」のみが羅列されている場合は、偽装の可能性が高いです。
正規ドメイン以外のメールは開封せず削除する
ヤマト運輸が使用するメールドメインは以下の通りです。
- @kuronekoyamato.co.jp
- @ml.kuronekoyamato.co.jp
- @ml2.kuronekoyamato.co.jp
- @shop.rakuten.co.jp(楽天購入時)
これら以外の送信元ドメインで届いた場合は、迷惑メールと判断して削除してください。なお、正規ドメインを偽装したメールも存在するため、差出人名ではなくメールアドレスを必ず確認しましょう。
セキュリティソフトと迷惑メールフィルターを導入する
信頼できるセキュリティソフトを導入しておくことで、フィッシングメールの検出精度が高まり、誤って開いてしまった場合でも被害を最小限に抑えられる可能性があります。また、迷惑メールフィルターを強化設定にしておくことも効果的です。
家族や職場でも情報を共有しておく
同じような詐欺メールは多くの人に送られています。家族や職場のメンバーとも情報を共有し、「怪しいメールは必ず確認してから対応する」という共通認識を持つことが、被害防止につながります。

被害を防ぐには、「疑ってかかる」ことが最大の防御です。少しでも不自然さを感じた場合は、自分一人で判断せず、公式情報にアクセスして確認する習慣を持ちましょう。
もしクリック・入力してしまった場合の対応手順
ヤマト運輸を装った詐欺メールに誤って反応してしまった場合は、迅速な対応が被害の拡大を防ぐ鍵となります。以下の手順に従って、冷静に対処してください。
1. 入力した情報に応じた初動対応を行う
パスワードを入力してしまった場合
- 該当サービスのパスワードをすぐに変更してください。
- 同じパスワードを使い回している他のサービスのパスワードも変更が必要です。
- 二段階認証が利用可能な場合は必ず有効にしてください。
クレジットカード情報を入力してしまった場合
- カード会社に連絡し、不正利用の可能性を報告してください。
- カードの利用停止や再発行の手続きが推奨されます。
- 利用履歴をこまめに確認し、不審な請求がないか監視を継続してください。
個人情報(氏名・住所・電話番号など)を入力してしまった場合
- 詐欺メールやなりすまし電話などの迷惑行為が増える可能性があります。
- 公的機関や金融機関を装った連絡には特に警戒し、安易に情報を提供しないよう注意が必要です。
ログインIDや認証コードを入力してしまった場合
- 該当するアカウントのログイン履歴を確認し、不正アクセスの有無を確認してください。
- 必要に応じてアカウントの停止・再設定を行ってください。
2. デバイスのセキュリティ確認
- メール内のリンクやQRコードからマルウェアが仕込まれている可能性があります。
- セキュリティソフトを最新の状態にし、ウイルススキャンを実施してください。
- 可能であれば、初期化や専門業者による診断も検討してください。
3. 関係各所への相談・報告
警察へ相談する場合
- 最寄りの警察署または「サイバー犯罪相談窓口」に連絡してください。
- 犯罪被害の証拠となるため、詐欺メールの画面や履歴は削除せず保管しておいてください。
ヤマト運輸に連絡する場合
- 正式な問い合わせ先を通じて、詐欺メールを報告してください。
- 同様の手口が確認されている場合、注意喚起や対策情報を提供してもらえる場合があります。
消費者ホットライン(188)への相談も有効です
- 消費生活センターが適切なアドバイスや対応先の案内をしてくれます。
4. 今後の被害を防ぐための対策
- メールのリンクや添付ファイルは不用意に開かず、公式アプリやマイページ経由で確認する習慣を持ちましょう。
- 「迷惑メールフィルター」や「SMSブロック」機能を有効に設定してください。
- 不審な連絡は放置せず、早めに家族や専門機関に相談することが大切です。
よくある質問(FAQ)
本物のヤマト運輸のメールアドレスは?
ヤマト運輸が公式に使用しているドメインは以下の通りです。
- @kuronekoyamato.co.jp
- @ml.kuronekoyamato.co.jp
- @ml2.kuronekoyamato.co.jp
- @shop.rakuten.co.jp(楽天市場経由)
これら以外のドメインから届いたメールは偽装の可能性が高いため、開封前に差出人を確認してください。ただし、正規のドメインであっても偽装された詐欺メールも確認されており、絶対に安心とは言えません。
SMSで届いた通知は本物?
ヤマト運輸は基本的にSMSによる通知を行っていません。SMS形式で「荷物のお届けに関するご連絡」などが届いた場合は、詐欺の可能性が高いです。本文中にURLが記載されている場合は、絶対にクリックせず削除してください。
荷物番号が存在していても詐欺の可能性はある?
実在する伝票番号を悪用して信頼性を装うケースもあります。メールに記載された伝票番号で荷物検索を行った際、「依頼受付」のみが表示されていたり、「発送済み」「輸送中」などの通常ステータスがない場合は偽装の可能性が高いです。また、公式サイトに表示される情報とメール本文の内容が一致しない場合も注意が必要です。
クロネコメンバーズ未登録でも通知は届く?
クロネコメンバーズに登録していない方に対して、個別のメール通知が届くことは基本的にありません。未登録状態で「ヤマト運輸からの通知です」とのメールが届いた場合は、詐欺メールを疑ってください。確認の際は、公式の「荷物お問い合わせシステム」やマイページを利用してください。
不審なメールを受け取った場合はどうすればいい?
- メールを開かずに削除するのが最も安全です。
- 開いてしまった場合でも、リンクやQRコードは絶対にクリックしないでください。
- 情報を入力してしまった場合は、すぐにパスワード変更や関連サービスの確認を行い、警察やヤマト運輸の窓口に連絡してください。
どこに問い合わせすればいい?
迷惑メールか判断がつかない場合は、ヤマト運輸の公式サービスセンターに問い合わせるか、警察のサイバー犯罪相談窓口に相談してください。メールのヘッダー情報などを添えて問い合わせるとスムーズです。