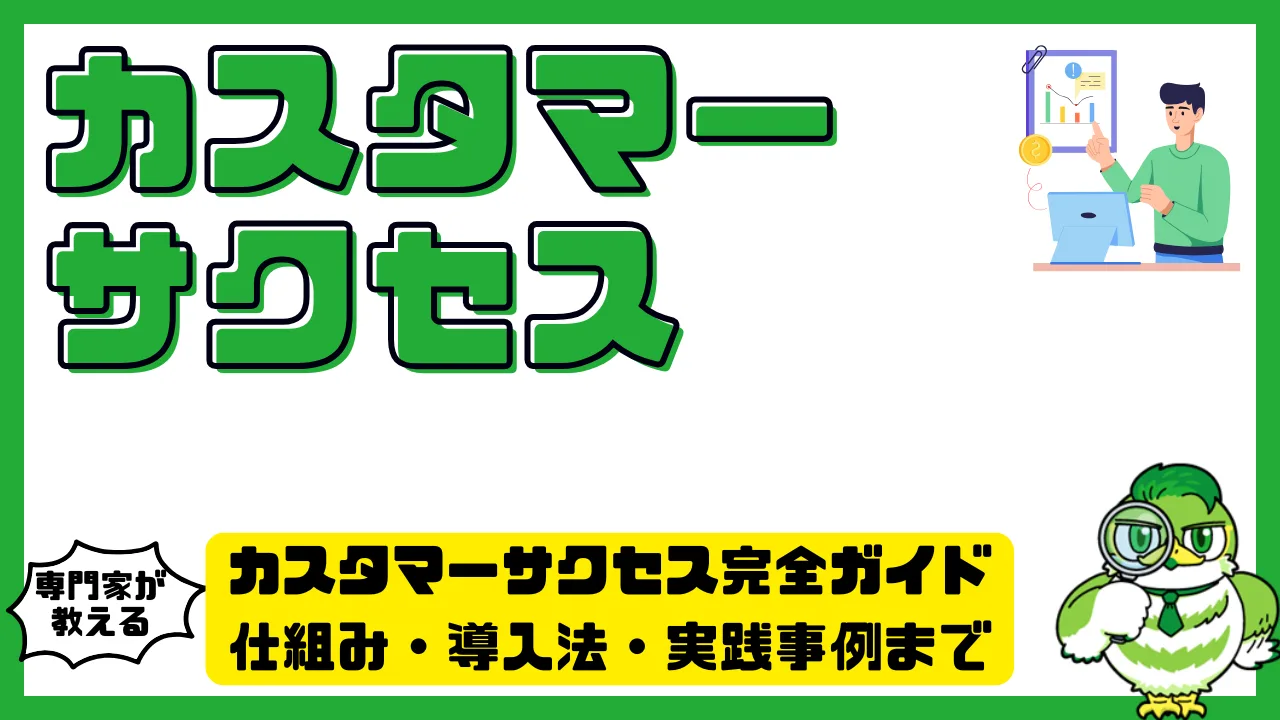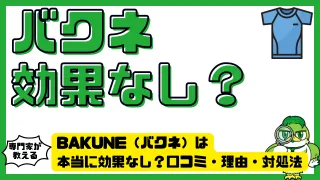本ページはプロモーションが含まれています。
目次
カスタマーサクセスとは何かを理解する
顧客の成功を支援する「能動的アプローチ」
カスタマーサクセス(Customer Success)とは、顧客が自社の製品やサービスを通じて期待以上の成果を得られるよう、企業側が積極的に支援していく取り組みです。ポイントは「能動性」です。つまり、顧客からの問い合わせを待つのではなく、企業側から先んじて働きかけを行い、課題の発見や解決に努めます。
この姿勢は、単に「トラブル解消」を目的とするカスタマーサポートとは根本的に異なります。カスタマーサクセスは、顧客の事業成長や業務改善に寄与し、継続利用やサービス拡張を後押しする“営業支援の延長線”にあるものと位置づけられます。
カスタマーサポートとの決定的な違い
| 項目 | カスタマーサクセス | カスタマーサポート |
|---|---|---|
| 目的 | 顧客の成功体験を支援 | 顧客の問題を解決 |
| アクションの起点 | 顧客の契約直後から | 顧客からの問い合わせ後 |
| 姿勢 | 能動的 | 受動的 |
| KPI例 | チャーンレート、LTV、NPS | 応答時間、解決率、満足度 |
このように、両者は「誰が先に動くか」「何をゴールとするか」で明確に区別されます。特に、解約率(チャーンレート)やアップセル・クロスセル率といった営業寄りのKPIを重視するのがカスタマーサクセスの大きな特徴です。
サブスクリプション時代に必要不可欠な役割
かつてのビジネスは、製品やサービスを「一度売れば完結」という売り切り型が主流でした。しかし、SaaSを中心としたサブスクリプション型モデルが広がる現代において、継続利用こそが売上を安定・拡大させる鍵となっています。
特にSaaSでは、顧客が月額料金を支払い続けることで事業が成立します。そのため、初期契約で終わらず、導入支援(オンボーディング)や継続的な活用支援を行うことで、解約を防ぎ、満足度とロイヤルティを向上させる必要があります。
つまり、カスタマーサクセスは「契約を起点とする営業戦略の一部」であり、契約後の顧客接点における重要なプロセスなのです。
The Modelにおけるカスタマーサクセスの位置づけ
近年の営業モデルの代表格である「The Model」では、以下のように営業プロセスを分業化しています。
- マーケティング:見込み顧客の獲得
- インサイドセールス:商談化
- フィールドセールス:契約獲得
- カスタマーサクセス:継続・拡大支援
この構造からも分かるように、カスタマーサクセスは営業活動の後半に位置する「収益の安定化・最大化を担う部門」として定義されており、もはや“アフターサービス”という域を超えた戦略的役割を担っているのです。

カスタマーサクセスは「売ったら終わり」から「売ってからが本番」へのシフトを象徴する存在。今や営業戦略の中心に据えるべき必須機能なんじゃよ
導入で得られる3つのビジネスメリット
1. 解約率(チャーンレート)の大幅な改善
カスタマーサクセスの導入により、顧客の課題や不満を先回りして解消できるようになります。これにより、顧客がサービスから離脱するリスクを最小限に抑えることが可能です。たとえば、導入初期につまずいた顧客に対してはオンボーディング支援を手厚く行い、継続的に利用状況を追跡する「ヘルススコア」を活用することで、解約の兆候を早期に察知し対応できます。
サブスクリプション型サービスでは、1件の解約が長期的な損失につながるため、チャーンレートの低下は経営インパクトも大きく、売上の安定化に直結します。
2. アップセル・クロスセルによる収益向上
カスタマーサクセスは、顧客のニーズや利用状況を深く理解した上で、適切なタイミングでの提案が可能になります。たとえば、ある機能を頻繁に使っている顧客に対しては上位プランのアップセルを提案したり、関連サービスへの関心が見られる場合にはクロスセルの機会を逃しません。
これらの提案は単なる売り込みではなく、顧客の成功体験を拡張する手段として行われるため、納得感のある購買につながりやすく、LTV(顧客生涯価値)の向上にも貢献します。
3. 顧客体験(CX)の質的向上によるブランド力強化
カスタマーサクセスは、単なる不満解消や問題対応にとどまらず、「期待を超えるサポート」を通じて、顧客にとってのブランド体験を高める役割を担います。定期的なフォローやウェビナー、成功事例の共有などを通じて、顧客は「大切にされている」という実感を持ちやすくなります。
このような良質な体験は、顧客満足度の向上だけでなく、口コミによる新規獲得や継続率の改善といった波及効果を生み出し、ブランド全体の信頼性を底上げします。

導入するだけで効果が出るわけではありません。顧客ごとの課題を見極め、適切なタイミングで支援を届ける“仕組み化”こそが、真のビジネスメリットを引き出す鍵です
カスタマーサクセスの主な業務と流れ
カスタマーサクセスの業務は、単に顧客の不満を解消するカスタマーサポートとは異なり、顧客の「成功」を目指して能動的に関わることが特徴です。以下では、ビジネスの成果に直結する主な業務フローを時系列で解説します。
導入支援(オンボーディング)
サービス導入初期の支援は、カスタマーサクセスの成否を左右する重要なフェーズです。顧客がサービスをスムーズに利用開始できるよう、以下の支援を行います。
- 初期設定や操作レクチャーの実施
- チュートリアルや導入ガイドの提供
- 初期目標の明確化とKGI・KPIの共有
この段階で顧客がつまずけば、その後の定着や継続利用に悪影響を及ぼすため、支援体制の整備が不可欠です。
活用定着支援(アダプション支援)
導入後もサービスを効果的に活用してもらうための支援を継続的に行います。
- 操作ウェビナーや活用事例セミナーの開催
- 顧客の業務課題に合わせた利用方法の提案
- ユーザーコミュニティの運営
単なる操作説明ではなく、「この機能が顧客の成果につながる」という視点での活用提案が求められます。
ヘルススコアによる状態監視とリスク検知
顧客の利用状況を定量的に把握し、離脱の予兆に早期対応します。
- ログイン頻度・利用率などのスコアリング
- サービス満足度アンケートの定点観測
- 顧客ごとのアクションプラン策定
ヘルススコアはカスタマーサクセスの羅針盤です。高リスク顧客に対しては、個別の打ち手を迅速に講じる必要があります。
継続利用・更新のアプローチ
契約更新やライセンス更新のタイミングに合わせて、継続利用を促す施策を実施します。
- 利用実績のレポート提出と成果共有
- 契約更新前の価値訴求や課題解決提案
- 解約意向の兆候に応じたカスタマイズ対応
「更新のための接点」ではなく、「成果の再確認と今後の期待値調整の場」として活用することが重要です。
アップセル・クロスセルによる収益最大化
顧客の成功体験に基づいた提案によって、収益向上を目指します。
- 上位プランや追加機能の提案
- 他サービスとの連携・拡張利用の提案
- 利用状況に基づいた導入タイミングの設計
アップセルは売り込みではなく、「さらなる成果を出すための提案」でなければなりません。
顧客の声を反映したフィードバックループ構築
顧客との継続的な対話から得られる情報を、プロダクト改善やマーケティング施策に還元します。
- 定期的な顧客インタビューやアンケート
- フィードバックからの要望抽出と社内共有
- 顧客の声を基にしたプロダクト改良提案
フィードバックの活用は、顧客との信頼構築とLTV向上に直結する施策です。

カスタマーサクセスの仕事は、単なるサポートではありません。導入から活用、継続、成長支援まで、顧客のビジネス成功を全方位で支える“伴走者”としての役割を全うしましょう
顧客に応じた「3つのタッチモデル」運用術
顧客ごとに異なるニーズやLTV(顧客生涯価値)に対応するためには、画一的な支援ではなく、戦略的にリソースを配分することが重要です。そこで活用されるのが「ハイタッチ」「ロータッチ」「テックタッチ」の3つのタッチモデルです。それぞれの特性と運用ポイントを解説します。
ハイタッチ:LTVが高い顧客に向けた手厚い支援
ハイタッチは、収益貢献度が高く、戦略的に重要な顧客に対して、専任担当者がついて個別支援を行うスタイルです。マンツーマンのミーティングや現地訪問、ワークショップなど、双方向かつパーソナライズされた対応が可能です。
主な施策例
- 定期的なビジネスレビューとKPI進捗報告
- 専任担当による業界課題に即した提案
- 契約更新やアップセル提案を前提とした中長期計画の共有
運用ポイント
- 1社あたりにかける時間が長くなるため、顧客選定は厳格に
- 対象顧客を「LTV」「拡張性」「紹介影響力」など複合指標で選別
- ヘルススコアで状況変化を把握し、重点フォローを調整
ロータッチ:効率性と満足度を両立する中間層向け支援
ロータッチは、一定の収益貢献が見込める顧客群に対して、効率的なグループ対応を行うスタイルです。共通課題をテーマにしたセミナー、動画講座、Q&Aセッションなどを通じて支援を行います。
主な施策例
- 定期開催のウェビナー(オンボーディング・活用編など)
- 顧客業界別の活用ガイドやテンプレート提供
- カスタマージャーニーに応じたタイミングでの自動メール支援
運用ポイント
- ハイタッチへの昇格候補としてLTV成長見込みを常に監視
- テンプレート化・再利用可能な支援コンテンツを拡充
- セグメント単位でのNPSや参加率などの分析を実施
テックタッチ:スケーラブルに広範囲をカバー
テックタッチは、ユーザー数が多く1社あたりのLTVが低めな層に向けて、ツールやデジタルコンテンツを駆使して対応するスタイルです。人的リソースを介さず、自己解決を促す仕組みづくりが主軸となります。
主な施策例
- ツール画面上のチュートリアル・ポップアップ導線設計
- チャットボット・FAQ・動画ライブラリの整備
- 定期的なナーチャリングメールの自動配信
運用ポイント
- 顧客行動データ(MA・SFA連携)をもとに細やかなパーソナライズを実装
- 利用率やログイン頻度をもとにアラートとキャンペーンを自動化
- 高ヘルススコア顧客をロータッチへ昇格するトリガー設定
タッチモデルの選定フローと自動運用のすすめ
3つのタッチモデルは、静的に分類するだけでは十分ではありません。顧客の成長や利用状況に応じて、タッチモデル間の「昇格」「降格」運用を自動化する仕組みが重要です。
理想的な運用フロー
- 初回契約時にLTV予測をもとに初期タッチ分類
- 利用状況やNPSを定期的に評価し、昇降格のトリガーを自動判定
- タッチ変更後はフォローアップ設計を切り替えてリスクを最小化
顧客の成功体験を継続的に最大化するには、静的支援ではなく、動的な支援設計が求められます。

一人ひとりに合った「ちょうどいい支援」を設計することが、カスタマーサクセスの本質的な仕事なんだよ
KPIで見る成功の指標と評価方法
カスタマーサクセスの成果は感覚的な満足度だけでは測れません。定量的に評価し、改善につなげるためには、明確なKPI(重要業績評価指標)の設定が欠かせません。ここでは、ビジネス成果に直結する4つの主要KPIと、それぞれの評価・活用方法について解説します。
LTV(顧客生涯価値)を最大化する
**LTV(Life Time Value)**は「1人の顧客が生涯を通じて企業にもたらす利益の総額」を意味します。カスタマーサクセスの取り組みが長期的に実を結んでいるかを示す、もっとも包括的な指標です。
主な計算式:
LTV = 平均年間売上 × 粗利率 × 平均契約継続年数注目ポイント:
- 高いLTVは「顧客が定着し、かつ価値の高い取引を続けている」証拠
- 契約年数を延ばす施策(継続支援)、単価を上げる施策(アップセル)と密接に連動
定期的にLTVをチェックすることで、顧客への価値提供の質がどれだけ事業成長に貢献しているかを客観的に把握できます。
NPS(ネットプロモータースコア)で信頼度を数値化する
**NPS(Net Promoter Score)**は「このサービスを他人に勧めたいと思うか?」という観点から、顧客ロイヤルティを数値化する指標です。
測定方法:
「0〜10点で評価してください」という質問に対し、回答を3分類します。
| 点数 | グループ |
|---|---|
| 9〜10 | 推奨者 |
| 7〜8 | 中立者 |
| 0〜6 | 批判者 |
NPS = 推奨者の割合 − 批判者の割合
活用ポイント:
- 業種によって基準値は異なるが、NPSがプラスであれば一定の信頼を得ている状態
- NPSが下がった場合は、直近の施策やサポート体制を見直すサイン
数字だけでなく、「なぜ勧めたい/勧めたくないのか?」の自由回答も分析対象にしましょう。
チャーンレート(解約率)で顧客の離脱を可視化する
カスタマーサクセスが最も重視する指標の一つがチャーンレート(解約率)です。
計算式:
チャーンレート(%) = 一定期間内の解約数 ÷ 総契約数 × 100留意点:
- 単純な解約数ではなく、割合で見ることで事業規模に左右されず比較が可能
- 月次・四半期ごとに分析し、改善活動(FAQ整備、プロダクト改善など)につなげる
離脱の原因を突き止め、対策を講じることがLTVやNPS向上にも直結します。
アップセル・クロスセル率で成長余地を探る
アップセル(上位プランへの移行)とクロスセル(関連サービスの追加購入)は、既存顧客からの収益を拡大するうえで有効な指標です。
把握すべきデータ:
- 追加購入率(サービス別)
- プランアップグレード比率
- 提案後の転換率(成約率)
実施ポイント:
- 顧客が直面する課題と解決手段をセットで提示する
- ユーザーの利用履歴や行動ログからニーズを予測する
KPIとして継続的にトラッキングすれば、「ただ売る」のではなく「成果の最大化を支援する」姿勢が定着します。

KPIは数字を見るための道具ではなく、顧客との関係性を深めるためのレーダーだよ。点数の上下に一喜一憂せず、改善に活かす視点がカスタマーサクセスの本質なんだ
成功に導く社内連携とツール活用
社内連携がカスタマーサクセスを左右する理由
カスタマーサクセスは単独の部門活動ではなく、営業・サポート・マーケティング・開発といった複数部門の連携によってはじめて機能します。顧客の成功体験を継続的に支援するためには、すべての部門が一貫した情報と目的を共有していることが不可欠です。
とくにBtoBのSaaSビジネスでは、フィールドセールスから引き継いだ契約情報、マーケティング部門が保有する行動ログ、サポートに寄せられる問い合わせ内容など、顧客接点の情報が複数の部門に散在します。これらを統合・共有しない限り、カスタマーサクセス部門は最適なアプローチを選べません。
さらに、営業部門とカスタマーサクセス部門の目標が乖離している場合、アップセル提案や継続利用支援のタイミングがズレ、結果として解約リスクを高めてしまう恐れもあります。KPIや評価制度を共有し、両部門が「顧客LTV最大化」という共通ゴールに向かうことが求められます。
情報共有を促進するツール選定のポイント
部門間連携を実現するためには、ツールの整備が欠かせません。とくに重要なのが以下の3種のシステムです。
CRM(顧客関係管理システム)
顧客の属性、購買履歴、サポート履歴、やりとりの内容を一元管理することで、あらゆる部門が共通の情報にもとづいた施策を展開できます。
SFA(営業支援システム)
営業活動の進捗、案件ステータス、契約内容などを記録・共有することで、カスタマーサクセス部門が「どのような期待値で契約されたか」を正確に把握できます。
CS専用ツール(カスタマーサクセスプラットフォーム)
顧客の利用状況をリアルタイムでトラッキングし、ヘルススコアを自動算出。リスク予兆の検知や、対応の優先度判定に活用できます。例として「HiCustomer」「Gainsight」「Fullstar」などが挙げられます。
これらのツールを分断的に導入するのではなく、API連携などで情報を横断的に活用できる構成にすることが重要です。顧客がどこでつまずいているか、どのタイミングで満足度が下がっているかを早期に把握し、対応施策を即時に打てる環境を整えることが成果直結につながります。
業務の「脱属人化」と標準化による継続性の確保
優秀な担当者に依存する運用は長期的なリスクとなります。業務の属人化を防ぐには、ナレッジの蓄積と共有が必須です。具体的には以下のような取り組みが効果的です。
- よくある質問・対応フローのマニュアル化
- 成功した対応ケースの共有(ナレッジベース構築)
- CRM/SFA上への議事録・アクションログの記録徹底
また、データドリブンな意思決定を行うためには、ツールから得られるKPIや顧客の動向を定期的に分析・可視化する仕組みも重要です。たとえば、アラート機能やダッシュボードを活用すれば、解約予兆を放置せず即座に対応できます。

社内連携は「同じゴールを全員で見ること」。CRMやCSツールを上手に使えば、顧客との関係も社内の連携もぐっとスムーズになりますよ
成果を上げたカスタマーサクセスの実践事例
Apple|ジーニアスバーによる徹底した対面サポート
Appleでは「Genius Bar(ジーニアスバー)」という対面サポート体制を設けることで、製品購入後の顧客に対して継続的な支援を提供しています。単なる修理窓口にとどまらず、利用者がiPhoneやMacの価値を最大限に活用できるよう支援する役割を担っており、これがAppleブランドへの信頼・満足度を高める大きな要因となっています。
特に購入初期に起きやすい設定ミスや操作上の疑問に対して、プロフェッショナルが個別に対応することで、顧客の不安を早期に解消。店舗を訪れるたびに安心できる体験が得られることで、「何度でも通いたくなる店舗」へと進化させています。
Sansan|オンボーディング重視で解約率0.6%の実績
名刺管理サービス「Sansan」を提供するSansan株式会社では、「オンボーディング=カスタマーサクセスの核心」と位置づけ、導入後の初期支援に注力しました。
単なる機能説明ではなく、顧客企業の業務プロセスに沿った活用方法の提案や、現場での実践的な操作支援までを丁寧に行うことで、顧客がスムーズにサービスを利用できる環境を構築。結果として、業界平均を大きく下回る0.6%という驚異的なチャーンレートを実現しています。
また、顧客の「定着フェーズ」に合わせて複数回のフォローアップを実施し、単なる導入支援に終わらない長期的なリレーション構築も成功の鍵となっています。
スターバックス|カードによるファン化戦略
スターバックスが行っているカスタマーサクセス施策のひとつに、「スターバックスカード」の導入があります。2002年に国内で始まったこのプリペイドカードは、利便性を高めるだけでなく、来店の動機付けや継続利用の促進にも大きな役割を果たしています。
顧客が自身でチャージして使う仕組みは心理的ロックインを生み、結果として来店頻度が向上。また、デザインの豊富さや限定カードなどの収集性がブランドへの愛着を育てる要素にもなっており、顧客ロイヤルティの強化につながっています。
このように、単なる決済手段にとどまらず「体験の一部」としての仕組みを構築したことで、サブスクリプション型ではない小売業態においても、継続的な関係構築を実現しています。
SmartHR|業務定着を促進するカスタマーサクセスマーケティング
クラウド人事労務ソフトを提供するSmartHRでは、サービス導入後の「業務定着」に向けて、マーケティング視点を取り入れたカスタマーサクセス施策を展開しています。
業界別・業種別に最適化された操作ガイドの提供、定期的なWebセミナーの開催、顧客同士をつなぐコミュニティ運営などを通じて、「わからない」を「なるほど」に変える場を継続的に提供。その結果、ヘルススコアの安定化やLTV向上に寄与しています。
また、初期対応だけでなく、利用フェーズごとの行動トリガーに応じてリテンション施策を打つ構造化された体制が、施策の再現性と成果の持続性を支えています。
マネーフォワード|分業体制とスコアリングによるターゲティング強化
マネーフォワードでは、カスタマーサクセス部門を業種特化型チームに分け、セグメントごとに最適化されたフォローを実現しています。
ヘルススコアに加え、利用データから抽出したカスタマースコアを軸に優先順位をつけ、アプローチの効率化と質の向上を両立。LTVが高い見込み顧客にはマンツーマンの定例フォローを、一定の自立度が見込まれる層にはウェビナーやナレッジコンテンツで対応するなど、タッチモデルを柔軟に展開しています。
さらに、定期的なKPIレビューによってチャーン兆候の早期発見・先回り対応を可能にし、リテンション率の維持・改善に貢献しています。

成功事例の本質は「顧客と長く付き合う覚悟」じゃ。ツールや施策は多種多様じゃが、顧客の成功を共に目指す姿勢だけは、どの事例にも共通しておるぞ
カスタマーサクセス導入でよくある課題と対策
初期導入で現場が混乱する原因と整備のポイント
カスタマーサクセスを導入する際、最初に直面しやすいのが「現場の混乱」です。従来の営業やサポート業務との役割の違いが曖昧なまま運用を始めると、業務の重複や対応漏れが頻発し、顧客対応の品質低下を招きます。
この問題の解決には、まず「業務プロセスの可視化」が欠かせません。導入前にワークフロー図を作成し、どの部門がいつ、どの顧客に、どのような支援を行うのかを明確にしましょう。特に、オンボーディングからリテンションまでのフローを具体化することで、社内の役割分担が整理され、スムーズな連携が可能になります。
また、プロセス設計だけでなく、担当者のスキルセットを定義し、必要な教育を事前に行うことで、属人化を防ぎ、混乱の抑制につながります。
リソースが足りず全顧客をフォローできない問題への対応
「すべての顧客にきめ細かな対応ができない」というのも、多くの企業が抱える課題です。特に、少人数で運用するスタートアップや中堅企業では、ハイタッチ型の対応を全顧客に提供するのは現実的ではありません。
ここで重要なのが「顧客のセグメンテーション」と「タッチモデルの活用」です。LTVや契約規模に応じて、ハイタッチ(対面・個別対応)、ロータッチ(セミナー・一斉支援)、テックタッチ(自動化コンテンツ)を組み合わせることで、限られたリソースでも効果的な支援が実現できます。
さらに、FAQ・動画・チュートリアルなどのナレッジコンテンツを整備し、顧客が自ら解決できる仕組みを構築することで、人的リソースの圧迫を軽減できます。
KPIが形骸化し、継続運用が続かない場合の対処法
カスタマーサクセスを継続的に運用していくには、明確なKPI設定と評価制度の整備が不可欠です。ところが、「数値だけが先行し、業務と結びつかない」「評価されるポイントが曖昧でモチベーションにつながらない」といった問題が頻発します。
この課題を解決するには、KPIの定義を“現場視点”で見直すことが重要です。たとえば「LTVの向上」や「解約率の低下」といった定量指標だけでなく、「導入直後3ヶ月のオンボーディング完了率」「初回ウェビナー参加率」など、日々のアクションに直結するKPIも導入すべきです。
また、営業・サポート・プロダクト部門とKPIを共有し、連携による成果も評価の対象とすることで、部門間の分断を防ぎ、継続的な取り組みにつなげられます。

カスタマーサクセス導入でつまずくのは「やり方」ではなく「仕組み」の欠如が多いんだ。整備と運用の土台づくりが、成功の分かれ道になるぞ