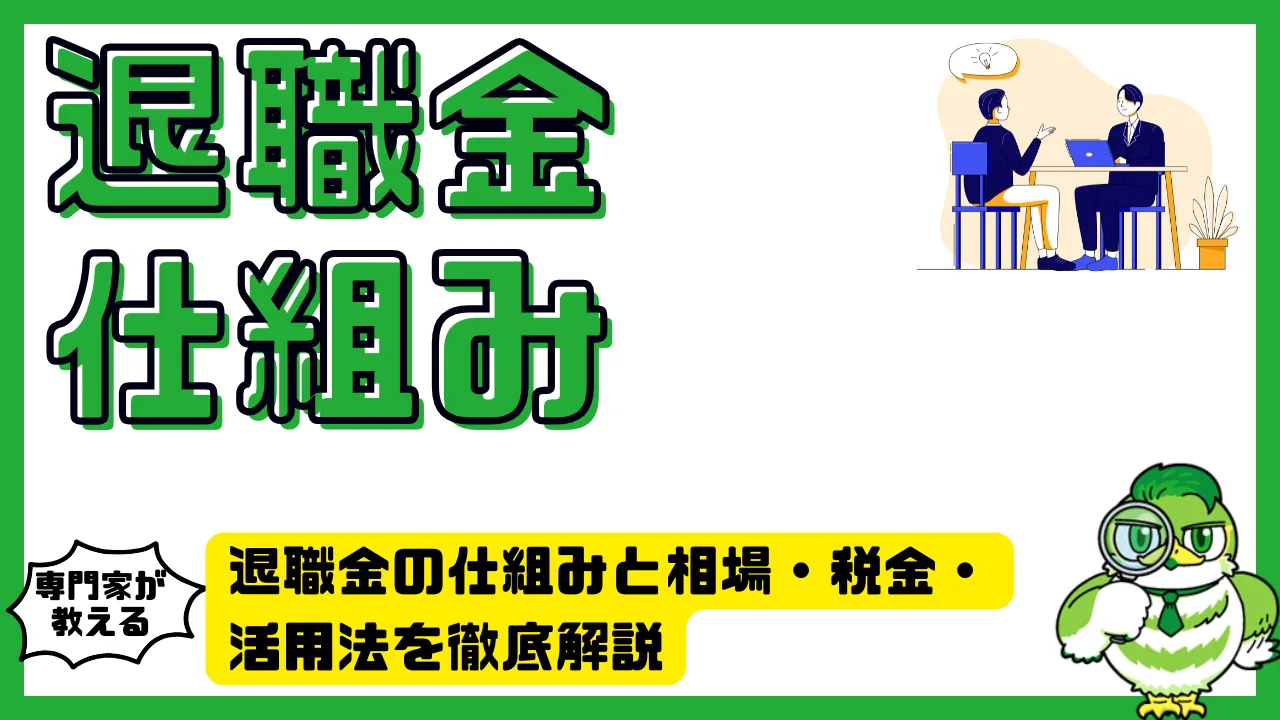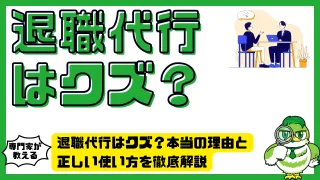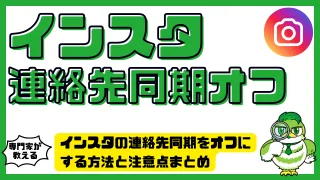本ページはプロモーションが含まれています。
目次
退職金制度の基本を理解する
退職金の役割と位置づけ
退職金は、長年勤務した従業員に対して企業から支払われる「労働の成果の集大成」といえるものです。老後の生活資金を支える柱の一つとして期待されており、公的年金だけでは不足しがちな生活費や医療・介護費用を補う役割を果たします。特に日本では平均寿命が長く、人生100年時代といわれる中で、退職金の有無が老後の安定度に大きな影響を与えます。
退職一時金と退職年金の違い
退職金の支給方法には大きく分けて「一時金」と「年金」の2つがあります。
- 退職一時金
退職時にまとまった金額を一括で受け取る方式です。住宅ローンの返済や子どもの教育費、リフォーム資金など大きな支出に活用しやすいのが特徴です。ただし一度に使いすぎてしまうリスクがあるため、計画的な利用が求められます。 - 退職年金
退職後に定期的に分割して支給される方式です。生活費として安定的に使えるメリットがあり、長寿リスクに備えやすいのが特徴です。企業によっては「一時金と年金の併用」が可能な場合もあります。
企業の導入率と導入目的
厚生労働省の調査によると、退職金制度を導入している企業の割合は7割を超えており、大企業ほど導入率が高い傾向にあります。大企業では「一時金と年金の併用」を採用するケースが多く、中小企業では「一時金のみ」が主流です。
企業が退職金制度を設ける目的は、従業員の定着を促し、優秀な人材を長期的に確保するためです。長く勤めるほど退職金額が増える仕組みは、働く側にとってもモチベーションを高める要因となります。一方で、退職金は法律で義務付けられている制度ではないため、企業ごとに内容や有無は異なります。必ず自社の就業規則や人事制度を確認しておくことが大切です。

退職金は「老後資金の土台」になる制度です。一時金か年金か、その仕組みを理解しておくことが安心への第一歩ですよ
企業規模別に見る退職金の相場
退職金の額は勤続年数や学歴だけでなく、企業の規模によっても大きく差が出ます。特に大企業と中小企業では、制度の充実度や積立余力の違いから、支給される退職金額に明確な差が存在します。ここでは、最新の調査データをもとに相場感を整理します。
大企業の退職金相場
厚生労働省「令和5年賃金事情等総合調査」によると、大企業(資本金5億円以上かつ従業員1,000人以上)の定年退職者の平均退職金は以下の水準です。
- 大学卒:2,139万円前後
- 高校卒:2,019万円前後
制度としては「退職一時金」と「確定給付企業年金(DB)」の併用型が多く、長期勤続者に有利な仕組みが整えられているのが特徴です。学歴差は100万円前後に留まりますが、安定した福利厚生の一環として大企業の強みが表れています。
中小企業の退職金相場
一方、中小企業(東京都産業労働局「中小企業の賃金・退職金事情 令和6年版」)の定年退職者の平均退職金は以下の通りです。
- 大学卒:1,149万円前後
- 高校卒:974万円前後
中小企業では内部積立が難しいため「中小企業退職金共済(中退共)」を利用するケースも目立ちます。ただし、制度自体を導入していない企業も少なくなく、調査では退職金制度なしと回答した割合が約3割に達しています。
大企業と中小企業の差
上記を比較すると、大企業と中小企業では以下のような開きがあります。
- 大学卒:差額 約990万円
- 高校卒:差額 約1,046万円
つまり同じように40年勤務しても、勤務先が大企業か中小企業かで1,000万円前後の差が出るのが実態です。この差は退職後の生活に直結するため、転職やキャリア選択の際には見過ごせないポイントといえます。
学歴による違い
大企業では学歴差が100万円前後に収まる一方、中小企業では約175万円の開きがあります。学歴に応じた初任給や昇給幅の違いが、退職金にまで影響していると考えられます。
相場の変動傾向
過去15年の推移を見ると、退職金額は全体的に減少傾向にあります。例えば大学卒の平均退職金は2008年に2,300万円を超えていましたが、2023年には1,896万円まで下落しました。企業規模を問わず、将来はさらに縮小する可能性があり、退職金への依存度を下げる準備が重要になっています。

退職金は企業規模や学歴によってこれほど差が出ます。大企業なら安定的に高水準が期待できますが、中小企業では制度の有無そのものを確認する必要があります。数字だけで安心せず、将来の減少傾向も踏まえて、自分のキャリア選択と老後資金の戦略を立てることが大切ですよ
業種別・職種別の退職金相場
退職金は企業規模だけでなく、業種や職種によっても大きな差が生まれます。特に「利益率」「労働環境」「人材定着率」といった要因が影響しており、同じ学歴・勤続年数でも業界ごとに数百万円単位で違いが出ることがあります。ここでは主要な業種別・職種別の相場を整理します。
業種別の特徴
金融・保険業界
平均退職金額は大学卒で約1,940万円、高校卒で約1,497万円と全業種の中でも突出して高い水準です。金融業は利益率が高く、長期雇用を前提とする企業が多いため、制度も手厚く設計されています。
製造業
大学卒で約1,108万円、高校卒で約1,027万円と、比較的安定した水準です。大手メーカーでは退職金制度が古くから整備されており、終身雇用の文化が反映されています。
建設業
大学卒929万円、高校卒991万円と、学歴によって逆転するケースがあるのが特徴です。技能職の比重が高く、現場での勤続が重視されるため、学歴差が小さいのも建設業の特性です。
卸売・小売業
大学卒1,239万円、高校卒881万円と幅があります。小売は離職率が高く、制度が簡素な企業も多いため、業種内で差が大きいのが実情です。
サービス業・飲食業
退職金制度そのものが存在しない企業が多く、制度があっても水準は低い傾向です。中小企業庁の調査では、宿泊業・飲食サービス業で制度未導入率が約6割に達しています。
医療・福祉業
公的病院や大規模法人では安定した退職金がありますが、中小規模の福祉施設では支給額が数百万円規模にとどまることも珍しくありません。
職種・役職による違い
退職金は「職務等級」「役職加算」で大きく差がつきます。多くの企業はポイント制を導入し、役職が上がるにつれて加算ポイントが増える仕組みを採用しています。
- 管理職(部長・課長クラス)
勤続30年以上で2,000万円超が一般的。大企業の部長クラスでは2,500万円を超えることもあります。 - 一般職
大学卒で1,000万〜1,500万円程度が目安。中小企業では800万〜1,200万円程度に収まることが多いです。 - 専門職(研究職・技術職)
製造業・IT業界などでは専門性に応じて加算される場合があり、管理職に匹敵する水準を得るケースもあります。 - 営業職
成果に基づくインセンティブ型給与が多いため、退職金は一般職水準に近い場合が多いですが、大手金融や保険業では営業でも高額退職金を得られる傾向があります。
業種別相場まとめ(大学卒・定年退職モデル)
- 金融・保険業:1,900万円前後
- 製造業:1,100万円前後
- 卸売・小売業:1,200万円前後
- 建設業:930万円前後
- 運輸・郵便業:940万円前後
- サービス業(他分類含む):1,000万円前後
- 飲食・宿泊業:数百万円〜制度なしが多い

退職金は業種や職種によって大きな差がありますね。自分のキャリアと所属する業界の傾向を把握しておくことが、老後の資金計画を立てる上で欠かせませんよ
勤続年数と退職理由による差
退職金は「どれだけ長く働いたか」と「どのような理由で退職するか」によって金額が大きく変わります。勤続年数は支給額を決める最も基本的な要素であり、退職理由はその金額に加えて増減をもたらす重要な条件です。ここでは実際のデータを踏まえて詳しく解説します。
勤続年数による金額の推移
厚生労働省や東京都の調査によると、勤続10年程度では数百万円前後、20年で1,000万円前後、30年を超えると2,000万円以上に達するケースが多いです。特に定年退職時には企業規模や学歴によって差はあるものの、大企業では2,000万円を超える水準が一般的とされています。
ただし注意すべきなのは、勤続30年を超えるあたりから金額の伸びが鈍化する傾向があることです。つまり、勤続年数が長ければ長いほど無限に増えるわけではなく、一定のラインで伸び率が抑えられることを理解しておく必要があります。
自己都合退職と会社都合退職の違い
退職理由によって退職金の額は大きく変わります。
- 自己都合退職の場合は、企業側が減額規定を設けていることが多く、同じ勤続年数でも会社都合より数割少なくなるケースが一般的です。特に勤続年数が短い段階での自己都合退職では、支給額が大幅に減ったり、まったく支給されないこともあります。
- 会社都合退職(リストラや経営不振による整理など)の場合は、退職者に不利益が及ばないように法律や労使協定で手厚い金額が支払われるケースが多く、自己都合退職よりも高額となります。
この違いは短期間勤務ほど顕著に表れ、例えば勤続5年未満では自己都合での退職金はごくわずか、あるいはゼロとなることも少なくありません。
短期間勤務で支給されないケース
退職金制度のある会社でも、勤続3年未満などの場合は「不支給」とする規定を設けているケースがあります。これは「長期勤務に対する報奨」という退職金の性格上、短期間勤務では積み立て原資が少なく、支給対象とならないためです。転職が当たり前になりつつある時代でも、退職金を期待するなら最低限の勤続年数を満たすことが必要です。

退職金は「勤続の長さ」と「退職理由」で大きく変わるんだよ。特に自己都合退職は減額されることが多いから、転職や早期退職を考えるときは必ず勤務先の規定を確認しておこうね。短期間で辞めると退職金ゼロのケースもあるから要注意だよ
退職金にかかる税金と控除制度
退職金はまとまった金額を受け取れる大切な資金ですが、そのまま手元に残るわけではなく、税金が関わります。ただし、通常の給与と比べて大幅に優遇された仕組みがあり、控除制度を理解することで手取り額を増やすことが可能です。
退職所得控除の基本
退職金を一時金で受け取る場合は「退職所得」として課税され、退職所得控除を差し引いたうえで計算されます。控除額は勤続年数によって決まり、勤続が長いほど有利です。
- 勤続年数20年以下
40万円 × 勤続年数(最低80万円) - 勤続年数20年超
800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)
さらに、控除後の金額を1/2に圧縮して課税対象とするため、給与所得に比べて圧倒的に税負担が軽くなります。
例:勤続30年・退職金1,700万円の場合
退職所得控除=1,500万円
(1,700万円-1,500万円)÷2=100万円が課税対象
→ 所得税・住民税合わせて約15万円の負担で済みます。
一時金受け取りと年金受け取りの違い
退職金の受け取り方法によって税区分が変わります。
- 一時金受け取り
退職所得として分離課税。退職所得控除の恩恵が大きく、税負担が最も軽くなる傾向があります。 - 年金受け取り
雑所得として扱われ、公的年金等と合算して課税。適用されるのは「公的年金等控除」ですが、控除額が小さいため一時金よりも税負担が増えるケースが多いです。 - 併用受け取り
一部を一時金、残りを年金形式で受け取る方法。まとまった資金と生活資金の両立ができ、控除も併用されます。ただし勤務先の制度により選択できない場合があるため、事前確認が必須です。
税金を最小化する工夫
- 退職所得申告書を必ず提出
勤務先へ「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、会社側で源泉徴収が完了し、確定申告不要になります。 - 受取時期の調整
退職金と企業年金やiDeCoの受け取り時期を重複させると課税負担が増えることがあります。タイミングをずらすことで控除を最大限活用できます。 - 他の控除との組み合わせ
医療費控除や生命保険料控除などと合わせて確定申告を行うと、結果的に税金が還付されるケースもあります。

退職金は優遇税制のおかげで、思った以上に手取りが残ります。ただし受け取り方によって負担は変わるので、自分のライフプランに合わせて「一時金か年金か」をしっかり検討するのが大事ですよ
退職金を補うための自助努力
退職金は老後の生活を支える大切な資金ですが、企業規模の差や制度縮小の流れにより、十分な額を受け取れないケースも増えています。安心して老後を迎えるためには、自ら準備する「自助努力」が欠かせません。ここでは代表的な方法を整理します。
NISAを活用した資産形成
NISA(少額投資非課税制度)は、投資で得た利益が非課税になる制度です。2024年からは非課税保有限度額が大幅に拡大され、つみたて投資枠(年間120万円)と成長投資枠(年間240万円)を併用することで、最大年間360万円まで非課税で運用可能です。老後まで長期運用することで、複利効果を最大限に活かせます。退職金だけに頼らず、働いている間から少額でも積み立てていくのが有効です。
iDeCoによる長期積立と税制優遇
iDeCo(個人型確定拠出年金)は、老後資金づくりに特化した制度で、掛金が全額所得控除となるのが大きな魅力です。さらに運用益も非課税、受け取り時も税制優遇が受けられます。ただし原則60歳まで引き出せない点や、元本割れの可能性がある点には注意が必要です。長期的に安定して老後資金を積み立てたい方に向いています。
個人年金保険の活用
保険会社が提供する個人年金保険も、老後資金を補う手段のひとつです。契約内容によっては所得控除の対象となり、税負担を抑えながら積立ができます。健康状態に左右されにくく加入できるケースも多いため、他の制度と併用しやすいのが特徴です。ただし、途中解約すると元本割れする可能性があるため、長期継続を前提に利用することが望まれます。
定年後の就業で収入を確保
近年は定年後も働き続ける人が増えています。短時間勤務や嘱託制度を利用して、年金の受給を補いながら安定した収入を得る方法です。在職老齢年金の仕組みにより年金額が調整される場合もあるため、給与と年金のバランスを考えた働き方を選ぶことが大切です。
分散投資でリスクを抑える
退職金を受け取った後も、定期預金や投資信託など複数の金融商品に分散して運用することで、リスクを軽減しながら資産を増やすことができます。特にNISAを利用した投資信託は、長期的な運用に適しています。安全性を重視したい場合は、定期預金や国債を組み合わせるのも効果的です。

退職金が減少傾向にある今の時代では、NISAやiDeCoなどの制度をうまく組み合わせて資産形成するのが大事なんです。退職後も働く選択肢や、保険を活用した備えも加えるとさらに安心できますよ。早めに始めるほど老後資金に余裕が生まれるので、一歩踏み出すことが何より重要です
退職金の有効な活用法
退職金は、老後資金の柱となる一方で、まとまった大きな金額が手元に入るため、使い道を誤ると将来の生活に不安を残すことになります。ここでは、安全性を重視する方法から、資産形成につなげる方法まで、代表的な活用法を整理します。
定期預金で安全に運用する
もっとも堅実な選択肢は定期預金です。元本が保証され、預金保険制度によって一定額まで保護されるため、生活費の予備資金として安心して預けられます。特に、近年は金利上昇の影響で定期預金の利息が改善傾向にあり、安全に利息収入を得たい方に向いています。突発的な医療費や修繕費などに備えて、流動性の高い普通預金と組み合わせて管理するのが効果的です。
投資信託で分散投資とリスク管理
退職金をそのまま眠らせておくのではなく、将来に備えて資産を成長させたい方には投資信託が有効です。投資信託は、運用のプロが株式や債券などに分散投資を行うため、個別株よりリスクを抑えつつリターンを狙えます。特にNISA制度を活用すれば、運用益が非課税となり、長期的に大きな差を生み出すことが可能です。短期的な値動きに左右されず、長期運用を意識することがポイントです。
住宅ローン返済やリフォーム費用への充当
住宅ローンの残債がある場合は、退職金で繰り上げ返済を行うと、毎月の返済負担を軽減し、老後のキャッシュフローを安定させられます。また、自宅のリフォームやバリアフリー化に充てるのも有効です。特に高齢期は住環境が生活の質に直結するため、安心して暮らせる住まいづくりに退職金を活かすことは長期的な安心につながります。
外貨預金・国債・保険商品の活用
インフレ対策や分散投資の観点から、外貨預金や国債、年金型保険などを組み合わせる方法もあります。外貨預金は為替リスクがあるものの、日本円だけに偏らないことで資産の目減りを防ぐ効果が期待できます。年金型の保険商品は、一定期間にわたり定額を受け取れるため、生活費を安定的に補う手段として役立ちます。
専門家への相談とプラン設計
退職金は金額が大きいからこそ、独断で全額を投資や消費に回すのはリスクがあります。信頼できるファイナンシャルプランナーや金融機関に相談し、老後のライフプランや資金計画を踏まえた活用方法を設計することが大切です。退職金の一部は生活防衛資金として安全資産に置き、残りを長期投資や返済に分散させると安心です。

退職金は一度受け取るとやり直しがきかない資金ですから、まずは生活を守る部分を確保してから、余剰分を投資や返済に回すのが基本ですよ。焦らずに、ライフプラン全体を見据えた活用を心がけてください
退職金制度がない場合の対策
退職金制度は法律で義務付けられているものではなく、導入していない企業も一定数存在します。特に中小企業やサービス業では制度がないケースも多く、老後の資金形成を自分で工夫する必要があります。ここでは、退職金がない場合に備えるための具体的な方法を整理します。
勤務先の制度有無を正しく把握する
まずは自分の勤務先に退職金制度があるのかを確認しましょう。就業規則には必ず記載されているため、イントラネットや人事部門で確認できます。制度がない場合でも「前払い退職金制度」といって、毎月の給与や賞与に退職金相当額を上乗せする形で支給している企業もあります。その場合は退職時にまとまった金額はもらえませんが、在職中に収入を多めに得られる仕組みです。
自助努力で退職金を設計する方法
退職金制度がない企業に勤めている人は、自ら老後資金を積み立てる仕組みを構築することが重要です。代表的な方法は次の通りです。
iDeCo(個人型確定拠出年金)
自分で掛金を拠出し、金融商品を運用して積み立てる制度です。掛金は全額所得控除となり、運用益も非課税なので節税効果が大きいのが特徴です。60歳以降まで原則引き出せない制約はありますが、「強制的に老後資金を確保できる」仕組みとして有効です。
NISA(少額投資非課税制度)
投資信託や株式を非課税で運用できる制度です。iDeCoと異なり途中で解約が可能なため、柔軟に資産を運用できます。2024年からは非課税期間が恒久化されたことで、退職金の代替資産形成手段としてさらに注目されています。
個人年金保険
保険会社の商品を利用して60歳以降から定期的に年金を受け取れる仕組みです。生命保険料控除や個人年金保険料控除が利用できるため、税制面でも一定のメリットがあります。元本保証型もあり、投資が不安な方に適しています。
定年後の就労による補完
退職金がない場合、定年後も働いて収入を得るという選択肢も現実的です。在職老齢年金制度の調整を意識しながら働き方を工夫すれば、年金と給与のバランスを取りながら老後資金を補うことができます。
制度を組み合わせて不足を補う
退職金制度がないからといって、老後資金が必ず不足するわけではありません。iDeCoで長期積立を行い、NISAで流動性を確保し、必要に応じて個人年金保険を活用するなど、複数の制度を組み合わせておくことで退職金代わりの資産形成が可能になります。

退職金制度がなくても、焦らずに「仕組みで貯める」ことを考えてください。給与の一部を計画的に積み立て、節税制度を活用すれば、将来的に退職金に近い資金を自分でつくれますよ
| 順位 | サービス名 | ポイント | 料金 | タイプ | 代行内容 | 支払いタイミング | 支払い方法 | 対応時間 | 対応エリア | LINE対応 | 弁護士の監修 | 書類テンプレート | 追加料金なし | 返金保証 | 転職支援 | LINE公式の自動回答機能 | 分割払い対応 | 対応内容の質 | 料金の安さ | サービスの多さ | 対応時間の長さ | 総合 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 退職代行トリケシ | 訴訟非対応だが、深夜でも自動チャットで疑問をすぐに解決 | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、モバイル決済、あと払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 2.93 | 5.00 | 5.00 | 3.70 | 退職代行トリケシ 公式サイト | |||||||
| 2位 | リーガルジャパン | 有給取得や書類対応に強み。LINEで簡単に退職手続きが可能 | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成 | 前払い | クレジットカード、銀行振込、モバイル決済 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 2.77 | 2.93 | 4.00 | 5.00 | 3.67 | リーガルジャパン 公式サイト | |||||||
| 3位 | 退職代行モームリ | LINEで完結&低価格。実務に強い信頼の代行サービス | 12,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、Paidy、モームリあと払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 3.77 | 4.00 | 5.00 | 3.99 | 退職代行モームリ 公式サイト | |||||||
| 4位 | 退職代行オイトマ | 交渉が必要なら頼れる一社。後払いで不安を抑えて依頼可能 | 24,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、Paidy | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.88 | 4.00 | 5.00 | 3.19 | 退職代行オイトマ 公式サイト | |||||||
| 5位 | 退職代行ニコイチ | 有給交渉に強いが、サービス範囲の確認は事前に必要 | 27,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込、モバイル決済 | 7:00〜23:30(年中無休) | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.13 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 退職代行ニコイチ 公式サイト | |||||||
| 6位 | 退職代行 | 法的対応が必要な方に最適。費用や連絡手段には注意が必要 | 27,500円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (成功報酬として20%+税が発生) | 4.45 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.86 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 7位 | 退職代行ローキ | 弁護士と労働組合のWサポートで、法的にも安心して退職できる | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成、未払い給与・残業代の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ローキ分割払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 4.52 | 2.93 | 5.00 | 5.00 | 4.36 | 退職代行ローキ 公式サイト | |||||||
| 8位 | 退職代行 | 訴訟にも対応可能。コスパ重視の本格派弁護士サービス | 12,000円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | (未払い給与・未払い退職金の支払い請求、パワハラ慰謝料請求の成功報酬代として、経済的利益の22%(税込※裁判外の請求) | 4.45 | 3.77 | 2.00 | 5.00 | 3.80 | 退職代行 公式サイト | ||||||
| 9位 | 退職代行 | 法的対応も含めてLINEで完了。費用と安心のバランスが秀逸 | 25,000円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 5.00 | 1.63 | 2.50 | 5.00 | 3.53 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 10位 | 辞めるんです | 使いやすいLINE完結型。料金の明瞭さが高評価の理由 | 27,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 1.13 | 3.00 | 5.00 | 3.08 | 辞めるんです 公式サイト | |||||||
| 11位 | 退職代行プラスサービス | 費用は安いが、LINE機能やサポート体制にはやや物足りなさも | 16,280円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 3.33 | 3.00 | 5.00 | 3.30 | 退職代行プラスサービス 公式サイト | |||||||
| 12位 | 退職代行EXIT(イグジット) | 業界初の老舗ブランド。低料金が魅力だが後払いには非対応 | 20,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 2.88 | 3.00 | 5.00 | 3.19 | 退職代行EXIT(イグジット) 公式サイト | |||||||
| 13位 | 退職代行サラバ(SARABA) | 費用は安めだが、支払い案内が早く安心感にやや欠ける | 24,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 1.88 | 2.50 | 5.00 | 3.14 | 退職代行サラバ(SARABA) 公式サイト | |||||||
| 14位 | 退職代行Jobs | LINEで完結&後払い対応。気軽に相談しやすい安心設計 | 27,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、Paidy | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.13 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 退職代行Jobs 公式サイト | |||||||
| 15位 | 退職代行 | 労組ならではの交渉力。安心して実務を任せられる体制 | 18,700円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 8:00〜21:00 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 2.77 | 3.08 | 2.00 | 3.00 | 2.71 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 16位 | ネクストステージ | 費用を抑えてLINEで完結。交渉が不要な人に適したサービス | 15,000円~ | 民間業者 | 退職意思の伝言 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.00 | 3.46 | 4.00 | 5.00 | 3.37 | ネクストステージ 公式サイト | |||||||
| 17位 | やめたらええねん | LINE完結で格安。費用重視派におすすめの選択肢 | 16,500円~ | 民間業者 | 退職意思の伝言 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.00 | 3.31 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | やめたらええねん 公式サイト |