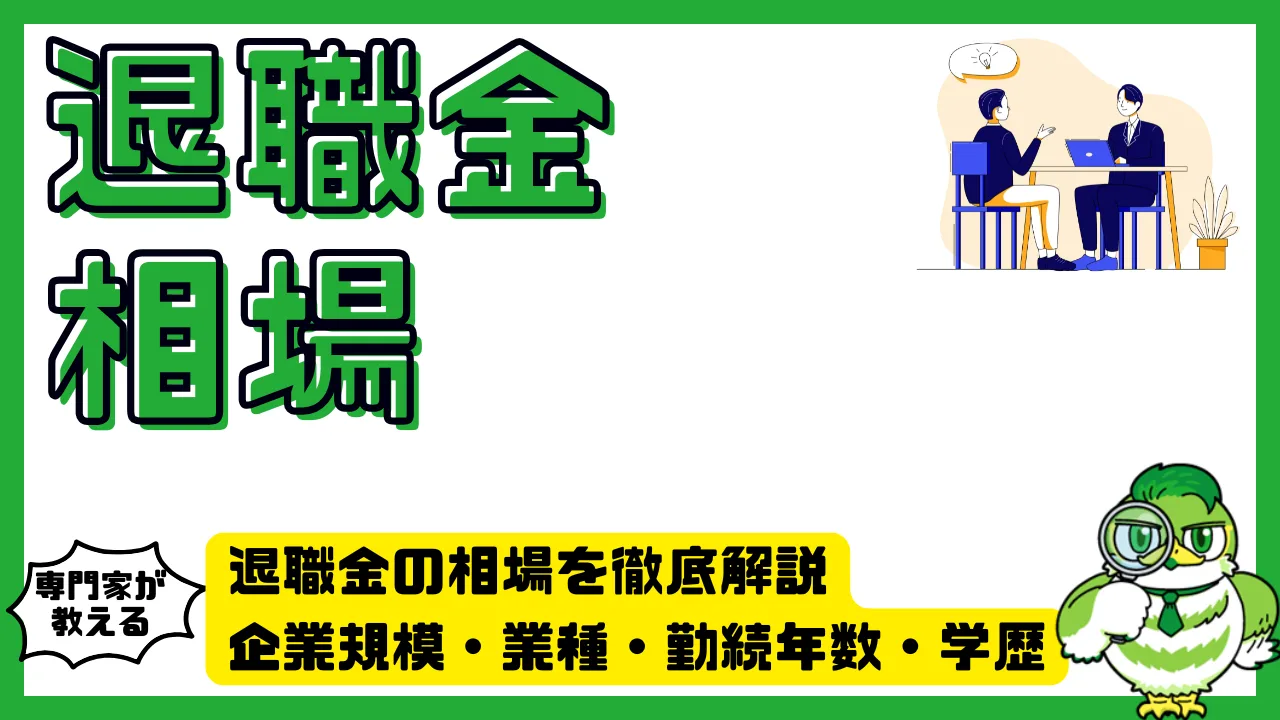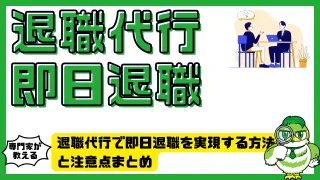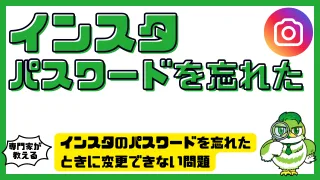本ページはプロモーションが含まれています。
目次
近年の退職金事情と全体的な傾向
退職金制度の減少傾向
かつては多くの企業が当然のように導入していた退職金制度ですが、近年は制度そのものを持たない企業が増えています。厚生労働省の調査でも、制度を設けている企業の割合は2000年代から徐々に減少しており、導入率は70%台にとどまっています。特に中小企業では資金繰りの難しさから、退職金制度を縮小または廃止するケースが目立っています。
支給額の平均値の低下
制度が残っている場合でも、支給額の水準は長期的に下がり続けています。2000年代初頭と比較すると数百万円規模での減額が進んでおり、老後資金としての期待値が低下しているのが現実です。背景には、企業の業績変動や低金利環境による積立金運用の難しさがあり、退職金を十分に準備できない企業が増えています。
成果主義型への移行
従来の年功序列型から、成果や役職に応じて退職金額を決定する仕組みへ移行する企業が増加しています。特にポイント制や別テーブル制を導入する企業が多く、単純に勤続年数だけで評価されるのではなく、在職中の役割や実績によって差が出やすくなっています。この流れにより、同じ勤続年数でも受け取れる退職金額の格差が広がっています。
確定拠出年金型制度の拡大
企業型確定拠出年金(DC)の導入が進んでいるのも近年の特徴です。企業が掛金を拠出し、従業員が自ら運用先を選ぶ仕組みのため、将来の退職金額は運用成果に左右されます。従業員自身の投資リテラシーが受け取る金額に直結するため、従来型の「保証された退職金」とは大きく性質が異なります。
老後資金の自己防衛の必要性
このような背景から、退職金だけで老後の生活資金を賄うのは難しくなっています。企業に依存せず、iDeCoやNISAなどを通じて自分で資産形成を進めることが一般的になりつつあります。退職金制度は今後も縮小傾向が続くと予想されるため、早めの準備が重要です。

退職金は昔よりもらえる額が減ってきていて、制度そのものを持たない会社も増えています。その一方で成果主義型や確定拠出年金型にシフトする流れが強まっているんですね。だからこそ「会社任せ」ではなく、自分自身でも老後資金を計画的に準備しておくことが大切なんです
退職金相場を決める主な要因
退職金の支給額は一律ではなく、複数の要素が組み合わさって決定されます。ここでは代表的な要因を整理して解説します。
企業規模による影響
大企業と中小企業では、資金力や福利厚生制度の充実度に大きな差があり、退職金額にも格差が生じます。一般的に資本金や従業員数が多い企業は退職金制度が整っており、平均額も高めです。一方で、中小企業は経営資源に限りがあるため、大企業と比べると支給額が低くなる傾向があります。
業種ごとの水準
所属する業界によっても退職金の相場は異なります。金融・保険業のように収益性が高く利益率の大きい業界は水準が高い傾向があります。逆に、医療・福祉やサービス業など、収益構造が安定しにくい業種では退職金額が低いケースが多く見られます。業界特性が従業員への還元度合いに直結しているといえます。
勤続年数と学歴の影響
勤続年数が長いほど、企業への貢献度が評価され退職金は増加します。定年まで勤め上げた場合と数年で退職した場合では、支給額に数百万円から数千万円の差が出ることもあります。また学歴も一因で、大学卒や大学院卒は初任給や昇給幅が高いため、基本給連動型の退職金制度では高卒よりも支給額が多くなる傾向があります。
退職理由による差
退職理由によっても退職金額は大きく変動します。定年退職や会社都合退職では比較的高額が支給されるのに対し、自己都合退職は減額されることが一般的です。さらに懲戒解雇の場合は、規定により支給ゼロとなることもあります。円満な退職であるかどうかが金額に直結するため、注意が必要です。

退職金は「企業規模」「業種」「勤続年数・学歴」「退職理由」が主な決定要因になります。自分がどの立場にあてはまるかを整理すれば、将来の受け取り額をより現実的にシミュレーションできますよ
企業規模別に見る退職金の相場
退職金の支給額は企業規模によって大きな差があります。資金力の豊富な大企業ほど高水準の退職金を支給できる傾向があり、中小企業は制度の有無や金額に幅があるのが現実です。ここでは、大企業と中小企業の相場を整理し、さらに従業員数ごとの違いも解説します。
大企業の退職金相場
厚生労働省の調査によると、資本金5億円以上または従業員1,000人以上の大企業では、定年退職者の退職金が平均して2,000万円を超える水準です。大学卒・総合職では2,200万円前後、高校卒でも2,000万円を超えるケースが一般的とされています。豊富な財務基盤や福利厚生制度が整っているため、長期勤続者に対して手厚い給付が行われることが特徴です。
中小企業の退職金相場
一方、中小企業(従業員10〜299人規模)では相場が大きく下がります。東京都産業労働局のデータによれば、大学卒でおおよそ1,100万円前後、高校卒では1,000万円を下回る水準が平均です。大企業と比較すると約2倍近い差があり、同じ勤続年数でも受け取れる金額に大きな格差が生じます。中小企業では退職金制度そのものがない場合もあり、退職後の資金設計で不安を抱える方が少なくありません。
従業員数ごとのモデル退職金
中小企業をさらに細分化すると、従業員規模の違いでも差が表れます。例えば、大学卒・定年退職の場合のモデル退職金は、従業員100~299人規模で約1,300万円、50~99人規模で約1,100万円、10~49人規模では1,000万円を下回る水準です。規模が小さくなるほど退職金の原資を確保するのが難しくなり、支給額も縮小する傾向があります。
企業規模が与える影響
退職金は単なる一時金ではなく、企業の体力や人材への投資姿勢を反映しています。大企業は制度が安定しており、将来の見通しが立てやすいのに対し、中小企業では「制度があるかどうか」「自己都合退職でも支給されるか」といった条件を事前に確認することが非常に重要です。

企業の規模によって、退職金は2倍以上の差がつくこともあります。自分がどの水準に該当するのか早めに把握して、老後資金計画に組み込んでおくことが大切ですよ
業界別に見る退職金の相場
退職金の水準は、所属する業界によって大きく異なります。業界ごとの収益構造や人材確保の必要性が背景にあり、同じ勤続年数や学歴であっても、受け取れる退職金額には数百万円以上の差が生じることがあります。以下では、主な業界ごとの相場感と特徴を解説します。
金融・保険業
最も退職金が高水準とされる業界です。大卒定年退職で1,400万円を超えるケースが平均的に見られ、会社都合の場合はさらに増える傾向があります。金融や保険は収益性が高く、優秀な人材を長期的に確保する目的から、退職金制度も手厚く設計されているのが特徴です。
建設業
建設業も比較的高い相場を維持しています。大卒定年時で約1,200万円前後となり、長期のプロジェクトに関わる従業員の貢献を反映した水準といえます。人手不足が慢性的な業界であるため、退職金を人材確保のインセンティブとして活用している企業が多いことも背景にあります。
情報通信業
ITや通信分野は、近年の成長産業として水準が上昇傾向にあります。大卒で定年退職する場合は約1,190万円が平均で、特に大手の通信会社やSIerではさらに高額になるケースもあります。人材流動性が高いため、長期的に勤めてもらう目的で退職金制度を厚めに設計する企業が目立ちます。
運輸・郵便業
運輸・郵便業も比較的高めで、大卒定年退職で1,300万円を超えるデータがあります。人員規模が大きく、業務の安定性もあるため、福利厚生として退職金がしっかり支給されやすい業界です。
製造業
日本の産業を支える主要分野ですが、退職金相場は中堅的な水準です。大卒定年退職で1,060万円前後とされ、企業規模による差が大きいのが特徴です。大企業では2,000万円近いケースもある一方、中小製造業では半分程度にとどまることもあります。
医療・福祉業
業界の中で最も低水準となるのが医療・福祉分野です。大卒定年退職でも300万円台にとどまるケースが多く、財源の制約や公定価格制度が影響しています。介護職や福祉職は人材確保の課題を抱える一方で、退職金水準が低いため、労働者にとっては厳しい現状といえます。
不動産・物品賃貸業
不動産業界は業績の波が大きいため、退職金水準も業界内でばらつきがあります。大卒定年退職で1,000万円前後が平均ですが、好調な企業とそうでない企業での差が顕著です。業績連動型の退職金制度を採用するケースも見られます。
教育・学習支援業
学校教育以外の教育・学習支援分野では、大卒定年退職で1,200万円を超える水準が確認されています。人材育成を担う性質上、安定的に働いてもらうための待遇が整えられている場合が多いのが特徴です。

業界ごとの退職金相場は、会社の収益力や人材戦略に直結しているんですね。金融・保険や情報通信などの高収益業界は退職金も高く、医療・福祉のように制度的に財源が限られる業界では低水準にとどまります。自分が働く業界の特徴を理解しておくことが、将来のライフプランを考えるうえで大切ですよ
勤続年数別に見る退職金の相場
退職金は「どれだけ長く勤務したか」が大きな判断基準になります。勤続年数が短い場合は退職金が少なく、長く勤めるほど大きくなるのが一般的な傾向です。ここでは公的調査をもとに、勤続年数別の目安を整理します。
勤続3〜5年
入社から数年で退職した場合、退職金はあまり大きな金額にはなりません。
東京都産業労働局のデータでは、自己都合退職で 20万〜50万円程度、会社都合でも 30万〜70万円程度が相場となっています。退職金規定によっては「勤続3年以上から支給」と定めている企業もあるため、短期退職の場合は無支給のケースも珍しくありません。
勤続10〜20年
10年以上になると退職金は一気に増え始めます。
10年勤務で 100万〜150万円程度、20年勤務になると 300万〜400万円台に達するケースが一般的です。企業によっては役職や昇給によって加算される仕組みがあり、中堅層に差がつきやすいのもこの時期の特徴です。
勤続30年以上
30年以上勤め上げた場合、退職金は一つの大台に乗ります。
中小企業の場合でも 600万〜750万円前後、大企業では 1,500万〜2,000万円以上が支給されることもあります。定年退職の場合は特に金額が大きく、自己都合退職との差も顕著です。長期的に勤務し、役職に就いていたかどうかで金額に大きな差が生まれます。
勤続年数と退職理由の関係
同じ勤続年数でも「自己都合」か「会社都合」かによって差が出ます。一般的には会社都合の方が多めに支給され、長期勤続者が人員整理などで退職する際には割増金が加算される場合もあります。
一方、自己都合退職では減額されることが多く、特に短期間での退職では無支給や低額支給となるリスクがあります。

勤続年数が長いほど退職金は着実に増えていきます。ただし「自己都合か会社都合か」「大企業か中小企業か」で大きな違いが出るので、自分の立場をよく確認しておくことが大切ですよ
学歴別に見る退職金の違い
退職金の金額は企業規模や業種、勤続年数だけでなく、学歴によっても差が生じます。これは入社時点での初任給水準やキャリアの進み方が異なることに起因しています。特に「最終学歴と勤続年数の掛け合わせ」によって、大きな違いが出る点が特徴です。
大学卒と高校卒の差
厚生労働省や地方自治体の調査によると、大企業における大学卒の定年退職時の退職金平均はおおよそ2,200万円前後、高校卒は約2,000万円程度となっています。中小企業の場合は大学卒で1,090万円前後、高校卒で990万円程度とされ、どの規模の企業でも大学卒が高めの傾向です。これは基本給が学歴によって異なるため、退職金計算式に直接反映されるためです。
高専・短大卒の位置づけ
高専・短大卒は、大学卒と高校卒の中間に位置し、モデル退職金では大学卒より低いが高校卒よりやや高めとなるケースが多いです。特に中小企業では高専・短大卒が定年まで勤めた場合、退職金はおよそ980万円前後とされています。
勤続年数との関係
学歴による退職金格差は「勤続年数」が長いほど広がりやすくなります。大学卒は入社時点の給与水準が高く、昇給や役職の進展スピードも速いため、定年時の退職金で大きな差につながります。一方で高校卒は早く就業を開始する分、勤続年数が長くなる傾向があり、その結果として短大卒よりも退職金が多くなる逆転現象も一部で見られます。
学歴差が生まれる背景
- 初任給水準の違い
- 基本給を基礎とする計算方式の影響
- 昇進スピードの差
- 勤続年数の長さによる逆転現象
退職金は「学歴だけ」で決まるものではなく、勤続年数や企業規模との組み合わせで最終額が大きく変わる点を押さえておくことが重要です。

学歴が高いほど退職金も増える傾向がありますが、必ずしも学歴だけで一方的に差がつくわけではありません。勤続の長さや職務内容、企業の制度設計が大きく関わっているんですよ。自分の立場やキャリアパスを踏まえて、将来の退職金を見積もってみることが大切です
退職金の計算方法と仕組み
退職金は企業ごとに制度や規定が異なりますが、大きく分けると「給与連動型」「定額制」「別テーブル制」「ポイント制」「確定拠出年金(DC)」といった方式があります。仕組みを理解しておくことで、自分の将来の退職金額をシミュレーションしやすくなります。
基本給連動型(給与比例制)
退職時の基本給を基準に、勤続年数や係数を掛け合わせて算出する方式です。例えば「退職金=基本給 × 支給率 × 勤続年数」といった形です。基本給が高いほど退職金も多くなり、役職や昇給による影響が大きいのが特徴です。
定額制
勤続年数や退職理由に応じて、あらかじめ定められた一定額を支給する方式です。年功的要素が強く、同じ年数を働けばほぼ同額を受け取れるシンプルな仕組みです。業績や給与水準に左右されにくい点が特徴ですが、近年は導入企業が減っています。
別テーブル制
役職や職種、退職理由などを細かく区分した表に基づいて金額を決定する方式です。例えば「課長職で30年勤続・定年退職」といった条件に応じて金額が決まります。企業規模が大きいほど複雑なテーブルが採用される傾向があります。
ポイント制
近年増えているのが、勤続年数・役職・資格・業績などを「ポイント」として積み上げ、その合計にポイント単価を掛けて退職金額を算出する方法です。「退職金=累計ポイント × ポイント単価 × 支給率」という形で計算されます。成果や能力を反映しやすい反面、想定額が分かりにくい点もあります。
確定拠出年金(DC)
企業が毎月一定額を拠出し、従業員が投資信託や預金などで運用する制度です。将来の退職金額は運用成績次第で増減します。会社は支払い額を確定でき、従業員は投資の知識や自己責任で運用する必要があります。運用次第では大きく増える可能性もありますが、リスク管理が必須です。
成果主義型の広がり
年功序列的な計算方式から、成果主義型やポイント制に移行する企業が増えています。これは人件費の抑制や成果重視の評価制度の一環であり、従業員にとっては勤続年数だけでなく成果も大きく影響するようになっています。

退職金の仕組みは会社ごとに大きく異なるんですね。基本給や勤続年数に比例する方式もあれば、成果や運用成果によって将来の金額が変わる方式もあります。自分の勤め先の規定を必ず確認し、どの仕組みで計算されるのか理解しておくことが、老後資金を見積もる第一歩ですよ
退職金にかかる税金と手取り額の実態
退職金は老後の生活を支える大切な資金ですが、そのまま全額が手元に残るわけではなく、税金がかかります。制度を正しく理解することで、受け取り額を最大化することができます。
退職金にかかる税金の仕組み
退職金を一括で受け取る場合は「退職所得」に分類され、所得税と住民税が課されます。ただし、給与と同じ扱いではなく「退職所得控除」という大きな優遇制度があるため、税負担は軽減されます。
- 退職所得控除額
- 勤続20年以下:40万円 × 勤続年数(最低80万円)
- 勤続20年超:800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)
控除額を差し引いた残りの金額の1/2に対してのみ課税されるため、長く勤めるほど税負担が大幅に減る仕組みになっています。
一時金受け取りと年金受け取りの違い
退職金は「一時金」「年金」「併用」の3つの方法で受け取れます。受け取り方によって税金の扱いが変わるため、手取り額に差が出ます。
- 一時金受け取り
- 大きな退職所得控除が適用される
- 勤続年数が長いと、退職金の大部分が非課税になるケースも多い
- 「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出すれば、源泉徴収で完結し確定申告不要
- 年金受け取り
- 「公的年金等控除」が適用される
- 毎年の所得と合算して課税されるため、他の収入があると税負担が増えることもある
- 医療費控除やふるさと納税を利用する場合は、確定申告をした方が還付を受けられる可能性あり
- 併用型
- 一部を一時金で受け取り、残りを年金で受け取る
- 退職所得控除と公的年金等控除を併用できるが、全体的な税負担は年ごとの所得状況に左右されやすい
手取り額を最大化するための工夫
- 受け取り方を一括か年金かでシミュレーションし、税金が少なく済む方法を選ぶ
- 「退職所得の受給に関する申告書」を必ず提出して、不要な確定申告を避ける
- 医療費控除や寄附金控除を活用して税還付を狙う
- 将来の生活費計画に合わせて、一括でまとまった資金を得るか、年金で安定収入を得るかを判断する

退職金にかかる税金は複雑に見えますが、控除を使えば想像以上に手取りが残ります。大切なのは、自分の勤続年数や受け取り方法に応じて「どのくらい税金が引かれるのか」を事前に確認しておくことです。これを理解しておけば、退職後の資金計画に余裕を持って臨めますよ
| 順位 | サービス名 | ポイント | 料金 | タイプ | 代行内容 | 支払いタイミング | 支払い方法 | 対応時間 | 対応エリア | LINE対応 | 弁護士の監修 | 書類テンプレート | 追加料金なし | 返金保証 | 転職支援 | LINE公式の自動回答機能 | 分割払い対応 | 対応内容の質 | 料金の安さ | サービスの多さ | 対応時間の長さ | 総合 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 退職代行トリケシ | 訴訟非対応だが、深夜でも自動チャットで疑問をすぐに解決 | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、モバイル決済、あと払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 2.93 | 5.00 | 5.00 | 3.70 | 退職代行トリケシ 公式サイト | |||||||
| 2位 | リーガルジャパン | 有給取得や書類対応に強み。LINEで簡単に退職手続きが可能 | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成 | 前払い | クレジットカード、銀行振込、モバイル決済 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 2.77 | 2.93 | 4.00 | 5.00 | 3.67 | リーガルジャパン 公式サイト | |||||||
| 3位 | 退職代行モームリ | LINEで完結&低価格。実務に強い信頼の代行サービス | 12,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、Paidy、モームリあと払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 3.77 | 4.00 | 5.00 | 3.99 | 退職代行モームリ 公式サイト | |||||||
| 4位 | 退職代行オイトマ | 交渉が必要なら頼れる一社。後払いで不安を抑えて依頼可能 | 24,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、Paidy | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.88 | 4.00 | 5.00 | 3.19 | 退職代行オイトマ 公式サイト | |||||||
| 5位 | 退職代行ニコイチ | 有給交渉に強いが、サービス範囲の確認は事前に必要 | 27,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込、モバイル決済 | 7:00〜23:30(年中無休) | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.13 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 退職代行ニコイチ 公式サイト | |||||||
| 6位 | 退職代行 | 法的対応が必要な方に最適。費用や連絡手段には注意が必要 | 27,500円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (成功報酬として20%+税が発生) | 4.45 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.86 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 7位 | 退職代行ローキ | 弁護士と労働組合のWサポートで、法的にも安心して退職できる | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成、未払い給与・残業代の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ローキ分割払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 4.52 | 2.93 | 5.00 | 5.00 | 4.36 | 退職代行ローキ 公式サイト | |||||||
| 8位 | 退職代行 | 訴訟にも対応可能。コスパ重視の本格派弁護士サービス | 12,000円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | (未払い給与・未払い退職金の支払い請求、パワハラ慰謝料請求の成功報酬代として、経済的利益の22%(税込※裁判外の請求) | 4.45 | 3.77 | 2.00 | 5.00 | 3.80 | 退職代行 公式サイト | ||||||
| 9位 | 退職代行 | 法的対応も含めてLINEで完了。費用と安心のバランスが秀逸 | 25,000円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 5.00 | 1.63 | 2.50 | 5.00 | 3.53 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 10位 | 辞めるんです | 使いやすいLINE完結型。料金の明瞭さが高評価の理由 | 27,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 1.13 | 3.00 | 5.00 | 3.08 | 辞めるんです 公式サイト | |||||||
| 11位 | 退職代行プラスサービス | 費用は安いが、LINE機能やサポート体制にはやや物足りなさも | 16,280円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 3.33 | 3.00 | 5.00 | 3.30 | 退職代行プラスサービス 公式サイト | |||||||
| 12位 | 退職代行EXIT(イグジット) | 業界初の老舗ブランド。低料金が魅力だが後払いには非対応 | 20,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 2.88 | 3.00 | 5.00 | 3.19 | 退職代行EXIT(イグジット) 公式サイト | |||||||
| 13位 | 退職代行サラバ(SARABA) | 費用は安めだが、支払い案内が早く安心感にやや欠ける | 24,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 1.88 | 2.50 | 5.00 | 3.14 | 退職代行サラバ(SARABA) 公式サイト | |||||||
| 14位 | 退職代行Jobs | LINEで完結&後払い対応。気軽に相談しやすい安心設計 | 27,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、Paidy | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.13 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 退職代行Jobs 公式サイト | |||||||
| 15位 | 退職代行 | 労組ならではの交渉力。安心して実務を任せられる体制 | 18,700円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 8:00〜21:00 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 2.77 | 3.08 | 2.00 | 3.00 | 2.71 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 16位 | ネクストステージ | 費用を抑えてLINEで完結。交渉が不要な人に適したサービス | 15,000円~ | 民間業者 | 退職意思の伝言 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.00 | 3.46 | 4.00 | 5.00 | 3.37 | ネクストステージ 公式サイト | |||||||
| 17位 | やめたらええねん | LINE完結で格安。費用重視派におすすめの選択肢 | 16,500円~ | 民間業者 | 退職意思の伝言 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.00 | 3.31 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | やめたらええねん 公式サイト |