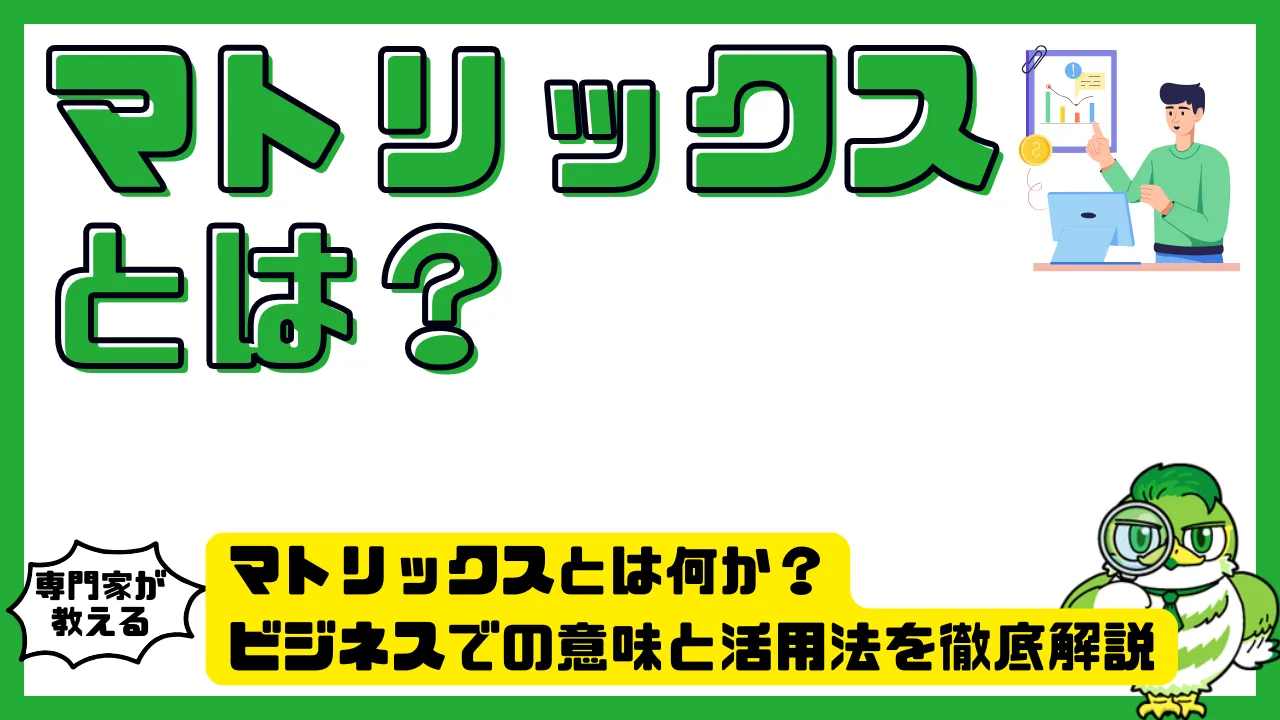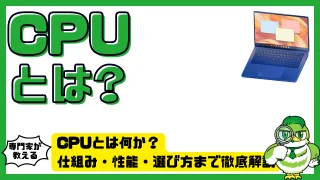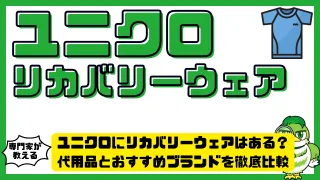本ページはプロモーションが含まれています。
目次
マトリックスの意味とビジネスでの使われ方
「マトリックス」の語源と基本定義
「マトリックス(matrix)」という言葉は、もともと「母体」や「基盤」を意味するラテン語に由来しています。数学的には「行列」と訳され、縦と横に要素を配置した表を指します。ビジネスではこの行列構造を応用し、情報を視覚的に整理・比較できるツールとして活用されます。
たとえば、縦軸に「市場の成長性」、横軸に「自社のシェア」を配置したマトリックスでは、自社製品のポジションを4象限で分類できます。このように、複数の観点を掛け合わせて分析するための「構造」そのものがマトリックスの基本概念です。
ビジネスにおける2つの主要な文脈
ビジネスで「マトリックス」という言葉が使われる文脈は主に2つあります。
1. 情報整理のための図表(マトリックス図)
ビジネス戦略やマーケティングで多用される「マトリックス図」は、情報を2軸で分類することで、課題の全体像や優先順位を視覚的に把握できるフレームワークです。たとえば、「SWOT分析」や「アイゼンハワーマトリックス」などがその代表例です。
この図表の強みは以下の点にあります。
- 複雑な情報を構造化できる
- 抜け漏れや重複を防げる
- 判断基準を可視化できる
- 議論や意思決定の共通言語になる
2. 組織構造としての「マトリックス組織」
もうひとつは「マトリックス組織」という管理手法です。これは、部門別(機能別)とプロジェクト別(製品・地域など)の2つの指揮系統を掛け合わせた複合的な組織形態を指します。
たとえば、マーケティング部門の社員が、同時に新製品プロジェクトにも属しているようなケースです。この構造によって、柔軟性や専門性の活用が進む一方で、指揮命令系統の複雑化という課題も生まれます。
このように、マトリックスは「情報の整理手法」としても「組織管理のフレーム」としても用いられており、目的に応じて使い分けることが重要です。
「マトリクス」との表記揺れ
「マトリックス」と「マトリクス」は、どちらも英語の「matrix」のカタカナ表記ですが、意味や用途は基本的に同じです。ビジネス領域では「マトリックス」という表記の方が一般的に使われています。企業の研修資料や業界書籍でも「マトリックス組織」「SWOTマトリックス」といった形で広く定着しています。
一方で、工学・理数系の文脈では「マトリクス」と表記される場合もあり、用途によって表記の傾向が異なることを覚えておくと便利です。

マトリックスは「ただの図」じゃなく、考えを整理して伝えるための“思考の補助線”なんじゃ。うまく使えば、情報も議論も驚くほどスッキリまとまるぞ
マトリックスが注目されるビジネス上の理由
マトリックスは、単なる図表以上に、ビジネスの複雑な意思決定や戦略策定を支える「思考の枠組み」として注目されています。特に、営業活動やマーケティング、業務改善の現場で効果を発揮しやすく、次のような理由から活用が広がっています。
複雑な情報を視覚的に整理できる
ビジネス課題は、複数の要素が絡み合っていることが多く、口頭やテキストだけでは全体像を把握しにくくなります。マトリックスを使えば、縦軸と横軸の組み合わせで情報を二次元的に整理でき、全体構造が一目でわかるようになります。
- 市場ポジションの比較(例:価格×品質)
- タスクの分類(例:重要度×緊急度)
- 顧客層の特性分析(例:年齢×購買頻度)
直感的な理解を促し、意思決定のスピードを上げることができます。
抜け漏れや偏りを防げる
要素を軸に沿ってマトリックス上に展開することで、必要な視点を強制的に網羅することができます。これにより、分析や戦略立案の際にありがちな「思いつき」や「感覚頼り」の判断から脱却できます。
- SWOTマトリックスでは4つの視点(強み・弱み・機会・脅威)をバランスよく検討
- PPMではプロダクト全体のバランスを可視化し、リソースの再配分に役立つ
多面的な視点をもたらすため、思考の穴をふさぐフレームワークとして有効です。
優先順位や対応策が明確になる
マトリックスは、縦横軸の組み合わせによって要素を分類し、「どこに注力すべきか」が視覚的に明確になります。
- 緊急度×重要度のマトリックスでは、今すぐ着手すべき業務を明示
- 市場成長率×シェアのマトリックスでは、成長戦略の方向性が見える
抽象的な議論に終始せず、行動につなげやすくなるのが大きな特徴です。
チーム間の認識を統一しやすい
会議やプロジェクトでの意思共有において、マトリックスは強力な「共通言語」として機能します。視覚化された図をもとに議論を進めることで、言葉の定義のズレや誤解を最小限に抑えられます。
- メンバーごとの思考整理が進む
- 説得材料としての説得力が増す
- 合意形成までの時間を短縮できる
特に異なる立場のメンバー(営業・開発・マーケなど)が関わる場面で効果的です。
あらゆる業務領域に応用できる汎用性がある
マトリックスは、業界や部門に関係なく使える点でも優れています。営業施策、製品戦略、リスク分析、リーダー育成まで、あらゆる場面で活用されています。
- 営業:顧客セグメント×提案内容で営業戦略を最適化
- 開発:課題のインパクト×対応コストで優先順位を設定
- 人事:社員のスキル×意欲で人材配置を最適化
「図にすれば見える」「見えれば動ける」——そんな発想を支えるツールとして、多くの現場に浸透しています。

マトリックスは、思考を整理するだけでなく“行動を引き出す図解の力”を持っています。複雑さに直面したとき、まずは軸を決めてマトリックスで分解してみましょう。それが突破口になります
マトリックス図の主な種類と特徴
マトリックス図は、複雑な情報を二次元上に整理して視覚化するための有力なビジネスツールです。ここでは、営業やマーケティング、経営戦略に活用される代表的なマトリックス図の種類と、それぞれの特徴を紹介します。
L型マトリックス
縦軸と横軸に要素を設定し、それらの交点に関連情報を記入する基本的な形式です。
特徴は以下の通りです。
- 情報の対応関係を一目で確認できる
- タスク管理や機能分解、要件定義などで活用される
- 情報が増えても構造が崩れにくい
例:部門×課題の整理表、製品×顧客ニーズの対応表
4象限マトリックス
2つの評価軸を基に、マトリックス内を4つの象限に分けて情報を整理します。
優先順位や戦略決定に特に効果的です。
- 重要度と緊急度などの“対極評価”に適している
- 各象限で意思決定や行動方針が明確になる
- 縦軸と横軸の設定次第で柔軟にカスタマイズ可能
例:アイゼンハワーマトリックス(緊急度×重要度)
ポジショニングマップ型
相対的な立ち位置や競争環境を視覚化する際に用いられるマトリックスです。
主にマーケティングや戦略立案の現場で活用されます。
- 自社や競合のポジションを直感的に把握できる
- 定量的・定性的な両軸での分析が可能
- ブランド認知度×品質評価などの組み合わせで使われる
例:競合比較マップ、ブランドポジション分析
マッピングマトリックス
4象限構造をベースに、要素を図上にプロットして分布や関係性を表現する図です。
特に製品分析や市場分析に強みを持ちます。
- 要素の密集・分散状況を直観的に捉えやすい
- 各要素のサイズや重みを視覚的に反映可能
- 要素同士の距離感・関連性を把握しやすい
例:BCGマトリックス、PPM分析
DMM(Design Matrix Map/機能展開マトリックス)
中心に分析対象(機能・課題)を配置し、それを8方向から細分化・分析していく9ブロック型のマトリックスです。
- 製品や業務の階層的構造の把握に適している
- 複雑な要素を漏れなく整理できる
- 分析の初期段階での構造把握や要素洗い出しに有効
例:製品開発時の機能要件分析、プロセスの整理

どのマトリックスを選ぶかは、整理したい情報の性質や目的によって決まります。焦らず「何を伝えたいのか」を軸に考えれば、自然と適した形式が見えてきますよ
ビジネスで使える代表的なマトリックスフレームワーク
ビジネスシーンでは、複雑な状況を整理し、戦略的な意思決定を行うためのフレームワークとして、マトリックス図が数多く活用されています。ここでは、営業戦略や経営判断に特に有効な7つの代表的マトリックスフレームワークを紹介します。
SWOT分析
企業の内部環境と外部環境を整理し、自社の現状を可視化する基本フレームワークです。
- 縦軸に「強み(Strength)」「弱み(Weakness)」、横軸に「機会(Opportunity)」「脅威(Threat)」を設定
- 現状把握と戦略立案の起点として汎用性が高く、新規事業や営業戦略立案にも有効
TOWSマトリックス
SWOTの要素を組み合わせて具体的な施策を導き出す応用型マトリックスです。
- 「強み×機会」など4象限の掛け合わせから戦略を具体化
- SWOTの結果を実行可能な行動に変換したいときに最適
アンゾフマトリックス
市場と製品の観点から成長戦略を導くフレームワークです。
- 縦軸に「市場(既存/新規)」、横軸に「製品(既存/新規)」を設定
- 「市場浸透」「市場開拓」「製品開発」「多角化」の4パターンで展開戦略を検討
BCGマトリックス(プロダクト・ポートフォリオ・マネジメント)
事業や製品ごとの資源配分の最適化に用いられるフレームワークです。
- 縦軸に「市場成長率」、横軸に「相対的市場シェア」
- 「花形」「金のなる木」「問題児」「負け犬」の4象限に分類して経営資源の集中判断を行う
GEビジネススクリーン
BCGマトリックスの進化版で、多事業を展開する大企業向けに最適です。
- 縦軸に「業界の魅力度」、横軸に「自社の競争力」
- 9象限に分類し、投資・維持・撤退の判断材料に活用できる
アドバンテージマトリックス
競争環境の構造と自社の戦略タイプを分析するためのフレームワークです。
- 縦軸に「競争の多様性」、横軸に「競争優位の持続性」
- 特にBtoBの営業戦略や業界分析で、競争の本質を見抜くために役立つ
アイゼンハワーマトリックス(重要度・緊急度マトリックス)
日常業務の優先順位整理に最適なマトリックスです。
- 縦軸に「重要度」、横軸に「緊急度」
- タスクの棚卸し、リソース配分、チームマネジメントなどで活用可能

どのマトリックスも“図にして初めて見える真実”があります。課題が整理できないとき、戦略に迷ったときは、まずは2軸で構造化してみましょう。そこから一気に霧が晴れることも多いですよ
マトリックス図の正しい作り方と導入ステップ
マトリックス図をビジネスで効果的に活用するためには、「ただ作る」だけでなく、目的や状況に応じた構成・手順を正しく踏むことが重要です。以下に、実践的な導入ステップと注意点を整理します。
目的を明確にする
マトリックス図は“比較・分類・分析”の道具です。まず「何のために使うのか」「誰に説明するためか」を具体化しましょう。
例:
- 営業施策の優先順位を整理したい
- 経営戦略の意思決定を可視化したい
- タスクを分類してリソースを最適配分したい
目的が曖昧なまま作ると、情報過多・意味不明な図になるリスクが高まります。
マトリックスのスタイルを選ぶ
目的に応じて適した図の型を選びます。
| マトリックス型 | 特徴とおすすめ用途 |
|---|---|
| 4象限マトリックス | 緊急度×重要度、成長率×市場占有率などに最適 |
| テーブル型マトリックス | 属性や評価を整理したいときに便利 |
| ポジショニングマップ型 | 自社や競合の立ち位置、差別化を視覚化したいとき |
| DMM(機能展開マトリックス) | 機能分析・業務プロセス分解に強い |
業務目的に対して「どの構造がもっとも伝わりやすいか」で選定してください。
軸と項目を設定する
マトリックス図の軸は、分析の「基準」となるものです。軸選びに失敗すると、図の説得力が大きく低下します。
設定のポイント:
- 軸は「対になる評価軸」(例:重要度 vs 緊急度)を選ぶ
- 抽象的すぎず、第三者が理解しやすい表現にする
- できるだけ定量評価できる軸(スコアや順位)を使うと精度が高まる
特に営業や戦略においては、感覚や主観でなく、データやファクトに基づく軸設定が不可欠です。
情報を整理して配置する
マトリックス図には、「軸に対する各要素(項目)」を具体的にマッピングしていきます。
- 要素は付箋やメモなどを使って、仮配置から始めると視覚的に整理しやすくなります
- 配置バランスを意識しながら、極端に偏らないよう調整
- 各象限に「何が含まれるのか」を端的に記述することで理解を促進
優先順位や属性分類など、意図した整理軸に合っているかを常に確認しましょう。
最後に伝えるべきメッセージを定める
作っただけで満足してしまいがちなマトリックス図ですが、ビジネスにおいて最も大切なのは「そこから何が言えるか」です。
例:
- 今期注力すべきターゲットセグメントはどこか
- 優先対応すべきタスクはどれか
- 戦略上、リソースをどこに集中させるべきか
1つの図から“複数の結論”を引き出そうとせず、明確な1つの核心メッセージに絞ることが成果につながります。

マトリックスは図じゃない。戦略思考を形にするツールなんだよ。作る過程こそが、チームの認識を揃え、判断を加速するカギになるんだ
マトリックスの活用で成功した企業事例
マトリックスを活用することで、複雑な戦略や情報整理を直感的かつ効果的に行い、成果に直結させている企業は少なくありません。ここでは、営業・事業戦略の場面でマトリックスを導入し、明確な成功を収めた事例を紹介します。
Apple|製品ラインを整理して業績をV字回復
Appleは1997年、スティーブ・ジョブズ氏が経営に復帰したタイミングで深刻な業績不振に陥っていました。当時、製品数は多岐にわたり、消費者にとっても分かりにくい状況でした。そこでジョブズ氏が用いたのが、2×2の「製品マトリックス」です。
- 縦軸:コンシューマー向け/プロ向け
- 横軸:デスクトップ/ポータブル
この4象限に製品戦略を集約し、混乱していたラインナップをわずか4製品に絞りました。結果、ユーザーにとって選びやすいシンプルな製品構成となり、Appleは短期間でブランドイメージと業績の再建に成功しました。
この事例は、「意思決定のシンプル化」と「顧客目線の製品戦略」にマトリックスがいかに有効かを示す典型です。
富士フイルム|アンゾフマトリックスで事業転換に成功
フィルム市場の縮小に直面した富士フイルムは、早い段階から構造転換を進めてきました。ここで活用されたのがアンゾフマトリックスです。
- 既存製品 × 既存市場:インスタントカメラ「チェキ」のリブランディング
- 既存製品 × 新市場:医療分野への写真技術の応用
- 新製品 × 既存市場:写真に関連したスキンケア商品の開発
- 新製品 × 新市場:化粧品ブランド「アスタリフト」などの新規展開
このように4象限に分けた戦略立案により、衰退産業に依存する体制から多角化に成功し、収益の柱を再構築しました。単なる「撤退」ではなく、「既存資産の応用」によって新たな市場での成長機会を創出した点が注目されます。
トヨタ|GEビジネススクリーンでグローバル戦略を強化
トヨタは、複数の事業・地域ごとの優先順位を判断するために、GEビジネススクリーンを活用しています。
- 縦軸:市場魅力度(需要規模、成長性など)
- 横軸:自社の競争力(ブランド力、現地シェアなど)
この9マスのマトリックスで各事業・地域を評価し、重点投資すべきセグメントを明確化。例えば新興国市場ではハイブリッド車より小型車を軸にするなど、限られたリソースを的確に配分し、グローバル展開を加速させました。
マトリックスを「俯瞰」「比較」「選別」の道具として活用したことで、経営戦略の質が向上した事例です。
P\&G|SWOT+TOWSマトリックスで新ブランドの立ち上げに成功
消費財の世界的企業P\&Gでは、新ブランド立ち上げ時にSWOT分析とTOWSマトリックスを組み合わせて戦略構築を行っています。
- 強み(S)× 機会(O):差別化要因となる特許技術を新市場に活用
- 弱み(W)× 脅威(T):認知度不足に対応するプロモーション設計
この分析により、単なる強み・弱みの棚卸しにとどまらず、「どの組み合わせでどんなアクションを取るべきか」という具体的な施策へと落とし込めるようになりました。新製品の市場投入時の成功確率を高めるフレームとして定着しています。

マトリックスは「整理」だけじゃない。正しく使えば、事業の選択と集中、戦略立案、リーダーの意思決定までブレなく進められるようになりますよ
マトリックス活用でよくある失敗と注意点
軸の選定ミスで判断基準がブレる
マトリックスの効果は、縦軸・横軸にどの要素を設定するかで大きく変わります。しかし、軸の選定に失敗すると、判断の土台があいまいになり、実用的な気づきが得られません。
たとえば「顧客の購買意欲」を評価する際に、「購入回数」と「年齢層」を軸にすると、行動と属性が混在してしまい、分析が中途半端になるケースがあります。
対策
- 「同じ分類軸同士(定量×定量、定性×定性)」を組み合わせる
- 現場のヒアリングや既存データをもとに、仮説を立てて軸を検証する
- フレームワークごとに定番の軸を参考にする(例:BCGなら市場成長率と市場占有率)
評価が主観に偏り、バイアスがかかる
マトリックスは視覚的にシンプルなぶん、記号や点数で項目を評価しがちです。その際に、チームメンバーの経験値や価値観によって評価がぶれてしまうことがよくあります。
特に営業戦略や商品評価に使うと、「好み」や「先入観」が無意識に反映され、冷静な分析が損なわれる恐れがあります。
対策
- 評価基準を数値や指標で明文化しておく(例:「優れている=月間売上100万円以上」など)
- 複数名で評価し、平均や中央値で判断する
- ワークショップ形式で合意形成をとる
活用されずに「作って終わり」になる
マトリックスは「考えるツール」であると同時に「伝えるツール」でもあります。しかし、せっかく時間をかけて作っても、関係者に共有されなかったり、意思決定に活かされなければ意味がありません。
特にExcelやPowerPointで作成しただけで、現場での活用が不十分という状況はよく見られます。
対策
- マトリックス図の「結論(キーメッセージ)」を必ず一文で明示する
- チームMTGや営業会議などで発表し、アクションにつなげる
- 結果を元に作戦を立てたうえで「どの象限の何を実行するか」を明確化する
フレームワークの使い分けに失敗する
「とりあえずSWOT」「何となく4象限」など、課題に合わないフレームワークを選んでしまうと、見かけ上は整っていても意思決定に役立たない分析図になります。
問題が整理されていない初期段階では、TOWSやGEスクリーンのような複雑なマトリックスは逆効果になることもあります。
対策
- 分析の目的を明確にしたうえで、それに合ったマトリックス手法を選ぶ
- フレームワーク選定の基準(複雑性、関係者数、課題の種類)を一覧化しておく
- 結果よりも「整理のプロセス」に注目する姿勢を忘れない

マトリックスは「描くこと」より「どう使うか」が大事です。軸を適切に選び、評価の透明性を保ち、使い切ることが成功の秘訣ですよ
マトリックスを日常業務に活かす具体的な使い方
マトリックスは戦略策定だけでなく、日々の業務レベルでも非常に効果的なツールです。複雑な情報の整理、優先順位の明確化、リソース配分の最適化など、現場で即活用できる具体的な使い方を紹介します。
営業施策の優先順位づけに活用する
営業チームが複数の施策やアプローチを検討している場合、どれに注力すべきかを判断するのは容易ではありません。ここで有効なのが「重要度×実現可能性」のマトリックスです。
- 縦軸:営業施策のビジネスインパクト(売上インパクト・成約率向上)
- 横軸:実現までの工数やコスト
このマトリックスに施策をプロットすることで、「すぐに効果が期待できる施策」「時間はかかるがインパクトが大きい施策」などの分類が明確になり、意思決定が早まります。
タスク管理とリソース配分の最適化
個人やチームのタスクを整理する際には、「緊急度×重要度」のアイゼンハワーマトリックスが効果的です。
- 緊急かつ重要:今すぐ対応すべき業務
- 緊急でないが重要:計画的に対応すべき戦略タスク
- 緊急だが重要でない:委任または削減対象
- 緊急でも重要でもない:優先度を下げるか排除
この整理により、属人的な判断ではなく論理的な優先順位付けが可能になり、業務の質とスピードが向上します。
顧客分析とセグメント管理
マーケティングや営業戦略を検討するうえで重要なのが、顧客の理解です。「顧客価値×収益性」などの2軸で顧客をマトリックス分類すると、適切なアプローチが明確になります。
- 高価値×高収益:戦略的に維持・強化
- 高価値×低収益:単価アップや継続率向上施策を検討
- 低価値×高収益:効率的なサポート体制を構築
- 低価値×低収益:撤退または最小対応へ
CRMやSFAとの連携でデータを可視化し、アカウントプランニングにも活用できます。
経営戦略や企画立案時のアイデア整理
新規事業や商品企画のブレストでは、アイデアが乱立しがちです。そこで「実行可能性×市場魅力度」などのマトリックスを用いることで、論点を整理しながら論理的に評価できます。
たとえば、マーケティング担当がSNS施策やオフライン施策を提案する際、それぞれをマトリックスに当てはめることでチームの共通認識を得やすくなり、説得力ある提案に繋がります。

マトリックスを業務に活かすコツは、”軸の設計”がすべてじゃ。目的に応じた明確な2軸を選ぶだけで、判断のブレが減って意思決定がスムーズになる。毎日の会議に1枚、マトリックスを取り入れてみるのじゃ