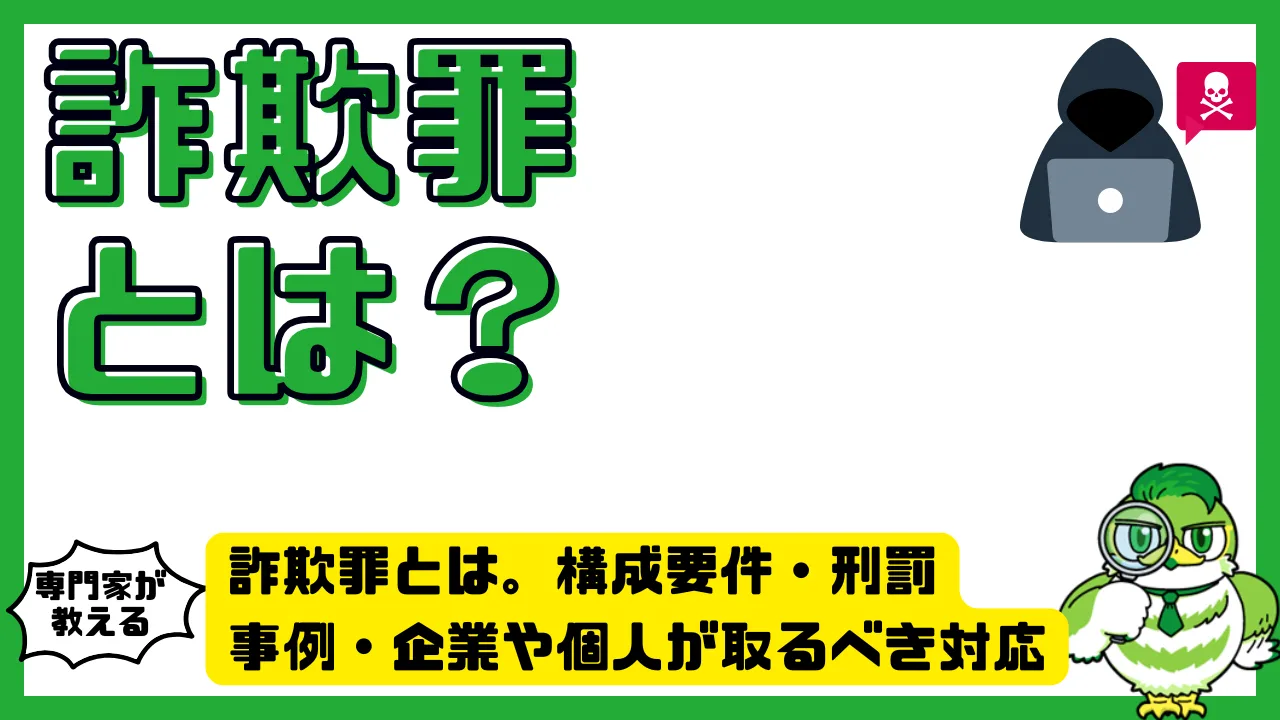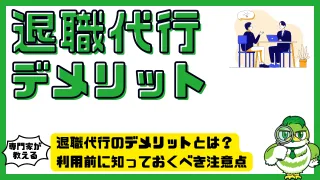本ページはプロモーションが含まれています。
目次
詐欺罪の基本的な意味と刑法上の位置づけ
刑法246条に定められる詐欺罪
詐欺罪は、日本の刑法246条において規定されています。条文では「人を欺いて財物を交付させた者」や「財産上不法の利益を得、または他人に得させた者」を処罰対象とし、10年以下の懲役刑が科されるとされています。つまり、他人をだまして財物や利益を移転させる行為そのものが、刑法上の犯罪として厳しく位置づけられているのです。
「人を欺いて財物を交付させる」行為の本質
詐欺罪の本質は、被害者の自由な意思決定を不正に操作する点にあります。具体的には、虚偽の説明や事実の隠蔽によって相手に誤解(錯誤)を与え、その結果として財産や利益を自ら交付させることが特徴です。ここでは被害者が「自分の意思で渡した」と思っている点が重要であり、意思に反して奪われる窃盗や強奪とは異なります。
財産犯における詐欺罪の位置づけ
詐欺罪は、財産を侵害する犯罪である「財産犯」の一種です。財産犯には窃盗罪や横領罪などがありますが、これらと比較すると詐欺罪は「被害者の錯誤を利用する」という独自の要素を持ちます。例えば、窃盗罪は被害者の意思に反して物を奪う行為であり、横領罪は委託を受けて占有している物を自己のものとする行為ですが、詐欺罪は相手を誤解させて自発的に財産を交付させる点で異なるのです。
IT分野における重要性
近年では、インターネット取引やキャッシュレス決済などデジタル環境に関連する詐欺が急増しています。フィッシングメールや架空請求などは典型例で、被害者自身が「正当な手続き」と信じて入力や送金を行うため、まさに詐欺罪の枠組みに当てはまります。ITに関わる人々にとって、詐欺罪の基本的な意味を理解することはリスク管理の観点から不可欠です。

つまり、詐欺罪は「だまされたから仕方ない」では済まされず、法律上きちんと処罰対象になる重大な犯罪なんです。特にIT関連の取引では錯覚を利用した巧妙な手口が多いので、条文上の意味を理解しておくことが、自分や組織を守る第一歩になりますよ
詐欺罪の種類と分類
詐欺罪は刑法246条に規定されており、同じ条文の中でも内容によっていくつかのタイプに分けられます。ここでは、代表的な分類方法と具体的な特徴について整理します。
財物詐欺と利益詐欺
詐欺罪は「財物を対象とするもの」と「財産上の利益を対象とするもの」に分けられます。
- 財物詐欺(1項詐欺罪)
他人をだまして現金や商品などの有体物を交付させる行為です。例えば、粗悪品を高額商品と偽って販売し代金を受け取る場合が典型例です。 - 利益詐欺(2項詐欺罪/詐欺利得罪)
財物ではなく「財産上の利益」を不法に得る行為です。例えば、代金を支払う意思がないのにサービス提供を受けて料金を踏み倒す、第三者に不当な利益を与える行為などがこれにあたります。
詐欺罪の典型的な分類例
詐欺罪は手口や対象によってさらに細かく分類されます。ITや企業活動に関わる分野でも多くの事例があります。
- 無銭飲食や無銭宿泊
飲食店や宿泊施設を利用しながら代金を支払う意思が最初からないケース。 - 投資詐欺・金融詐欺
「必ず儲かる」など虚偽の説明をして投資資金を集める手口。近年は暗号資産やクラウド投資を利用した詐欺も多発しています。 - 給付金詐欺や保険金詐欺
実際には条件を満たさないのに虚偽申告を行い、給付金や保険金を不正受給する行為。企業や個人が対象となる場合も少なくありません。 - 結婚詐欺や恋愛詐欺
信頼関係を利用し、結婚や交際を装って金銭をだまし取る行為。オンラインマッチングアプリを介したケースも増えています。 - 架空請求詐欺
架空の利用料や契約を口実にして「未払い料金がある」と通知し、金銭を支払わせる手法。メールやWebサイトを利用するケースが典型です。 - 特殊詐欺(振り込め詐欺等)
電話やSNSを使って「親族」「役所職員」「警察官」などを装い、現金を振り込ませたりキャッシュカードをだまし取ったりする組織的な手口です。
企業や個人が関与しやすい類型
- 企業間取引における発注詐欺
支払う意思のない注文を行い、商品を受け取る行為。商慣習を悪用した事例です。 - 情報商材やITサービスを利用した詐欺
「必ず収益が出る」と誇大広告で契約を迫り、実際には無価値なサービスを提供するパターン。 - サブスクリプションの不正利用
登録時に虚偽情報を入力し、料金を支払わずにサービスを受け続ける行為。
これらはいずれも、財物または財産上の利益をだまし取る構造を持っており、詐欺罪として処罰の対象になります。

詐欺罪の分類は大きく「財物詐欺」と「利益詐欺」に分けられますが、実際の事例は無銭飲食から給付金詐欺、特殊詐欺まで多岐にわたります。被害に遭わないためには、怪しい取引や条件に出会ったときに立ち止まって確認する習慣を持つことが大切です。
詐欺罪の構成要件を理解する
詐欺罪は、刑法246条に規定される財産犯の一つであり、成立するためには一定の要件をすべて満たす必要があります。単に「だまされた」と主張するだけでは足りず、法律上の要件を満たして初めて詐欺罪として成立します。ここでは、その4つの構成要件と因果関係について詳しく解説します。
1. 欺罔行為(人をだます行為)
欺罔行為とは、被害者を誤解させる目的で虚偽の事実を告げたり、事実を隠したりする行為を指します。積極的に嘘をつく場合だけでなく、本来伝えるべき重要な情報を意図的に黙っていた場合(不作為)も含まれます。
例えば、システムの不具合を知りながら「問題はない」と説明して高額の契約を結ばせた場合や、欠陥のある商品を正常と偽って販売する行為などが該当します。
2. 被害者の錯誤
錯誤とは、欺罔行為によって被害者が誤った認識を抱くことです。
例として、実際には投資目的で集めた資金を運用する意思がないにもかかわらず「必ず利益が出る」と説明され、被害者がそれを信じ込むケースが挙げられます。錯誤が生じなければ、詐欺罪は成立しません。
3. 被害者による交付行為
詐欺罪は、被害者が自ら財産を相手に渡す「交付行為」があって初めて成立します。錯誤に基づく意思表示であっても、被害者が自ら財物や財産上の利益を移転させることが要件です。
例えば、クラウドサービス契約において「セキュリティ万全」と信じて料金を支払った場合、その支払いが交付行為にあたります。これがなければ単なる未遂にとどまります。
4. 財物または利益の移転
被害者の交付行為により、財物や財産上の利益が実際に加害者へ移転したとき、詐欺罪は既遂となります。金銭の振込や商品の受け渡しが完了した時点で成立します。もし受け取り前に摘発された場合は、詐欺未遂罪として処罰されます。
5. 一連の因果関係
以上の4つの要件は独立して存在するのではなく、連続した因果関係で結びついている必要があります。
「だます行為」→「錯誤」→「交付」→「財産移転」の流れが立証されて初めて、詐欺罪の既遂が認められるのです。
もし被害者がだまされなかった場合や、情けから自主的に財産を渡した場合は、詐欺罪は成立せず、未遂罪やその他の法的評価にとどまることになります。

詐欺罪の成り立ちは、だましの行為がただあるだけでは足りず、それによって被害者が誤解し、財産を渡し、結果的に移転が完了するという流れが必要なんです。この流れを理解することで、どこまでが犯罪として扱われるかが見えてきますよ
詐欺罪と他の財産犯との違い
窃盗罪との違い
窃盗罪(刑法235条)は、他人の財物を被害者の意思に反して奪う行為を指します。たとえば財布を盗む、無断で商品を持ち出すといった行為です。これに対して詐欺罪では、被害者自身が錯誤に陥り、自ら財物を交付する点が決定的に異なります。つまり、窃盗は「無理やり奪う」行為であるのに対し、詐欺は「騙して自発的に渡させる」行為といえます。さらに、窃盗罪では財物そのものに限られますが、詐欺罪は財産上の利益も対象になるため、サービスの無銭利用なども処罰対象になります。
横領罪との違い
横領罪(刑法252条)は、他人から委託されて占有している財物を不正に自己のものとする行為を指します。たとえば、会社の経費を私的に流用するケースなどが典型です。詐欺罪の場合は、もともと被害者が占有している物を「だまして交付させる」のに対し、横領罪は加害者がすでに占有している物を裏切って処分する点に特徴があります。また、業務上横領では信任関係を裏切る悪質性が考慮され、詐欺罪と同等の刑罰(10年以下の懲役)が科される場合があります。
恐喝罪との違い
恐喝罪(刑法249条)は、相手を脅して財物や利益を交付させる犯罪です。ここでは「脅迫」が手段であり、被害者は畏怖のために財産を差し出します。一方で詐欺罪は「欺く」ことが手段であり、被害者は虚偽の情報を信じて自発的に交付してしまいます。恐喝は強制力を伴い、詐欺は錯誤を利用する点で明確な区別がされます。
IT関連の場面での違い
IT分野では、例えば「フィッシング詐欺」によって本人を騙してパスワードを入力させるケースは詐欺罪に当たり得ますが、システムへの不正侵入でデータを抜き取るケースは不正アクセス禁止法や窃盗罪の領域です。また、企業の従業員が顧客データを無断で持ち出した場合は横領罪に該当し、強制的に「金を払わなければデータを公開する」と脅す場合は恐喝罪となります。このように、行為の手段と被害者の意思の状態によって犯罪の区別がなされます。

詐欺罪は「だまして渡させる」、窃盗罪は「黙って奪う」、横領罪は「預かって裏切る」、恐喝罪は「脅して出させる」という違いを覚えておくと整理しやすいですよ
詐欺罪の刑罰と時効
法定刑の内容
詐欺罪は刑法246条に規定されており、法定刑は「10年以下の懲役」です。罰金刑は設けられていないため、有罪となれば必ず懲役刑が科される可能性があります。有期懲役の下限は1か月とされているため、判決は1か月以上10年以下の範囲で決まります。
量刑を左右する要素
裁判所が具体的な刑期を決定する際には、行為の悪質性や被害の規模だけでなく、さまざまな事情が考慮されます。代表的な要素には以下のようなものがあります。
- 被害額の大きさ
- 被害者への弁済や示談の有無
- 犯行が計画的か否か、組織的か否か
- 前科や余罪の有無
- 被害者や社会への影響の程度
初犯であっても高額被害や複数人を巻き込んだ悪質な事件では、実刑判決が言い渡されることも少なくありません。一方で、被害額が少なく弁済や示談が成立している場合には、執行猶予が付与されるケースもあります。
執行猶予の可能性
執行猶予は、裁判で有罪判決を受けても直ちに刑務所に収容されず、一定期間を無事に過ごせば刑の執行が免除される制度です。詐欺罪の場合、懲役3年以下の刑であれば執行猶予の可能性が残ります。もっとも、被害額が大きい、示談が成立していない、組織的犯行に関わっていたといった事情があれば、執行猶予は認められにくくなります。
公訴時効
詐欺罪の公訴時効は7年と定められています。これは犯罪が終了した時点から起算され、7年を経過すると検察官は起訴できなくなります。例えば、振り込め詐欺で金銭を受け取った日から7年が経過すれば、その件については新たに訴追されません。ただし、捜査機関が事件を把握していれば、その間に逮捕・起訴される可能性は十分にあります。
IT関連での注意点
インターネット取引や電子商取引の拡大により、詐欺行為は従来以上に多様化しています。オンライン決済詐欺やフィッシング詐欺といった形態でも、詐欺罪として刑事責任を問われることがあります。デジタル上の証拠は消えやすいため、企業や個人は取引記録や通信履歴を保全しておくことが重要です。

詐欺罪の刑罰は「懲役のみ」で重く、初犯だからといって必ずしも軽い処分になるわけではありません。被害額や示談の有無によって大きく変わりますし、時効は7年とされているので長期にわたり責任を問われる可能性があります。IT関連の取引では証拠保全が特に重要ですから、少しでも不安を感じたら早めに専門家に相談することが大切ですよ
企業が直面する詐欺罪の典型例
企業間取引は信頼を前提に成り立っていますが、この信頼を悪用する形で詐欺行為が行われることがあります。以下では、企業が現実に直面しやすい典型的な詐欺罪の事例を解説します。
代金を支払う意思のない商品発注
掛け払い取引では、商品を先に受け取り代金を後払いするケースが一般的です。この仕組みを悪用し、最初から支払う意思がないにもかかわらず発注を行う企業があります。発注自体が「支払い能力がある」という信頼を前提としているため、この虚偽を前提に商品を受け取った場合、詐欺罪が成立します。相手企業が疑念を抱かず商品を渡してしまえば、実害が発生するため深刻です。
欠陥品を隠して販売
通常の売買契約では、契約内容に適合した商品を提供する義務があります。それにもかかわらず、欠陥品であることを知りながら隠して販売した場合、相手を欺く行為に該当します。特に製造業やIT機器など高額な取引では、欠陥隠しが企業の信用失墜に直結し、損害賠償請求や刑事責任を問われるリスクがあります。
倒産状態を隠した融資申請
融資を受ける際、金融機関に正確な財務状況を開示することは不可欠です。倒産状態や著しい資金繰りの悪化を隠して融資を申し込み、資金を引き出した場合、金融機関を欺いて利益を得たものとされ、詐欺罪が成立します。金融機関にとっては貸し倒れのリスクを強制的に負わされるため、極めて悪質な行為と判断されます。
IT取引における典型的な詐欺
現代の企業活動ではオンライン取引が増えており、次のような形で詐欺が行われるケースも少なくありません。
- 架空のソフトウェア開発契約を結び、実体のない納品物で報酬を請求する
- サイバー攻撃や偽装メールを利用し、企業担当者を騙して送金させる(ビジネスメール詐欺)
- ライセンス数や利用状況を偽って過大な請求を行う
こうしたIT関連の事例は一見通常の商取引に見えるため、被害が発覚した時点で既に損害が拡大していることが多いのが特徴です。

企業取引に潜む詐欺は「支払わない」「欠陥を隠す」「財務を偽る」という典型パターンに加え、近年ではITを悪用した巧妙な手口も増えています。企業の皆さんは、契約時の信用調査や取引後のモニタリングを徹底し、少しでも不自然さを感じたら早めに法務部や弁護士に相談することが大切ですよ
詐欺罪に巻き込まれた場合の対応方法
詐欺被害に遭った場合は、迅速かつ適切な行動を取ることが被害の拡大を防ぎ、損失回復につながります。特に企業や個人事業主は取引の信頼を守る必要があるため、初期対応が極めて重要です。
警察への届け出と刑事手続き
詐欺が疑われるときは、まず警察へ被害届を提出することが基本です。犯人の特定や被害金の返還につながる可能性があるため、できる限り早期に動くことが求められます。処罰を強く望む場合には、告訴状を提出することで捜査が加速することもあります。
契約解除と証拠保全
取引の中で詐欺行為が発覚した場合は、契約を直ちに解除することが必要です。その際には、解除の事実を記録として残すために内容証明郵便を用いると効果的です。また、メールや請求書、送金履歴などの証拠を確実に保存し、後の裁判や交渉に備えましょう。
損害回復のための請求
被害を受けた後は、法的手段による回復を検討します。代表的なのは以下の二つです。
- 不当利得返還請求
契約解除後、相手が不正に得た利益を返還させることが可能です。民法上、加害者が悪意の受益者である場合には利息を付けて返還義務が生じます。 - 損害賠償請求
契約違反や不法行為に基づき、直接的な金銭的被害だけでなく、信用低下や対応にかかったコストについても請求できます。
弁護士への相談
個人での交渉は難航することが多く、専門的な法知識が必要となります。早期に弁護士へ相談することで、適切な戦略を立て、示談交渉や訴訟を有利に進められる可能性が高まります。IT関連の取引では証拠がデジタルデータに集中するため、法的に有効な形で証拠を確保するためにも専門家の助言は不可欠です。
企業の場合の社内対応
企業が被害に遭った場合は、外部対応だけでなく社内体制の見直しも重要です。内部調査によって不正が内部から持ち込まれたのか、外部から仕掛けられたのかを明確化し、再発防止策を策定する必要があります。従業員への啓発や取引先の信用調査の徹底も効果的です。

詐欺に巻き込まれたときは冷静さが大切です。まずは証拠を残して、警察や弁護士に相談し、被害回復と再発防止を同時に進めていきましょう。特にIT関連の取引ではデジタル証拠の扱いが鍵になりますから、専門家と連携することを強くおすすめします
個人や企業が詐欺被害を防ぐための対策
詐欺は巧妙化しており、被害を未然に防ぐには日常的な警戒と仕組み作りが欠かせません。特にオンライン取引やITサービスを利用する場面では、従来型の手口に加えてデジタル技術を悪用した詐欺も増えています。ここでは個人と企業が取り組むべき主な予防策を解説します。
個人が取るべき予防策
個人の場合、日常生活の中で遭遇するリスクに備える意識が重要です。
- 取引相手の確認
ネット通販やフリマアプリでは、運営元や販売者の評価・実在性を必ず確認することが大切です。公式サイト以外の決済リンクや連絡先には注意してください。 - 不自然な条件への警戒
「期間限定で半額」「通常ではありえない利回り」など、過度に有利な条件を提示してくる場合は詐欺の可能性が高いです。 - 個人情報の管理
IDやパスワードを複数サービスで使い回さず、二段階認証を導入することが推奨されます。フィッシングサイトへの誘導を見抜くため、メールやSMSのリンクを不用意にクリックしないことも重要です。 - 金融詐欺の回避
投資や副業の勧誘は、金融庁登録の業者かどうかを必ず確認しましょう。未登録業者による高配当の勧誘は典型的な詐欺手口です。
企業が取るべき予防策
企業は被害規模が大きくなる傾向があるため、組織的な対策が不可欠です。
- 取引先の信用調査
初めて取引する相手については、登記簿や帝国データバンクなどを用いた与信調査を行いましょう。Webサイトだけで判断せず、代表者や所在地の実在性を確認することも有効です。 - 社内教育と通報体制
社員向けに「詐欺メールの見分け方」や「不審な請求書への対応」を共有する研修を実施し、疑わしい案件を速やかに相談できる窓口を設けることが大切です。 - 契約書の整備
曖昧な条件の契約は避け、支払い条件や納期、解除事由を明記することで詐欺的行為に巻き込まれた際の法的対応を容易にします。 - 情報セキュリティの強化
なりすましメールによる送金指示型詐欺(BEC)を防ぐため、送金依頼は必ず複数の承認を経るような業務フローを導入することが効果的です。
弁護士や専門家への相談
個人・企業を問わず、不審な取引や請求を受けた場合は早期に弁護士や消費生活センターへ相談することが推奨されます。専門家に早く相談するほど、被害を未然に防ぎやすくなります。

詐欺の被害を防ぐためには「おかしい」と思った時点で立ち止まり、裏付けを取ることが大事なんです。個人は日常の取引や投資で慎重さを保ち、企業は仕組みとしてチェックと教育を徹底することが効果的ですよ