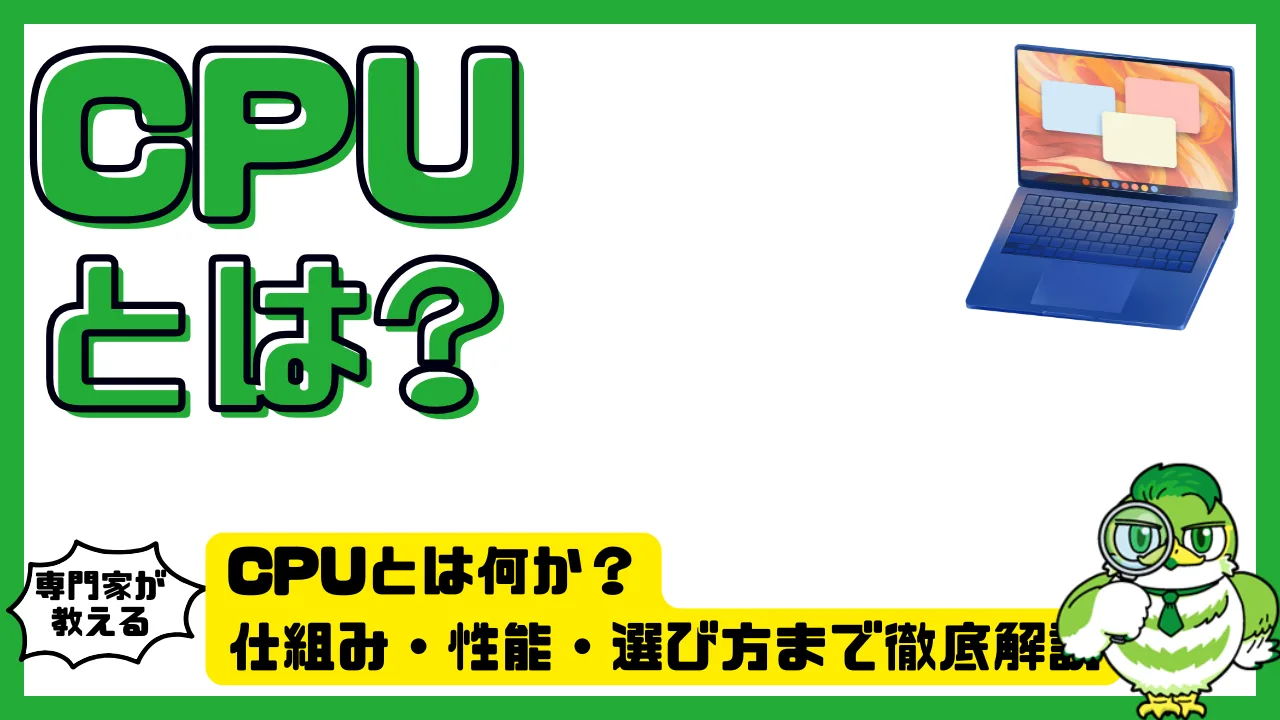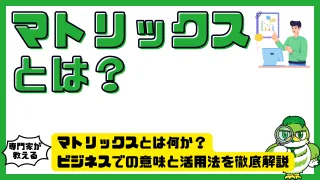本ページはプロモーションが含まれています。
目次
CPUとは何かをわかりやすく解説
CPUはパソコンの「頭脳」
CPUは「Central Processing Unit(中央演算処理装置)」の略称で、コンピューターの中核を担う部品です。人間に例えると「頭脳」にあたり、命令を読み取り、計算・判断・制御などを行う役割を持っています。パソコンやスマートフォンが「動く」のは、すべてCPUが背後で処理をしているからです。
たとえば、文字を入力したり、動画を再生したり、アプリを開いたりといった日常的な操作はすべて、CPUが受け取った命令を解析し、それに沿って計算処理を行うことで実現しています。
正式名称と意味
「Central Processing Unit」という名前の通り、コンピューター全体の“中央”で“処理”を行う“装置”です。コンピューターの各部品(メモリ、ストレージ、グラフィックボードなど)と連携しながら、最終的な判断をCPUが下しています。このようにCPUは、コンピューターのすべての動作に関わる非常に重要なパーツなのです。
CPUが担う3つの主な役割
- 演算処理(計算)
数値計算や論理判断など、アプリやシステムが必要とする演算を行います。これが基本的な処理機能です。 - 制御処理(指示)
「何を・いつ・どうやって実行するか」を決め、ほかのパーツ(メモリやGPUなど)に指示を出します。CPUが司令塔の役割を果たしています。 - 情報の読み書き(データのやりとり)
メモリや記憶装置にあるデータを読み込み、処理し、結果を出力します。この動作を高速で繰り返すことにより、スムーズな動作が可能になります。
CPUが活躍する身近な例
- インターネットでページを表示する
- YouTubeで動画を再生する
- Zoomなどのオンライン会議を行う
- WordやExcelなどの文書作成ソフトを使う
- ゲームや動画編集をする
これらの処理を「速く・安定して」こなせるかどうかは、搭載されているCPUの性能に大きく左右されます。

パソコンの性能って何を見ればいいの?

CPUのことを「頭脳」と呼ぶ理由がわかりましたね。コンピューターのすべての動きを司る司令塔、それがCPUです。どんな作業をしたいのかによって、必要な“脳力”も変わってきますよ
CPUの基本性能を構成する4つの要素
CPUの性能を理解するうえで、基礎的かつ重要な要素が4つあります。それぞれがパソコン全体の快適さや処理速度に大きく影響するため、購入や比較検討の際には必ず押さえておきたいポイントです。
コア数とスレッド数
コア数とは
コアは、CPUの中で実際に処理を行う「頭脳」の数です。1つのCPUの中に複数のコアが内蔵されている場合、同時に複数の処理を行うことができます。これを「マルチコアCPU」と呼びます。
- 1コア:1つの作業を順番に処理
- 4コア:最大4つの作業を同時に処理可能
- 8コア以上:動画編集や3Dレンダリングなどの重たい作業にも適する
コア数が多いほど、並列処理性能に優れ、複数のソフトを同時に快適に動かすことができます。
スレッド数とは
スレッドは、コアが同時に処理できる「作業単位」のことです。通常は1コア1スレッドですが、ハイパースレッディング(Intel)やSimultaneous Multithreading(AMD)といった技術により、1コアで2スレッド処理が可能なCPUもあります。
たとえば:
- 4コア4スレッド → 実質4つの作業
- 4コア8スレッド → 同時に8つの作業が可能
スレッド数が多いと、アプリの動作がよりスムーズになりますが、物理コア数の多さも重要です。
クロック周波数(GHz)
クロック周波数とは、CPUが1秒間に処理できる命令の回数を示す数値です。単位は「GHz(ギガヘルツ)」で、数値が高いほど動作は高速になります。
- 2.0GHzより3.5GHzの方が高速処理が可能
- ゲームや高負荷な作業には高クロックが有利
ただし、高クロック=高性能とは限らず、コア数や設計とのバランスが重要です。また、クロック周波数が高くなるほど発熱や消費電力も増えるため、冷却性能も必要になります。
キャッシュメモリ
キャッシュメモリとは、CPUの内部に搭載された超高速の一時記憶装置です。CPUが繰り返し使うデータを一時的に保存し、メインメモリ(RAM)よりも早くアクセスできるようにします。
キャッシュの階層は一般に3段階あり、L1、L2、L3の順に容量が大きくなりますが、速度はL1が最も速くL3が遅めです。
- L1キャッシュ:最速・最小
- L2キャッシュ:中速・中容量
- L3キャッシュ:大容量・低速(といっても高速)
キャッシュ容量が多いほど、処理の遅延を減らせるため、特にゲームや複雑な演算処理では恩恵が大きくなります。
TDP(熱設計電力)
TDP(Thermal Design Power)とは、CPUが最大負荷時に発生する熱量の目安です。単位はワット(W)で、冷却設計の参考になります。
- TDPが高い=性能が高いが発熱も多い
- TDPが低い=省電力でノートPCに向いている
TDPが高いCPUは、高性能な代わりに発熱も大きく、専用の冷却システムや電源ユニットが必要になる場合があります。逆に、TDPの低いCPUは静音・省電力が求められる用途に最適です。

CPUの性能って、コア数だけ見ればいいと思いがちだけど、実は「コア×スレッド×クロック×キャッシュ」のバランスが超大事!あと、TDPを見ておかないと冷却が追いつかなくて大惨事になることもあるから要注意だよ
CPUメーカー2強|IntelとAMDの違い
パソコン用CPU市場において、Intel(インテル)とAMD(エーエムディー)は2大巨頭として長年シェアを競い合ってきました。それぞれに明確な特長と強みがあり、用途や予算に応じて選択肢が分かれます。
Intelの特長と主なラインアップ
Intelは世界最大手の半導体メーカーであり、多くのメーカー製パソコンやノートPCに採用される「安定性と互換性の高さ」が評価されています。
主なシリーズと特徴
- Celeron / Pentium
ネット閲覧や文書作成などの軽作業向け。価格重視の入門モデル。 - Core iシリーズ(i3 / i5 / i7 / i9)
汎用性が高く、性能・価格のバランスに優れた主力シリーズ。 - Core i3: 軽作業メイン
- Core i5: 一般〜中級者向け
- Core i7: 高負荷の作業も対応
- Core i9: ゲームや動画編集などプロ向け
- Core Ultraシリーズ
最新アーキテクチャによるAI処理機能と省電力性を両立。高性能ノートPC向け。 - Xeon(ジーオン)
サーバーやワークステーション向け。マルチスレッド性能に特化。
Intelの強み
- ノートPCとの親和性が高く、バッテリー持ちが良い
- 長年の市場実績による安定動作
- ソフトウェア側の最適化が進んでおり不具合が起きにくい
AMDの特長と主なラインアップ
AMDは近年大きく躍進しているCPUメーカーで、「高性能×コストパフォーマンス」が強みです。特に自作PC市場やゲーミングPCで人気を集めています。
主なシリーズと特徴
- Athlon(アスロン)
CeleronやPentiumと競合するローエンドモデル。軽作業向き。 - Ryzen(ライゼン)シリーズ
マルチコア・マルチスレッド性能が高く、コスパにも優れた定番シリーズ。 - Ryzen 3: 軽作業向き
- Ryzen 5: 一般用途〜ミドルゲーム
- Ryzen 7: 動画編集・配信にも対応
- Ryzen 9: ゲーム・クリエイティブ用途のハイエンドモデル
- Ryzen Threadripper(スレッドリッパー)
最大96コアなど極めて高性能なプロフェッショナル向けモデル。3DCGや研究開発向け。
AMDの強み
- 同価格帯でのコア数・スレッド数が多く、マルチタスク処理に強い
- 内蔵GPU性能が高く、グラフィック性能も優れる(特にRyzen Gシリーズ)
- CPUとマザーボードの互換性が長く、アップグレードがしやすい
IntelとAMDの比較一覧
| 項目 | Intel | AMD |
|---|---|---|
| 性能の傾向 | 単一コアの処理速度が高い | 複数コアでの並列処理に強い |
| 内蔵グラフィックス | 安定性重視、AI支援型も登場 | Ryzen Gシリーズはゲームも可能な性能 |
| 価格帯 | やや高めだがブランド力あり | 同クラスでコスパが高い |
| ノートPC搭載率 | 非常に高い | ゲーミング・高性能機に多く採用される |
| 対応マザーボード | 世代ごとに互換性に注意が必要 | 同一ソケットでの世代互換が比較的長い |
| 向いているユーザー | 安定動作・長期サポートを重視する方 | 性能・価格のバランスを重視する方 |

どちらを選んでも間違いではありませんが、予算が限られていても性能を妥協したくないならAMD、信頼性や長期使用を重視するならIntelが安心です
型番の見方で性能を見抜く方法
CPU選びに迷ったとき、型番の意味を正しく理解することで、性能や用途に合う製品かどうかを見極められます。IntelとAMD、それぞれの型番には明確なルールがあり、慣れればスペック表を見なくても基本性能が把握できるようになります。
Intel CPUの型番の読み方
例:Core i5-13600K
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| Core i5 | シリーズ名(Core i3\<i5\<i7\<i9) |
| 13 | 世代(第13世代) |
| 600 | 製品ランク(数値が大きいほど高性能) |
| K | サフィックス(機能や特性を表す) |
主なサフィックスの意味
| サフィックス | 特徴 |
|---|---|
| K | オーバークロック対応 |
| F | 内蔵GPUなし(グラフィック機能非搭載) |
| KF | K+F(OC可+内蔵GPUなし) |
| T | 省電力モデル(低TDP) |
| U | モバイル向け超低電圧モデル(ノートPC用) |
| H/HX | 高性能モバイル向け(ゲーミングノート等) |
数字部分を見るだけで、世代・グレード・パフォーマンスがざっくりと判断できます。例えば「i7-14700KF」は、第14世代のハイパフォーマンスモデルで、GPU非搭載・OC対応という意味になります。
AMD CPUの型番の読み方
例:Ryzen 7 7800X
| 要素 | 意味 |
|---|---|
| Ryzen 7 | シリーズ名(Ryzen 3<5<7<9) |
| 7 | 世代(第7世代=Ryzen 7000番台) |
| 800 | 製品ランク(数字が高いほど高性能) |
| X | サフィックス(性能や用途を示す) |
主なサフィックスの意味
| サフィックス | 特徴 |
|---|---|
| X | 高性能モデル(クロックが高い) |
| G | グラフィック内蔵モデル(APU) |
| U | 超低電圧・省電力モデル(モバイル向け) |
| H | モバイル向け高性能(ゲーミングノート等) |
| E | 省電力モデル(デスクトップ向け一部) |
Ryzenシリーズは特に「G」モデルが初心者には分かりやすく、グラボ不要で映像出力できるため、オフィスやネット用途に向いています。数字の大きさとサフィックスの組み合わせで、コストと性能のバランスを見極めやすい設計になっています。
型番で性能を見抜くためのポイントまとめ
- 世代を見れば「設計の新しさ」がわかる(13世代より14世代の方が高性能)
- 数字が大きいほど「グレードが高くなる」傾向
- サフィックスで「用途の違い」や「GPU有無」が判断可能
- Intelは「F」「K」、AMDは「G」「X」の意味に注目するのがコツ

型番はCPUの履歴書のようなもの。読めるようになれば、予算や目的に合ったCPUが自分で選べるようになりますよ
自分に合ったCPUの選び方と用途別おすすめ
CPU選びで最も重要なのは「何に使うか」という目的の明確化です。性能が高い=最適ではなく、使い方に合わないオーバースペックはコストの無駄になります。ここでは、用途別にどのようなCPUが適しているかをわかりやすく解説します。
ネット閲覧・メール・事務作業におすすめのCPU
特徴
- 軽量なタスクが中心
- 複数アプリの同時起動も少なめ
おすすめCPU
- Intel Core i3(第12世代以降)
- AMD Ryzen 3(4000番台以降)
- Intel Nシリーズ(省電力モデル)
選び方のポイント
- コア数は4コア以上あれば十分
- 内蔵グラフィック搭載モデルが望ましい
- クロック周波数は2.5GHz以上あれば快適
オンライン授業・テレワーク・Zoom会議向け
特徴
- 複数のソフトを同時使用
- カメラ処理や音声処理の負荷も発生
おすすめCPU
- Intel Core i5(第12世代以降)
- AMD Ryzen 5(5000番台以降)
選び方のポイント
- 6コア以上、マルチスレッド対応が望ましい
- TDPは高すぎない範囲(15W〜35W)で
- 内蔵GPU性能もチェック(Intel Iris XeやAMD Radeon)
動画編集・画像加工・DTMなどのクリエイティブ用途
特徴
- マルチスレッド性能が重要
- 高速な処理・キャッシュ容量が求められる
おすすめCPU
- Intel Core i7 / i9(第13世代以降)
- AMD Ryzen 7 / 9(7000番台以降)
選び方のポイント
- 8コア以上、16スレッド以上が目安
- キャッシュ容量(L3 16MB以上)に注目
- メモリやストレージとのバランスも重要
ゲーム(軽め〜高負荷のPCゲーム)
特徴
- シングルコア性能+グラフィック処理が重要
- フレームレート安定のためにCPU/GPUのバランスが必要
おすすめCPU
- Intel Core i5 / i7(K付きモデル)
- AMD Ryzen 5 / 7(X付きモデル)
選び方のポイント
- クロック周波数は3.5GHz以上が理想
- 内蔵GPUよりも外部GPUとの組み合わせを想定
- オーバークロック対応モデル(K/X)も検討
AI開発・3Dレンダリング・プログラミング用途
特徴
- 並列処理+メモリ帯域の効率が求められる
- 高性能なワークステーションクラスが適す
おすすめCPU
- Intel Core i9 / Xeon
- AMD Ryzen Threadripper / Ryzen 9
選び方のポイント
- 12コア以上、24スレッド以上が基準
- ECCメモリ対応CPU(特にXeon)も検討
- PCIeレーン数が多いCPUは拡張性にも優れる
省スペース&静音性重視のミニPCやノート用途
特徴
- ファンレスや低消費電力設計が必要
- サーマル制限に強いCPUが適している
おすすめCPU
- Intel Core Ultra(モバイル向け)
- AMD Ryzen Uシリーズ
選び方のポイント
- TDPは15W前後
- GPU統合型が前提
- PassMarkなどのベンチマークスコアも参考にする
CPU選びに迷ったときのチェックポイント
| チェック項目 | 目安や選定基準 |
|---|---|
| コア数・スレッド数 | 日常用途:4コア / ゲーム・編集:6〜12 |
| クロック周波数 | 最低2.5GHz、ゲームや編集は3.5GHz以上 |
| TDP(発熱・電力) | ノートPC:15〜28W、デスクトップ:65W以上 |
| 内蔵GPUの性能 | グラボ非搭載ならIntel Iris Xe以上推奨 |
| サフィックスの意味 | K=OC可、F=内蔵GPUなし、X=高性能 |

「高いCPU=正解」じゃないぞ。自分の使い方をまず整理するのが第一歩じゃ。必要以上の性能は電力や予算のムダになるからの。特に「ゲームもやりたい・編集もしたい」みたいに目的が増えるときは、バランス型のRyzen 7やCore i7がおすすめじゃよ
CPUの確認方法(Windows/Mac対応)
パソコンの性能を把握する第一歩は、搭載されているCPUを正しく確認することです。ここではWindowsとMac、それぞれのOSにおけるCPU確認手順と、確認すべきポイントをわかりやすく解説します。
WindowsでのCPU確認方法
方法1:タスクマネージャーから確認する
- キーボードの「Ctrl + Shift + Esc」を同時に押してタスクマネージャーを起動
- 上部メニューの「パフォーマンス」タブを選択
- 左側の「CPU」をクリック
- 右上に「CPU名(例:Intel Core i5-12400)」とクロック数(GHz)が表示される
※Windows 11/10どちらでも有効な手順です。
方法2:設定メニューから確認する
- 「スタートボタン」を右クリックし、「設定」を選択
- 「システム」→「詳細情報」をクリック
- 「デバイスの仕様」内の「プロセッサ」の欄に、CPUの型番と詳細が表示される
MacでのCPU確認方法
方法:このMacについて
- 画面左上のAppleロゴをクリック
- 「このMacについて」を選択
- 表示されるウィンドウ内に「チップ」または「プロセッサ」の欄があり、CPUの型番(例:Apple M2、Intel Core i7など)が表示される
※Appleシリコン搭載モデルでは「M1」「M2」などと表示されます。Intel製CPUの場合は従来通り型番表記されます。
型番・スペックの読み解きポイント
CPU名には、処理性能や世代を示す情報が含まれています。以下のポイントを押さえておくと便利です。
- ブランド名:Intel Core / AMD Ryzenなど
- グレード:Core i3/i5/i7/i9 や Ryzen 5/7/9 など
- 世代:型番の中に「12400」→第12世代、「7800X」→Ryzen 7000番台
- サフィックス(末尾記号):
- Intel:「K」=オーバークロック可能、「F」=内蔵GPUなし
- AMD:「X」=高クロックモデル、「G」=内蔵GPUあり
型番から何がわかる?
| 項目 | 例(Intel) | 例(AMD) | 内容 |
|---|---|---|---|
| グレード | Core i5 | Ryzen 7 | 性能ランク |
| 世代 | 12400 → 第12世代 | 7800X → 7000シリーズ | アーキテクチャの新しさ |
| サフィックス | K / F | X / G | 特別機能の有無 |

難しく考えすぎなくて大丈夫!自分のPCの「頭脳」が何かを知るだけでも、今後の買い替えや性能判断にきっと役立ちますよ
CPUの進化と世代ごとの特徴
CPUは数年ごとに新たなアーキテクチャが登場し、そのたびに性能や機能が大きく進化しています。最新世代のCPUは単に処理速度が速いだけでなく、電力効率やAI支援、グラフィックス性能など、多角的な性能向上が行われています。ここでは、IntelとAMDのCPUの進化の流れと、世代ごとの特徴をわかりやすく紹介します。
Intelの世代ごとの主な特徴
第10世代(Comet Lake)
- 従来の14nmプロセスを継続
- 最大10コア20スレッド
- Wi-Fi 6やThunderbolt 3への対応強化
- 主にデスクトップ向けの安定モデル
第11世代(Rocket Lake / Tiger Lake)
- CPUアーキテクチャを刷新(Willow Cove)
- PCIe 4.0に対応
- 内蔵GPU(Iris Xe)の性能大幅向上
- シングルスレッド性能の強化
第12世代(Alder Lake)
- ハイブリッドアーキテクチャ採用(Pコア+Eコア)
- DDR5メモリ・PCIe 5.0に対応
- マルチタスク・省電力性能が飛躍的に向上
- Windows 11で最適動作
第13世代(Raptor Lake)
- 第12世代の改良版で、Eコアの増加とキャッシュ容量の増強
- ゲームやクリエイティブ用途でさらに高性能に
- 上位モデルは24コア(8P+16E)まで搭載
第14世代(Raptor Lake Refresh)
- 第13世代をベースにクロック周波数を強化
- AI処理支援やGPU性能は引き続き維持
- 最新マザーボードとの互換性に優れる
AMDの世代ごとの主な特徴
Ryzen 3000シリーズ(Zen 2)
- 7nmプロセス採用で電力効率が向上
- 最大16コア搭載可能で、マルチスレッド性能に優れる
- PCIe 4.0に初対応
Ryzen 5000シリーズ(Zen 3)
- IPC(命令あたりの処理数)が大幅向上
- ゲームやアプリの実行速度が目に見えて速くなる
- シングル・マルチともに高いバランスを実現
Ryzen 7000シリーズ(Zen 4)
- DDR5メモリ・PCIe 5.0に対応
- 5nmプロセスにより電力効率と動作周波数が向上
- GPU内蔵モデルが主流に(APU性能の底上げ)
Ryzen 8000/9000シリーズ(Zen 4+/Zen 5)
- Ryzen AI搭載により、AI処理支援が標準化
- モバイル向けではバッテリー駆動時間が改善
- 最新ゲームや動画編集に最適化されたアーキテクチャ
世代を重ねるメリットと注意点
メリット
- 高速なメモリ・ストレージ対応による処理全体の高速化
- AI処理や省電力対応など、最新アプリに強い
- セキュリティ面の強化(ハードウェアレベルでの脆弱性対策)
注意点
- 新世代CPUは旧マザーボードと互換性がない場合が多い
- DDR5メモリや新チップセットなど、周辺パーツの追加コストが発生
- 高性能化に伴う発熱対策が必要になることも

古い世代のCPUでもまだ使える?という疑問はよくありますが、日常利用や事務作業なら第8世代以降のCore i5やRyzen 5でも十分快適です。ただし、最新のゲームやAIアプリを使いたいなら、新世代へのアップグレードを検討しましょう
CPUに関するよくある質問(FAQ)
CPUを交換すればパソコンの動作は速くなりますか?
CPUをより高性能なモデルに交換することで、処理速度や快適さは向上します。ただし、マザーボードのソケット形状やチップセットとの互換性、電源容量、冷却性能なども関係するため、交換前に対応状況を必ず確認する必要があります。ストレージ(SSD)やメモリとのバランスも重要です。
ノートパソコンのCPUは交換できますか?
基本的にノートパソコンのCPUはマザーボードにはんだ付けされており、ユーザーが交換することはできません。ごく一部の高性能ノートではCPUがソケット式で交換可能なモデルもありますが、一般的ではなく技術的なリスクも高いため、実質的には「交換できない」と考えてください。
CPUクーラーは絶対に必要ですか?
はい、必要です。CPUは動作中に高温になるため、冷却装置(CPUクーラー)がなければオーバーヒートして動作不良や故障の原因になります。自作PCではCPUに付属のリテールクーラーを使うか、別売りの静音型や高冷却型クーラーを選ぶことが一般的です。静音性や見た目を重視する方は、カスタムクーラーの導入も検討するとよいでしょう。
スマホのCPUとパソコンのCPUの違いは何ですか?
スマホのCPUは「ARMアーキテクチャ」、パソコンのCPUは「x86アーキテクチャ」が主流です。スマホ用は省電力性と発熱の少なさを重視しており、パソコン用は高い処理性能を追求しています。最近では、Apple Mシリーズのように、ARM系CPUでもパソコン用途に使える高性能モデルも登場しています。
世代の違いはどれくらい影響しますか?
同じブランド・グレードのCPUでも、世代が新しいものほど性能や省電力性が向上している傾向があります。たとえばIntel Core i5でも第10世代と第14世代では、AI処理、内蔵GPU、マルチタスク性能などに大きな差が生まれます。新しい世代ほど対応ソフトやOSとの相性も良く、長期的に安心して使えます。
ゲーム用なら何コア以上が必要ですか?
多くのゲームでは4コア以上であれば十分動作しますが、近年のAAAタイトルや配信・録画を同時に行う場合は、6〜8コア以上が望ましいです。例えば「Ryzen 5 7600X」や「Core i5-13600K」などは、コストパフォーマンスに優れた人気モデルです。
型番だけで性能は完全に判断できますか?
ある程度の性能は型番から判断できますが、正確な比較には「PassMark」などのベンチマークスコアを確認するのが効果的です。同じ世代・同じグレードでも型番末尾のアルファベット(サフィックス)によって内蔵GPUの有無やオーバークロックの可否などが異なるため、用途に応じた確認が必要です。
CPUの温度はどこまでが安全ですか?
一般的に、CPUの安全な動作温度は40〜80℃程度とされています。高負荷時に90℃近くになることもありますが、継続して高温が続くと寿命を縮める原因になります。CPU温度は「HWMonitor」などのソフトで確認でき、必要に応じてファン速度調整や冷却強化を検討してください。

「CPUに関する疑問が出たら、まずはここで確認するのがコツ。質問と答えをひと通り読んでおくだけで、購入時や設定変更時の不安もぐっと減るはずです」