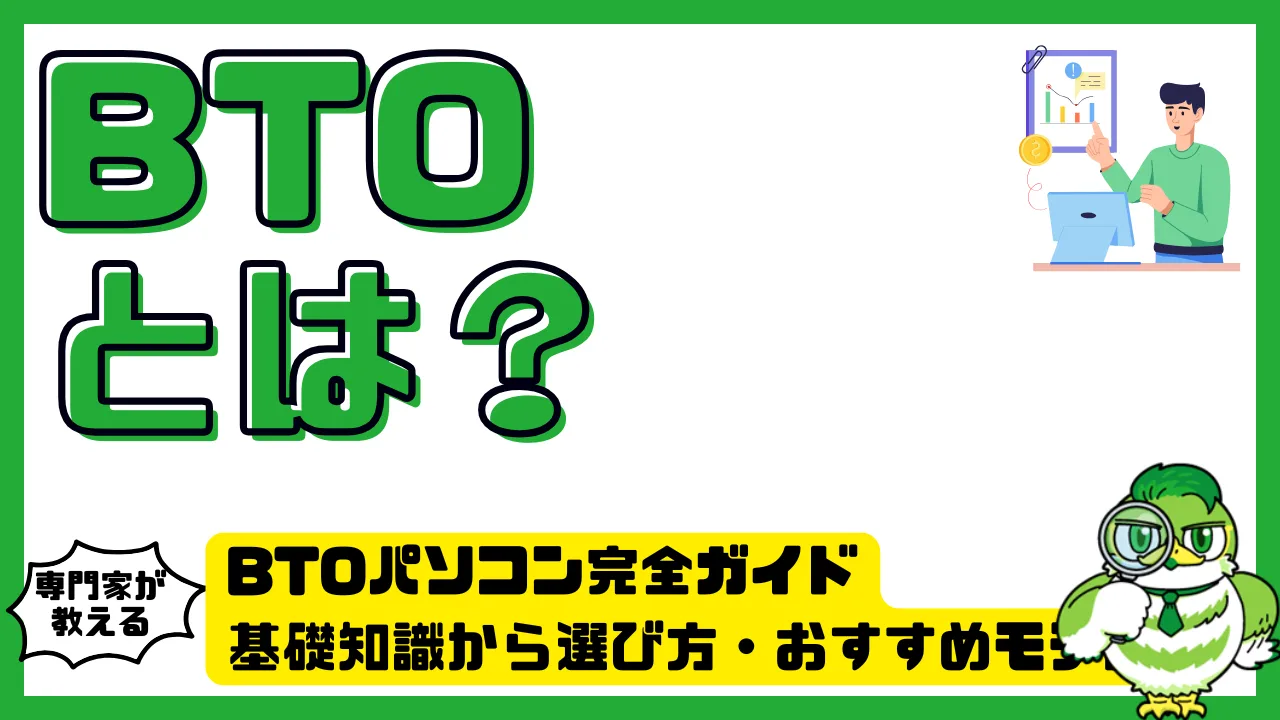本ページはプロモーションが含まれています。
目次
BTOとは何か基礎からわかる解説
BTOの意味と仕組み
BTOとは「Build To Order」の略で、日本語にすると「受注生産」を意味します。これは、既製品のパソコンをそのまま購入するのではなく、ユーザーの希望に応じてパーツ構成を選び、その内容で組み立てられる仕組みです。注文を受けてから生産されるため、自分の用途や予算に合わせたパソコンを手に入れることができます。
既製パソコンとの違い
既製パソコンは家電量販店などに並んでいる完成済みの製品で、購入後すぐに使用できる手軽さがあります。一方、BTOパソコンはCPUやメモリ、ストレージ、グラフィックボードといった主要パーツを自分で選択できるのが大きな特徴です。無駄な機能を省いたり、逆に必要な部分を強化したりすることで、コストを抑えつつ性能を高めることが可能になります。
注文から完成までの流れ
BTOパソコンの注文は、まず希望する基本モデルを選び、そこからパーツの種類や容量をカスタマイズします。例えば、写真編集を重視する場合は大容量のストレージを追加したり、ゲーム用なら高性能なGPUを搭載するといった具合です。注文内容が確定するとメーカーが組み立てを行い、検品を経て出荷されます。一般的には数日から1週間程度で手元に届くことが多いですが、パーツの在庫状況や注文内容によって納期が変わることもあります。

BTOというのは一言でいえば「自分仕様のパソコンを注文できる仕組み」なんです。既製品より自由度が高い分、どのパーツを選ぶかで快適さが大きく変わります。まずは自分が何にパソコンを使うのかを整理して、その目的に合わせた選び方を意識すると失敗しませんよ
BTOパソコンを選ぶメリットとデメリット
BTOパソコンは、既製品では得られない自由度やコスト効率を持つ一方で、注意しておくべき点もあります。ここでは、代表的なメリットとデメリットを整理して解説します。
メリット
必要な性能に合わせたカスタマイズが可能
CPU・メモリ・ストレージ・GPUなどを自分の用途に応じて選べるため、無駄のない構成が可能です。文書作成やインターネット利用が中心なら低価格構成で十分ですし、ゲーミングや動画編集なら高性能パーツを選んで強化できます。
コストパフォーマンスに優れる
市販の既製PCでは不要なソフトや過剰なパーツが含まれていることがありますが、BTOなら必要最小限の構成から組めるため、価格を抑えながら性能を確保できます。結果として「同じ予算でワンランク上の性能」を得やすいのが特徴です。
初期状態がシンプル
BTOメーカーの多くは、不要なアプリケーションを最初から入れないシンプルな環境を提供しています。そのため、動作が軽快で、初心者でも混乱せずに使い始められます。
将来的な拡張性が高い
自作PCに近い構成で組まれるため、メモリ増設やストレージ追加などのアップグレードが比較的容易です。長期間の利用を想定する場合でも柔軟に対応できます。
デメリット
選択肢が多すぎて迷いやすい
パーツの種類や性能の差を理解して選ぶ必要があるため、初心者には難しく感じられる場合があります。誤った選択をすると性能が不足したり、予算オーバーになることもあります。
納期が既製品より長いことがある
注文を受けてから組み立てる仕組みのため、在庫品のPCに比べて到着まで数日〜1週間程度かかる場合があります。急いでPCを必要としている人にはデメリットです。
初期設定や動作確認が必要
組み立て済みで届きますが、OSの初期設定やドライバ更新などを自分で行う必要があるケースがあります。PCに不慣れな方は少し手間取ることがあります。
サポートや保証の仕組みがメーカーによって異なる
標準保証の期間や、電話・チャットサポートの体制はメーカーごとに差があります。購入前に保証内容を確認しておかないと、トラブル時に不安を感じることがあります。

BTOパソコンは自由度とコスパの高さが大きな魅力ですが、初心者には「選び方」と「納期の長さ」がハードルになることがあります。選ぶ際は、自分の用途と予算をしっかり整理してからカスタマイズを考えるのがポイントですよ
用途別におすすめのBTO構成
BTOパソコンは「自分に必要な性能だけを選べる」ことが大きな魅力です。ここでは代表的な利用シーンごとに、必要なパーツ構成と目安スペックを整理します。初めて選ぶ方でも迷わないよう、優先度の高いポイントを中心に解説します。
ビジネス・事務作業向け
文書作成、表計算、メール、Web会議などを快適にこなすには安定性と応答速度が重要です。グラフィック性能は不要なため、コストを抑えやすい構成が選べます。
- CPU:Intel Core i5 / AMD Ryzen 5 クラス
- メモリ:8GB〜16GB
- ストレージ:SSD 500GB以上(OSと業務ソフトが快適に動作)
- GPU:内蔵グラフィックスで十分
- その他:静音性や省電力を重視、Officeソフトの追加が便利
ゲーミング向け
最新ゲームやeスポーツタイトルを快適に楽しむためには、高性能CPUと独立GPUが必須です。描画のなめらかさやロード時間短縮を意識しましょう。
- CPU:Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 以上
- GPU:GeForce RTX 4060〜RTX 4070以上(予算とプレイするタイトルに応じて選択)
- メモリ:16GB〜32GB(DDR5対応ならさらに快適)
- ストレージ:NVMe SSD 1TB以上(ロード短縮のため推奨)
- 冷却:空冷よりも水冷CPUクーラーがおすすめ(高負荷でも安定)
動画編集・クリエイティブ向け
動画編集、3DCG制作、写真現像などではCPU性能と大容量メモリが重要です。加えて高速なストレージと信頼性の高いGPUが作業効率を大きく左右します。
- CPU:Intel Core i7〜i9 / AMD Ryzen 9
- メモリ:32GB以上(プロジェクト規模によって64GB推奨)
- GPU:GeForce RTX 4070 Ti 以上、もしくはプロ向けGPU
- ストレージ:OS用SSD 1TB+作業用SSD 2TB+保存用HDDなど複数構成
- 電源:余裕のある高効率電源(80PLUS GOLD以上)
学生・ライトユーザー向け
レポート作成、動画視聴、SNS利用などが中心なら、性能を抑えても問題ありません。価格を重視しつつ快適さを確保できます。
- CPU:Intel Core i3 / AMD Ryzen 3 以上
- メモリ:8GB
- ストレージ:SSD 256GB〜500GB
- GPU:内蔵グラフィックスで十分
- 特徴:小型・軽量ノートや省スペースデスクトップが便利
プログラミング・開発環境向け
開発者向けには、複数ソフトを同時に立ち上げられるメモリと、仮想環境を快適に動かすCPU性能が欠かせません。
- CPU:Intel Core i7 / AMD Ryzen 7 クラス
- メモリ:16GB〜32GB
- ストレージ:NVMe SSD 1TB以上(プロジェクトやデータの保存に余裕が必要)
- GPU:プログラム内容により選択。ゲーム開発やAI系ならRTXシリーズ必須
- その他:デュアルディスプレイ対応や静音ケースがあると効率的

BTOパソコンは「使う目的」に合わせて構成を決めるのが大切です。性能を上げすぎると無駄なコストになりますし、逆に妥協しすぎると作業効率が落ちます。用途を整理してからCPU・メモリ・GPUを優先的に選ぶと失敗しにくいですよ
BTOでカスタマイズできる主要パーツの解説
BTOパソコンでは、必要な用途や予算に合わせて主要パーツを自由に組み合わせることができます。各パーツの役割を理解することで、最適な一台を選べるようになります。
CPU(プロセッサー)
CPUはパソコンの「頭脳」と呼ばれる最重要パーツです。クロック周波数、コア数、スレッド数が性能を左右します。
- 一般的な事務作業:Core i3 / Ryzen 3 クラスで十分
- ゲームや動画編集:Core i5 / Ryzen 5 以上がおすすめ
- 4K動画編集や3Dモデリング:Core i7・i9 / Ryzen 7・9 クラスが理想
処理内容に応じてグレードを上げることが快適な動作につながります。
GPU(グラフィックボード)
グラフィックス処理を担うパーツで、3Dゲームや動画編集には必須です。
- 一般用途:CPU内蔵グラフィックスでも十分
- ゲーム:NVIDIA GeForce RTXシリーズやAMD Radeon RXシリーズ
- クリエイター用途:高性能GPUで映像処理を高速化
用途に直結する性能差が出やすいため、最も投資を検討すべきパーツのひとつです。
メモリ(RAM)
メモリは「作業机」に例えられる領域で、容量が多いほど同時作業に強くなります。
- 一般用途:8GB〜16GB
- ゲームや動画編集:16GB〜32GB
- 大規模データ処理や映像制作:32GB以上
また、DDR5対応のメモリは処理効率が高く、最新モデルでは標準になりつつあります。
ストレージ(SSD・HDD)
データの保存領域で、速度や容量に違いがあります。
- SSD:起動やアプリの動作が高速。システムドライブに必須
- HDD:大容量データ保存向き。コストを抑えて動画や写真を保存できる
- NVMe SSD:さらに高速な転送速度で、ゲームや編集作業で有利
SSD+HDDの組み合わせがコストパフォーマンスの高い選択です。
電源ユニット
安定動作に欠かせない部分で、軽視するとトラブルの原因になります。
- 消費電力に合わせた容量(500W〜850Wが目安)
- 80PLUS認証(変換効率を保証する規格)を確認
高性能GPUや多くのパーツを搭載するなら、余裕を持った容量を選ぶことが大切です。
冷却システム
高負荷時に発生する熱を効率的に処理する仕組みです。
- 空冷クーラー:価格が安くメンテナンスしやすい
- 水冷クーラー:冷却性能が高く静音性にも優れる
長時間のゲームや動画編集を行うなら、水冷モデルの導入も検討すると安心です。
その他のカスタマイズ可能パーツ
- 光学ドライブ(DVD/Blu-ray):映像の書き込みや再生が必要な場合に追加
- ネットワークカード:Wi-Fi 6Eなど最新規格に対応可能
- ケースやファン:デザイン性やエアフロー改善に寄与
必要性が低ければ削減し、コストを抑える工夫も可能です。

主要パーツはそれぞれ役割が違うので、用途に直結する部分から優先的に強化すると満足度が高くなりますよ。CPUとGPUは性能に直結、メモリとストレージは作業快適度に直結、電源や冷却は安定性に直結します。初心者の方は「用途別の優先度」を意識してカスタマイズを選んでいくと失敗が少なくなります
初心者が失敗しないBTOパソコンの選び方
まずは用途を明確にする
BTOパソコンを選ぶ際に最も重要なのは「何に使うか」をはっきりさせることです。
インターネットや文書作成が中心であれば、CPUやグラフィックボードは最上位である必要はありません。
一方で、最新ゲームや動画編集を快適に行いたい場合は、高性能なGPUや大容量メモリが必須になります。
まず「普段の使い方」「将来の使い方」を書き出して、必要最低限のスペックを整理すると無駄な出費を防げます。
予算の中で優先順位を決める
限られた予算内で最も効果的に性能を引き出すためには、パーツごとに優先順位を付けることが大切です。
例えば、処理速度に直結するCPUやSSDは優先度が高く、データ保存用のHDDや光学ドライブなどは後回しにしても問題ありません。
また、グラフィック性能が不要な用途ではGPUを省き、その分をメモリやSSDに回すと体感的な快適さが向上します。
初心者におすすめの基本構成
- CPU:Core i5 または Ryzen 5 クラス以上
- メモリ:16GB(ゲームや編集をするなら32GB推奨)
- ストレージ:SSD 500GB以上+必要に応じてHDD追加
- GPU:ゲーミングなら GeForce RTX 4060/4070 以上、一般用途なら内蔵GPUでも十分
この程度の構成であれば、多くの作業を快適にこなすことができます。無理に最上位モデルを選ぶ必要はありません。
不要なカスタマイズを避ける
初心者が失敗しやすいポイントのひとつが「必要以上に高性能なパーツを選んでしまうこと」です。
冷却用の水冷クーラーや大容量電源ユニットなどは、特殊な用途や長時間の高負荷作業をしない限り不要です。
また、オフィスソフトやセキュリティソフトは後から購入や変更が可能なので、初期構成で無理に追加する必要はありません。
将来の拡張性も意識する
最初からすべてを完璧に揃えなくても、後からメモリやストレージを増設できるのがBTOパソコンの強みです。
購入時点では必要最低限に抑え、将来必要に応じてアップグレードすることで、コストを抑えながら長く使うことができます。

BTOパソコン選びで大事なのは「やりたいことを整理して、予算の中で優先順位をつける」ことです。高すぎるスペックを選んでしまうより、バランスを取るのが失敗しないコツですよ
主要BTOメーカーの特徴と比較
BTOパソコンを選ぶ際は、メーカーごとの強みやサポート体制を把握することが大切です。ここでは代表的な国内主要メーカーを取り上げ、それぞれの特徴を整理しました。
マウスコンピューター
マウスコンピューターは国内生産にこだわり、品質管理やサポートを重視しているメーカーです。特徴は24時間365日の電話サポートと3年間の無償保証(一部製品除く)が標準で付属している点です。初心者にも安心できる体制が整っています。
製品ラインは幅広く、普段使いの「mouse」、ゲーミング特化の「G-Tune」、クリエイター向けの「DAIV」、法人向けの「MousePro」などがあり、用途に応じて選びやすいのも魅力です。また、余計なソフトがほとんど入っていないシンプルな初期状態や、最短翌営業日の出荷サービスも強みです。
ドスパラ(GALLERIA)
ドスパラは全国展開の店舗とオンラインショップを持ち、サポートや購入相談を気軽に受けられる点が特徴です。ゲーミングブランド「GALLERIA」は知名度が高く、プロゲーマーからの支持も厚いです。最短当日出荷が可能で、急ぎでPCが必要な場合にも対応できます。
カスタマイズの自由度が高いだけでなく、店舗スタッフによる直接相談や修理対応も受けられるため、実店舗でのサポートを重視するユーザーに向いています。保証は標準で1年間ですが、有償で延長可能。月額サービス「セーフティサービス」を利用すれば物損保証やパーツ保証も追加できます。
パソコン工房
パソコン工房は地方を含め全国に実店舗が多く、幅広いユーザー層に対応できる点が強みです。価格競争力が高く、同等スペックでも比較的安く購入できるケースが多いです。ゲーミングブランド「LEVEL∞」やクリエイター向け「SENSE」など、用途ごとにシリーズを展開しています。
実店舗ではパーツ交換や修理、相談対応が可能で、初心者から自作経験者まで幅広く利用されています。保証期間は標準1年ですが、有償で延長保証や安心パックを追加でき、地方在住者でもサポートを受けやすいのが利点です。
まとめ
主要BTOメーカーは、それぞれ得意分野とサポート体制に特徴があります。マウスコンピューターは「手厚い保証と国内生産」、ドスパラは「ゲーミング性能とスピード対応」、パソコン工房は「価格と店舗ネットワーク」が強みです。自分が重視するポイントに合わせて選ぶことで、満足度の高いBTOパソコンを手に入れることができます。

大事なのは、自分がどの点を重視するかを整理することです。保証やサポートを重視するならマウスコンピューター、ゲーミング性能と即納ならドスパラ、コスパや店舗サポートを求めるならパソコン工房が向いています。メーカーごとの違いを理解して、自分に合った一台を選んでくださいね
注文から納品までの流れと納期の目安
BTOパソコンは完成品と異なり、注文後に組み立てや検査を行うため、納期はカスタマイズ内容やメーカーの在庫状況によって変動します。流れを理解しておくことで、納品までの不安を減らすことができます。
注文から納品までの基本ステップ
- 製品とカスタマイズの選択
メーカー公式サイトでベースモデルを選び、CPUやメモリ、ストレージ、GPUなどを用途に合わせてカスタマイズします。必要に応じて保証や周辺機器も追加できます。 - 注文内容の確認・支払い
選択した内容をカートに入れ、構成・金額を確認したうえで注文を確定します。クレジットカード、分割払い、コンビニ払いなど複数の支払い方法が用意されています。 - 組み立て・検査工程
注文が確定すると、国内工場や提携工場でパーツの組み立てが行われます。その後、動作確認や品質検査を経て出荷準備に入ります。特に高性能パーツを選んだ場合は、冷却性能や安定性のチェックが丁寧に行われます。 - 発送・配送
出荷が完了すると、登録したメールアドレスに配送番号が通知されます。一般的には宅配便で届けられ、受け取り時に本人確認が必要な場合もあります。 - 納品後の初期設定
到着後はOSの初期設定やネットワーク接続、必要なアプリケーションのインストールを行います。メーカーによっては、初期設定代行やデータ移行サービスをオプションで用意している場合があります。
納期の目安
- 通常納期
多くのメーカーでは、注文確定から出荷まで 約5〜10営業日 が一般的です。パーツ在庫が豊富でシンプルな構成なら、1週間程度で届くこともあります。 - 短納期モデル・当日出荷サービス
ドスパラではカスタマイズをしても最短当日出荷が可能で、翌日受け取りに対応しています。マウスコンピューターも「翌営業日出荷サービス」を提供しており、13時までの注文で翌営業日に出荷されます。 - 繁忙期や在庫不足時
年末年始や大型セール時期は注文が集中し、納期が 2〜3週間以上 に延びる場合があります。新発売のCPUやGPUを指定した場合も、供給状況により納期が長くなることがあります。
納期を早めたいときの工夫
- 短納期対応モデルや当日出荷サービスを選ぶ
- 複雑なカスタマイズを避け、標準構成に近いモデルを選択する
- 在庫が豊富なパーツを選ぶことで、部材待ちによる遅延を防ぐ

注文から納品までの流れは大きく5ステップに分かれます。通常は1〜2週間程度ですが、短納期サービスを利用すれば即日出荷も可能です。繁忙期や在庫状況で納期が変動するので、余裕を持った注文が安心ですよ
購入後のサポートと保証内容をチェック
BTOパソコンは購入時のスペックや価格だけでなく、購入後のサポート体制や保証内容も安心して使い続けるために重要な要素です。ここでは、標準保証・延長保証・修理対応・サポート体制の4つの観点から確認すべきポイントを解説します。
標準保証の内容
多くのBTOメーカーでは、購入時に1年間の無償保証が標準で付帯しています。自然故障や初期不良が対象で、パーツ交換や修理費用が無償でカバーされることが一般的です。
一方で保証期間や対象範囲はメーカーごとに異なり、例えばマウスコンピューターでは3年間無償保証が標準付帯しているケースもあります。購入前に「保証期間が何年か」「自然故障と物損の違いはどうか」を必ず確認しましょう。
延長保証と追加サービス
BTOメーカーは有償で保証を延長できるオプションを提供している場合が多いです。標準1年の保証を3~5年まで延長できるプランや、落下や水濡れといった物損にも対応する「セーフティサービス」「プレミアム保証」などがあります。
また、法人向けにはオンサイト修理(出張修理)や代替機の貸し出しサービスを用意しているメーカーもあり、業務用途での利用を考える場合は大きな安心材料になります。
修理や交換の流れ
修理対応の流れはメーカーによって異なりますが、一般的には「電話やWebでの故障診断 → 修理依頼 → 引き取りまたは持ち込み → 修理後返送」といったステップです。
マウスコンピューターでは72時間以内の修理対応を掲げており、ドスパラでは最短で当日修理や即日交換が可能なサービスを展開しています。購入後に「修理時の送料負担が必要か」「データ復旧は有料か」といった点も確認しておくと安心です。
サポート体制の見極め方
初心者にとって重要なのがサポート体制です。24時間365日対応の電話サポートやチャット・LINE対応があるメーカーは、トラブル時にすぐ相談できるため安心感が高いです。
また、全国に実店舗を展開しているドスパラのようなメーカーなら、直接スタッフに相談できる点も大きな強みです。法人利用であれば専用窓口や担当者サポートの有無も選定の決め手になります。

購入後の安心は、保証期間の長さだけでなく「修理の速さ」「サポート窓口の使いやすさ」で決まります。初心者の方は、延長保証や24時間サポートがあるメーカーを選ぶと、万一のトラブルにも落ち着いて対応できますよ