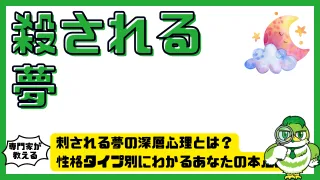本ページはプロモーションが含まれています。
目次
Midjourneyとは?基本と特徴をわかりやすく整理

Midjourneyは、入力したテキストから高品質な画像を自動生成するAIツールです。言葉でイメージを伝えるだけで、写真風のリアルな表現からイラスト調のアート作品まで幅広く作り出せるため、クリエイターだけでなく初心者にも利用しやすいサービスとして注目されています。
Midjourneyの基本的な仕組み
プロンプト(指示文)を入力すると、AIがその内容を解析し、最適な構図・色・質感をもとに画像を生成します。AIモデルの学習データをもとに、テキストに含まれるニュアンスやキーワードを理解する仕組みのため、短い文章でもビジュアルを作成できるのが特徴です。
プロンプトが英語の場合はより細かなニュアンスを伝えやすい傾向がありますが、日本語でも問題なく利用できます。意図を正確に伝えるために、ChatGPTで英文を整えてから入力するユーザーも増えています。
幅広い表現が得意な画像生成AI
Midjourneyが支持されている理由のひとつが、幅広いスタイルに対応できる点です。
たとえば次のような表現を自然に生成できます。
- 現実の写真に近い写実的な表現
- 絵画やアニメのようなアート表現
- 幻想的な世界観のイメージ
- デザイン案・コンセプトアートの作成
特定のクリエイターの作風に寄せたスタイルや、ライティング・色調を細かく調整したビジュアルもつくれます。
独特の美しい仕上がりが特徴
Midjourneyの大きな特徴として、「独自の美しさ」を持つ生成結果があります。ディテールの表現力が高く、構図が自然で、アート寄りのバランスが取れた画像が得意です。構図や陰影が整っているため、SNSや商業用途のビジュアル作成でも活用されています。
Web版とDiscord版の両方で利用可能
Midjourneyはブラウザから利用できるWeb版と、コマンドを使って操作するDiscord版の2つがあります。
- Web版:直感的なUIで操作でき、画像管理もわかりやすい
- Discord版:細かなコマンド操作ができ、画像のバリエーション生成や情報確認などが柔軟
どちらを使っても生成される画像の品質は変わらないため、用途に合わせて使い分けられます。
初めてでも使いやすい理由
Midjourneyは、専門知識がなくても画像生成が始められる点が人気です。テキストを入力するだけで4枚の候補画像が作成され、そこからアップスケールやバリエーションを選ぶだけで完成します。
また、生成速度が速く、待ち時間が少ないのも魅力です。短時間で多数の案を比較したいときにも便利で、デザインの下書き作成やアイデア出しにも向いています。
画像生成AIの中でも特に人気を集める理由
Midjourneyは他の画像生成AIと比べても「完成度の高いビジュアル」を得やすい点が大きな魅力です。特にアート性の高い作品を求めるユーザーから高く評価されており、SNSではMidjourney特有の美しい質感が注目されています。
加えて、アップデートが頻繁に行われ、表現力が常に向上し続けている点も強みです。新機能の追加によって、スタイルの統一、画像のリファレンス参照、カスタマイズ性の向上など、より柔軟なクリエイティブ制作が可能になっています。

Midjourneyは、言葉からイメージを具現化してくれる心強いツールです。特徴を理解しながら使えば、初心者でも驚くほど高品質な画像を作れますよ。まずはシンプルな指示から試して、少しずつプロンプトの精度を上げていくのがおすすめです
Midjourneyでできること一覧
Midjourneyは、1行のテキストから驚くほど高品質なビジュアルを生み出す画像生成AIですが、実際に使える機能は「画像生成」だけにとどまりません。制作の幅を一気に広げるための加工・編集・スタイル統一・調整機能が数多く用意されています。ここでは、初心者でも迷わず理解できるように、主要な機能を目的別に整理して解説します。
テキストから画像を生成する
Midjourneyの最も基本的な機能が、テキストを入力して画像を生成するプロンプト生成です。
短い指示でも4枚の画像が自動生成され、そこからさらに拡大・別パターンを選びながら作品の方向性を固めていく使い方ができます。
英語プロンプトが推奨されていますが、日本語での入力も可能で、初心者でも簡単に操作できます。
画像の雰囲気や質感を引き継ぐスタイルリファレンス
手持ちの画像を参考として読み込ませることで、その「色味」「光」「質感」「タッチ」を新しい画像に反映できます。
複数の画像の世界観を統一したいときや、ブランドのビジュアルガイドラインに合わせたいときに特に便利な機能です。
- 既存画像のトーン・画材感を反映
- 複数画像で一貫した作風を生成
- Web版・Discord版どちらでも利用可能
画像を微調整・大胆に変化させるバリエーション生成
生成した画像をもとに、異なる構図・細部の違い・雰囲気の変化を加えた「別パターン」を自動生成できます。
- 微調整向けのサブトル・バリエーション
- 大きく構図が変わるストロング・バリエーション
1つのプロンプトから複数の方向性を試すことができ、デザイン検討のスピードが大きく向上します。
バージョン切り替えでスタイルを変更する
Midjourneyはモデルバージョンごとに特徴が大きく異なります。目的に合わせて旧バージョンに切り替え可能です。
- 写真風が強いモデル
- イラスト・アニメ特化モデル(Niji)
- シャープで色彩豊かなモデル
- ノイズが少なく扱いやすいモデル
最新モデルで満足いく結果が得られない場合も、旧バージョンを選ぶことで理想に近づくケースが多くあります。
プロンプトの解像度を上げる高度なパラメータ指定
Midjourneyでは、画像生成の仕上がりを細かくコントロールするためのパラメータが利用できます。
たとえば以下のような調整が可能です。
- アスペクト比(–ar)でサイズ比率を変更
- 品質(–q)で解像感と処理時間を調整
- 生成の芸術性(–stylize)で作風の強さをコントロール
- 指定要素を除去する(–no)
- シード値(–seed)で再現性を確保
- アニメ特化モード(–niji)
- テクスチャ制作向けのシームレス生成(–tile)
操作に慣れていくほど、生成の精度を大きく高めることができます。
画像をベースにした生成(画像プロンプト)
テキストだけでなく、画像そのものをプロンプトとして使用できます。
構図やポーズ、形状を引き継ぎつつも、全く新しいイメージへ変換することが可能です。
- 写真をアニメ風に変換
- 手描きラフを高品質なアートへ昇華
- 素材画像の別バリエーション作成
発想を形にする制作ツールとして非常に強力です。
写真・イラストの精細アップスケール
気に入った1枚を選び、さらに画質を向上させるアップスケール機能も利用できます。
- 解像度の向上
- 細部の描写強化
- 質感・光の表現を最適化
作品として仕上げたり、商用利用向けの高解像度素材に仕上げたいときに必須となる工程です。
タイル画像・パターン生成
背景用のテクスチャや壁紙など、つなぎ目のない連続パターンを生成できます。
デザイン制作やWebサイト・アプリ制作、資料用素材作成など幅広い用途に役立ちます。

生成AIの機能は多く見えますが、1つずつ触っていくとすぐに慣れていきます。特にバリエーションとパラメータを覚えると、思い通りの画像が作れて楽しくなりますよ。自分の制作目的に合わせて、試しながら理解を深めていきましょう
Midjourneyの始め方とアカウント準備
Midjourneyを使い始めるための手順はシンプルですが、初めての方は「どこから始めればいいのか分からない」「Discordとブラウザ版どちらを選ぶべきか迷う」といった悩みが多く寄せられます。ここでは、最短で迷わず始められるように、競合サイトの要素を踏まえつつも実際に使いこなせるレベルまで掘り下げて整理します。
アカウント準備の前に知っておくべき基本ポイント
Midjourneyは現在、無料トライアルが停止されているため、有料プランを契約しないと利用を開始できません。登録前に以下を把握しておくとスムーズです。
- GoogleアカウントまたはDiscordアカウントを使用してログインする仕組み
- 年齢要件は13歳以上(未成年の場合は保護者の同意が必要)
- 利用には規約とコミュニティガイドラインの遵守が必須
- ブラウザ版とDiscord版で操作方法が異なる
ここを理解した上で、実際の登録手順に進むと戸惑いを減らせます。
Midjourneyのアカウント作成手順
Midjourneyの登録は、公式サイトから数ステップで完了します。重要なポイントや初心者がつまずきやすい箇所も併せて説明します。
1. 公式サイトにアクセスする
トップページにある「Sign Up」を選択します。アカウント作成と同時に有料プランの契約選択が必要です。
2. ログイン方法を選ぶ
表示される選択肢から次のいずれかを選びます。
- Googleアカウント
- Discordアカウント
どちらを選んでも機能的な違いはありませんが、Discord版も使う予定がある場合はDiscordアカウント連携がおすすめです。
3. アカウント連携の許可
ログイン後、Midjourneyがアカウント情報へアクセスするための認証画面が表示されます。アクセス範囲を確認して許可します。不安がある方は、必要最低限の情報だけが共有される仕組みになっていることを理解しておくと安心です。
4. 初期設定を確認する
ログイン後、Web版の「Create」ページが表示され、すぐにプロンプトの入力ができます。
初期状態では設定が最適化されているため、最初に細かい調整は不要です。
Web版とDiscord版、どちらから始めるべきか
Midjourneyには二つの利用方法があります。それぞれの特徴を理解して、自分に合う方から始めるのが効率的です。
Web版(Midjourney Alpha)
- 直感的に操作できるUI
- 過去の生成画像が一覧で管理しやすい
- 画像アップロードやスタイルリファレンスが簡単
- 「とにかく簡単に始めたい」方に向いている
Discord版
- /imagine や /describe などの高度なコマンドが使える
- コミュニティ内で他ユーザーの作品を見ながら学べる
- パラメータ操作や細かい指示が行いやすい
- プロンプト制御を細かく行いたい方に向いている
最初はWeb版で操作を覚えながら、必要に応じてDiscord版を併用する流れが一番スムーズです。
ミスを防ぐためのアカウント初期設定チェックポイント
登録後に必ず確認しておきたい設定をまとめます。
- プランが意図した内容か(Basic/Standard/Proなど)
- ギャラリー公開設定(商用利用を前提にするならPro以上でステルスモード推奨)
- 使用デバイス(スマホ・PC)のログイン環境が統一されているか
- 支払い方法の登録状況
この段階で設定が整っていれば、「プロンプトを入力したのに反応がない」「画像生成が途中で止まる」などの初歩的なトラブルを防げます。
登録後すぐに画像生成できるようになるまで
アカウントが準備できたら、次のステップで即画像生成が可能です。
- Web版にログインし「Create」ページを開く
- Imagineバーにキーワードを入力する
- Enterで送信すると4枚の画像が自動生成
この一連の操作ができれば、基本的な画像生成は完了です。日本語でも入力できますが、細かなニュアンスは英語のほうが伝わりやすいため、ChatGPTで英訳したプロンプトを使うのが有効です。

Midjourneyの登録でつまずきやすいポイントは、ほとんどが「どのアカウントを使えばいいのか」「Web版とDiscord版の違いが分からない」といった初歩的な部分です。この記事で紹介した手順に沿って進めれば、初日のうちに問題なく画像生成を始められます。安心して取り組んでくださいね
Midjourneyの使い方。プロンプト入力から生成まで
Midjourneyの画像生成は、基本の流れさえつかめば誰でも扱えるようになります。ここでは初心者がつまずきやすいポイントを避けつつ、Web版を中心に、最短で画像を作れる手順を整理します。プロンプトの工夫や生成後の操作も加えて、実際に使いこなせるレベルまで理解できる構成にしています。
Midjourneyの基本操作フローを理解する
Midjourneyで画像を生成する流れは大きく分けて3ステップです。
- Imagineバーにプロンプト(指示文)を入力
- 送信して画像生成を開始
- 4枚の初期画像からアップスケール・バリエーションを選択
細かい設定を覚える前に、この3つの流れを自然に操作できれば十分です。
Imagineバーにプロンプトを入力する
MidjourneyのWeb版には、画面上部に「Imagine」という入力欄があります。これがプロンプトの入力場所です。
テキストを入力して送信すると、AIが文脈を解析して画像を生成します。日本語でも動作しますが、ニュアンスを正確に伝えたい場合は英語のほうが安定します。英語が苦手な場合は、ChatGPTで「プロンプトを英語にしてください」と依頼するとスムーズです。
最初は短い文章でも問題ありません。
例a cat sitting on a chair, soft lighting, detailed fur
文章が長すぎると意図を読み違えることがあるため、必要最低限から始めて徐々に加えていくほうが効率的です。
4枚の画像が生成される仕組み
プロンプトを送信すると、初期の画像が4枚まとめて生成されます。これはMidjourneyの標準仕様で、以下のために用意されています。
- 構図や雰囲気の候補を比較できる
- 意図に近いものを基準に細かい調整がしやすくなる
生成される4枚は「完成品」ではなく、ここから調整していくための“素案”のような位置づけです。
気に入った画像をアップスケールする
4枚の中に気に入ったものがあれば、「アップスケール(U)」を実行できます。Uを押すと、画質が向上した大きめの画像が生成されます。
アップスケール後は以下の操作が可能です。
- 高解像度でダウンロード
- 再度アップスケールして細部をより鮮明に
- 微調整バリエーションを作成
特にSNS投稿や素材利用を考える場合はアップスケールが必須です。
バリエーション機能で別パターンを試す
初期の4枚から「雰囲気は好きだけど構図を変えたい」「もう少し違う角度の案が欲しい」という場合は、バリエーション(V)を選びます。
- Subtle Variation:小さな変化で要素を維持
- Strong Variation:大胆に構図を変更
最初からプロンプトを作り直す必要はなく、小さな調整を繰り返すことで理想の画像に近づけることができます。
プロンプトから生成までのコツ
Midjourneyの生成品質はプロンプトの書き方で大きく変わります。操作に慣れてきたら、以下の視点を追加すると生成が安定します。
明確に伝える
曖昧なワードより、状況や質感、光の状態などを具体化すると意図が伝わりやすくなります。
不要な要素は「–no」で排除
例:beautiful portrait, –no text –no watermark
現実には含まれてしまいがちな余計な文字やロゴを避けたい場合に有効です。
画角・アスペクト比を決める
横長なら--ar 16:9
縦長なら--ar 9:16
目的に合った構図が最初から得られます。
Web版・Discord版での使い分け
Web版は直感的で分かりやすく、Discord版は細かいコマンド操作ができます。基本的にはWeb版で十分ですが、以下の用途ではDiscord版が有利です。
- コマンド入力による詳細な制御
- 他ユーザーの生成例を参考にする
- 画像を融合するBlend機能を使う
両方は自動で同期されるため、好きな方を使って問題ありません。
最初の一枚を確実に成功させるためのチェックポイント
- 主語(主題)を必ず入れる
- 不必要な要素は–noで排除する
- アスペクト比を決める
- 文量は多くし過ぎない
- 完成後はアップスケールして調整する
この5つが揃えば、ほとんどの初心者が「意図が伝わらない」といった失敗を避けられます。

プロンプト入力から生成までの流れは、一度手を動かすとすぐに慣れてきますよ。最初は短い文章で生成して、気になるところだけ調整していくと、無理なく理想の画像に近づけられます。焦らず、少しずつ操作に慣れていきましょう
プロンプト作成のコツと画像を狙い通りにする方法
Midjourneyで「思っていたのと違う」仕上がりになる最大の原因は、プロンプトの情報不足と構造の曖昧さです。AIは単語単位で意味を組み立てるため、主題・質感・光・構図などを明確に分けて伝えるほど、狙い通りの画像に近づきます。ここでは、初心者でもすぐ実践でき、競合が触れきれていない「精度を高める実用テクニック」を整理します。
主題・スタイル・環境を明確に書く
画像生成の軸となるのは「何を」「どんな見た目で」「どんなシーンで」です。抽象的な指示は誤解されやすいため、具体性が重要です。
例:
悪い例:beautiful landscape
良い例:a wide green valley with layered mountains, morning fog, soft sunlight, realistic nature photography
イメージを構成する代表的な要素は次のとおりです。
- 主題(人物・動物・物体・風景)
- メディア(写真・油絵・水彩・3D・ドローイング)
- ライティング(soft light / studio light / backlight)
- 雰囲気(cinematic / peaceful / dark fantasy)
- 色調(warm tone / pastel / monochrome)
- 構図(close-up / portrait / birds-eye view / wide shot)
これらを文章として繋ぐとAIが解釈しやすくなり、狙いどおりの結果に近づきます。
「パワーワード」で質感・雰囲気をコントロールする
Midjourneyは特定のキーワードに強く反応します。これらを組み込むだけで画風が大幅に変わるため、細かな調整を短い文で行うときに効果的です。
代表的なパワーワード:
- photorealistic(極めて写実的)
- cinematic lighting(映画のような光)
- ultra detailed / hyper realistic(ディテール強化)
- surreal / dreamy / dark fantasy(世界観の付与)
- minimalism / abstract / futuristic(デザイン方向の指定)
無理に多用するとノイズになるため、2〜4個程度にまとめるのが扱いやすい方法です。
クリエイター風のスタイルで方向性を寄せる
画家・写真家・デザイナーなどのスタイルを利用すると、まとまった雰囲気を作りやすくなります。
例:
inspired by Studio Ghibli
in the style of a 1970s film photographer
ただし、アーティスト名の扱いにはガイドラインがあるため、安全性を考慮して「特定作品の模倣」ではなく「時代・ジャンル・技法」を使った表現が有効です。
例:
oil painting style, 19th-century impressionist techniques
プロンプトウェイト(::)で重要度を調整する
Midjourneyは「::数字」をつけることで、単語ごとの強さを調整できます。特に複雑なシーンで活用すると効果的です。
例:
white cat::4 wooden desk::2 modern office::1
数字が大きいほど優先されるため、「絶対に入れたい要素」「できれば入ってほしい要素」を分けることができます。
マルチプロンプトで誤解を減らす
意味の区切りが曖昧だと、AIが単語を一つの概念として結合してしまう場合があります。そんなときは「::」で切り分けて別要素として理解させます。
例:
ice::cream → 氷とクリームという2つの概念として扱われる
ice cream → アイスクリームとして解釈される
複合語で誤解されやすいときに特に便利なテクニックです。
パラメータで比率・質感・モデル挙動をコントロールする
プロンプトの最後にパラメータをつけて、画像の最終仕上がりを調整します。特に次の5つは使用頻度が高く、初心者でも扱いやすいです。
- –ar(アスペクト比)
例:–ar 16:9/–ar 4:5 - –style raw(AIのスタイル補正を弱め、プロンプトの指示に忠実)
- –q(品質と生成速度の最適化)
例:–q 1(高品質)/–q 0.5(高速) - –s(スタイライズ:芸術性の強さ)
例:–s 50(自然)/–s 1000(アーティスティック) - –no(除外したい要素)
例:–no blur –no watermark
余計な要素が入りやすい構図ほど、–no の指定が大きな効果を発揮します。
「段階的に調整する」のが最速で狙いに近づく方法
一度にすべてを詰め込むとAIが迷い、意図から外れやすくなります。最短で狙い通りにするには以下の流れが合理的です。
- 主題・シーン・光だけで生成
- 必要に応じてスタイルを追加
- パワーワードで質感を整える
- ウェイトとマルチプロンプトで構造をクリアにする
- 最後にパラメータで微調整
段階的に洗練させることで、狙いに近い画像に着実に近づけます。
よくある「失敗の原因」と対処
- 情報量が少ない
→ 主題・シーンの具体化、構図の追加 - 要素を詰め込みすぎる
→ 重要な指示を優先して不要なものを削る - 複数要素が混ざる
→ マルチプロンプト・ウェイトで整理する - 全体がぼやける
→ –style raw や –q 1 で描写強化

プロンプトは“文章の組み立て方”が上手くなるほど、画像の精度も上がります。主題・光・構図をしっかり押さえておけば、大きく外れることはありません。まずはシンプルに作って、少しずつ足し引きしながら理想のイメージに近づけてみてくださいね
Midjourneyの料金プランと違い
Midjourneyは無料プランが提供停止となっているため、現在は4つの有料プランの中から選んで利用する仕組みになっています。生成速度や利用可能なモード、商用利用の条件がプランごとに大きく異なるため、目的や使用頻度に合わせた選択が重要です。ここでは各プランの違いと、ITが苦手な方でも迷わず選べるようにポイントを整理して解説します。
Basicプラン
もっとも安価に始めたい方向けのエントリープランです。高速GPU時間の範囲内で画像生成を行う仕組みなので、利用頻度が低い場合に向いています。
特徴
- 月額10ドル(年額96ドル)
- 高速GPU:3.3時間(200分)
- リラックスモードなし
- ステルスモードなし
- 同時生成:画像3件/動画1件
- 商用利用は可能(企業利用は条件あり)
生成枚数が多くなると高速GPUがすぐに消費されるため、頻繁に使う場合は物足りなくなりやすい点に注意が必要です。
Standardプラン
個人利用で最も選ばれやすいバランス型プランです。無制限のリラックスモードが利用できるため、時間を気にせず生成したいユーザーに向いています。
特徴
- 月額30ドル(年額288ドル)
- 高速GPU:15時間
- リラックスモード:無制限
- ステルスモードなし
- 同時生成:画像3件/動画3件
- 商用利用に十分対応
生成速度を優先したい場面と、じっくり生成したい場面の両方を使い分けられる点が魅力です。
Proプラン
商用利用や高頻度の生成に適したプランで、ステルスモードが利用できるため、画像を非公開で扱いたいケースに向いています。
特徴
- 月額60ドル(年額576ドル)
- 高速GPU:30時間
- リラックスモード:無制限
- ステルスモード:利用可能
- 同時生成:画像12件/動画6件
- 企業の商用利用にも対応(年商100万ドル未満)
大量生成やビジネスでの継続運用が必要な方に最適です。
Megaプラン
最上位プランで、高速GPUが最も多く、動画生成も含めて大量のクリエイティブを高速に処理できます。
特徴
- 月額120ドル(年額1,152ドル)
- 高速GPU:60時間
- リラックスモード:無制限
- ステルスモード:利用可能
- 同時生成:画像12件/動画12件
- 大規模な制作環境・法人利用向け
制作頻度が高い場合や、社内で複数人が1つの契約で大量に生成する場面でも安定して使えるよう設計されています。
どのプランを選べばいいか
プラン選びは生成枚数・仕事での利用の有無・非公開の必要性の3点で決めると失敗しません。
- とりあえず試したい → Basic
- 画像生成をたくさんしたい/副業や販売に使いたい → Standard
- 公開ギャラリーに出したくない/商用で本格運用したい → Pro
- 制作チームや企業で大量生成する → Mega
GPU時間を使い切りやすい方はStandard以上を選ぶと費用対効果が高くなります。

料金プランは目的ごとにかなり違うので、最初はStandardを選んで様子を見るのがいちばん無難ですよ。非公開で扱う必要が出てきたらProに上げると、安心して商用にも使えるようになります。
生成画像の商用利用と注意点
Midjourneyは有料プランを契約していれば商用利用が可能で、個人・企業どちらでもビジネス活用ができます。ただし、プランの条件や著作権、公開設定など、実際に商用利用するうえで押さえるべき重要なポイントが複数あります。誤った使い方をすると、著作権侵害や企業ポリシー違反など思わぬトラブルにつながるため、仕組みを正しく理解しておくことが大切です。
商用利用が可能になる条件
Midjourneyで生成した画像は、有料プラン契約中であれば商用利用できます。基本的にはどの有料プランでも商用利用が可能ですが、以下の条件だけは必ず確認してください。
- 企業・組織の年間売上が100万ドル(約1億円)を超える場合、Pro以上が必須
- プラン解約後でも、契約中に生成した画像は継続して商用利用可能
- 他人が作成した画像のアップスケール版は商用利用不可
企業の規模によって必要なプランが異なる点は見落としやすいため、ビジネス利用時は特に注意が必要です。
著作権の扱いとリスク
Midjourneyで生成した画像は自由に使えますが、著作権が完全にユーザーへ移るわけではなく、Midjourney側もライセンス権を保持します。これにより、以下のようなリスクが発生します。
生成画像の著作者はユーザーではなく「AI」
生成画像は「AIが自動生成したもの」と扱われるため、人間の創作性が十分に認められないケースでは、著作権が明確に付与されない可能性があります。そのため、作品の保護を期待する使い方には向きません。
既存作品に極端に似た画像の利用には要注意
AIは大量の学習データを元に生成するため、知らないうちに既存作品と雰囲気・構図が似てしまうことがあります。以下の場合は特に注意が必要です。
- 実在アーティスト名を連想させるプロンプトを使用した時
- 特徴的すぎるキャラクターやブランドに似てしまう時
- 有名な写真・アートの構図をほぼ再現してしまった時
商用利用する画像は、第三者の権利を侵害していないか慎重に確認してください。
公開設定とステルスモードの重要性
Midjourneyで生成した画像は、初期設定では「公開ギャラリー」に表示されます。他ユーザーから閲覧されるだけでなく、規約上は一定範囲で再利用を許可する扱いになります。
商用利用や企業案件で「他者に見られたくない」「複製されたくない」という場合は、Pro以上で使えるステルスモードが必須です。
ステルスモードを活用するメリット
- 生成した画像が公開ギャラリーに表示されない
- 他ユーザーからの閲覧・利用を防げる
- クライアント案件や未発表企画の素材を安全に扱える
商用目的であれば、ステルスモードの利用を前提にするほうが安全です。
商用利用の実例と注意点
Midjourneyの生成画像は、さまざまなビジネスで活用できます。
- ECサイトの商品イメージ案
- 広告バナーの背景素材
- 書籍・記事のメインビジュアル
- アプリ・ゲームのコンセプトアート
- NFTや小規模ブランドのアート作品
ただし、以下の点には必ず注意してください。
- 人物写真風の場合、実在人物との類似がないか確認する
- AIが生成した誤情報(架空の文字、歪んだアイテムなど)が含まれないかチェックする
- キャラクター系ビジネスでは版権管理に特に注意する
- 既存ブランドを連想させるデザインは避ける
- 生成した画像の公開・販売時は「AI生成である」と明示する企業も増えている
安全に商用利用するためには、画像チェックの工程を必ず挟むことが重要です。
商用利用する前に押さえるべきチェックリスト
過度にリストだらけにならないよう、必要最低限の項目だけをまとめます。
- 使っているプランが商用利用に適したプランか
- 画像が既存作品に似すぎていないか
- 実在の人物・企業・キャラに酷似していないか
- 公開設定のままになっていないか
- ステルスモードが必要な用途か
- 他者が生成した画像をそのまま使っていないか
商用利用前に確認しておくことで、後のトラブルを大きく減らせます。

商用利用はとても便利ですが、仕組みを理解しないまま使うと危険な場面もあります。特に企業規模によるプランの条件や、公開設定のまま利用するリスクは見落としがちです。安全にビジネスへ活用したい時は、必ず利用規約を確認して、生成画像のチェックを丁寧に行ってくださいね
Midjourneyを快適に使うPCスペックの目安
Midjourneyはクラウド上で画像生成処理を行うため、PCの性能が直接生成速度に影響するわけではありません。ただし、生成した画像を閲覧・保存・管理する作業や、高解像度データの編集、Stable Diffusionなど別の生成AIを併用する場合はPCスペックが作業効率に大きく関わってきます。
ここでは、用途別に必要なPCスペックの基準を整理しつつ、ITに詳しくない方でも迷わず最適なスペックを選べるようにわかりやすくまとめています。
基本用途(Midjourneyのみ利用)のPCスペック目安
Midjourneyはブラウザ上で動作するため、以下のような一般的なノートPCで問題ありません。
推奨スペック(最低ライン)
- CPU:Intel Core i3 / i5、AMD Ryzen 3 / 5
- メモリ:8GB以上
- ストレージ:SSD 256GB以上
- GPU:内蔵GPUで十分
- その他:ChromeやEdgeが快適に動く程度の性能
Web閲覧がストレスなく行えるPCであれば、Midjourneyの操作や画像ダウンロードは問題ありません。
画像編集や高解像度データを扱う場合のPCスペック
生成した画像をPhotoshopやCanvaで編集したり、大量の高解像度作品を扱う場合は、処理負荷が増えるためワンランク上のPCが必要になります。
推奨スペック(画像編集も行う場合)
- CPU:Intel Core i5以上、AMD Ryzen 5以上
- メモリ:16GB以上
- ストレージ:512GB以上のSSD
- GPU:内蔵GPUでも可だが、可能なら
- NVIDIA RTXシリーズ(VRAM 6〜8GB以上)があると快適
高解像度画像の読み込みやレイヤー編集が快適になり、ブラウザのタブを多数開いても動作が重くなりにくくなります。
Stable Diffusionなど「ローカル生成AI」も使う場合のPCスペック
Midjourneyはクラウド型ですが、Stable Diffusionのようなローカル生成AIはGPUを強く必要とするため、ハイスペックPCが必要になります。
推奨スペック(本格的に生成AIを使う場合)
- CPU:Intel Core i7以上、Ryzen 7以上
- メモリ:32GB以上
- ストレージ:1TB以上(モデルデータで容量を使うことが多いため)
- GPU:NVIDIA RTXシリーズ
- VRAM 12GB以上推奨(SDXLなどの大規模モデル向け)
生成速度が大幅に向上し、複雑なモデルの動作にも耐えられる環境になります。
用途別のPC選びのポイント
1. Midjourney中心で作業するだけなら
- 一般的なノートPCで十分
- 8GBメモリ以上を選んでおけば安心
2. SNS運用・画像加工・動画生成も行うなら
- メモリ16GB以上
- CPUはミドルクラス以上
- Adobeツールを使うならGPU搭載モデルが快適
3. 生成AIをローカルでも使うなら
- RTX 4070〜4080クラスのGPUがあると強力
- 大容量メモリ・ストレージを重視
動作を快適に保つためのチェック項目
PCスペックが十分でも、設定や環境が悪いと動作が重くなることがあります。
- ブラウザのキャッシュを定期的に削除
- 不要なタブやアプリを閉じる
- 画像編集ソフトは最新版に更新
- ストレージ容量を20%以上空けておく
- メモリ不足が頻発する場合は増設も検討
こうした基本メンテナンスだけでもブラウザ版Midjourneyの動作が安定しやすくなります。
どのPCを買えばよいか迷う場合の基準
- 10万円前後:Midjourneyの利用・軽い編集
- 15〜25万円:本格的な画像編集・SNS運用
- 30万円以上:Stable Diffusion併用・制作業務向け
用途が明確なほどPC選びで失敗しにくくなります。

Midjourneyを快適に使うPC選びは、用途に合った性能を見極めることが大切です。画像編集やローカル生成AIの併用を考えている場合は、CPUとメモリ、そしてGPUの3つを基準に判断すると間違いが少なくなりますよ