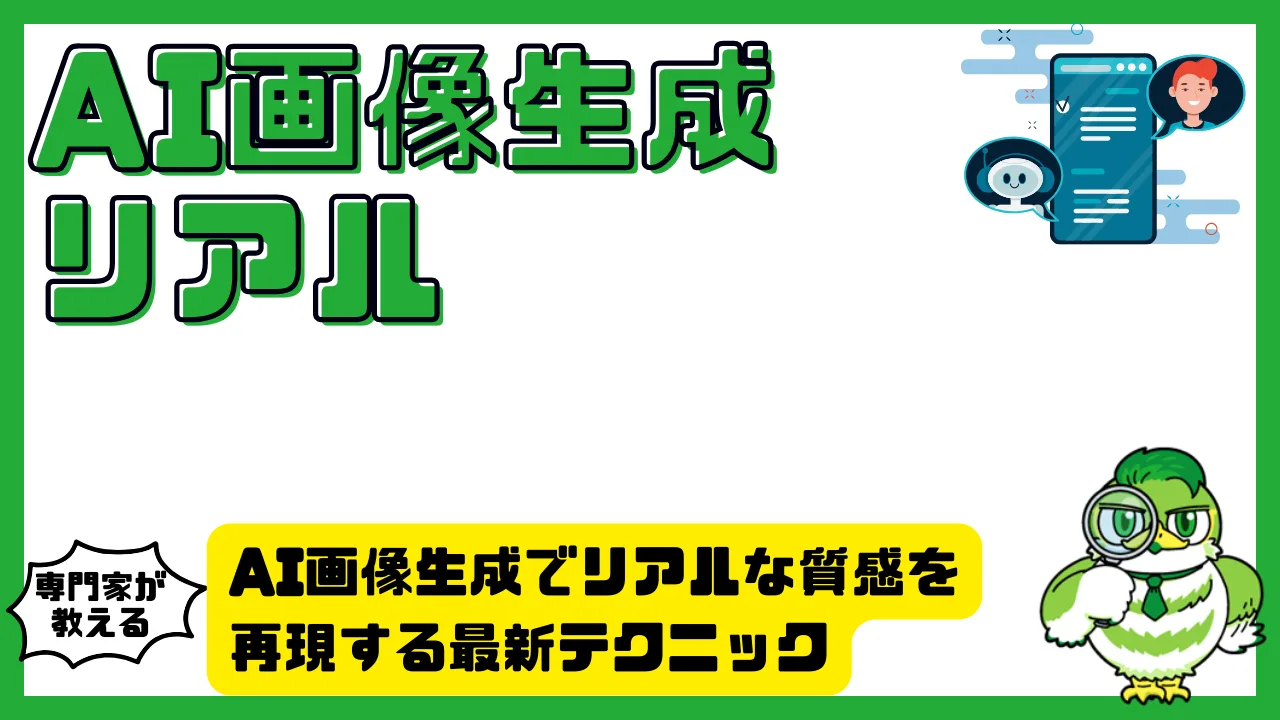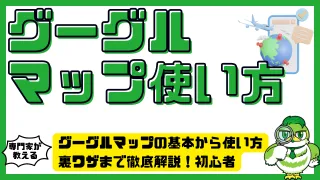本ページはプロモーションが含まれています。
目次
リアルなAI画像が求められる理由
SNSや広告で「AIっぽさ」が逆効果になるケース
AI画像生成は急速に普及していますが、宣伝やSNSの場面では「AIで作った」と分かる画像が逆効果になることがあります。例えば広告バナーで使う人物写真が不自然だと、ユーザーに不信感を与えてしまい、ブランド価値の低下や購買意欲の減少につながります。自然で生活感のあるリアルな質感が求められるのは、このように信頼性と直結しているためです。
日常的で自然な画像の需要が高まっている背景
最近では「インフルエンサーが普段の生活を投稿するような自然な写真」がマーケティングでも好まれています。過度に加工されたビジュアルよりも、素朴で現実的な表現の方がユーザーに共感されやすい傾向があります。そのため、AIで作る画像にもリアルさが強く求められるようになっています。
幅広い用途での実用性
リアルなAI画像は、人物や風景に限らず、商品写真やサービスの利用シーンを再現する際にも活用されています。特にECサイトの商品紹介やカタログ、ビジネス資料で利用する場合、写真と同等の信頼性を持つ表現が求められます。こうした場面で「違和感のないリアルさ」を実現できるAI画像は、コスト削減と表現力強化の両立につながります。

リアルなAI画像が求められるのは、信頼性・共感性・実用性の3つが大きな理由です。広告やSNSでの効果を高めたいなら、不自然さを徹底的に排除した画像を意識していくことが大切ですよ
AI感が出てしまう主な原因
AIで生成した画像が「いかにもAIっぽい」と見えてしまうのには、いくつかの共通した要因があります。ここでは、多くの利用者がつまずきやすい代表的な原因を整理します。
学習データの偏りによる表現の限界
画像生成AIは、大量の学習データをもとにパターンを再現しています。そのため、特定の国や文化圏の写真データに偏っていると、日本人の顔立ちや日常的な街並みが不自然に描かれることがあります。例えば、同じ「日本の通勤風景」と指定しても、実際には欧米風の街並みに似てしまうケースが多く見られます。
プロンプトの表現不足や構図の不自然さ
「リアルに見える画像」を生成するには、プロンプトの具体性が欠かせません。単に「女性が歩いている」と入力すると、モデルが自動的に「映える構図」や「モデル写真風」を選びがちです。その結果、現実にはあまりないポーズや不自然に整った表情になってしまいます。背景や小物、服装などの生活感を補う具体的な指示が不足すると、AI特有の違和感が出やすくなります。
光や背景処理の違和感
写真のリアルさは光の加減や背景処理に大きく左右されます。生成AIは被写体を強調するために背景を極端にぼかしたり、ライティングを過剰に調整したりする傾向があります。その結果、現実のスナップ写真にはない「作られた感」が出てしまいます。特に手や髪の毛など細部の陰影が曖昧だと、人間の目には一瞬で「不自然」と映ってしまいます。
ディテールの不一致や破綻
AI生成では、細部が崩れるケースがしばしば発生します。例えば指の本数やアクセサリーの形、背景にある看板の文字などです。人間は細部に敏感なため、こうした小さな矛盾が「AI感」を強調する原因になります。特に日常風景ではリアルさが要求されるため、違和感が目立ちやすいのです。

つまり、AIっぽさを消すためには「使うツール選び」「プロンプト設計の工夫」「光や背景の指定」「細部の修正」が大事なんです。僕の経験では、最初から完璧を目指すのではなく、生成後に違和感が出やすい部分を補正する意識を持つと、驚くほど自然な仕上がりになりますよ
リアルさに強い画像生成AIツール
AI画像生成で「リアル感」を出すには、ツールの選び方が非常に重要です。学習データの質やアルゴリズムの特性によって、日常的な人物や自然な風景の再現度が大きく変わってきます。ここでは、実際に利用者から評価の高い主要な画像生成AIを紹介します。
Google ImageFX
Googleが提供するImageFXは、日常的で自然な人物表現に強みを持っています。特に日本人の表情や生活感のあるシーンを再現しやすく、SNS投稿や広告素材としても実用性が高いです。英語のプロンプト入力を推奨しており、背景やシチュエーションを細かく指示すると、違和感の少ない自然な写真風画像を生成できます。さらに「SynthID」による透かし機能が搭載されており、画像の出所追跡にも対応しています。
Flux系モデル
Flux系列のモデルは、プロ向けの高精細な生成が可能で、映画のワンシーンのようなリアルな質感を出すことが得意です。ただし操作やプロンプト設計の難易度は高く、専門的な知識が必要になります。デザインや広告制作の現場で、高品質なビジュアルが求められる場合に特に適しています。
Midjourney
Midjourneyは芸術的な表現や独特の世界観を再現することに優れています。風景や抽象的なイメージは圧倒的に強い一方で、自然な日本人の表現にはやや弱い面があります。そのため、リアルさよりも「印象的なビジュアル」や「アート寄りの演出」が欲しい場合に適しています。
Stable Diffusion
Stable Diffusionはオープンソースの強みを活かし、自由度の高いカスタマイズが可能です。モデルや拡張プラグインを活用すれば、フォトリアルな人物や商品写真風の画像を作り出すこともできます。学習済みモデルの選択やLoRAの導入によって、ニッチなシーンや特定ジャンルのリアルさを引き出せる点が特徴です。

どのツールも一長一短がありますが、自然な日本人や日常感を求めるならImageFX、プロ品質の精細な質感ならFlux系、芸術性を重視するならMidjourney、自由なカスタマイズ性を活かしたいならStable Diffusionがおすすめです。自分の用途に合ったツールを選ぶことが、リアルなAI画像を作るための第一歩ですよ
リアルな画像を作るためのプロンプト設計
AI画像生成で「リアルさ」を引き出すには、ツールの性能だけでなくプロンプトの設計力が重要です。思い描いたシーンを正確にAIに伝えることで、自然な質感や日常感を再現することができます。
シチュエーションを具体的に描写する
「女性」「男性」など抽象的な指定では、AIが学習データから一般的すぎる構図を返してしまいます。リアルさを求めるなら「渋谷駅前の横断歩道を渡る20代の女性」「家庭のリビングでソファに座りスマホを見ている男性」など、場所・時間・状況を細かく指示することが大切です。特に「都市の雑踏」「狭い居酒屋」「雨上がりの公園」など具体的な背景設定が有効です。
生活感を与える小物や服装
現実的な画像には、日常を感じさせる要素が必要です。服装は「無地のTシャツとデニム」「少しシワのあるシャツ」といった細部まで指定すると自然になります。さらに「コンビニ袋を持っている」「散らかったテーブル」「自転車が置かれている」といった小物を加えると、一気にリアルな雰囲気に近づきます。
背景に雑多さを取り入れる
プロの写真は整った背景が多いですが、実生活では余計な要素が写り込みます。あえて「通行人が多い」「ポスターが剥がれかけている壁」「物が置かれたままの机」などを描写すると、自然な“生活感”が演出されます。過度に整理された背景はAI感を強めてしまうため、少しの「ノイズ」を意識することがポイントです。
表情と動作を具体的に指定する
リアルな画像は「止まっている人」よりも「動いている人」の方が自然に見えます。「笑顔で友人と話している」「スマホを操作している」「バッグを探っている」など、具体的なアクションを加えると生き生きとした印象になります。特に視線や表情のニュアンスを細かく指定すると、違和感の少ない人物描写が可能です。
英語プロンプトを活用する
多くの生成AIは英語学習データをベースにしているため、日本語よりも英語で指示した方が正確に反映される傾向があります。日本語で考えたプロンプトを翻訳ツールで英語に変換して入力すると、自然な仕上がりが得やすくなります。

リアルさを出すには「日常」を演出するのが鍵です。場面の細かい指定、小物や背景の生活感、そして人物の動作まで具体的に描写することで、AIは“プロ写真”ではなく“日常のスナップ”として理解してくれますよ
写真ライクな質感を再現する撮影風プロンプト
AI画像生成でリアルな質感を得るためには、単に被写体や背景を指定するだけでは不十分です。実際の写真撮影に近い要素をプロンプトに組み込むことで、自然な写真ライクな仕上がりを再現できます。ここでは、実際のカメラワークや光の扱いを意識した具体的な工夫を解説します。
レンズ指定と被写界深度の表現
写真のリアル感はレンズの種類や焦点距離によって大きく変わります。プロンプトに「35mm lens」「85mm portrait lens」「wide angle shot」などを加えると、カメラで撮影したような遠近感やボケが反映されます。特に人物写真では「shallow depth of field」「bokeh」などを指定すると、背景が自然にぼけ、被写体の存在感が際立ちます。
光源の種類と方向を意識する
写真らしさを出すには光の演出が欠かせません。自然光を想定する場合は「soft daylight」「golden hour lighting」など、屋内なら「fluorescent light」「warm indoor lighting」を指定することで雰囲気が変わります。さらに「backlight」「side lighting」など光の方向を明記すると、AIは陰影を自然に描写しやすくなります。
意図的なノイズや手ぶれの追加
あまりにクリアすぎる画像はかえってAIっぽさが出てしまいます。そこで「slight grain」「film texture」「motion blur」などを加えると、現実のカメラで撮った写真に近い質感が再現されます。特に「film photography」「analog style」といった指定は自然な不完全さを演出するのに有効です。
アングルとフレーミングの工夫
写真らしいリアリティは構図からも生まれます。プロンプトに「candid shot」「taken from smartphone」「low angle」「over the shoulder」などを加えると、プロが撮影したような演出ではなく、日常的に撮られた写真に近づきます。特に「snapshot」「casual framing」といった言葉は素人撮影風の雰囲気を表現するのに役立ちます。
具体的なプロンプト例
- 「A young woman in casual clothes, walking in Shibuya at night, taken with 35mm lens, shallow depth of field, candid snapshot style, slight grain」
- 「A cup of coffee on a wooden table, morning sunlight through the window, warm indoor lighting, film photography style, natural shadows」

ポイントは“撮影シーンをどう再現するか”を意識することです。レンズ・光・ノイズ・構図を組み合わせると、AI画像でも驚くほどリアルな質感に仕上がりますよ
商用利用と権利の注意点
AI画像生成は手軽にリアルな素材を作れる一方で、商用利用にはいくつかの法的リスクや制約があります。特に広告やECサイトでの利用を考えている場合、以下の点を理解しておくことが重要です。
透かしと出所追跡の仕組み
Google ImageFXなど一部のサービスでは「SynthID」という透かし技術が導入されています。これは目に見えない形で生成元を画像に埋め込み、後から出所を追跡できる仕組みです。商用利用時に「AI生成であることを隠す」といった行為は規約違反に当たる可能性があり、信用失墜のリスクも伴います。
肖像権とパブリシティ権
人物を生成した画像は、実在のモデルを用いたわけではなくても、特定の人物に酷似する場合があります。この場合、肖像権やパブリシティ権の侵害を指摘されるリスクがあります。特に著名人や公人に似た表現を使った広告素材はトラブルにつながりやすいため、プロンプト設計時に「誰かを想起させる表現」を避けることが安全です。
著作権と二次利用
AIで生成された画像は「完全に自由に使える」と誤解されがちですが、サービス提供者の利用規約や学習データの性質によって権利状況は異なります。MidjourneyやStable Diffusionでは基本的に商用利用が可能とされていますが、クレジット表記や有料プラン契約が条件になる場合があります。利用するプラットフォームごとの規約を必ず確認しましょう。
広告・EC利用時の法的リスク
生成AIの画像を広告に使用する場合、「実際の商品やサービスと誤解を招かないか」が特に重要です。例えば商品写真をAIで生成した場合、実物と異なる表現が含まれていると景品表示法や特定商取引法の違反に問われる可能性があります。ECや販促に使う際は「イメージ画像」「生成画像」といった注記を付け、誤認を避ける工夫が求められます。

商用利用は便利ですが、ルールを知らずに使うと大きなリスクにつながります。透かしや規約を確認し、肖像権や著作権の侵害にならないよう注意して使ってくださいね。広告やECで使うときは特に「誤解を招かない表現」がポイントですよ
リアルなAI画像を活用できる実用シーン
ネット広告やSNSでの活用
リアルなAI画像は、広告やSNS投稿において効果的に使うことができます。従来の広告用素材は撮影や加工にコストがかかりますが、生成AIを使えばターゲット層に合わせた自然な人物やシーンを短時間で用意できます。特にSNSでは「生活感のある写真風画像」がユーザーの共感を得やすく、広告のクリック率やエンゲージメント率を高めやすいという利点があります。
商品紹介やカタログ写真の代替
ECサイトやオンラインカタログでは、商品のリアルな質感を伝える画像が求められます。AI生成を使えば、背景や小物を調整してブランドイメージに合わせた写真風素材を作ることができます。実際の商品撮影が難しい初期段階や、バリエーション展開を素早く試したいときに特に有効です。
ブログや記事のアイキャッチ画像
記事やブログでは、アイキャッチ画像が読者の関心を左右します。無料素材だけでは差別化が難しい場合もありますが、AI生成ならテーマに沿った独自のリアルな画像を用意できます。背景や人物の自然さを重視することで「AI感」の少ないビジュアルを作り出し、記事の信頼性を高める効果も期待できます。
動画やプレゼン資料での活用
ビジネスのプレゼンテーションや動画制作では、オリジナルのリアルな画像素材を用いることで説得力が増します。特にシナリオに合わせて特定の場面や人物像を生成すれば、既存素材に頼らずにオリジナリティを持たせられます。背景を自然に演出できるため、教育系やビジネス向けの資料にも適しています。

リアルなAI画像は「撮影の代替」ではなく「新しい表現手段」として活用できるんです。広告、EC、ブログ、資料など幅広いシーンでコスト削減と表現力向上の両立が可能になりますよ
初心者でもリアル画像を作るステップバイステップ
AI画像生成は一見難しく感じるかもしれませんが、ポイントを押さえて順番に進めれば初心者でも自然な仕上がりが実現できます。ここでは最初の一枚を作るまでの流れを具体的に解説します。
ステップ1 GoogleアカウントでImageFXにログインする
Googleが提供するImageFXは、リアルな人物や日常的な風景を作るのに適したツールです。公式サイト(AI Test Kitchen)を開き、右上の「ログイン」からGoogleアカウントでサインインすればすぐに利用を開始できます。特別なインストール作業は不要です。
ステップ2 プロンプトを用意して英語に翻訳する
ImageFXは日本語も入力できますが、英語の方が精度が高い傾向があります。まずは日本語で「渋谷のスクランブル交差点でスマホを見ている若い女性」などのシチュエーションを考え、それを翻訳ツールで英語に変換します。できるだけ具体的に「服装」「表情」「周囲の環境」を盛り込むとリアルさが増します。
ステップ3 生成ボタンを押して画像を確認する
プロンプトを入力したら「作成」をクリックします。複数の画像が生成されるので、好みに近いものを選びましょう。この時点で「AIっぽい違和感」が残っても気にする必要はありません。後から修正が可能です。
ステップ4 シードロックで安定した再生成を行う
同じ構図でバリエーションを増やしたいときは「シードロック」を使います。これにより全く異なる画像ではなく、構図や雰囲気を保ちながら調整できます。人物の表情や小物の違いを出す際に有効です。
ステップ5 Photoshopなどで仕上げを整える
生成画像は正方形で出力されるため、そのままでは広告やブログに使いにくい場合があります。Photoshopや無料の編集ソフトを使って横長に拡張したり、色味や明るさを微調整すると、より自然な写真に近づきます。必要に応じてノイズを加えると「撮影した写真感」が増します。

ステップごとに進めれば誰でもリアルな画像を作れますよ。最初は翻訳プロンプトとシードロックの扱いに慣れることから始めて、仕上げは編集ソフトで整える。これだけでAIっぽさを抑えて自然な一枚になります