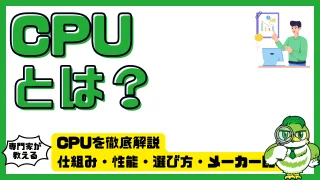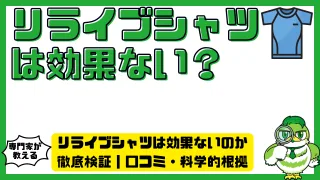本ページはプロモーションが含まれています。
目次
エクセルでデータを抽出する基本の考え方
抽出と検索の違いを理解する
検索は「ある値がどこにあるかを見つける」行為で、結果は位置情報(セル番地)や単一セルの値になりがちです。抽出は「条件に合うデータだけを取り出し直す」行為で、結果は一覧・別表・集計値など、分析可能な形に整理されます。抽出では“どの行を残し、どの列を見せるか”という視点が重要です。
ゴールから逆算する設計思考
抽出は手段ではなく“設計”です。次の順で考えると無駄がありません。
- 目的:何を判断したいのか(例:特定期間の売上トップ顧客を把握したい)
- 条件:目的を数式化できる論理に落とす(等号・不等号・範囲・部分一致・除外・複数条件)
- 対象範囲:どの表から取得するか(表の粒度・列の意味が一意であるか)
- 出力形:フィルター表示、別シート一覧、単一値、件数、集計のどれにするか
この順で決めると、フィルター・関数・ピボットのどれを使うかが自然に決まります。
抽出に強い“データの土台”を作る
正しい抽出は、正しいデータ構造から始まります。
- 一行一レコード(重複行はIDで管理し、同一キーの二重登録を防ぐ)
- 列の意味は一意(「住所」1列に市区町村と番地を混在させない)
- データ型を統一(数値・日付・文字列の混在を解消)
- 余分な空白や不可視文字を除去(TRIM/CLEANで前処理)
- 主キー(商品コード・社員番号など)を用意し、参照関係を安定化
- 表は「テーブル化」して構造化参照にする(列追加でも式が壊れにくくなります)
条件の表現力を身につける
抽出条件は論理の組み合わせです。
- 等号・不等号:=, <, >, <=, >=
- 範囲:開始日以上かつ終了日以下、金額○円以上など
- 文字列:前方一致(”A*”)、部分一致(”A“)、否定(”<>条件”)
- 複数条件:AND(かつ)/OR(または)の明確化
- 除外・欠損:空白のみ、エラーのみ、特定値以外
- 集約条件:Top N、重複排除、ユニーク抽出
どの条件が目的に直結するかを書き出し、曖昧語を数式に翻訳します。
手段選択の基準
- 一時的に目視で絞りたい:オートフィルター
- 複数列・複数条件を“条件表”で管理し、別出力したい:詳細設定(高度フィルター)
- キーに一致する情報を引く:参照関数(VLOOKUP、INDEX+MATCH)
- 件数・有無を知りたい:COUNTIF/COUNTIFS
- 切り替えながら直感的に見たい:テーブル+スライサー
- 集約・クロス集計で全体像を掴みたい:ピボットテーブル
“頻繁に同じ抽出を使うか”“条件が増減するか”“共有相手がいるか”で、操作型(フィルター)か数式型(関数)かを選びます。
抽出結果の“再現性”を確保する
- 条件はセルや“条件表”に可視化して、式中の直値を避ける
- 範囲はテーブル化や名前付き範囲で固定し、列追加に強くする
- 動的配列(対応版Excel)を使える場合は、溢れ出し範囲で一覧を自動更新
- コメントやシート注記で意図を残し、属人化を防ぐ
- 入力規則でデータの揺れ(表記ゆれ・型ブレ)を未然に防止
典型的なつまずきと対策
- 前後スペースや全角半角の違いで一致しない:前処理でTRIM/SUBSTITUTE、統一ルールを運用
- 日付が文字列:値の貼り付けやテキスト関数で正規の日付型に変換
- 参照キーが複合条件:結合キー(顧客ID&商品IDなど)を補助列で作成
- 近似一致の誤用:VLOOKUPは原則FALSE(完全一致)を徹底
- 範囲の列ズレ:参照はテーブルの構造化参照かINDEX+MATCHで列追加に強くする
- 隠れた重複:UNIQUEで重複検出、ピボットで件数チェック
抽出の価値を最大化する活用例
- 顧客セグメント別の反応率比較(地域×期間×商品カテゴリ)
- 在庫アラート(在庫数≦発注点、仕入先別の不足一覧)
- 期間売上の伸び率ランキング(前年比、Top10抽出)
- 問い合わせ管理のSLA逸脱検知(受付日と対応期限で抽出)
どれも“目的→条件→範囲→出力形”の設計で再現性高く回せます。

抽出は設計が9割です、目的を数式に翻訳しやすい形へデータを整え、用途に合う手段を選ぶだけで精度と再現性が一気に上がります
オートフィルターを使った基本的な抽出方法
オートフィルターは、Excelの表から特定の条件に合致するデータだけを一時的に表示できる機能です。元データを削除せずに必要な情報を絞り込めるため、日常的なデータ整理や分析に最もよく使われています。
オートフィルターを設定する手順
- 抽出したいデータ範囲を選択します(列見出しを含めることが重要です)。
- メニューの「データ」タブにある「フィルター」をクリックします。
- 各列見出しに▼マークが表示され、ここから条件を選択できるようになります。
特定条件での抽出
列見出しの▼をクリックすると、リスト形式でデータの候補が表示されます。ここから必要な値だけにチェックを入れることで、その条件に合う行だけを表示できます。たとえば「担当者=山田」を選択すれば、山田さんが担当した案件だけが表示されます。
複数条件での抽出
オートフィルターは複数の列にまたがって条件を設定できます。例えば「担当者=山田」かつ「売上金額が10万円以上」というように条件を組み合わせると、より精密な抽出が可能です。条件は列ごとに独立して設定できるため、表の横断的な分析に役立ちます。
数値や日付での抽出
オートフィルターには数値や日付専用のフィルターが用意されています。
- 数値フィルター:以上・以下・範囲指定などが可能です(例:「売上100000以上」)。
- 日付フィルター:特定の日付、月、四半期などを指定できます(例:「2026年1月だけ」)。
これらを活用すると、時系列データや売上データをすばやく分析できます。
テキスト条件での抽出
文字列の場合は「前方一致」「後方一致」「部分一致」なども指定可能です。例えば「商品名が“りんご”を含む」と設定すれば、”青森りんご”や”りんごジュース”などを一括で抽出できます。

オートフィルターはデータ整理の第一歩です。難しい関数を使わなくても、条件を選ぶだけで必要な情報をすぐに取り出せます。数値や日付の専用フィルターを活用すれば、日常業務の効率が大きく上がりますよ
詳細設定フィルターで複雑な条件抽出を行う
オートフィルターでは実現できない複数条件や高度な抽出を行いたいときに便利なのが「詳細設定フィルター」です。特定の列だけでなく、複数列や複数条件を組み合わせて柔軟に抽出できるのが大きな特徴です。
詳細設定フィルターの設定方法
- 条件範囲を作成する
抽出条件を指定するための「条件範囲」を作ります。これは元データと同じ列見出しをコピーし、その下に条件を入力する形で作成します。
例:商品名の列見出しをコピーし、その下に「りんご」と入力すると、「商品名がりんご」の条件になります。 - 詳細設定の呼び出し
「データ」タブ → 「並べ替えとフィルター」グループ → 「詳細設定」をクリックします。 - 条件を指定する
- リスト範囲:抽出対象の元データ全体を指定
- 抽出条件範囲:作成した条件範囲を指定
- 抽出先:元の場所にフィルターをかけるか、新しい場所に抽出結果を表示するかを選択可能
- 実行する
「OK」を押すと条件に一致するデータのみが表示、もしくは指定した場所に出力されます。
複数列・複数条件での柔軟な抽出
詳細設定フィルターの強みは、複数条件を組み合わせられる点にあります。
- 同じ行に条件を入力 → AND条件(すべてを満たす場合に抽出)
- 別の行に条件を入力 → OR条件(いずれかを満たす場合に抽出)
例えば「商品名がりんご かつ 売上が1000以上」という条件や、「商品名がりんご または みかん」といった複雑な抽出が可能です。
抽出結果を別シートに表示する方法
分析や報告資料を作るときには、抽出結果を別シートに出力すると便利です。
詳細設定フィルターの設定画面で「指定した範囲にコピーする」を選び、コピー先を新しいシートに設定することで、元データをそのまま残しつつ抽出結果だけを扱うことができます。
応用例
- 顧客管理表から「地域が東京かつ購入金額が5万円以上の顧客」を抽出
- 売上データから「商品A または 商品Bを購入した履歴」だけを一覧化
- 勤怠データから「出勤日数が20日以上かつ遅刻がゼロの社員」を抽出
業務ごとの条件を柔軟に設定できるため、分析や報告作業が大幅に効率化されます。

詳細設定フィルターは「条件を複雑に組み合わせたいときの強力な武器」なんです。条件範囲の作り方とAND・ORの使い分けをしっかり覚えておくと、欲しいデータだけを一瞬で取り出せますよ
VLOOKUP関数で条件に合ったデータを抽出する
基本構文と前提
=VLOOKUP(検索値, 検索範囲, 列番号, [検索方法])
左端列で検索して、見つかった行の「指定列」の値を返します。基本は完全一致(FALSE)を使います。近似一致(TRUEまたは省略)はしきい値判定に使い、左端列が昇順に並んでいることが前提です。
よくある業務シーン別の使い方
商品コードや社員番号から情報を引く
- 例:商品一覧(A\:C = 商品コード・商品名・単価)、見積表(E列=商品コード, F列=商品名, G列=単価)
- 商品名(F2)
=IFERROR(VLOOKUP($E2, $A$2:$C$100, 2, FALSE), "")- 単価(G2)
=IFERROR(VLOOKUP($E2, $A$2:$C$100, 3, FALSE), "")- ポイント
- 検索範囲は絶対参照(\$)にしてコピー時のズレを防ぎます。
- 文字列のコードと数値のコードが混在すると
#N/Aが出るため、必要に応じてVALUEやTEXTで型をそろえます。
部分一致で引きたい(ワイルドカード)
完全一致検索(FALSE)でも検索値にワイルドカードが使えます。
- 例:「山田」で始まる顧客の部署を取得(B列=氏名, D列=部署)
=VLOOKUP("山田*", $B$2:$D$500, 3, FALSE)*は任意の文字列、?は任意の1文字です。
近似一致でしきい値を判定したい
評価点に応じたランクを返すなど、範囲判定に適しています。左端列を昇順ソートしておきます。
- 例:点数(E2)からランクを返す(表:A列=下限, B列=ランク)
=VLOOKUP(E2, $A$2:$B$6, 2, TRUE)VLOOKUPの弱点と現実解
左端列制約の回避(列の入れ替えなしで解決)
検索したい列が左端にない場合は、CHOOSEで仮想的に並べ替えます。
- 例:商品名(B列)から商品コード(A列)を返す
=VLOOKUP(H2, CHOOSE({1,2}, $B$2:$B$100, $A$2:$A$100), 2, FALSE)CHOOSE({1,2}, 検索列, 返す列)で「検索列→返す列」の2列配列を作り、VLOOKUPで参照します。
参照列が増減しても壊れない列指定
列番号を固定数字にせず、見出し名から列番号を取得します。表の列追加に強くなります。
- 例:見出し行(A1\:C1)から「単価」の列番号を自動取得
=VLOOKUP($E2, $A$2:$C$100, MATCH("単価", $A$1:$C$1, 0), FALSE)複数条件で一意にしたい
VLOOKUPは1条件検索です。ヘルパー列で条件を連結して一意キーを作ります。
- 例:A列=顧客ID, B列=商品コード, C列=単価
- ヘルパー列(D2)にキー作成
=A2 & "|" & B2- 取得側でも同じ形式のキーを作り検索
=IFERROR(VLOOKUP($G2 & "|" & $H2, $D$2:$E$100, 2, FALSE), "")(E列に返したい値がある想定)
表(テーブル)化で壊れない式にする
元データをテーブル化(Ctrl+T)すると、範囲拡張に自動追従します。構造化参照を使うと可読性も上がります。
- 例:テーブル名「商品一覧」、キー列「[商品コード]」、返却列「[単価]」
=IFERROR(VLOOKUP([@商品コード], 商品一覧[[商品コード]:[単価]], 2, FALSE), "")精度と安定性を高める前処理
- 空白・余分なスペースを除去:
TRIM、印字不能文字はCLEAN - 数値と文字列の不一致を解消:
VALUE、TEXT(セル,"0") - 大文字小文字を区別したい場合:VLOOKUPは区別しないため、
EXACTを使ったフィルターや後段チェックで対応します。
エラー別の対処法
#N/A:未登録、型不一致、前後スペース。IFNA(...,"")やIFERRORで見た目を整え、根本は型とスペースを是正します。#REF!:範囲の列削除が原因。列番号の固定値をやめ、MATCHで列特定に切り替えます。- 想定外の値が返る(近似一致時):左端列が昇順でない、または
TRUEを使っている。ID検索は必ずFALSEにします。 - 重複キーで誤った行を拾う:VLOOKUPは最初に見つかった1件のみ。重複はデータクレンジング、または重複許容なら
FILTER関数(Microsoft 365)で一覧取得を検討します。
パフォーマンスと保守のコツ
- 同一範囲を大量に参照する場合、範囲に名前を付けるかテーブル化して再計算負荷を軽減します。
- 大規模シートでは
IFERROR(VLOOKUP(...),"")の多用が重くなることがあります。入力セルにデータ検証を設定し、エラー発生自体を抑えるのが有効です。 - 範囲の端を広く取りすぎない(例:A\:C 全列)は再計算を重くします。データ行数に応じた適切な範囲を指定します。
チェックリスト
- 左端列に検索キーがあるか
- 完全一致と近似一致は適切か
- 範囲・列番号は壊れにくい指定か(
MATCHやテーブル参照) - 文字列/数値、スペース混入を除去したか
- エラー表示は利用者にとって分かりやすいか(
IFNAなど)

VLOOKUPは「左端で探して横に取る」基本を守れば強力です。ID検索はFALSE、しきい値はTRUE、列増減にはMATCHとテーブルを組み合わせるのが実務の鉄板ですよ
INDEX関数とMATCH関数を組み合わせた高度な抽出
VLOOKUPでは難しい「左方向の検索」「複数条件」「行×列の二次元検索」「部分一致」「N番目や最後の一致」まで柔軟にこなせます。考え方はシンプルで、MATCHで「位置」を見つけ、INDEXで「その位置の値」を取り出します。
基本の型と設計のポイント
- 基本形
=INDEX(取り出したい列, MATCH(検索値, 検索対象列, 0))
完全一致で行位置を確定し、その行の値を返します。 - 二次元の基本形
=INDEX(データ範囲, MATCH(行条件, 行見出し列, 0), MATCH(列条件, 列見出し行, 0))
行と列の両方をMATCHで特定します。 - 壊れにくい設計
列番号を固定せず、列見出し名をMATCHで探すと列の追加や並べ替えに強くなります。=INDEX(表範囲, MATCH($H$2, ID列, 0), MATCH("単価", 見出し行, 0)) - エラー処理
該当なしの#N/Aは業務上よく起きます。=IFERROR(上記の式, "該当なし")として見やすくします。
実務で使う代表パターン
左方向の抽出(VLOOKUPの弱点を克服)
商品コードから左側の「商品名」を返すなど、列の左右に関係なく取り出せます。=INDEX(商品名列, MATCH($H$2, 商品コード列, 0))
複数条件で一意の行を特定
顧客名と商品名が両方一致する行の「単価」を返します。Microsoft 365 以降ならそのまま確定できます。
=INDEX(単価列, MATCH(1, (顧客列=$H$2)*(商品列=$H$3), 0)
)条件を増やすときは *(担当列=$H$4) のように掛け合わせます。
行×列の二次元検索(クロス表からの抽出)
行に顧客、列に月の売上表から、顧客×月の値を取得します。
=INDEX(売上範囲, MATCH($H$2, 顧客見出し列, 0), MATCH($H$3, 月見出し行, 0)
)部分一致・あいまい検索(ワイルドカード)
型番の前方一致などを行います。ワイルドカードは match_type=0 で使います。=INDEX(商品名列, MATCH($H$2&"*", 型番列, 0))
任意位置の含有なら ="*"&$H$2&"*" を使います。
近似一致でしきい値抽出(範囲に応じた段階判定)
昇順のしきい値表から評価を返します。=INDEX(評価列, MATCH($H$2, しきい値列, 1))1 は「以下で最大」を返すため、しきい値列は昇順に並べます。降順で「以上で最小」を探すなら -1 を使います。
最後の一致・N番目の一致
- 最後の一致の行を見つけて値を返す(条件が複数でも可)。0/1の配列に対し
match_type=1を使います。
=INDEX(結果列, MATCH(1, (顧客列=$H$2)*(商品列=$H$3), 1)
)データ途中の空白が多い場合は安定性のため、ヘルパー列で連番を付ける方法が安全です。
- N番目の一致(第n件目)
=INDEX(結果列, SMALL( IF(顧客列=$H$2, ROW(結果列)-MIN(ROW(結果列))+1), $H$3 )
)\$H\$3に取り出したい件数nを入れます。旧バージョンでは配列数式として確定します。
大量データの安定運用
- 範囲は必要十分な列・行に限定します。全列参照は計算負荷が高くなります。
- テーブル化して構造化参照(例:
Table1[顧客名])にすると読みやすく、集計範囲の自動拡張にも対応できます。 - 大文字小文字を区別したい場合は、
MATCH(TRUE, EXACT($H$2, 対象列), 0)を組み込みます。
よくあるつまずきと回避策
- 一致種別の取り違え
完全一致は0、近似一致は1または-1です。近似一致は並べ替え条件が厳格なので、表の並びを必ず確認します。 - データ型の不一致
数値が文字列になっていると一致しません。VALUEや--セルで数値化、またはTEXTで整形します。 - 見出し重複
MATCH("単価", 見出し行, 0)は最初の一致しか返しません。重複があり得る場合は見出しをユニークにするか、列番号を明示します。
すぐに使えるスニペット集
- 列名で列を動的指定
=INDEX(表範囲, MATCH($H$2, ID列, 0), MATCH($H$3, 見出し行, 0)) - 複合キーで完全一致
=INDEX(結果列, MATCH(1, (A列=$H$2)*(B列=$H$3)*(C列=$H$4), 0)) - 前方一致+属性一致
=INDEX(結果列, MATCH(1, (部門列=$H$2)*(型番列&"" LIKE $H$3&"*"), 0))
LIKEの代わりにMATCH($H$3&"*", 型番列, 0)を条件分岐で併用しても構いません。

INDEXとMATCHは「位置を探す→値を取る」の二段構えです。左検索や複数条件、二次元、部分一致、最後の一致まで型を覚えて使い分けると、抽出は驚くほど安定しますよ
COUNTIF・COUNTIFS関数で条件に合う件数を抽出する
データの中から「条件に合致する件数」だけを把握したい場合、COUNTIF関数やCOUNTIFS関数が非常に便利です。売上管理や顧客分析のように「いくつ該当するのか」を素早く知る場面でよく活用されます。
COUNTIF関数で単一条件を集計する方法
COUNTIF関数は「1つの条件に一致するセルの数」を数える関数です。基本構文は以下の通りです。
=COUNTIF(範囲, 条件)- 範囲:調べたいセル範囲
- 条件:抽出したい条件(数値・文字列・式が指定可能)
例えば、A列に顧客の申込ステータスが入っている場合、「申込済」の件数を数える数式は次の通りです。
=COUNTIF(A:A,"申込済")このように設定することで、条件に合う件数を即座に確認できます。数値条件も扱えるため、売上が「10万円以上」の件数を数える場合は =COUNTIF(B:B,">=100000") のように書けます。
COUNTIFS関数で複数条件を組み合わせる方法
複数の条件を同時に満たす件数を求めたい場合はCOUNTIFS関数を使います。構文は以下の通りです。
=COUNTIFS(範囲1, 条件1, 範囲2, 条件2, …)例えば、売上表で「担当者が田中」かつ「売上が10万円以上」の件数を数えたい場合は次のように書きます。
=COUNTIFS(A:A,"田中",B:B,">=100000")複数の条件を組み合わせられるため、顧客管理や営業実績の分析に役立ちます。
実務で役立つ活用例
- 顧客管理:会員登録済みで、かつ有料プランを利用している顧客の人数を把握
- 売上管理:特定の地域かつ一定金額以上の売上件数を集計
- 在庫管理:残数が一定以下の商品数を自動カウントし、発注判断に活用
条件を動的にセル参照にすれば、入力値を変えるだけで柔軟に分析可能です。これにより、フィルターをかけなくても必要な集計値を効率よく確認できます。

COUNTIFは「1つの条件で何件あるか」、COUNTIFSは「複数条件を満たす件数」を調べるときに使います。数字やテキストの条件を柔軟に設定できるので、売上や顧客分析の現場でとても重宝しますよ。
テーブル機能とスライサーで直感的にデータを抽出する
テーブル化で抽出と管理を簡単にする方法
大量のデータを扱う場合、まずは表を「テーブル」として設定するのがおすすめです。テーブルに変換することで、見出し行が常に固定され、データの追加や削除があっても範囲が自動で拡張されます。
操作手順は、データ範囲を選択した状態で「挿入」タブから「テーブル」をクリックするだけです。これにより、列ごとにフィルターが標準搭載され、条件抽出がスムーズに行えるようになります。
また、テーブルはスタイルを簡単に変更できるため、見やすさも向上します。さらに、数式に「構造化参照」という表記が使えるため、セル番地ではなく列名で指定でき、管理や共有の際にミスを減らせるのも利点です。
スライサーを使ったボタン操作でのデータ抽出
テーブル機能の真価を発揮するのが「スライサー」です。スライサーを挿入すると、特定の列項目をボタン形式で選択でき、クリックだけで抽出が可能になります。
例えば、売上データを「担当者」や「地域」でスライサー化すれば、ボタンを押すだけで対象のデータのみを瞬時に絞り込めます。複数のスライサーを組み合わせれば、担当者 × 商品カテゴリなどの条件抽出も直感的に行えます。
スライサーは視覚的にわかりやすく、フィルター条件を誰が見ても把握できる点が大きな強みです。関数に慣れていないユーザーや、業務チームで共有する場面でも便利に使えます。
グラフやダッシュボードと連動させる活用例
スライサーの魅力は、単なる表の抽出にとどまりません。グラフやピボットテーブルと連動させれば、ダッシュボードのようにデータを可視化しながら操作できます。
例えば、売上推移グラフと商品別テーブルをスライサーに紐づければ、「特定の担当者の販売傾向」や「地域別の月次売上」を即座に確認できます。リアルタイムに結果が反映されるため、会議や報告の場面で迅速な意思決定に役立ちます。

テーブルとスライサーを使うと、関数や複雑なフィルター設定を覚えなくても直感的にデータを絞り込めますよ。分析や会議でもすぐに使えるので、業務効率を上げたい人には特におすすめです
抽出機能を効率化する実践テクニック
エクセルには基本的な抽出機能だけでなく、業務をさらに効率化できる工夫があります。単なる条件抽出にとどまらず、見やすさや自動化を組み合わせることで、実務での負担を大幅に減らすことができます。ここでは知っておくと便利な実践テクニックを紹介します。
IF関数で条件に応じた表示を作る
IF関数を使うと、条件を満たす場合と満たさない場合で表示内容を切り替えることができます。
例えば売上データで「10万円以上なら“達成”、それ未満なら“未達成”」と表示させることで、単なる数値一覧を一目で把握できるリストに変えることが可能です。
=IF(B2>=100000,"達成","未達成")このように条件を分岐させておけば、抽出の前段階でデータをグループ化でき、後の集計や分析もスムーズになります。
条件付き書式で視覚的に強調する
条件付き書式は、セルの値に応じて色やアイコンを自動的に変更できる機能です。
たとえば「在庫数が10未満の行を赤く表示する」と設定すれば、フィルターをかけなくても重要なデータが目立つようになります。これにより、抽出結果を確認する作業が短縮でき、エラーや見落としを防ぐことができます。
ピボットテーブルで抽出と分析を一度に行う
大量のデータを扱う場合はピボットテーブルが非常に有効です。条件を設定してデータを集計・抽出するだけでなく、「売上高の上位10社だけ表示」といったランキング抽出や、期間ごとの集計結果を自動で切り替えるといった操作も可能です。
さらにスライサーやタイムラインと組み合わせれば、ボタンひとつで条件を変更し、柔軟にデータを切り替えることができます。
関数とフィルターを組み合わせた活用
関数で作成した条件列をオートフィルターやテーブルに組み込むと、より直感的な抽出が可能になります。
例えばIF関数で「重要顧客/一般顧客」と分類した列を追加しておき、その列をフィルターで絞り込めば、関数とフィルターを同時に活用できるわけです。こうした工夫で抽出作業は格段に効率化されます。

効率化のコツは“自動で分類・視覚化・集計”を組み合わせることです。条件を数式や書式で先に整えておくと、抽出がワンクリックで済むようになります。慣れないうちはIF関数や条件付き書式から始めて、最終的にはピボットテーブルで大規模なデータ分析までできるようにすると良いですよ