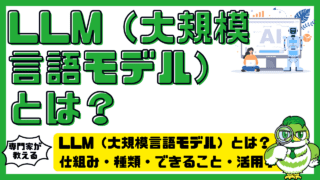本ページはプロモーションが含まれています。
目次
GoogleMeetの基本概要と特徴をシンプルに整理

GoogleMeetは、Googleが提供するオンライン会議サービスで、パソコン・スマートフォン・タブレットなど多様な端末から手軽に利用できます。特に、ブラウザだけでそのまま使える点や、Googleアカウントがあればすぐにミーティングを始められる手軽さが特徴です。
ビジネス利用はもちろん、学校やプライベートの通話でも広く使われており、初めての方でも迷わず操作できるシンプルな設計になっています。ミーティングURLを共有するだけで参加できるため、オンライン会議が初めての相手にも案内しやすいのが利点です。
GoogleMeetの基本的な仕組み
GoogleMeetは、アプリのインストールが不要(PC)で、ブラウザからすぐに利用できます。Google Chromeだけでなく、Edge・Safariなど主要ブラウザに対応しているため、環境を選ばずに使える柔軟さがあります。
スマートフォンでは専用アプリが用意されており、外出先でもビデオ会議や音声通話が可能です。Googleアカウントさえあれば基本機能を利用できるため、追加費用なしで幅広い用途に対応できます。
無料版でも十分に使える実用的な仕様
無料プランでも最大100人が同時参加でき、1回あたり60分までミーティングを継続できます。日常的な社内会議、学校の小規模授業、家族や友人とのオンライン通話など、一般的な利用シーンで困ることはほとんどありません。
また、GoogleMeetは通信の最適化機能により回線が弱い環境でも比較的安定しやすく、映像や音声が途切れにくい点が強みです。オンライン会議の経験が少ない方でも、トラブルが少ない環境で利用できます。
Googleの仕組みを活かしたセキュリティ
GoogleMeetは、同社のセキュリティ基盤を活用して設計されており、不正アクセスや情報漏えい対策が強化されています。ミーティングコードの保護、アクセス権限の管理、自動アップデートなど、利用者側で特別な設定をしなくても安全性が確保される構造です。
企業利用にも適した堅牢な仕組みを備えているため、ビジネスシーンでも安心して導入できます。

GoogleMeetは、誰でもすぐにオンライン会議を始められる“使いやすさ”と“安全性”が揃ったツールなんです。まずは気軽に触ってみて、必要に応じて機能を広げていくとスムーズに活用できますよ
GoogleMeetを使うメリットをわかりやすく解説
GoogleMeetはオンライン会議ツールの中でも、利用のハードルが低く、業務でも個人でも導入しやすい点が特長です。ここでは、日常のミーティングからビジネス利用まで幅広く役立つメリットを、悩みを抱えやすいIT初心者の方にもわかりやすい形で解説します。
すぐに使い始められる手軽さ
GoogleMeetはPCならブラウザだけで使えるため、アプリのインストールや初期設定が不要です。会社のPCにアプリを入れられない場合や、自宅と職場で環境が異なる場合でも、そのまま会議に参加できます。
スマホの場合はアプリが必要ですが、Googleアカウントにログインするだけで即利用でき、複雑な設定はありません。
Googleサービスとのスムーズな連携
GoogleカレンダーとGmailとの連携は特に便利で、日程調整から参加までの流れが非常にシンプルです。
- Googleカレンダーで予定を作成すると自動でMeetのURLが付与
- Gmailの画面からワンクリックでミーティング開始
- GoogleChatからすぐビデオ通話を立ち上げられる
会議URLの作成、招待、参加までの操作がひとつの導線で完結し、オンライン会議に慣れていない人でも迷わない仕組みになっています。
通信環境が弱くても安定しやすい
GoogleMeetはネットワークが不安定な場所でも、自動で画質や音質を調整して会議を維持しようとします。Wi-Fiが弱い場合でも「声だけ届く」「映像は落として音声は確保する」といった調整が働くため、打ち合わせが途切れにくい点が安心です。
映像が乱れることはあっても、音声が確保される場面が多いため、意思疎通に支障が出にくいメリットがあります。
基本機能がシンプルで直感的に使える
GoogleMeetの画面構成は見た目がシンプルで、必要な操作を迷わず使えるデザインになっています。
主要機能は直感的に使える位置にまとまっています。
- マイクのオンオフ
- カメラのオンオフ
- 画面共有(全画面・ウィンドウ・タブ)
- チャット・リアクション
- レイアウト変更
初めて利用する人でも、会議中に慌てずに操作できる点が大きな安心につながります。
プライバシー配慮や背景調整が充実
背景ぼかし・背景画像の変更機能が標準搭載されているため、自宅の様子を映したくない場面でも安心して参加できます。
ぼかしの強度が選べるほか、オリジナル画像のアップロードも可能です。ビジネス用途では落ち着いた背景、家庭内では生活空間を見せない工夫がしやすい点が大きな利点です。
参加人数100人・60分まで無料で使える
無料版でも100人まで参加でき、60分の会議が可能です。
ちょっとした打ち合わせから、社内ミーティング、オンライン授業、家族の集まりまで幅広く対応できます。
有料プランを使う場合は機能が拡張され、録画やブレイクアウトセッションなども利用可能になりますが、無料でも基本的なオンライン会議は十分こなせます。
URL共有だけで参加できるわかりやすさ
会議URLをクリックするだけで参加できるため、IT操作が苦手な方でも迷いにくい仕組みです。会議コードを入力して参加する方法もあるため、セキュリティを意識した運用にも向いています。

GoogleMeetのメリットは「簡単で迷わない」「他のGoogleサービスと自然につながる」「通信が弱くても途切れにくい」という点が大きいです。オンライン会議に不慣れな方でも扱いやすいので、まずは無料版から試しながら操作に慣れていくのがおすすめですよ
GoogleMeetの始め方と会議作成の手順
Google Meetは、思い立った瞬間に会議を開始できるシンプルな操作性が強みです。パソコン・スマホのどちらからでも利用でき、URLを発行するだけで相手を手間なく招待できます。このセクションでは、会議の「始め方」と「作成方法」を、初めて使う方でも迷わないように整理してまとめています。
Google Meetを起動する基本ステップ
Googleアカウントへログインした状態で、ブラウザからGoogle Meetのトップページにアクセスします。アプリ不要で動作するため、準備の手間がかかりません。
ページが開くと、画面左側に「新しい会議を作成」が表示されます。ここから、用途に応じて会議の開始方法を選ぶ流れになります。
新しい会議を作成する方法
会議の作成には複数の選択肢があります。状況別にどれを使うか判断できるようにすると、ムダな手順を踏まずに済みます。
すぐに会議を始めたい場合
「会議を今すぐ開始」を選択します。
・その場で通話画面が立ち上がり、すぐに参加できます
・画面上に表示される会議URLをコピーして相手に送るだけで招待できます
・予定を組む必要がない急な打ち合わせに便利です
URLだけ発行したい場合
「次回以降の会議を作成」を選びます。
・あらかじめURLを用意しておき、メールやチャットで共有できます
・会議開始時に慌てず、スムーズに参加者へ案内できます
・URLは何度でも利用できるため、定例会議でも使えます
Googleカレンダーで予定と会議をまとめて作成する
あらかじめスケジュールが決まっている場合は、Googleカレンダーで予定を作るのが最も効率的です。
- Googleカレンダーを開き、予定を作成
- イベント編集画面で「Google Meet ビデオ会議を追加」をクリック
- 自動で会議URLが生成され、参加者への招待にも反映されます
予定の変更があった場合も、同じ画面でURLをそのまま維持したまま更新でき、管理が容易です。
Gmail・Google Chatから会議を開始する
ブラウザを開き直す手間を省きたい場合は、普段使いのGoogleサービスから直接会議を立ち上げられます。
Gmailから会議を作成
左側メニューの「Meet」から「新しい会議を作成」を選ぶだけでURLを生成できます。Gmailを開いた状態で対応できるため、急ぎのやり取りでも素早く対応できます。
Google Chatから開始
チャット画面で相手を選ぶと、メッセージ入力欄にMeetアイコンが表示されます。クリックするとそのチャット相手とすぐにビデオ通話が始められます。
招待URLと会議コードの仕組み
Google Meetの会議は、次の2つの方法で参加できます。
- 会議URL
- 会議コード
URLはそのままクリックで参加でき、コードはmeet.google.comページで入力して利用します。どちらも主催者が共有するだけで参加できるシンプルな仕組みで、アカウントを持つ全員が共通で利用できます(ビジネス版主催の会議のみ、アカウントなしでも参加可能)。
参加者に渡すべき最低限の情報
会議にスムーズに参加してもらうためには、以下をセットで渡すとトラブルが防げます。
- 会議URL
- 開始時刻
- 必要に応じて会議コード
- 音声・カメラが使えない時の簡易案内(マイク・カメラ許可)
初心者の多い会議では、開始前にURLのクリック方法やブラウザ推奨環境を伝えておくとさらにスムーズです。

Google Meetの会議作成は、状況に合わせて使い分けることでかなり効率が上がりますよ。特に、URLだけ先に発行しておく方法やカレンダー連携は実務でよく使うテクニックです。まずは頻度の高い方法から覚えていくと迷わなくなります。
GoogleMeetの主な機能と操作ポイント
会議のURLから参加できたとしても、画面下のボタンが何を意味しているのか分からないと、肝心の打ち合わせに集中できません。ここでは、GoogleMeetの会議画面で「最低限ここだけ押さえておけば安心」という主な機能と、つまずきやすい操作ポイントを整理します。
マイクとカメラのオン/オフを確実にコントロールする
画面下中央付近に並んでいる「マイク」「カメラ」のアイコンが、会議中もっともよく使うボタンです。
- マイクアイコン
斜線付きで赤く表示されているときが「ミュート(音声オフ)」です。背景の生活音や周囲の話し声を拾わないよう、発言するとき以外はミュートにしておくのが基本的なマナーです。 - カメラアイコン
斜線付きで赤い状態が「映像オフ」です。寝ぐせや背景が気になるときは、最初からカメラをオフにして参加しても問題ありません。
操作に慣れていない方は、次の流れを意識すると混乱しにくくなります。
- 会議に入ったら、まずマイクがミュートかどうかを確認する
- 発言するときだけミュートを解除して話す
- 話し終わったら再度ミュートに戻す
マイクのマーク横に小さなメーターが動いている場合は、自分の声をどれくらい拾えているかの目安になります。反応がまったくないときは、設定からマイクデバイスが正しく選ばれているか確認してください。
画面共有の種類と安全な使い分け
GoogleMeetでは、資料や操作画面を相手に見せるための「画面共有」機能があります。画面下の「画面を共有」ボタンから、主に次の3つを選びます。
- 画面全体
デスクトップ全体が相手に見えるモードです。ウィンドウを切り替えながら説明したいときに便利ですが、意図しない通知や別アプリも見えてしまうリスクがあります。 - ウィンドウ
PowerPointだけ、ブラウザだけ、といった「特定のアプリ画面だけ」を共有するモードです。業務で使う場面では、基本的にこの選択が安全です。 - タブ
ブラウザの特定のタブだけ共有します。動画やアニメーションを見せたいときは、このモードを選ぶと映像と音声が比較的なめらかに相手に届きます。
トラブルを避けるための操作ポイントは次の通りです。
- 共有前に、メールソフトや社内チャットなど「見られたくない画面」は最小化しておく
- 資料だけを見せたい場合は「ウィンドウ」を選ぶ
- 動画や音付きスライドを見せる場合は「タブ」を選んで、ブラウザで再生する
共有中は、画面上に「◯◯を共有しています」と表示されます。共有をやめたいときは、その表示の近くにある「共有を停止」を押すだけで完了です。
チャット・リアクションで発言を補う
会議中のテキストチャットとリアクションは、音声だけでは伝えづらい内容の補足に役立ちます。
- チャット
画面右上付近の吹き出しアイコンから開きます。話を遮りたくないときにURLや数値、メモを共有するのに便利です。「あとで資料を送ります」などの短いメッセージもここに残しておくと、参加者が見返しやすくなります。 - リアクション・挙手
手のアイコンや絵文字のようなアイコンから利用できます。大人数の会議で「少し質問があります」「聞こえています」といった意思表示をしたいとき、マイクをオンにせず使えるのがメリットです。
特にITが苦手な方は、一度にたくさんのボタンを覚えようとせず、
- チャットでURLや補足を書ける
- 「挙手」を押してから発言する
この2つだけ意識すると、発言のタイミングで慌てなくなります。
レイアウト変更で「顔」と「資料」のバランスを整える
参加人数が増えると、誰の顔も小さくなってしまい、表情が読み取りづらくなります。そのようなときは、右下メニューの「レイアウトを変更」から画面構成を調整します。
代表的なレイアウトは次の3種類です。
- タイル
参加者の顔を均等に並べて表示します。小規模な会議で、全員の表情を見ながら話したいときに向いています。 - スポットライト
話している人や固定表示した人を大きく表示します。プレゼン発表や講義形式の場面に適しています。 - サイドバー
左右どちらかに発表者(または資料)を大きく表示し、横に他の参加者を小さく並べる形式です。資料をしっかり見せつつ、参加者の反応も最低限確認したいときに便利です。
さらに、特定の人や資料をクリックして「固定」することで、その画面を常に大きく表示することができます。資料と話者のどちらを中心に見たいかに応じて、その都度レイアウトを変えるクセを付けると、目の疲れや「誰が話しているか分からない」といったストレスを減らせます。
参加者一覧と主催者の基本コントロール
画面右上の「人のアイコン」からは、参加しているメンバーの一覧が見られます。ここでは次のような操作が可能です。
- 誰がミュートになっているかを確認する
- 名前をクリックして、特定の参加者を固定表示する
- 主催者であれば、参加者をミュートにしたり、退出させたりできる
特にビジネス用途では、「主催者用のコントロール」を一度確認しておくと安心です。主催者は、参加者が自由に画面共有できるか、チャットを使えるか、マイク・カメラをオンにできるかなどをまとめて制御できます。
- 社内会議:基本的に制限せず、自由に画面共有・発言してもらう
- 社外向けセミナー:参加者側の画面共有やマイクを制限し、チャットで質問してもらう
このように会議の目的に合わせて権限を調整すると、トラブルを減らしながら進行しやすくなります。
通話を安定させるための設定の押さえどころ
会議画面の「歯車アイコン」から開ける設定画面では、音声や映像のトラブルを防ぐための重要な項目を確認できます。
- 使用するマイク・スピーカー・カメラの選択
- ノイズ抑制のオン/オフ
- 回線が不安定な場合の画質の自動調整
ITに不慣れな方でも、事前にしておくと安心なのは次の2点です。
- 会議前にテスト用のMeetを立ち上げ、マイク・カメラのプレビューで映像と音声を確認する
- 在宅ワークなどで周囲の音が気になる場合は、「ノイズ抑制」を有効にしておく
一度設定しておけば、次回以降も基本的にはそのまま使えるため、「毎回バタバタと設定をやり直す」状況を防げます。

オンライン会議はボタンの数が多くて戸惑いやすいですが、「マイク・カメラ・画面共有・チャット・レイアウト」の5つだけ先に触っておけば、実務で困る場面はぐっと減りますよ。実際の会議前に1人でテスト用のMeetを開き、今日の内容をなぞるようにクリックしてみるだけでも、いざ本番での安心感がかなり違ってきます。
GoogleMeetをもっと便利にする応用機能
基本の「参加」「ミュート」「画面共有」だけでも会議はできますが、応用機能を使うと「疲れにくい・伝わりやすい・抜け漏れが少ない」ミーティングに変えられます。ここでは、ITが苦手な方でも使いこなしやすい代表的な応用機能と、実際の活用シーンをセットで整理します。
プライバシーを守る背景ぼかし・背景画像
自宅や共有スペースから参加するとき、「部屋が丸見えになるのは避けたい」「生活感を隠したい」という悩みは多いです。そんなときに役立つのが背景ぼかし・背景画像の機能です。
背景ぼかしは、人物はくっきり映したまま、背後だけをソフトにぼかしてくれます。背景画像は、オフィス風・シンプルな壁・風景などのテンプレートのほか、自分で用意した画像も使えます。
ビジネス用途でのおすすめは次のようなイメージです。
- シンプルな壁やオフィス風の画像
- 会社ロゴ入りの画像(ブランディングを意識したい場合)
- 色味の少ない落ち着いた背景(相手の目が疲れにくい)
背景のエフェクトは、PCの性能が低いと動きがカクつく場合があります。そのときは「強いぼかし」ではなく「軽いぼかし」や、負荷の軽いシンプル背景を選ぶと安定しやすくなります。
聴き取りを支えるリアルタイム字幕
「相手の声が小さくて聞き取りづらい」「イヤホンを使えない環境で内容だけ確認したい」といったときは、リアルタイム字幕が便利です。
話した内容をGoogleMeetが自動で文字起こしして画面下部に表示してくれるため、多少音声が聞き取りづらくても内容を追いやすくなります。雑音が入りやすい環境や、複数人が早口で話す会議、専門用語が多い打ち合わせで特に力を発揮します。
字幕機能を使うときのポイントは次の通りです。
- 完全な文字起こしではないため、固有名詞や専門用語はチャットで補う
- 録画や議事録の「完全な代わり」ではなく、聞き漏らし防止の補助として使う
- 会議参加者に「字幕表示ができる」ことを事前に案内しておくと安心感が増す
聴覚に不安がある方への配慮にもなり、オンライン会議のハードルを下げることができます。
ホワイトボード機能でアイデア出しをスムーズに
「口頭だけだと話がまとまらない」「図にしながら説明したい」という場面では、ホワイトボード機能が役立ちます。Googleのホワイトボード機能(Jamboard相当の機能群)を使うと、オンライン上で共有できるボードに
- 手書きメモ
- 付箋のようなテキスト
- 図形や矢印
- 画像の貼り付け
などを自由に描き込めます。
対面の会議室でホワイトボードに書くのと同じ感覚で、「課題」「原因」「対策」を並べたり、簡単なフローチャートを作ったりできるため、
- 要件定義や仕様のすり合わせ
- チームのブレインストーミング
- 教育・研修での板書代わり
といったシーンで重宝します。
会議後もホワイトボードはファイルとして残せるので、「せっかくまとめた内容が流れてしまった」という心配を減らせます。
録画機能で議事録・引き継ぎを効率化(有料版向け)
GoogleWorkspaceの対象プランでは、会議を録画しておくことができます。録画データは自動的にクラウド(Googleドライブ)側に保存されるため、ローカル保存の場所を気にする必要がありません。
録画機能が特に役立つのは次のようなケースです。
- 参加できなかったメンバーへの共有・キャッチアップ
- 仕様説明や操作説明など、「同じ説明」を何度も行っている場面
- 重要な打ち合わせで、言った・言わないの抜け漏れを防ぎたいとき
ただし、録画を活用するうえでの注意点もあります。
- 会議前に「録画します」と参加者へ必ず明示して同意を得る
- 個人情報や機密情報を含む内容については、社内ルールに従って取り扱う
- 長時間の会議を繰り返し録画すると、ストレージ容量を圧迫しやすい
「すべての会議を録画する」のではなく、「重要度が高い会議だけ録画して、リンクを議事録と一緒に共有する」といった運用にすると、負担が少なく効果的です。
画面共有を使い分けて資料を見やすくする
画面共有も、少しだけ使い方を工夫すると格段に見やすくなります。特に覚えておきたいのは「共有する範囲」と「動画・音声の扱い」です。
- 資料だけを見せたいときは「ウィンドウ共有」を使う
→ デスクトップ全体ではなく、プレゼン資料のウィンドウだけを共有することで、余計な通知やアイコンが映りません。 - 動画やアニメーションを見せたいときは「ブラウザのタブ共有」を使う
→ 音声も一緒に共有され、動きも比較的なめらかに表示されます。 - 個人情報が映り込みやすい画面(メールボックスや社内チャットなど)は、共有範囲から外しておく
社内で「画面共有時に映していいもの/いけないもの」のルールを決めておくと、ITに詳しくないメンバーでも安心して共有しやすくなります。
ミーティングの形を変えるブレイクアウト・コンパニオン活用
参加者が多い会議では、「聞いているだけで終わってしまう」「発言しづらい」といった悩みが出やすくなります。対応策として、GoogleMeetの一部プランでは次のような機能が使えます。
- ブレイクアウトルーム
大人数の会議を小さなグループに分けて、少人数でのディスカッションができます。全体進行→グループ作業→全体共有といった流れをオンラインで再現しやすくなります。 - コンパニオンモード
会議室の大画面+各自のPCという構成でミーティングするとき、個人端末側のマイクとスピーカーを無効化してハウリングを防ぎつつ、チャット・挙手機能・画面共有だけ使えるモードです。
これらを組み合わせると、
- 全社会議でのグループワーク
- オンライン研修での演習パート
- 会議室からのハイブリッド会議
などもスムーズに運営しやすくなり、「オンラインだとやりにくい」と感じていた会議の幅を広げられます。

応用機能は名前だけ聞くと難しそうに感じますが、「背景をぼかす」「字幕を出す」「必要なときだけ録画する」といった身近なところから少しずつ試していけば大丈夫です。まずは自分のよくある悩み(部屋を見せたくない、聞き漏らしが不安、議事録が大変など)に直結する機能から1つ選んで使ってみて、慣れてきたらホワイトボードやブレイクアウトなども順番に取り入れていくのがおすすめですよ
Googleサービスとの連携活用術
GoogleMeetは、単体で使うよりも「Googleサービスと組み合わせる」ことで、作業速度・会議準備・情報整理が一気にラクになります。特にカレンダー・Gmail・Chat・ドライブは業務の流れに自然に溶け込み、ITが苦手な方にとっても扱いやすく、ミスも減らせます。ここでは、実際の利用シーンごとに活用ポイントを整理します。
Googleカレンダーと連携してスケジュール管理を自動化
GoogleMeetと最も相性が良いのがGoogleカレンダーです。会議URLの自動生成や通知機能が揃っており、会議準備の手間とミスを大幅に減らせます。
主なメリット
- カレンダーで予定を作ると同時にMeetのURLが自動作成される
- ゲスト追加で招待メールも自動送信
- 会議ごとの参加設定(マイク許可や共有権限など)をカレンダー側で管理できる
- 通知やリマインダーで会議忘れを防げる
活用シーン
- 社内外の調整が多い担当者
- 定例ミーティングの一括管理
- 会議URLの貼り間違い・送信漏れを防ぎたい環境
Gmailからワンクリックで会議作成・参加
Gmailの画面から直接Meetを始められるため、メールでのやり取りが複雑になったときに即座に“口頭での確認”へ切り替えられます。
できること
- Gmail左メニューからすぐにMeetの作成・参加
- メール内容を確認しながら会議URLを共有
- 設定を有効化しておけば、常にGmail上でMeet操作が可能
便利なケース
- メールで説明しづらい内容をすぐに確認したい
- 添付資料を画面共有しながら説明したい
- やり取りのタイミングを逃さず即座に打ち合わせしたい
Googleドライブと連携した録画・資料管理
GoogleWorkspaceの有料プランでは録画機能を利用でき、その保存先はGoogleドライブに統一されます。動画ファイルの管理が簡単になり、共有ルールも明確にできます。
メリット
- 録画データが自動でGoogleドライブに保存
- プロジェクトや用途別にフォルダ管理が容易
- ドライブの共有設定を使って社内メンバーに限定公開できる
活用場面
- 欠席したメンバーへのアーカイブ配布
- 研修・オンライン講義などの保存
- トラブル時に内容を振り返りたい場合
GoogleChatと連携した即時ビデオ通話
GoogleChatとMeetはスムーズに連携しており、チャットの流れを止めずにビデオ通話へ移行できます。
活用メリット
- DMやグループチャットからワンクリックでMeetを起動
- チャット履歴を見ながら会議を進行可能
- 「少し相談したい」というときに最速で通話へ移行できる
向いているケース
- リモートメンバー同士の細かな確認
- 設計・資料内容の微修正を即座に共有
- チームが常に連携しながら作業したい場面
Googleドキュメント・スプレッドシート・スライドとの同時編集
GoogleMeetの画面共有とリアルタイム編集を組み合わせると、オンラインでの資料作成が非常に早くなります。
活用例
- スプレッドシートを使った数値確認
- ドキュメントの議事録を全員で編集
- スライドの修正をリアルタイムで確認
会議しながら資料が完成していくため、後作業の時間を削減できます。
GoogleWorkspace利用環境での高度な統合
企業でGoogleWorkspaceを導入している場合、Meetはさらに高度に連携します。
実現できること
- 組織アドレス帳との同期
- 物理会議室の予約とMeet会議を同時作成
- 共有ドライブに録画や資料を一元管理
- 組織単位の権限設定で管理を統一
会議運用を企業単位で標準化できるため、大規模な組織でも扱いやすくなります。

Googleサービスと連携するだけで、GoogleMeetは「ただの会議ツール」から「作業の中心」に変わります。特にカレンダーとGmailの連携は効果が大きく、準備や共有のミスも自然と減りますよ。まずはよく使うサービスから連携してみるのがおすすめです
Google MeetとZoomの違いと選び方
Google MeetもZoomも「オンライン会議ツール」としては同じカテゴリですが、得意分野や向いている使い方が少しずつ違います。
ここでは、ITにあまり自信がない方でも「自分はどっちを選べばいいのか」を判断できるように、比較ポイントと選び方の考え方を整理します。
無料版でまず押さえておきたい違い
両方とも無料で使えますが、「どこまでできるか」に差があります。代表的なポイントだけをシンプルにまとめると、次のようなイメージです。
| 比較項目 | Google Meet | Zoom |
|---|---|---|
| 1回の会議時間(無料) | 最大60分程度 | 最大40分程度 |
| 参加人数(無料) | 目安100人前後 | 目安100人前後 |
| アカウント | GoogleアカウントがあればOK | Zoomアカウントを作成 |
| アプリ | PCはブラウザで利用しやすい | 専用アプリ推奨 |
| 録画(無料) | 原則不可 | ホストPC側で録画可能 |
| ブレイクアウトルーム | 無料では制限あり・要プラン確認 | 無料でも利用可能 |
細かい仕様はプランや時期で多少変わることがありますが、ざっくり言うと次のように考えておくと分かりやすいです。
- 「インストールなしでサッと会議したい」「Googleカレンダー中心で予定を組んでいる」
→ Google Meetが相性が良いケースが多いです。 - 「録画を残したい」「小グループに分かれてディスカッションしたい」
→ Zoomのほうが無料でも機能が揃っていることが多いです。
アプリが必要かどうかと導入のハードル
ITに不慣れなメンバーが多いと、最初の「導入のしやすさ」が大きな差になります。
Google Meetの導入しやすさ
- PCの場合、Chromeなどのブラウザだけで参加しやすい
- Googleカレンダーからワンクリックで参加できる
- アプリのインストールや更新作業が不要なため、社内のITサポート負荷も軽くなりやすい
ブラウザでそのまま使えるので、「相手にアプリの入れ方を説明しているだけで会議が始まらない」といったトラブルが起きにくいのが特徴です。
Zoomの導入しやすさと注意点
- 専用アプリを入れてしまえば、安定した動作と機能の豊富さが魅力
- ただし、初回だけ「アプリのインストール」という一手間が必要
- セキュリティポリシーが厳しい会社では、アプリ導入に申請が必要な場合もあります
社内のPCを管理している部門がある場合、「新しいアプリを入れて良いか」がネックになることがあるので注意が必要です。
機能面の違いでチェックすべきポイント
どちらも「画面共有」「背景ぼかし・背景変更」「チャット」「リアクション」など、オンライン会議の基本機能は揃っています。
違いが出やすいのは、次のような「一歩進んだ使い方」をする場面です。
ブレイクアウトルーム(小グループに分かれて話す機能)
- Zoom
- 無料プランでもブレイクアウトルームが使える構成が一般的で、研修やワークショップで定番の機能です。
- Google Meet
- ホスト側の契約プランによって利用可否が変わることが多く、無料利用だけでは制限があるケースもあります。
研修、勉強会、グループワークなど「全体→小グループ→全体」の流れを多用するなら、Zoomのほうが運営しやすい場面が多いです。
録画機能
- Zoom
- 無料プランでもPCに録画を保存できるケースがあり、会議の議事録代わりに残しやすいです。
- Google Meet
- 会議の録画は、ビジネス向けの有料プラン(Google Workspace)の一部で提供されることが多く、無料利用だけでは使えないことがよくあります。
「会議を後で見返したい」「参加できなかった人向けに録画を共有したい」というニーズが強いなら、録画のしやすさは重要な比較ポイントになります。
ビジネス利用で押さえたい管理機能とコスト感
社内標準ツールとして導入する場合は、「機能の多さ」だけでなく「管理しやすさ」と「トータルコスト」を見る必要があります。
Google Meet(Google Workspace)の特徴
- Gmail、Googleカレンダー、ドライブなどと一体になっているため、すでにGoogle Workspaceを使っている企業とは相性が良いです。
- 利用ユーザーや会議設定を、Google Workspace管理コンソールから一括管理しやすいです。
- メール・カレンダー・ファイル共有・オンライン会議が「ひとつの契約」でまとまるため、別々のサービスを組み合わせるよりシンプルな運用になりやすいです。
Zoomの特徴
- 会議の詳細な設定(待機室、参加者の権限、ウェビナー機能など)が豊富で、オンラインセミナーや大規模配信に強いです。
- すでにメール・カレンダーは別のサービスを使っていて、「オンライン会議だけZoomで強化したい」という場合に選ばれやすいです。
- 有料プラン同士で比較すると、プランによってはZoomのほうが月額料金が高めになるケースもあり、「どこまでの機能が本当に必要か」を整理してから選ぶことが大切です。
こんな人・こんな場面にはどっちが向いているか
ざっくりとした「向き・不向き」をイメージできるように、典型的なパターンごとに整理します。
Google Meetが向いているケース
- 社内・個人ともにGmailやGoogleカレンダーを日常的に使っている
- 「アプリのインストールは難しい」という相手とよく会議する
- 少人数の打ち合わせや1対1の面談が中心で、複雑な機能までは必要ない
- IT部門が少人数で、ツールを増やしたくない・管理をシンプルにしたい
Zoomが向いているケース
- 研修やセミナー、オンライン講座などでブレイクアウトルームを多用したい
- 録画を前提に、後から見返す運用をしたい
- 参加者の人数が多く、ウェビナー形式や細かい権限設定が必要
- すでにOffice系の環境を使っていて、オンライン会議だけ別途強化したい
「どちらか一方だけに決めないといけない」ということはなく、
社内の打ち合わせはGoogle Meet、社外向けセミナーはZoomというように、用途で使い分ける会社も少なくありません。
迷ったときに使えるチェックリスト
最後に、「自分はどっちを主軸にすべきか」を判断するための簡単なチェックリストです。
当てはまる項目が多いほうを、まず第一候補として考えると選びやすくなります。
Google Meetを第一候補にしやすいチェックポイント
- 社内のメール・カレンダーがすでにGoogleベースになっている
- 社員や取引先に「アプリのインストールは極力させたくない」
- 会議時間は1時間前後が多く、無料枠でも困らない
- ITサポート担当者が少なく、シンプルな運用を優先したい
Zoomを第一候補にしやすいチェックポイント
- 研修やセミナーで小グループに分かれることが多い
- 会議の録画を標準運用にしたい
- 社外イベントやオンライン講座など、大人数向け配信をよく行う
- 「オンライン会議のために多少コストをかけてもいい」と考えている
どちらを選んでもオンライン会議そのものは十分に実現できますが、「何を優先したいか」をあらかじめ決めておくと、ツール選びで迷いにくくなります。

Google MeetとZoomは、どちらか一方が絶対に正解というより「自分たちの使い方にどちらがハマるか」で選ぶツールなんですよね。日頃からGmailやGoogleカレンダーを使っていて、難しい機能はいらないならGoogle Meetを軸にするほうがストレスが少ないですし、研修・セミナー・録画前提の運用をしっかりやりたいならZoomをメインに据えるほうが後悔が少ないです。まずは無料版で両方を試してみて、「誰が・どの場面で・どんな頻度で使うか」をイメージしながら、無理のないツール選びをしていきましょう。
Google Meetでよくあるトラブルと解決方法
Google Meetはシンプルで使いやすい反面、設定のズレやブラウザの権限不足などでトラブルが起きやすい場面があります。ここでは、実際の問い合わせやユーザーがつまずきやすい点をもとに、原因と対処方法をできるだけわかりやすく整理します。複雑な操作を避け、ITに不慣れな方でもその場で問題を解決できる内容にまとめています。
マイクが認識されないときのチェックポイント
マイクが反応しない場合、多くは「権限」と「端末側の設定」が原因です。まずは次の順番で確認すると、ほとんどのケースで改善します。
1. ブラウザの権限を確認
Google Meetはブラウザ経由で動作するため、ブラウザがマイクをブロックしていると音声を送れません。
- Chromeの場合
- 右上の「鍵アイコン」→「サイトの設定」→「マイク」→「許可」
- Edge・Safariも同様に、サイトの権限からマイクをONにする
2. Google Meet側の入力マイク設定
Meet画面右下の「設定」→「音声」から正しいマイクが選ばれているか確認します。
3. パソコン本体のマイク設定
Windows・Macともに「入力デバイス」が無効化されているケースがあります。
- Windows:「設定」→「システム」→「サウンド」→入力デバイス
- Mac:「システム設定」→「サウンド」→「入力」
カメラが映らないときのチェックポイント
カメラトラブルの多くも「権限」と「他アプリとの競合」が原因です。
1. ブラウザにカメラ使用を許可する
マイク同様、「鍵アイコン」→「カメラ」で許可状態にします。
2. Meet側で正しいカメラが選択されているか
「設定」→「動画」から、内蔵カメラ・外付けカメラを選択できます。
3. 他のアプリがカメラを占有している
Zoom、Teams、カメラアプリなどが起動中だとMeetで利用できません。
不要なアプリを完全に終了し、ブラウザを再起動します。
画面共有ができない原因と解決方法
画面共有ができない場合は、OSレベルでの「画面収録許可」が無効になっていることがほとんどです。
Windowsの場合
- 「設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「カメラ」「マイク」「スクリーンキャプチャ」
- ブラウザの権限をONにする
Macの場合
- 「システム設定」→「プライバシーとセキュリティ」→「画面収録」
- 使用ブラウザ(Chrome・Safari・Edge)をON
※ONにしたあとブラウザの再起動が必要です。
ブラウザ選択の注意点
画面共有はChromeだともっとも安定します。
Safari・Firefoxはタブ共有が制限される場合があります。
会議URLから参加できないときの確認項目
「参加できません」「アクセスが拒否されました」と出る場合、設定や権限の問題がほとんどです。
1. 主催者の承認待ちになっている
Googleアカウント未ログインや別アカウントで開くと承認が必要になります。
2. 組織(Workspace)側の制限
職場・学校のアカウントでは外部参加をブロックしていることがあります。
別のGoogleアカウントを使って参加できるか試すと原因切り分けが可能です。
3. URLに誤りがある
改行やURLの途中切れが多く報告されています。
- 送られてきたURLをコピーし、アドレスバーにそのまま貼り付ける
- スマホでタップできない場合、PCからアクセスする
音声が聞こえないときの原因整理
音声が聞こえない場合は「再生側の設定」が原因です。
- スピーカーの出力先が間違っている
- Bluetoothのイヤホンが自動接続されている
- PC内蔵スピーカーがオフになっている
- Meetの設定 →「音声」→「スピーカーのテスト」で確認
- OSの音量ミキサーでブラウザだけ音量0になっていないか確認(Windows)
映像・音声の遅延やフリーズの対処法
ネットワークが不安定な場合に起きやすい症状です。
改善しやすいステップ
- 他アプリ(YouTube、クラウド同期など)を終了
- Wi-Fiを5GHz帯に切り替える
- スマホの場合はモバイル通信に変更して改善するケースあり
- Meetの「画質を低くする」で大幅に安定する
スマホでMeetが落ちる・動作が重い場合
- バックグラウンドアプリをすべて終了
- スマホの空き容量を確保
- アプリ版Google Meetを最新バージョンに更新
- 低速モード(省データモード)がオンになっていないか確認(iPhoneで起こりやすい)
録画が開始できないときの原因
録画は以下の条件が厳密に決まっています。
- 主催者または同じ組織のユーザーのみ録画可能
- 無料版では録画不可(Workspaceの対象プランのみ)
- ドライブ容量不足だと録画開始ボタンが出ない
録画が必要な場合、事前にGoogleドライブの容量を確保しておくのがおすすめです。
背景変更が反映されないときの対処
背景変更が使えない原因は性能不足か設定の問題です。
- Chrome以外のブラウザでは利用できない場合がある
- 端末のスペック不足で自動的に無効化される
- 拡張機能が干渉している場合、Chromeの拡張機能を一時OFFにする

Google Meetのトラブルは「権限」「ブラウザ設定」「ネット環境」がほとんどの原因です。困ったときは焦らず、上から順番に確認すると必ず改善できますよ。