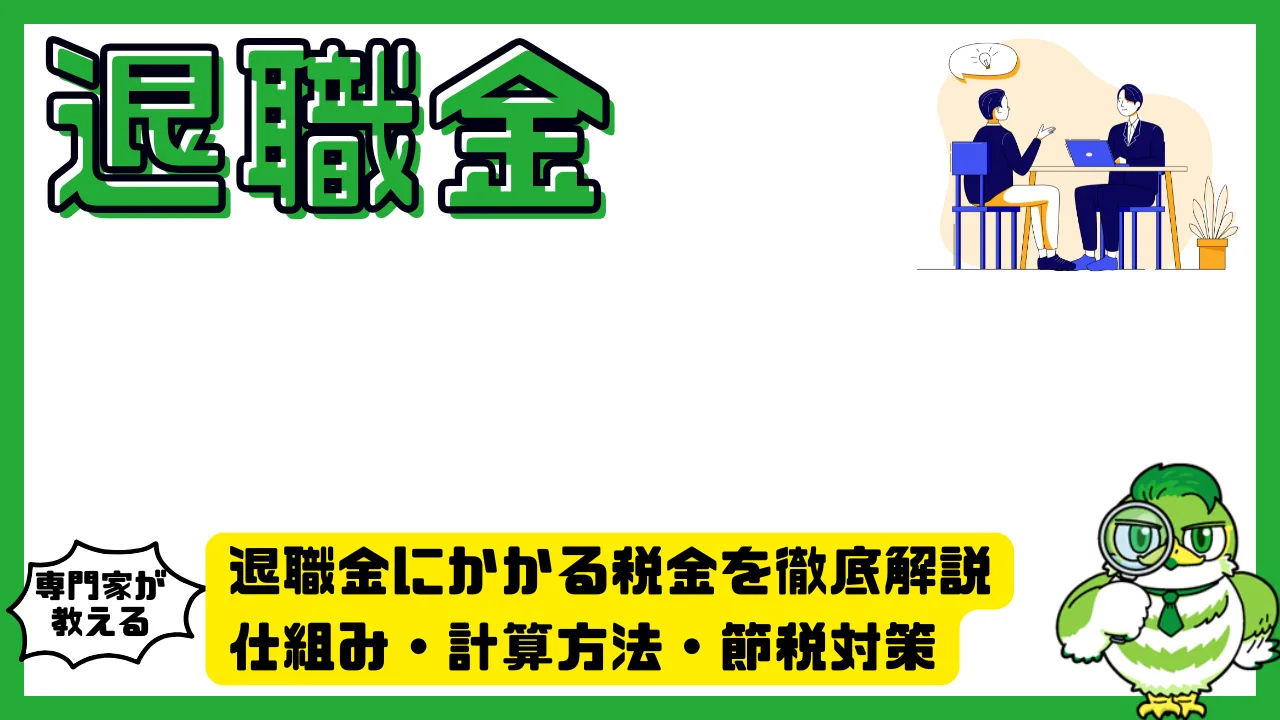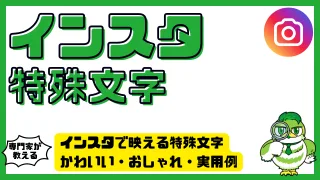本ページはプロモーションが含まれています。
目次
退職金にかかる税金の基本構造
課税対象となる税金
退職金には主に「所得税」と「住民税」が課されます。これらは通常の給与所得と同じ税目ですが、退職金は「退職所得」という特別な区分で扱われるのが特徴です。給与や事業所得と合算されず、独立した形で計算される「分離課税」が適用されます。そのため、一般の給与に比べて優遇された課税方法となっています。
また、所得税については2037年まで「復興特別所得税」が加算され、算出された所得税額に2.1%が上乗せされます。住民税については一律で10%(市区町村民税6%+道府県民税4%)が課税されます。
退職所得控除による軽減
退職金には「退職所得控除」という制度が用意されています。これは長年の勤務に対する功労を考慮し、課税負担を軽くするための仕組みです。
控除額は勤続年数に応じて計算され、金額が大きくなるほど非課税枠が広がります。結果として、勤続年数が長い人ほど税負担が軽減される構造です。
課税所得の計算方法
退職所得の計算は次のような手順で行われます。
- 退職金の受取額から退職所得控除額を差し引く
- 差額を2分の1にする(ただし短期勤続者や役員等には例外あり)
- その金額に所得税率や住民税率をかけて税額を算出する
この「2分の1課税」が大きな特徴であり、通常の給与所得よりも大幅に税金が抑えられる理由となっています。
分離課税のメリット
退職金が分離課税の対象であることにより、他の所得(給与や年金、事業所得など)と合算されません。累進課税による高税率を避けることができ、一定の範囲までは非課税で受け取れるケースも多くあります。特に長期勤続者の場合、退職金全額が控除額に収まることも珍しくありません。

退職金の税金は通常の給与とは違い、特別な優遇措置が組み込まれているんです。勤続年数が長いほど非課税枠が広がり、さらに2分の1課税で税負担が軽くなるという構造を理解しておくと安心ですよ
退職所得控除の仕組みと計算方法
退職金にかかる税金を計算する上で最も重要なのが「退職所得控除」です。これは勤続年数に応じて設定される非課税枠で、長く勤務した人ほど大きな控除額が認められる仕組みになっています。退職金は老後生活の基盤となる資金であるため、税負担を和らげる優遇措置として用意されています。
退職所得控除額の計算方法
退職所得控除額は、勤続年数によって以下のように計算します。
- 勤続年数が20年以下の場合
40万円 × 勤続年数(最低80万円)
例えば勤続10年なら「40万円×10年=400万円」となり、これが退職所得控除額になります。 - 勤続年数が20年を超える場合
800万円+70万円 ×(勤続年数-20年)
例えば勤続30年なら「800万円+70万円×10年=1,500万円」が控除額です。 - 勤続年数の端数処理
勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。例えば「10年3か月」なら「11年」として計算します。
退職所得の計算ステップ
控除額を計算したあとは、以下の手順で課税対象額を算出します。
- 退職金の額から退職所得控除額を差し引く
退職金が控除額以下なら課税されません。控除額を上回る部分だけが課税対象です。 - 差引後の金額に1/2を掛ける
これが「退職所得」と呼ばれる金額です。給与所得や事業所得と違い、退職所得は2分の1課税という特例があるため、税負担が軽減されます。 - 所得税率を適用して税額を計算
退職所得に所得税の累進税率を掛け、さらに復興特別所得税(2037年まで2.1%上乗せ)が加算されます。
住民税は一律10%(都道府県民税4%+市区町村民税6%)で計算されます。
勤続5年以内の例外
短期勤続で退職する場合は計算方法が変わります。
- 役員等の場合
控除額を差し引いた残額がそのまま課税退職所得になります(1/2課税は適用されません)。 - 役員等以外の場合
控除額を差し引いた後の金額が300万円以下なら、その金額の1/2が課税退職所得です。
300万円を超える場合は「150万円+(控除差引後の金額-300万円)」で計算します。
まとめのイメージ
例えば勤続25年で退職金が2,000万円の場合、退職所得控除額は「800万円+70万円×5年=1,150万円」となります。差し引き後の金額は850万円で、これを2分の1にして425万円が退職所得です。この金額に税率を当てはめて所得税と住民税を計算する流れです。

退職所得控除は、退職金の税負担を大きく減らすための重要な仕組みです。控除額は勤続年数に比例して増えるので、まずは自分の勤続年数でいくら非課税枠があるのかを正確に計算することが大切ですよ
退職金の税金シミュレーション事例
退職金にかかる税金は「退職所得控除」と「1/2課税」により大きく軽減されますが、勤続年数や退職金額によって手取り額は大きく変わります。ここでは代表的なケースを具体的に計算し、イメージを持てるように整理します。
勤続年数10年・退職金900万円の場合
勤続年数10年の控除額は「40万円×10年=400万円」となり、課税対象は以下の通りです。
- 退職所得控除額:400万円
- 課税退職所得金額=(900万円-400万円)×1/2=250万円
- 所得税率10%・控除額9万7,500円を適用すると所得税は約15万2,500円
- 復興特別所得税はその2.1%で約3,200円
- 住民税は250万円×10%=25万円
合計で約40万5,700円が税負担となり、手取りは約859万4,300円です。勤続10年でも退職所得控除と1/2課税で大きく軽減されているのが分かります。
勤続年数25年・退職金2,300万円の場合
勤続年数25年の控除額は「800万円+70万円×(25-20年)=1,150万円」となります。
- 退職所得控除額:1,150万円
- 課税退職所得金額=(2,300万円-1,150万円)×1/2=575万円
- 所得税率20%・控除額42万7,500円を適用すると所得税は約72万2,500円
- 復興特別所得税はその2.1%で約1万5,200円
- 住民税は575万円×10%=57万5,000円
合計で約131万2,700円の税負担となり、手取りは約2,168万7,300円です。金額が大きくても控除額も大きくなるため、負担割合は抑えられます。
勤続5年・退職金1,000万円の場合(短期退職)
勤続5年以内の場合、役員かどうかで計算方法が異なります。一般社員として退職した場合を例にすると、控除額は「40万円×5年=200万円」です。
- 控除後の退職金:1,000万円-200万円=800万円
- うち300万円までは1/2課税で150万円、それを超える500万円はそのまま課税
- 課税退職所得金額=650万円
この650万円に対して所得税率20%・控除額42万7,500円を適用すると所得税は約87万2,500円、復興特別所得税は約1万8,300円、住民税は65万円となります。合計で約154万円の負担です。短期退職は控除額が小さく、課税額が大きくなりやすいため注意が必要です。

退職金は控除や優遇措置のおかげで税負担が軽くなりますが、勤続年数や受け取り方で手取り額は大きく変わります。自分のケースをシミュレーションしておくことで、老後の資金計画もより安心して立てられますよ
退職金の受け取り方法と課税の違い
退職金は受け取り方によって課税方法が大きく異なります。選択肢としては「一時金」「年金」「一時金と年金の併用」があり、それぞれ税制上の扱いが異なるため、事前に理解しておくことが重要です。
一時金として受け取る場合
一時金受取りは、退職金を一括で受け取る方法です。課税上は「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されます。控除後の金額をさらに1/2に圧縮して課税するため、税負担は大幅に軽減されます。また、ほかの所得と切り離して分離課税されるため、給与などの所得に影響を与えないのも特徴です。
一括でまとまった資金を確保できるため、住宅ローンの返済や老後の資金準備に活用しやすい一方、大きな額を受け取ることで資金管理が難しくなり、使いすぎのリスクもあります。
年金として受け取る場合
退職金を分割して受け取る方法では、公的年金等と同じ「雑所得」として扱われます。雑所得は総合課税の対象であり、給与や事業所得など他の所得と合算して課税額が決まります。結果として所得税や住民税が高くなるケースもあるため注意が必要です。
ただし、公的年金等控除が適用されるため、一定額までは非課税となります。例えば65歳以上であれば、年金収入が年間110万円以下なら税金はかかりません。定期的に受け取るため生活資金として安定しやすく、浪費のリスクを避けやすい点がメリットです。
一時金と年金の併用
一部を一時金、残りを年金として受け取る方法も可能です。この場合、一時金部分には退職所得控除と1/2課税、年金部分には公的年金等控除と総合課税が適用されます。控除のバランスを取りやすいため、節税を意識した受け取り方として有効です。会社の制度によっては選択できない場合もあるため、就業規則や退職金規程を確認しておく必要があります。
受け取り方法を決める際の考慮点
- 一時金のメリット:税制優遇が大きい、住宅ローン返済や大きな出費に対応しやすい
- 一時金のデメリット:一度に大金を得るため資金管理が難しい
- 年金のメリット:安定的に資金を受け取れる、使いすぎ防止になる
- 年金のデメリット:総合課税のため他の所得と合算され課税額が増える可能性がある

退職金の受け取り方は、税金面だけでなくライフプラン全体に影響します。一時金で資金を確保したいのか、年金として安定した収入を望むのか、自分の生活設計に合った方法を選ぶことが大切ですよ
退職金に関する確定申告の要否
退職金を受け取る際、多くの方が「自分で確定申告をする必要があるのか」と疑問を持ちます。基本的には勤務先で必要な手続きが行われ、確定申告は不要ですが、条件によっては申告が必要になるケースがあります。ここでは、確定申告の要否を整理します。
確定申告が不要なケース
退職金の税金は、通常「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出することで、源泉徴収により納税が完結します。提出済みであれば、退職所得控除や1/2課税といった優遇措置が適用され、支給時に正しく税額が調整されます。そのため原則として自ら申告する必要はありません。
確定申告が必要になるケース
以下のような場合には、自分で確定申告を行う必要があります。
- 申告書を提出しなかった場合
「退職所得の受給に関する申告書」を提出していないと、一律20.42%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。実際の税額より多く引かれることが多いため、確定申告を行えば還付を受けられる可能性があります。 - 年末調整を受けていない場合
退職日が年末前で、その後に給与収入がなく年末調整を受けられなかった場合は、過不足の精算ができていません。確定申告をすれば、多めに徴収された税金が戻ることがあります。 - 所得控除を受けたい場合
国民健康保険料・任意継続の保険料・介護保険料などを支払っている人は「社会保険料控除」が適用できます。さらに生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除なども、申告をすることで退職金から源泉徴収された税金の一部を還付してもらえる可能性があります。 - 公的年金等を含む雑所得がある場合
退職金を年金形式で受け取る場合は雑所得扱いとなり、他の所得と合算して課税されます。特に次の条件では確定申告が必要です。
・公的年金等の収入が年間400万円を超える場合
・公的年金等以外の所得が20万円を超える場合
確定申告をすべきか判断するポイント
退職金が一時金か年金か、また控除をどの程度活用できるかによって、申告の要否は変わります。迷う場合は、源泉徴収票と控除証明書を手元に揃え、国税庁の「確定申告書等作成コーナー」で試算することをおすすめします。場合によっては還付金が数十万円規模になるケースもあるため、確認を怠らないようにしましょう。

退職金の確定申告は「原則不要だけど場合によって必要になる」と覚えておきましょう。特に控除や還付を受けられる可能性がある人は、積極的に申告したほうが有利になりますよ
退職金を受け取った翌年の税金の考え方
翌年の税負担が気になる理由
退職金を受け取ると、「翌年に大きな税金がかかるのではないか」と心配される方が多いです。実際には退職金は支給時に所得税・復興特別所得税・住民税が源泉徴収されるため、翌年に追加の課税が直接発生することはありません。ただし、給与所得や住民税の仕組みの影響で負担感が増すケースがあります。
所得税と住民税の扱いの違い
- 所得税
退職金にかかる所得税は「退職所得」として分離課税され、受取時点で精算が完了します。そのため翌年に再度課税されることはありません。 - 住民税
退職金にかかる住民税も同様に、受給した年に課税されます。ただし、退職した年の給与収入や賞与にかかる住民税は、通常どおり翌年に課税されるため、退職金と混同して「翌年の税金が高い」と感じる人がいます。
普通徴収による心理的負担
退職後は給与天引きによる住民税の納付(特別徴収)ができなくなり、自分で納付する「普通徴収」に切り替わります。年4回に分けて、または一括で納める必要があるため、一度の支払い額が大きく感じられます。これが翌年の負担感につながる大きな要因です。
退職年の給与水準の影響
退職した年に役職手当やボーナスが多く支給されていた場合、その所得に基づく住民税が翌年に課税されます。結果として「退職金のせいで翌年の住民税が上がった」と誤解されやすいのです。実際には退職金自体は翌年の住民税に反映されませんが、退職前の給与が高いと翌年の負担が増えることは覚えておく必要があります。
資金計画のポイント
翌年の住民税や国民健康保険料の支払いに備えて、退職金の一部を取り分けておくと安心です。特に事業開始や再就職を急がない方は、数十万円単位の納付が一時的に発生することを想定し、余裕を持った資金管理を意識しましょう。

退職金を受け取った翌年に「税金が増えた」と感じても、実際には退職金そのものではなく給与所得や納付方法の変化が原因です。翌年の支払いスケジュールを把握して、退職金の一部を生活資金とは別に管理しておくのが大切ですよ
退職金課税制度の今後の動向
勤続年数優遇の見直し議論
現行の退職金課税制度は、勤続年数が長いほど控除額が大きく、結果的に税負担が軽減される仕組みです。しかし、労働市場の流動化が進む中で「長期勤続者が過度に優遇されている」との指摘が出ています。転職が一般化している現代の働き方に制度が適合していないため、短期勤続者との税負担の不均衡を是正する議論が進められています。
税制改正における検討状況
これまで複数回、退職金課税制度の見直しは税制改正大綱で議題に挙がりました。2023年・2026年の検討では大きな変更は見送られましたが、将来的に優遇措置が縮小される可能性は依然残っています。特に、退職所得控除の縮小や「1/2課税制度」の見直しが候補に挙げられています。
少子高齢化と税収確保の影響
日本の財政状況や少子高齢化による社会保障費の増大を背景に、退職金に対する優遇が縮小される可能性が指摘されています。特に高額の退職金を受け取る経営層や長期勤続者に対しては、税負担を強める方向で検討されることが考えられます。逆に、中小企業勤めや短期勤続者にとっては大きな影響を受けにくいよう、段階的な調整が行われる見通しです。
今後の個人への影響
制度変更が実施されると、退職金の手取り額が減少するリスクがあります。特に、将来的に退職金を老後資金の柱と考えている方にとっては大きな影響となるため、資金計画の柔軟な見直しが必要です。また、退職金以外の老後資金(企業型DC、iDeCo、NISAなど)の活用がより重要性を増していく可能性があります。

退職金の課税制度は、今後も社会情勢や働き方の変化に応じて見直される可能性があります。長期的なライフプランを考える際には、制度が変わった場合の影響も想定して準備しておくことが大切ですね
退職金の税負担を軽減する実務ポイント
退職金は老後の大切な生活資金になるため、できる限り手取りを多く残すことが重要です。税制の仕組みを理解し、実務的な工夫を取り入れることで税負担を抑えることができます。
一時金と年金の組み合わせを最適化する
退職金を一括で受け取る場合は退職所得控除が適用され、さらに控除後の金額は2分の1に圧縮されます。一方で年金形式で受け取ると雑所得扱いとなり、ほかの所得と合算して課税されるため、課税が重くなる場合があります。
企業によっては一時金と年金の併用が可能な制度を設けているため、退職所得控除額に収まる範囲で一時金を受け取り、残りを年金として受け取ると効率的に非課税枠を活用できます。
控除枠を活かした資金計画
退職所得控除の範囲内で退職金を受け取れば、課税所得をゼロにすることが可能です。長期勤務者ほど控除額が大きいため、企業から提示される退職金見込み額と控除額を比較し、必要に応じて受け取り方を調整すると良いでしょう。また、退職後に加入する国民健康保険や介護保険料、生命保険料などの支出を「社会保険料控除」「生命保険料控除」として活用すれば、追加で還付を受けられるケースもあります。
特殊な退職ケースの税務確認
早期退職優遇制度や役員退職金は、通常と異なる課税ルールが適用される場合があります。たとえば、勤続5年以下の役員等は「1/2課税」が認められず、課税対象額が大きくなるため注意が必要です。特殊ケースに該当する場合は、退職前に会社や専門家に確認し、想定外の税負担を避けることが大切です。
専門家に相談するメリット
退職金の課税は制度が複雑であり、将来の税制改正の影響も受けやすい領域です。税理士やファイナンシャルプランナーに相談することで、個々の勤続年数や退職金額、家族構成に応じた最適な受け取り方を設計できます。特に高額退職金の場合は、数十万円以上の節税につながる可能性があります。

退職金の税負担は事前の準備で大きく変わります。控除の仕組みや受け取り方を理解し、自分の状況に合った戦略を立てることが肝心ですよ
| 順位 | サービス名 | ポイント | 料金 | タイプ | 代行内容 | 支払いタイミング | 支払い方法 | 対応時間 | 対応エリア | LINE対応 | 弁護士の監修 | 書類テンプレート | 追加料金なし | 返金保証 | 転職支援 | LINE公式の自動回答機能 | 分割払い対応 | 対応内容の質 | 料金の安さ | サービスの多さ | 対応時間の長さ | 総合 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 退職代行トリケシ | 訴訟非対応だが、深夜でも自動チャットで疑問をすぐに解決 | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、モバイル決済、あと払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 2.93 | 5.00 | 5.00 | 3.70 | 退職代行トリケシ 公式サイト | |||||||
| 2位 | リーガルジャパン | 有給取得や書類対応に強み。LINEで簡単に退職手続きが可能 | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成 | 前払い | クレジットカード、銀行振込、モバイル決済 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 2.77 | 2.93 | 4.00 | 5.00 | 3.67 | リーガルジャパン 公式サイト | |||||||
| 3位 | 退職代行モームリ | LINEで完結&低価格。実務に強い信頼の代行サービス | 12,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、Paidy、モームリあと払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 3.77 | 4.00 | 5.00 | 3.99 | 退職代行モームリ 公式サイト | |||||||
| 4位 | 退職代行オイトマ | 交渉が必要なら頼れる一社。後払いで不安を抑えて依頼可能 | 24,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、Paidy | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.88 | 4.00 | 5.00 | 3.19 | 退職代行オイトマ 公式サイト | |||||||
| 5位 | 退職代行ニコイチ | 有給交渉に強いが、サービス範囲の確認は事前に必要 | 27,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込、モバイル決済 | 7:00〜23:30(年中無休) | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.13 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 退職代行ニコイチ 公式サイト | |||||||
| 6位 | 退職代行 | 法的対応が必要な方に最適。費用や連絡手段には注意が必要 | 27,500円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (成功報酬として20%+税が発生) | 4.45 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.86 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 7位 | 退職代行ローキ | 弁護士と労働組合のWサポートで、法的にも安心して退職できる | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成、未払い給与・残業代の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ローキ分割払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 4.52 | 2.93 | 5.00 | 5.00 | 4.36 | 退職代行ローキ 公式サイト | |||||||
| 8位 | 退職代行 | 訴訟にも対応可能。コスパ重視の本格派弁護士サービス | 12,000円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | (未払い給与・未払い退職金の支払い請求、パワハラ慰謝料請求の成功報酬代として、経済的利益の22%(税込※裁判外の請求) | 4.45 | 3.77 | 2.00 | 5.00 | 3.80 | 退職代行 公式サイト | ||||||
| 9位 | 退職代行 | 法的対応も含めてLINEで完了。費用と安心のバランスが秀逸 | 25,000円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 5.00 | 1.63 | 2.50 | 5.00 | 3.53 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 10位 | 辞めるんです | 使いやすいLINE完結型。料金の明瞭さが高評価の理由 | 27,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 1.13 | 3.00 | 5.00 | 3.08 | 辞めるんです 公式サイト | |||||||
| 11位 | 退職代行プラスサービス | 費用は安いが、LINE機能やサポート体制にはやや物足りなさも | 16,280円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 3.33 | 3.00 | 5.00 | 3.30 | 退職代行プラスサービス 公式サイト | |||||||
| 12位 | 退職代行EXIT(イグジット) | 業界初の老舗ブランド。低料金が魅力だが後払いには非対応 | 20,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 2.88 | 3.00 | 5.00 | 3.19 | 退職代行EXIT(イグジット) 公式サイト | |||||||
| 13位 | 退職代行サラバ(SARABA) | 費用は安めだが、支払い案内が早く安心感にやや欠ける | 24,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 1.88 | 2.50 | 5.00 | 3.14 | 退職代行サラバ(SARABA) 公式サイト | |||||||
| 14位 | 退職代行Jobs | LINEで完結&後払い対応。気軽に相談しやすい安心設計 | 27,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、Paidy | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.13 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 退職代行Jobs 公式サイト | |||||||
| 15位 | 退職代行 | 労組ならではの交渉力。安心して実務を任せられる体制 | 18,700円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 8:00〜21:00 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 2.77 | 3.08 | 2.00 | 3.00 | 2.71 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 16位 | ネクストステージ | 費用を抑えてLINEで完結。交渉が不要な人に適したサービス | 15,000円~ | 民間業者 | 退職意思の伝言 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.00 | 3.46 | 4.00 | 5.00 | 3.37 | ネクストステージ 公式サイト | |||||||
| 17位 | やめたらええねん | LINE完結で格安。費用重視派におすすめの選択肢 | 16,500円~ | 民間業者 | 退職意思の伝言 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.00 | 3.31 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | やめたらええねん 公式サイト |