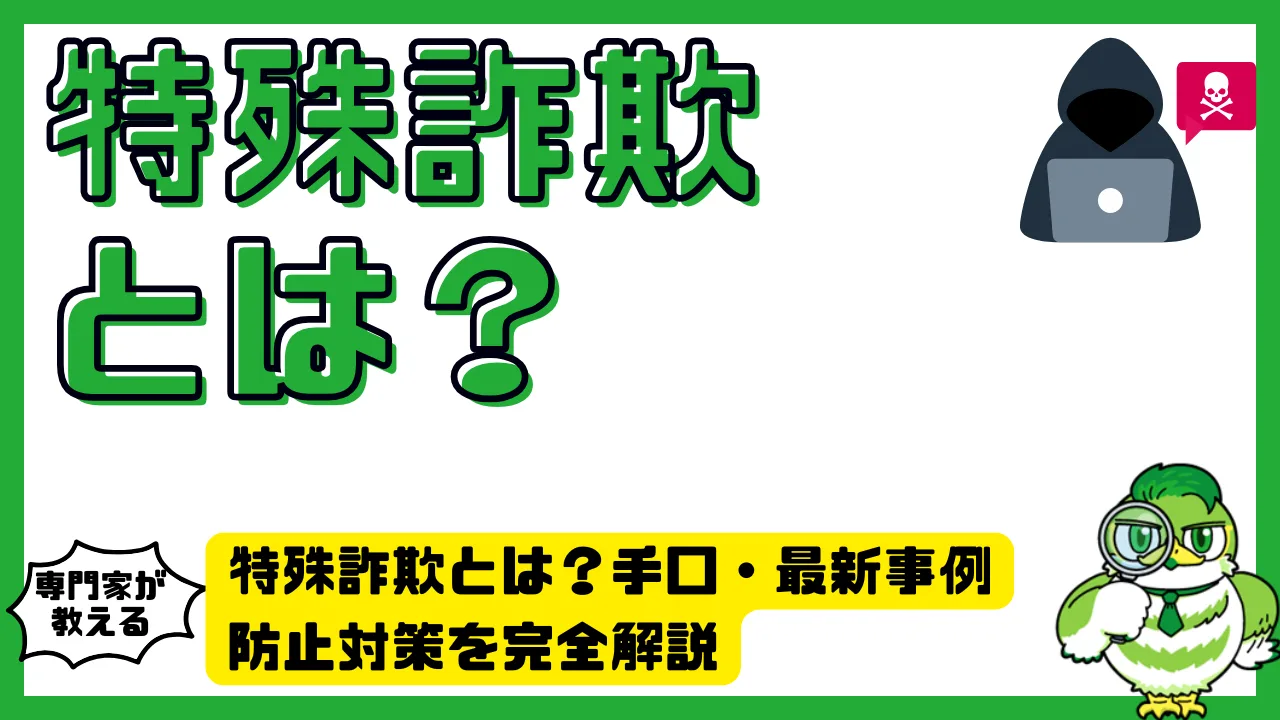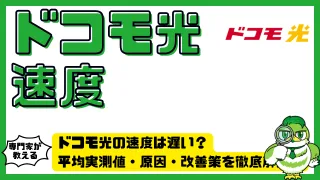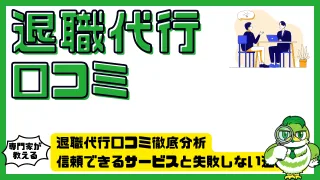本ページはプロモーションが含まれています。
目次
特殊詐欺とは?定義と基本の仕組みを理解する
特殊詐欺とは、電話・メール・SNSなどの通信手段を使って、相手を信用させて金銭をだまし取る犯罪の総称です。犯人は警察官や役所の職員、家族、銀行員などに成りすまし、被害者の心理を巧みに操作して「自分のために正しいことをしている」と思い込ませます。
現金やキャッシュカードを直接受け取るケースのほか、ATM操作を指示して送金させるケースも多く、被害者が自ら行動してしまう点が特徴です。
特殊詐欺の定義
警察庁の定義によると、特殊詐欺は「電話やハガキ、電子通信などで被害者をだまして金銭や財産を交付させる犯罪」とされています。
この中には、オレオレ詐欺・還付金詐欺・架空料金請求詐欺・投資詐欺・融資保証金詐欺・ロマンス詐欺など、複数の手口が含まれています。
最近では、キャッシュカードをすり替える「キャッシュカード詐欺盗」や、AI音声やディープフェイク技術を悪用した詐欺も増加しています。
犯行の基本的な流れ
特殊詐欺は、一見単純な電話詐欺のように見えて、実際は複数のステップで構成されています。
- 信用の獲得
犯人は「公的機関の職員」や「家族」を名乗り、信頼を得ることから始めます。
声のトーンや話し方まで巧妙に作り込まれており、被害者は疑う余地を持ちにくくなります。 - 不安の植え付け
「口座が犯罪に使われている」「お金を返さないと訴えられる」など、不安を煽る発言で冷静さを奪います。
焦りや恐怖を感じると、人は判断を誤りやすくなります。 - 行動の誘導
「今すぐATMで手続きを」「カードを預かります」など、犯人の指示通りに行動させるよう仕向けます。
このとき、被害者が自分の意思で動いていると錯覚させるのがポイントです。 - 金銭の搾取
最終的に現金・キャッシュカード・暗証番号などをだまし取られ、被害が発生します。
送金先の口座は「受け子」や「出し子」と呼ばれる別の人物が管理していることが多く、資金はすぐに分散されてしまいます。
なぜ「特殊」と呼ばれるのか
一般的な詐欺との違いは、被害者が「自ら行動してしまう」点にあります。
犯人が直接脅迫するのではなく、心理的に追い込むことでATM操作やカードの引き渡しなどを自発的に行わせる構造が、「特殊詐欺」と呼ばれる理由です。
この心理操作型の構造が、検挙や防止を難しくしている最大の要因です。
特殊詐欺の特徴的なポイント
- 犯人は公的な立場や親族を装って信頼を得る
- 電話やSMS、SNSなどの通信を悪用する
- 被害者に自分で行動させることで罪悪感を薄れさせる
- 不安・焦り・秘密保持を巧みに利用する

詐欺は「自分には関係ない」と思った瞬間に入り込んできます。仕組みを理解しておくことが、最初の防御になりますよ
特殊詐欺の主な種類と特徴
特殊詐欺は、被害者の心理や状況につけ込み、電話・メール・SNSなどを使って金銭や個人情報をだまし取る犯罪です。ここでは、警視庁の分類と最新の動向をもとに、代表的な手口と特徴を整理します。
オレオレ詐欺(なりすまし型)
最も古くからある手口で、「自分だよ」「事故を起こした」などと親族を装い、示談金や急な支払いを求めます。
特徴
- 声が違うことを「風邪をひいた」などとごまかす
- 新しい電話番号を信じ込ませる
- 複数の人物(警察官・弁護士など)を装って信頼性を演出する
ポイント
電話でお金を要求されたら、必ず本人に直接確認することが重要です。
還付金詐欺(ATM誘導型)
「医療費や税金の還付金がある」と役所職員を装い、被害者をATMへ誘導して送金させる手口です。
特徴
- 「今なら手続きできる」「今日が期限」と焦らせる
- ATM操作でお金が戻るように錯覚させる
- 音声案内や通話を通じて送金を誘導する
ポイント
ATMで還付金を受け取ることは絶対にありません。電話でATM操作を指示されたら即座に通話を切ることが防止策になります。
架空料金請求詐欺(デジタル請求型)
「未納料金があります」「利用料金を支払ってください」といったメール・SMS・サイト表示を悪用し、支払いを迫る詐欺です。
特徴
- 有名サイト名や裁判所名を装う
- 電子マネーカードやQR決済を要求する
- ウイルス感染警告などで不安をあおる
ポイント
不審な請求は無視し、決して記載の連絡先には電話しないことが大切です。
投資詐欺・金融商品詐欺(高利誘導型)
「必ずもうかる」「著名人が推奨」などとSNS広告やチャットで信用させ、投資金や手数料をだまし取る手口です。
特徴
- 有名人の画像や偽アカウントを悪用
- 最初は少額の利益を見せて信用させる
- チャットグループで「仲間」を装い心理的に囲い込む
ポイント
SNS経由の投資話は基本的に詐欺と疑い、金融庁の登録業者かを必ず確認しましょう。
融資保証金詐欺(資金繰り狙い型)
「低金利で融資します」と持ちかけ、融資の前に「保証金」や「手数料」を要求して金銭を奪う手口です。
特徴
- 審査なし・即日融資などを強調
- 前金を支払わせた後に連絡を絶つ
- 実在する会社名や金融機関名を装う
ポイント
前払いが必要な融資はすべて詐欺を疑い、貸金業登録業者かを確認してください。
ロマンス詐欺(感情操作型)
SNSやマッチングアプリを通じて恋愛関係を装い、信頼や同情を利用してお金をだまし取ります。
特徴
- 魅力的な写真を盗用して偽プロフィールを作成
- 長期的に連絡を取り合い、感情を深く結びつける
- 「病気」「事業資金」「送金が止まっている」などの理由で支払いを要求
ポイント
ネット上で出会った相手への送金は絶対に避けましょう。会ったことのない相手の金銭要求はすべて危険信号です。
キャッシュカード詐欺盗・ニセ警察詐欺(公的機関なりすまし型)
警察官や銀行職員を装い、「あなたのカードが不正利用されています」などと騙し、カードを預かったふりをして盗む手口です。
特徴
- 公的機関を装って不安を煽る
- 「カードを交換する」「預かる」と言って奪う
- 隙を見て別のカードとすり替える
ポイント
警察や銀行が自宅に来てキャッシュカードを受け取ることは絶対にありません。
その他の詐欺(ギャンブル・交際あっせんなど)
「パチンコ打ち子募集」「女性紹介」などを口実に登録料・情報料をだまし取るケースもあります。
また、近年はSNS広告や副業サイトを装った新型詐欺も増加しています。

どの手口も、「不安」「焦り」「秘密」を使って判断を鈍らせるのが特徴です。電話・SMS・SNSのどれであっても、金銭やカードに関する話が出た時点で一度立ち止まることが、最も効果的な防止策ですよ
最新の特殊詐欺手口とデジタル化による進化
近年の特殊詐欺は、電話やはがきといった従来型の手口から、SNS・チャットアプリ・AI技術を悪用したデジタル型へと急速に進化しています。巧妙な心理操作に加えて、最新のIT技術が組み合わさることで、詐欺の見分けが難しくなっているのが現状です。
SNS・チャットアプリを悪用した「投資グループ」型詐欺
SNS上で「投資仲間」「FX・暗号資産グループ」などを装い、被害者をチャットに誘導する手口が急増しています。
最初は「利益が出た」「成功者が多い」と信じ込ませ、少額の出金を体験させて信用を得ます。その後、「もっと大きく稼げる」と追加投資を促し、大金を入金させた後にグループごと消えるという流れです。
特に、LINEやTelegramなどのアプリを通じて「金融庁登録済み」「有名人も利用」といった偽情報を流すケースもあります。
主な特徴
- SNS・メッセージアプリ内で完結するやりとり
- 少額で「成功体験」を演出して信用させる
- グループ全体が演技をして被害者を心理的に囲い込む
AI音声やディープフェイクを利用したなりすまし詐欺
AIの普及により、詐欺師が「親族の声」「上司の声」をAIで再現するケースが現れています。
音声データを数秒取得するだけで、声質やイントネーションを模倣できるため、「声で本人確認する」という従来の防衛策が通用しなくなっています。
また、ディープフェイク(AIで作られた偽映像)を利用して「Zoomで実在の人物と会話しているように見せかける」事例も報告されています。企業の経理担当者に対し、上司を装って送金を指示する「AIビジネス詐欺」も拡大しています。
危険なポイント
- 声の一致やビデオ通話の外見だけでは本人確認が不可能
- メール・チャット・ビデオを組み合わせた複合的な詐欺
- 企業の送金手続きを狙うケースが増加中
暗号資産・ネットバンキングを狙う送金誘導型詐欺
オンラインバンキングや暗号資産取引の普及を背景に、送金を巧みに誘導するタイプの詐欺も急増しています。
「口座の不正利用がありました」「安全な口座に移してください」といったメッセージを送り、被害者自らが犯人指定の口座に送金してしまう仕組みです。
この手口では、正規の銀行や取引所の画面を模した偽サイト(フィッシングサイト)が用いられることが多く、スマートフォンからアクセスすると見分けがつかないほど精巧に作られています。
典型的な手口
- 本物そっくりのURL・ロゴ・デザインを使用
- SMSやメールで緊急を装う通知を送る
- 暗号資産や電子マネーでの送金を要求する
デジタル化が進むほど「個人情報」が狙われる
特殊詐欺グループは、SNSやフリマアプリ、就職サイトなどに登録された「氏名・電話番号・メールアドレス・住所」を収集し、個別に攻撃を仕掛けます。
個人データをAI分析にかけて「高齢者・独居・投資関心が高い人」などを特定し、ターゲットを絞り込む動きも確認されています。
このため、単なる迷惑メールやSNSのDMであっても、背後ではAIが「あなた個人を狙っている」可能性があると理解する必要があります。

技術が進化するほど、詐欺も“デジタル化”しているんです。AIの声や動画が本物に見えても、慌てず一度立ち止まってください。「本当にその人か」を別ルートで確認するだけで、被害を防げるケースが多いですよ
被害者の心理を突く詐欺師のテクニック
特殊詐欺の成功率を高めているのは、犯人たちの「心理操作の巧妙さ」です。彼らは人間の感情や思考のクセを緻密に研究し、相手の警戒心を溶かしていきます。ここでは、被害者の心理を突く代表的な手法を解説します。
不安と焦りを利用して判断力を奪う
詐欺師は、被害者の「不安」と「焦り」を意図的に煽り、冷静な判断をできなくさせます。
「あなたの口座が犯罪に使われています」「今すぐ手続きしないと差し押さえになります」などの言葉で、時間的プレッシャーを与えるのが典型的です。
人は強いストレスや恐怖を感じると、論理的な思考よりも感情的な反応が優先され、誤った判断を下しやすくなります。特に高齢者は「早く解決しなければ」という責任感が働きやすく、詐欺師の狙いどおりの行動を取ってしまうケースが多いです。
信頼と罪悪感を組み合わせる「ダブル心理攻撃」
詐欺師は最初に「信頼関係」を築くことを重視します。家族や役所、銀行、警察など、権威や身近さを感じる存在になりすまし、被害者に安心感を与えます。
その上で、「あなたのせいで迷惑がかかる」「内密に処理してもらわないと困る」といった“罪悪感”を植え付ける発言を行い、心理的な支配状態に導きます。
このように「信頼」と「罪悪感」を組み合わせることで、相手が自ら行動してしまうよう誘導するのが詐欺師の狡猾な戦略です。
複数人による“チーム演出”で信憑性を高める
特殊詐欺の多くは、1人ではなく複数の犯人が役割分担して行います。
たとえば「銀行職員」「警察官」「弁護士」といった人物が次々に登場し、別々の立場から同じ情報を繰り返すことで、あたかも本当に組織的な対応が行われているように錯覚させます。
この“演出型詐欺”は、人が「多数派の意見=正しい」と思い込みやすい心理(社会的証明)を悪用しているのです。
「秘密」「今すぐ」「限定」などのキーワードで思考を停止させる
詐欺師がよく使う言葉には明確な意図があります。
- 「誰にも言わないで」:孤立させ、第三者の冷静な判断を排除する
- 「今すぐ対応して」:焦りを生み、冷静な確認をさせない
- 「今日だけ」「限定」:特別感を演出して判断を鈍らせる
これらの言葉は、詐欺だけでなくマーケティング心理学にも通じる“行動促進ワード”です。詐欺師はこれを悪用し、被害者に「確認する余裕を与えない」ことで、詐取行動へと導きます。
SNS時代の「共感型」心理操作
近年では、SNSやチャットアプリを使った“共感型詐欺”も増えています。犯人は、被害者の投稿内容や趣味嗜好から心理状態を読み取り、「あなたの気持ち、わかります」「自分も同じ経験をした」といったメッセージで共感を演出します。
信頼感が芽生えると、相手の発言を疑いにくくなり、恋愛詐欺や投資詐欺へと発展することがあります。人は「自分を理解してくれる人」に対して警戒心を下げる傾向があるため、この心理を悪用した詐欺は特に危険です。

詐欺師は“感情のスイッチ”を押してくるんです。焦り・信頼・罪悪感のどれかを感じたら、一度深呼吸して、必ず第三者に相談してください。冷静な一言が、被害を防ぐ最大の武器になりますよ
特殊詐欺を防ぐための具体的な対策
特殊詐欺は、個人の心理やデジタル環境の隙を突いてくるため、「自分は大丈夫」と思っている人ほど危険です。ここでは、誰でも今すぐ実践できる防止策を、ITの観点も交えて具体的に解説します。
電話・メール・SNSの発信元を疑う習慣を持つ
詐欺師は、公的機関や家族、金融機関を名乗って接触してきます。しかし、そのほとんどは偽装された番号やアカウントです。
- 電話番号は簡単に偽装できます。「警察」「銀行」「市役所」などの表示でも信用しない
- メールやSMSは、ドメイン(@以降の部分)を必ず確認する
- SNSのDMやLINEのメッセージは、まず「なりすまし」かを疑う
特にAI音声技術を悪用した「声のなりすまし詐欺」が増えています。家族や知人を装う電話があった場合は、必ず別の連絡手段で本人確認を行いましょう。
ATM操作を求められたら即座に詐欺を疑う
「還付金」「支援金」「返金」などを名目にATM操作を誘導する手口は、典型的な詐欺です。ATMはお金を“受け取る”ための機械ではなく、“送金する”ための装置です。どんな理由でも、電話口でATM操作を指示された時点で詐欺と判断してください。
また、銀行アプリやネットバンキングでも同様です。「今すぐ送金しろ」「セキュリティ解除が必要」などの指示は、絶対に従ってはいけません。
家族・知人との“詐欺防止ルール”を決める
家族や友人との間で、事前に「合言葉」や「確認ルール」を作っておくことで、詐欺を未然に防ぐことができます。
- お金の話が出たら、必ず本人に直接確認する
- 「秘密にして」「すぐに送金して」と言われたら、すぐに共有する
- LINEなどのアイコンや名前を変更された場合は、念のため本人に確認する
特に高齢の家族がいる場合は、定期的に「詐欺電話が増えているから気をつけてね」と話題にするだけでも効果的です。
スマートフォン・PCのセキュリティ設定を見直す
詐欺メールや偽サイトの多くは、デジタル上のセキュリティ設定が不十分なことを狙っています。以下の基本設定を徹底しておきましょう。
- SMS・メールのフィルタリング機能を有効にする
- 不審なアプリのインストールを制限する設定にする
- 二段階認証(2FA)を有効にし、アカウント乗っ取りを防ぐ
- セキュリティアプリやフィッシング対策アプリを導入する
また、無料Wi-Fiや不明なQRコード経由でアクセスしたサイトに個人情報を入力するのは避けましょう。
金融機関・公的機関への「再確認」を習慣にする
詐欺の多くは「公的な連絡」を装って信頼を得るため、冷静な確認行動が最も有効な防御策です。
- 不審な連絡を受けたら、必ず自治体・警察・銀行の公式窓口に自分で問い合わせる
- メールやSMSのリンクは開かず、公式サイトの検索からアクセスする
- 不明な入金・出金があれば、即座に金融機関のコールセンターに連絡する
特に「東京都消費生活センター」「警視庁相談窓口」「金融庁相談ダイヤル」などは、詐欺関連の相談にも対応しています。
SNS・デジタル社会での詐欺防止マインド
現代の特殊詐欺は、SNSやメッセージアプリを通じて個人の情報を分析し、心理的に入り込んできます。
情報を“出さない・信じすぎない・共有する”という3原則を意識してください。
- 自分や家族の写真・勤務先・資産状況をSNSに投稿しない
- 「有名人が勧める投資」「AIで稼げる副業」などの広告を信用しない
- 不審なアカウントやメッセージを見つけたら、すぐに通報・ブロック
SNSでの情報拡散スピードを逆に利用し、家族・友人に詐欺情報を共有することも防止につながります。

「詐欺は“信じてしまうこと”から始まります。送金・連絡・返信の前に“確認”を1回挟むだけで、防げるケースがほとんどなんです。焦らず、疑う勇気を持ってくださいね。」
家庭や企業でできる特殊詐欺の予防策
特殊詐欺の多くは、「情報」と「心理」を狙った犯罪です。家庭でも企業でも、日常的な習慣とITの仕組みを少し工夫するだけで、被害を大きく減らすことができます。ここでは、身近にできる現実的な予防策を紹介します。
家庭での特殊詐欺対策
高齢者の家庭を中心に、電話やスマートフォンを悪用した手口が依然として多発しています。被害を防ぐには、「不審な連絡を遮断する」「冷静に確認できる仕組みを持つ」ことが重要です。
通信面での対策
- 非通知・海外発信の拒否設定を行う
固定電話では非通知・海外番号の着信拒否を設定し、迷惑電話防止機能付き電話機を活用しましょう。 - 自動録音・警告メッセージ機能の導入
「この通話は録音されます」という自動音声は、詐欺犯にとって効果的な抑止になります。 - SMS・メールのリンクを絶対にタップしない
税金や公共料金などの「還付金」「未払い」を装うメッセージは、リンクを開く前に公式サイトや窓口で確認を。
家族間での連携
- 「合言葉」を決めておく
家族の誰かを名乗る電話がかかってきた場合、あらかじめ決めておいた「詐欺防止コード(合言葉)」を使って本人確認を。 - 家族チャットやSNSで情報共有
不審な電話やSMSを受けた場合は、家族LINEやグループチャットにスクリーンショットを共有して注意喚起します。 - 「自分は騙されない」という思い込みを捨てる
詐欺の多くは「知っていても引っかかる」構造です。知識よりも確認行動を重視することが大切です。
企業での特殊詐欺対策
企業は「金銭」と「データ」を狙われます。特に中小企業では、経理担当者を狙った「ビジネスメール詐欺」や「偽の請求書」被害が急増しています。組織としてルールを明確にし、情報共有を徹底することが必要です。
ITシステム面の防御
- メールの送信元ドメインを確認する習慣を徹底
取引先を装った偽メール(例:@abc.co.jp → @abc-co.jp)を見抜くには、メールヘッダーやドメイン確認の教育が有効です。 - セキュリティソフトとスパムフィルタの強化
サーバー側で不審メールを自動隔離できるよう、社内IT担当または外部のセキュリティ業者に設定を依頼しましょう。 - VPNと多要素認証の導入
外出先や自宅からの接続では、VPNやワンタイムパスワードを利用し、不正アクセスを防止します。
組織ルールと教育
- 送金や振込の「二重確認ルール」を徹底
経理担当が送金前に上司や代表者へ確認する仕組みを運用します。メールだけでなく、電話・チャットなど別経路で再確認することが有効です。 - 「不審メール報告チャネル」を設ける
従業員が怪しいメールを見つけた際、即時共有できる内部チャットやフォームを整備します。 - 定期的な模擬詐欺訓練の実施
社内教育として、架空請求メールや不審電話の「模擬対応訓練」を行い、実際の行動を身に付けさせます。
テクノロジーを活用した新しい防犯対策
AIやIoTの普及により、特殊詐欺の防御も進化しています。家庭や企業で導入できる現実的な仕組みとして、以下のような方法があります。
- AI搭載電話(自動応答+不審判定)
AIが通話内容を分析し、詐欺と疑われる場合は自動的に通話を遮断。 - 銀行アプリの不正送金検知機能の活用
特定の異常な取引や深夜送金を検出してアラートを出す機能を設定します。 - スマートホーム連携で高齢者を見守る
高齢者宅の電話機やスマホに不審着信があった場合、家族に自動通知されるIoTデバイスの導入も効果的です。

家庭でも企業でも、「確認」と「共有」を習慣化することが最大の防御です。テクノロジーを味方につけて、詐欺犯に“入り込む隙”を与えないようにしましょう
もし特殊詐欺の被害にあってしまったら
特殊詐欺の被害にあった場合、最も大切なのは「一刻も早い対応」です。時間が経つほど、犯人の足取りや送金先の追跡が困難になり、返金の可能性が低くなります。焦らず冷静に、次の手順を実践してください。
1. すぐに警察へ通報する
被害を確認したら、迷わず 110番 に通報してください。詐欺であることが確定していなくても構いません。「もしかして詐欺かも」と思った段階で通報することが重要です。
また、最寄りの警察署や「サイバー犯罪対策課」に直接相談することも可能です。電話・メール・SNS経由の詐欺の場合は、受信したメッセージや送金指示の画面 を証拠として保存しておきましょう。
2. 金融機関に口座凍結を依頼する
送金やキャッシュカードの情報を相手に渡してしまった場合は、すぐに取引銀行へ連絡し、被害口座の利用停止・出金停止の手続き を行います。
銀行・信用金庫・ネットバンクなど、どの金融機関でも詐欺被害専用の対応窓口が設けられています。特に次の点を必ず伝えましょう。
- 「特殊詐欺に関与した可能性がある」こと
- 「送金先の口座番号」「取引日時」「金額」などの詳細
- 「自分の口座・カード情報を相手に伝えた」場合のリスク
迅速に凍結処理が行われれば、犯人の引き出しを防げる可能性があります。
3. 証拠を残し、被害届を提出する
警察に通報した後は、必ず「被害届」を提出します。
その際には以下の資料を整理して持参すると、捜査や補償対応がスムーズになります。
- 詐欺メールやメッセージのスクリーンショット
- 電話番号や通話履歴
- 送金記録(ATMの明細・振込履歴など)
- 相手とやりとりしたSNS・アプリのアカウント情報
これらは警察だけでなく、後の返金請求や金融機関との協議の際にも重要な証拠となります。
4. 消費生活センター・預金保険機構に相談する
お金を取り戻す可能性がある場合は、消費生活センター(188番) や 預金保険機構(金融庁管轄) にも相談しましょう。
「振り込め詐欺救済法」に基づき、被害者に資金を返還する手続き(被害回復分配制度)が適用される場合があります。
ただし、返還を受けるには期限内に申請する必要があります。迷ったら、すぐに窓口へ問い合わせてください。
5. 今後の被害拡大を防ぐための行動
被害を受けた直後は混乱しやすいですが、再被害を防ぐための行動も欠かせません。
特にデジタル・IT環境に関連する部分では、次の対応が重要です。
- SNSやメールのパスワードをすべて変更する
- 2段階認証を有効にする
- キャッシュカード・クレジットカードを再発行する
- 家族や知人に被害状況を共有し、同様の詐欺への注意を促す
詐欺師は「一度だまされた人は再び狙える」と考え、再接触してくるケースもあります。電話やメールで「返金します」「犯人を追跡中」といった連絡があっても、すべて無視してください。
6. 心理的ダメージを軽視しない
特殊詐欺の被害者は金銭的損失だけでなく、「自分を責める」心理的ダメージを受けやすい傾向があります。
しかし、詐欺は巧妙に仕組まれた犯罪であり、誰でも被害に遭う可能性があります。落ち込むよりも、再発を防ぐ知識を持ち、周囲に注意を広めることが大切です。
必要に応じて、地域の相談窓口や心理カウンセラーへの相談も検討しましょう。

冷静に対応できる人ほど被害を最小限にできます。焦らず、警察・金融機関・公的窓口にすぐ連絡して行動してください。自分を責めるより、正しい情報を共有して、次の被害を防ぐ側に回ることが大切ですよ
身近に潜むサインを見抜く!詐欺の前兆とチェックリスト
特殊詐欺の多くは、ある日突然に起きるわけではありません。実際には、被害に遭う前に「違和感」や「小さなサイン」が現れることがほとんどです。詐欺師は心理的な揺さぶりや情報操作を巧みに使い、被害者を少しずつ“信じ込ませる状態”へ導きます。ここでは、そうした前兆を早期に察知し、被害を防ぐためのチェックポイントを整理します。
不自然な連絡・要求を見抜く
まず意識すべきは、「通常ではありえない状況や要求」に気づくことです。詐欺師は電話・SMS・SNS・メールなど、あらゆる通信手段を使って接触してきます。
- 「○○税の還付金があります」「料金未納のため法的手続きになります」といった“緊急性を煽る”メッセージ
- 「家族や警察を名乗るが、声や文面が不自然」「新しい番号を使ってきた」などの“設定の不自然さ”
- 「今すぐATMに行って」「秘密にして」と指示される“思考停止を誘う文言”
- SNSやメールで「簡単に儲かる」「限定の投資グループ」などの“甘い誘い”
これらはすべて「一度立ち止まるべきサイン」です。特に「電話番号が変わった」「すぐ返金できる」「期限が今日中」といったワードが出たら、冷静に確認を取りましょう。
技術を悪用した“新しい前兆”にも注意
近年は、AIやディープフェイクを悪用した詐欺が急増しています。
電話やビデオ通話で、家族の声や顔を“本物そっくりに模倣”されるケースもあります。
また、金融機関や配送業者を装った「偽サイト」へ誘導し、ログイン情報を盗み取るパターンもあります。
- URLが「https」ではなく不自然なドメイン(例:.xyz、.top)
- ログイン画面のデザインが微妙に違う
- メール差出人のアドレスが企業名と一致しない
- AI音声がやや機械的、返答が一瞬遅い
IT知識を持つ人ほど「技術的にすごい」と思ってしまい、信じ込むことがあります。
しかし、「本物そっくり」に見えるほど危険であるという認識が大切です。
家庭・職場で確認したいチェックリスト
身近な場所で「不審なサイン」に気づくには、普段のルールづくりが欠かせません。
以下のチェック項目に1つでも該当する場合は、詐欺被害の“入口”に立っている可能性があります。
- 電話やメールでお金・個人情報・暗証番号を求められた
- 「家族」「警察」「金融機関」から“急ぎの指示”を受けた
- SNSやLINEで投資・副業の勧誘を受けた
- 「今だけ」「特別」「秘密」などの言葉を多用された
- 自分でも「少し変だ」と感じたが、相手に言いくるめられた
- 家族や上司に相談しづらい雰囲気を作られた
このチェックリストは、家庭や職場でも共有することが大切です。
「変だな」と思ったときに、すぐに第三者へ確認できる体制を整えておくことで、被害は未然に防げます。
早期発見のためのデジタル防御策
ITの力で詐欺の前兆をキャッチする方法もあります。
- 迷惑電話フィルター・自動録音機能を固定電話に設定する
- メールの送信元ドメイン認証(DMARC・SPF)を確認できるアプリを使う
- SNSやメッセージアプリで「不審アカウント報告」機能を活用する
- 企業や金融機関の公式アプリからのみログインする
こうした基本的なITリテラシーを持つことが、最も効果的な詐欺予防策です。

「あれ?おかしいな」と感じた瞬間が、被害を防ぐチャンスなんです。焦らず一呼吸おいて、家族や信頼できる人に相談してみてくださいね