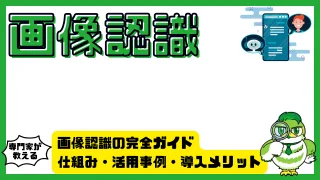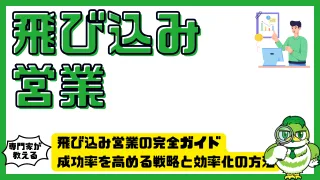本ページはプロモーションが含まれています。
目次
Excelでグループ化を使うメリット
大量データを見やすく整理できる
Excelで扱う表は、項目が増えると一気に複雑になり、必要なデータを探すのに時間がかかってしまいます。グループ化を利用すると関連する行や列をまとめて折りたためるため、必要な部分だけを開いて確認できます。スクロール量も減り、視覚的にすっきりとした状態で作業を進められます。
必要な情報だけを効率的に表示できる
グループ化を活用することで、分析や報告に不要な細かいデータを隠し、要点だけを強調した状態で表を確認できます。特に定例会議やクイックチェックの場面では、全データを開かずとも重要な数値だけを見せられるため効率的です。
印刷資料のレイアウトを整えやすい
Excelのグループ化は印刷時にも有効です。不要な行や列を折りたたんで印刷すれば、用紙に収まる見やすいレイアウトで資料を作成できます。顧客向けや社内共有用に無駄を省いた整った資料を短時間で仕上げるのに役立ちます。
集計や比較作業がスムーズになる
多段階のグループ化を設定すれば、年度→月→週といった階層的な確認が可能になります。必要な粒度まで展開して集計を見たり、比較のために一部だけ開いたりと柔軟に操作でき、集計作業の効率を大幅に向上させられます。

グループ化のメリットは「見やすさ」「効率性」「資料作成のしやすさ」にありますよ。特に大量のデータを扱う人にとっては、視覚的な整理と情報の絞り込みが一度にできる点が大きな強みです。業務のスピードを上げたいならぜひ活用してみてください
グループ化の基本操作手順
Excelのグループ化は、複雑な表を折りたたんで見やすく管理できる便利な機能です。行や列を対象にまとめることで、必要な情報だけを表示し、不要な部分を一時的に非表示にできます。ここでは初心者でも迷わないように、基本的な手順を整理して解説します。
1. 対象となる行や列を選択する
まず、グループ化したい範囲をマウスでドラッグして選択します。例えば、4行目から12行目をまとめたい場合は、その範囲を指定します。列の場合も同様に、B列からD列などを選びます。
2. 「データ」タブからグループ化を実行する
リボンメニューの「データ」タブをクリックし、右側の「グループ化」ボタンを選択します。ダイアログが表示されたら「行」または「列」を指定してOKを押します。
3. 折りたたみ・展開を切り替える
グループ化されると、シートの左端や上端に「-」「+」のボタンが表示されます。「-」をクリックすると選択範囲が折りたたまれ、「+」をクリックすると再び展開されます。これにより、必要なときだけ詳細データを確認できるようになります。
4. グループ化を複数設定する場合
同じシート内で複数の範囲をグループ化することも可能です。ただし、連続していない範囲を一度に選択してグループ化することはできないため、それぞれの範囲ごとに操作を繰り返す必要があります。

グループ化の手順はとてもシンプルですが、ポイントは「必ず連続した範囲を選ぶこと」と「折りたたみの操作に慣れること」です。これさえ意識すれば、見やすい資料作りや効率的なデータ管理がぐっと楽になりますよ
行をグループ化する方法
行のグループ化は、表の縦方向に並ぶデータをひとまとまりにして折りたたむ機能です。部署ごとや月ごとの売上データなど、一定の範囲をまとめて整理したいときに便利です。非表示にしたい行を単純に隠すのではなく、グループ化しておくことで「+」「-」のボタンで簡単に切り替えができ、どの部分が折りたたまれているかも一目で分かります。
基本的な手順
- グループ化したい行をドラッグして選択します。例えば、4行目から12行目をまとめたい場合は、その範囲を指定します。
- メニュー上部の「データ」タブをクリックします。
- 「アウトライン」グループ内にある「グループ化」を選択します。
- ダイアログボックスが表示された場合は「行」を選び、「OK」をクリックします。
- 選択範囲の左側に「-」ボタンが表示され、クリックすると該当行が折りたたまれます。再度表示したいときは「+」をクリックします。
活用例
- 月次売上データの整理
1月から12月までの売上を記録している場合、各月の詳細データをまとめておくと、年度全体のサマリーをすぐに確認できます。必要な月だけ展開すれば、表の見通しが大幅に改善されます。 - プロジェクトごとの管理
タスク一覧表で、プロジェクト単位に行をまとめておけば、進行中のプロジェクトだけを展開することができます。会議や報告資料のときに、不要な情報を折りたたんで見せられるので便利です。 - 印刷用資料の調整
補足データや詳細記録をグループ化しておけば、印刷時に折りたたんだ状態で出力でき、紙面をすっきりさせることができます。
複数のグループを作成する
複数の範囲をそれぞれグループ化することも可能です。例えば、1~10行、11~20行を別々にまとめれば、段階的に開閉して管理できます。ただし、複数範囲を同時に選んで一度にグループ化することはできませんので、範囲ごとに操作を繰り返す必要があります。

行をグループ化すると、単なる非表示とは違って「どこをまとめたか」が明確に見えるのが大きな利点です。作業効率も見やすさもぐっと上がりますので、まずは小さな表から試してみるといいですよ
列をグループ化する方法
列のグループ化は、横方向に並ぶ複数の項目をまとめて整理したいときに便利です。売上データの「商品カテゴリ」や「地域別データ」など、列単位で情報を隠したり表示したりすることで、表をシンプルに保ちながら必要な部分だけを確認できます。
基本手順
- グループ化したい列をドラッグして選択します
例:B列からD列までをまとめたい場合、B~D列を選択します。 - リボンの「データ」タブを開き、「グループ化」をクリックします
- ダイアログボックスが表示された場合は「列」を選んで「OK」を押します
- 列の上部に「-」ボタンが表示され、クリックすると選択した列が折りたたまれます。「+」を押せば再表示できます
実用的な使い方
- カテゴリごとの整理
製品A・製品B・製品Cなどを1つのグループにまとめ、他の製品列は非表示にして分析をしやすくします。 - 不要な情報を一時的に非表示
計算の途中で必要な補助列や確認用列をグループ化して折りたたむことで、資料として見せる際に表がすっきりします。 - 印刷時の見やすさ改善
不要な列を折りたたんだ状態で印刷すれば、資料がコンパクトになり読みやすくなります。
複数グループの作成
B~D列・F~H列・J~L列といったように複数の範囲をグループ化する場合は、それぞれの範囲を選んで同じ操作を繰り返します。一度に離れた範囲を選択してまとめることはできないため、分けて設定する必要があります。
注意点
- セル結合されている列を含むと正しくグループ化できない場合があります
- 非連続列は一括で選択できません。範囲ごとに操作を繰り返してください
- フィルターを使っている場合は表示切り替えの挙動に影響が出ることがあります

列のグループ化は「表をシンプルにする」ための強力な手段です。必要なときにだけ表示するという使い方を覚えておくと、資料作成や分析作業がぐっと効率的になりますよ
グループ化を解除する手順
グループ化を使ってデータを整理したあと、不要になった場合には解除することができます。解除の操作を理解しておくことで、必要なときに柔軟にデータ表示を切り替えられます。
部分的に解除する方法
- グループ化を解除したい行または列をドラッグして選択します。
- 「データ」タブをクリックし、アウトラインの「グループ解除」を選択します。
- ダイアログが表示された場合は「行」または「列」を指定してOKをクリックします。
この操作により、選択した範囲のグループだけが解除され、他のグループはそのまま維持されます。
すべてのグループを解除する方法
- 任意のセルを選択した状態で、「データ」タブを開きます。
- 「グループ解除」の右にあるメニューを開き、「アウトラインの設定をクリア」を選択します。
この操作を行うと、シート内に設定されたすべてのグループ化が一括で解除されます。
ショートカットキーで解除する
グループ化を解除するときもショートカットが利用できます。
- Alt + Shift + ←キー を押すと、選択範囲のグループが解除されます。
マウス操作に比べて素早く処理できるため、頻繁にグループを解除する場合に便利です。
注意点
- 解除する際には、範囲選択が正しく行われているかを確認してください。範囲がずれていると、意図しない部分まで解除される場合があります。
- 階層的にグループ化している場合は、外側のグループを解除すると内側のグループも消えることがあるため注意が必要です。

グループ化は便利ですが、解除手順を覚えておけば安心して使いこなせますよ。部分解除と全解除を正しく使い分けることで、作業効率がぐんと上がります
階層的なグループ化と応用例
多段階のグループ化でデータを整理する
Excelでは1つの表に対して複数の階層を持つグループ化を設定できます。例えば、売上データを「年度 → 月 → 週」の順にまとめると、最初は年度ごとだけを表示し、必要に応じて月や週の詳細を展開できます。これにより、膨大なデータもアウトラインを使って整理しやすくなり、全体像と詳細を自在に切り替えられます。
設定方法は、まず大きな範囲(例:1年分のデータ)をグループ化し、その後さらに小さい範囲(例:1か月単位)を追加でグループ化する手順を繰り返します。左側のアウトライン番号が階層を示すので、どの段階で折りたたんでいるのかが一目で確認できます。
小計や集計機能との組み合わせ
階層的なグループ化は、小計機能や集計機能と組み合わせると効果を発揮します。たとえば、部署ごとの売上データをグループ化し、小計を設定すると、展開・折りたたみに応じて各階層の合計が見やすく表示されます。これにより、年度の総合計から月別、さらに個人別の売上まで一貫して把握できます。
小計の自動計算機能を利用すると、各グループごとに合計・平均・最大値・最小値を自動で追加でき、集計作業の手間を大幅に削減できます。特に会議資料や報告書の作成時に役立ち、必要な詳細度でデータを簡単に提示できます。
実務での活用シーン
- 経理業務:年度→月→勘定科目の順で階層化し、支出の詳細を整理
- 営業管理:支社→営業所→担当者の順に展開して、売上や契約件数を確認
- プロジェクト進行管理:プロジェクト全体→各フェーズ→作業タスクという形で段階的に表示
このように階層をつけることで、状況に応じて全体と詳細を自在に切り替えられるため、分析効率が格段に高まります。

階層的なグループ化は、全体の流れと細部を切り替えながら確認できる便利な機能です。年度や部署ごとの大きなまとまりを俯瞰しつつ、必要なときに細かい単位まで掘り下げられるのが強みですね。小計と組み合わせれば、分析や資料作成がもっと効率的になりますよ
グループ化ができないときの原因と対策
Excelでグループ化を実行しようとしても、思ったように動作しない場合があります。代表的な原因と、それに応じた解決策を整理しました。
非連続範囲を選択している
グループ化は「連続した行または列」にしか適用できません。Ctrlキーで飛び飛びの範囲を選択するとエラーになります。
対策としては、一度にまとめたい範囲を必ず「連続したセル」で選び直してください。複数の範囲をまとめたい場合は、範囲ごとにグループ化を繰り返す必要があります。
セル結合が含まれている
結合セルがグループ範囲内にあると、グループ化ができないケースがあります。特に列方向に結合されていると失敗しやすいです。
この場合は、対象範囲の結合を一度解除し、必要ならグループ化後に結合し直す方法をとってください。
フィルター機能との干渉
オートフィルターが有効な状態で一部のデータが非表示になっていると、範囲の指定が正しく反映されずグループ化できないことがあります。
対策は、フィルターを一時的に解除してからグループ化を行い、その後再度フィルターを設定することです。
ピボットテーブル内のデータ
ピボットテーブルでは、通常の行・列グループ化はできません。ピボットテーブル専用の「グループ化」機能を使う必要があります。
日付のグループ化や数値の区切りでまとめたい場合は、右クリックから「グループ化」を選択してください。
保護シートの制限
シート保護が有効になっていると、グループ化や解除の操作が制限されることがあります。
シートを保護している場合は、まず保護を解除し、グループ化が完了してから再度保護を設定すると安全です。
アウトライン設定が無効になっている
Excelのオプション設定で「アウトライン記号を表示する」が無効になっていると、+/-ボタンが表示されず操作ができないように見えます。
オプションの「詳細設定」→「表示」項目から「アウトライン記号を表示する」にチェックを入れて確認してください。

グループ化できないときは、範囲の選び方・セル結合・フィルターや保護の設定を一つずつ確認すると解決しやすいですよ。焦らずチェックしていけば、必ず原因が見つかります
ショートカットや便利技で効率化
グループ化はメニューから操作するのが基本ですが、ショートカットや工夫を使えば大幅に作業スピードを上げられます。毎日の業務で同じ手順を繰り返す人にこそ役立つテクニックです。
キーボードショートカットで素早く操作
- グループ化
Alt + Shift + →(右矢印)で選択範囲を一瞬でグループ化できます。 - グループ解除
Alt + Shift + ←(左矢印)で即座に解除できます。
マウスでメニューを探すよりも直感的に扱えるので、表を頻繁に整理する作業では必須です。
表示切り替えを一括で行う便利操作
ワークシートの左上に表示される「1」「2」「3」といったアウトライン番号をクリックすると、全体の表示レベルを一括で切り替えられます。
例えば「1」をクリックすれば最上位レベルだけが表示され、大枠の集計だけを確認できます。「2」「3」に切り替えれば詳細な階層まで展開できます。
マクロやVBAで自動化
よく使う範囲を毎回グループ化するのが面倒な場合は、マクロを登録すると効率化できます。
例えば「毎回、月ごとのデータをグループ化する」という処理をVBAで作成しておけば、ボタン1つで自動処理が可能になります。業務で同じ表を繰り返し扱う人に特に有効です。
見やすい資料作りの工夫
印刷やプレゼン資料に使う場合は、不要な行や列をグループ化して折りたたみ、必要な部分だけを展開して出力すると表がすっきりします。
また、列幅を調整してグループ境界を揃えると、折りたたみ後も見栄えが整い、資料の完成度が高まります。

ショートカットを覚えるだけでも業務効率は一気に上がりますし、マクロを組み合わせれば定型作業を自動化できます。グループ化はただの整理機能ではなく、工夫次第で「時短」と「見やすさ」を両立できる便利なツールなんですよ