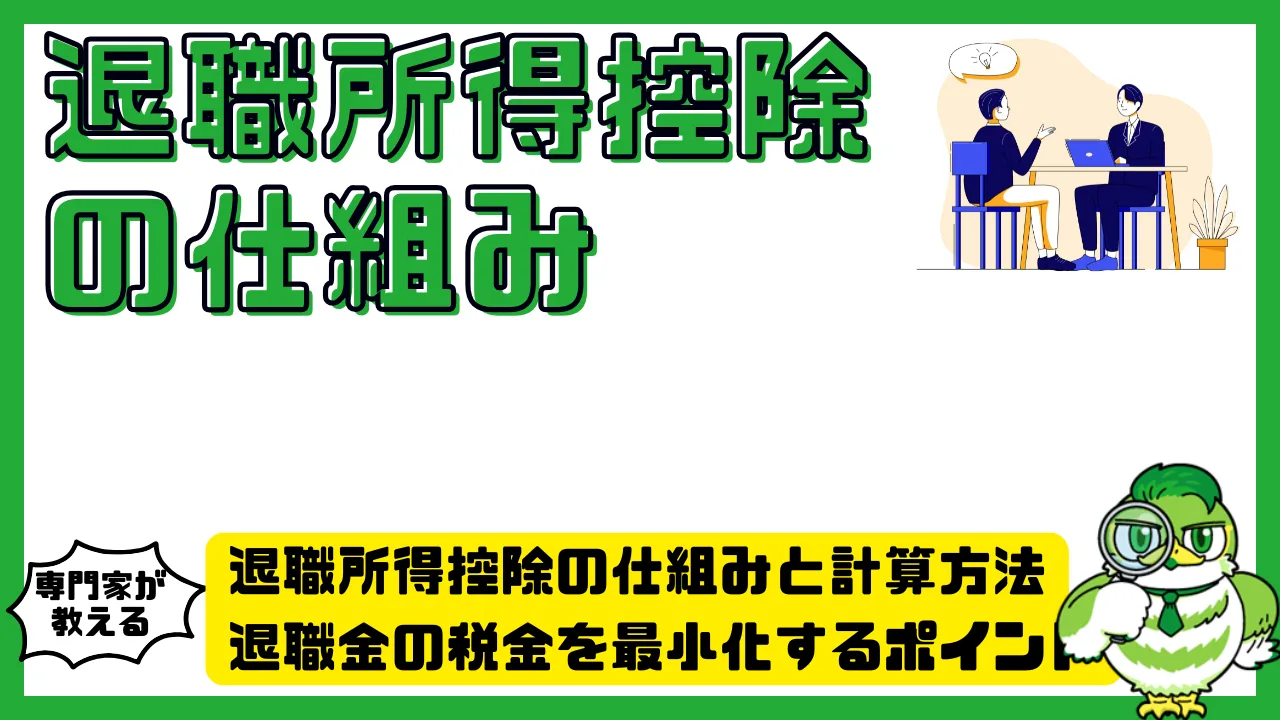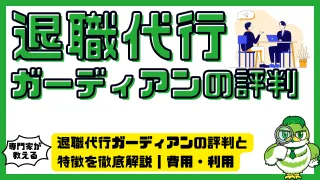本ページはプロモーションが含まれています。
目次
退職所得控除とは何かを理解する
退職所得控除とは、退職金を受け取る際に課される税金を軽減するために設けられた制度です。通常の給与や事業所得と違い、退職金は「退職所得」という区分で扱われ、他の所得と分離して計算されます。これを「分離課税」と呼びます。分離課税によって、退職金に対しては特別な計算方法が適用され、税金の負担が大きく軽くなる仕組みになっています。
退職金は長年の勤務に対する労いの意味合いが強く、老後の生活資金としての役割も持っています。そのため、退職金にかかる税金が過度に重くならないよう、退職所得控除という優遇措置が設けられているのです。この控除は勤続年数に応じて金額が大きくなり、長く働いた人ほど大きな控除を受けられる仕組みになっています。
また、退職金にかかる税金は、退職所得控除を差し引いた残りの金額をさらに「2分の1」にして計算されるのが特徴です。つまり、実際に課税される金額は受け取った退職金の一部に限られ、結果として税率が抑えられる形になります。これは老後資金を確保するための政策的な配慮といえます。
さらに、障害を理由に退職した場合には、控除額に特別加算があるなど、個々の事情に応じた優遇も整備されています。こうした仕組みを理解しておくことで、自身の退職金の手取り額を正しくイメージでき、老後の生活設計にも役立てることができます。

退職所得控除は、退職金の税金を大幅に減らすための制度です。勤続年数に応じて控除額が増えるうえ、計算時にさらに半分にする仕組みがあります。老後資金を守るための大切な優遇措置ですから、まずは仕組みをしっかり理解しておくことが大事ですよ
退職所得控除額の基本計算式
退職所得控除額は、勤続年数に応じて自動的に増えていく仕組みになっており、退職金の税負担を軽減する重要な要素です。基本的な計算式は以下のとおりです。
勤続年数20年以下の場合
- 40万円 × 勤続年数
- ただし、計算結果が80万円未満となる場合は 最低80万円 が控除されます
(短期勤務であっても一定額が確保される仕組みです)
例
勤続年数5年の場合
40万円 × 5年 = 200万円(→200万円が控除額)
勤続年数20年を超える場合
- 800万円 + 70万円 ×(勤続年数-20年)
例
勤続年数30年の場合
800万円 + 70万円 ×(30-20)= 1,500万円
障害退職の場合
障害が原因で退職した場合は、上記で算出した控除額に 100万円を加算 できます。
退職理由による優遇措置のひとつで、負担軽減が手厚く設計されています。
計算のポイント
- 1年未満の端数は切り上げて1年 として計算するため、10年2か月勤務の場合は「11年」として扱います。
- 複数回に分けて退職金を受け取った場合や、他社からも同一年内に退職金を受け取った場合は、計算方法が異なる特例が適用されることがあります。
- 控除額を正しく把握しなければ、退職金の実際の手取り額を見誤る可能性があるため注意が必要です。

退職所得控除の計算はシンプルに見えて実は例外も多いので、必ず自分の勤続年数や退職理由に当てはめて確認してくださいね。控除額が大きいほど税金が軽くなるので、制度を理解しておくことが安心につながりますよ
勤続年数の数え方と端数の扱い
退職所得控除の計算では「勤続年数」が基準になります。勤続年数の捉え方を誤ると、控除額が大きく変わってしまうため正確に理解しておくことが重要です。
勤続年数の基本的な数え方
勤続年数は、入社日から退職日までの期間を年数でカウントします。途中で異動や契約形態の変更があっても、同じ企業で勤務を継続している場合は通算して計算します。正社員だけでなく、契約社員やパートタイマーであっても「勤続」とみなされれば対象になります。
1年未満の端数は切り上げ
退職所得控除の大きな特徴は、1年未満の端数がある場合には「切り上げ」て1年として計算される点です。
例えば、勤続10年2か月で退職した場合、勤続年数は「11年」として扱われます。この端数切り上げによって、控除額が大きくなるケースもあります。
端数処理の具体例
- 勤続10年1か月 → 11年として計算
- 勤続19年11か月 → 20年として計算
- 勤続20年1か月 → 21年として計算
こうした切り上げのルールにより、退職所得控除額が40万円〜70万円単位で増えることがあるため、実際の税負担に大きな差が生まれることがあります。
複数の勤務先から退職金を受け取る場合
過去に退職金を受け取ったことがある場合や、同じ年に2か所以上の勤務先から退職金を受け取る場合は特例の計算が適用されます。その場合、各退職金について勤続年数を調整し、控除額を重複して適用しないように扱われます。誤解しやすい部分なので、必ず税務署や専門家に確認することが推奨されます。
役員の場合の勤続年数
取締役や執行役などの「役員」として勤務した年数を区別して計算する必要があります。役員期間についても端数は同様に切り上げ処理が行われますが、控除や課税方法に特例があるため注意が必要です。

勤続年数は1年未満の端数を切り上げるルールがあるので、退職のタイミングによって控除額が大きく変わります。月単位で数か月待つだけで控除額が数十万円増えることもあるので、退職時期を決める際には必ず確認してくださいね
退職所得控除を使った税額計算の流れ
退職金にかかる税金を正しく理解するには、控除額の算出だけでなく、課税所得や税率の流れを把握することが大切です。ここでは、退職所得控除を踏まえた税額計算の全体像を整理します。
課税退職所得金額の計算
退職金から退職所得控除額を差し引いた後、その金額をさらに1/2にすることで課税退職所得金額を算出します。
計算式は次のとおりです。
課税退職所得金額=(退職金額-退職所得控除額)×1/2
この「1/2計算」によって、他の所得に比べて大幅に税負担が軽減されるのが退職所得の特徴です。なお、特定役員退職手当等や短期退職手当等に該当する場合は例外処理となり、1/2計算が適用されない点に注意が必要です。
所得税の計算
課税退職所得金額が求められたら、これをもとに所得税を計算します。所得税は累進課税方式のため、課税退職所得金額に応じて税率と控除額が段階的に決められています。
計算式は次のとおりです。
所得税額=課税退職所得金額×税率-控除額
さらに、2037年までは東日本大震災復興財源として「復興特別所得税」が課されます。これは、算出された所得税額に対して2.1%を上乗せして計算されます。
住民税の計算
退職金には住民税も課税されますが、こちらは全国一律で10%とシンプルです。都道府県民税4%と市区町村民税6%を合算したものになり、課税退職所得金額に対して直接乗じて計算されます。
住民税額=課税退職所得金額×10%
税額計算の流れをまとめると
- 退職金から退職所得控除額を引く
- 残額を1/2にして課税退職所得金額を求める
- 課税退職所得金額に所得税率をかけ、控除額を差し引く
- 復興特別所得税(所得税額×2.1%)を加算する
- 課税退職所得金額に10%を乗じて住民税を算出する
この流れを踏むことで、退職金の手取り額が正確に把握できるようになります。

退職所得控除を使った税額計算は、まず控除額を正しく計算することが基本です。その上で、課税退職所得金額→所得税→復興特別所得税→住民税という順序で処理していけば迷わず進められますよ
特定役員退職手当等や短期退職手当等の例外
退職所得控除は基本的に「退職金-控除額」の2分の1を課税対象とする優遇制度ですが、すべてのケースでこの計算が認められるわけではありません。特に、勤続年数が短い場合や役員としての在籍期間が短い場合には例外規定があり、誤解すると税額が大きく変わってしまいます。
特定役員退職手当等とは
「特定役員退職手当等」とは、役員や公務員などが勤続5年以下で退職した場合に支払われる退職金のことです。
この場合は退職所得控除を差し引いた後、2分の1にする優遇措置が認められません。つまり、控除後の全額が課税対象となります。
役員等の範囲には以下が含まれます。
- 法人の取締役、監査役、執行役、理事など経営に携わる立場
- 国会議員や地方議会議員
- 国家公務員や地方公務員
例えば、取締役として勤続3年で退職し、退職金を受け取った場合は「(退職金-退職所得控除額)」がそのまま課税退職所得金額となります。通常より税負担が大きくなるため、役員就任後すぐに退職するケースでは注意が必要です。
短期退職手当等とは
「短期退職手当等」とは、役員以外の一般従業員が勤続5年以下で退職する場合に支払われる退職金のことです。
この場合は、退職所得控除を差し引いた後の金額のうち300万円までが2分の1課税の対象になりますが、300万円を超える部分については2分の1計算が認められません。
例として、勤続3年で退職し控除後の金額が500万円だった場合、
- 最初の300万円 → 2分の1課税(150万円)
- 残り200万円 → 全額課税対象
となり、合計350万円が課税退職所得金額になります。
よくある誤解と注意点
- 勤続年数は1年未満の端数を切り上げて計算します。4年11か月でも「5年」と扱われるため、特定役員退職手当等や短期退職手当等に該当するかどうかの境界で大きな差が出ます。
- 役員就任前の勤務期間は「一般従業員としての勤続年数」に含まれるため、役員期間が5年以下であっても、通算勤続年数が長ければ通常の退職所得扱いとなることもあります。
- 税務上の扱いを誤ると源泉徴収額や確定申告での納税額に差が生じるため、退職金の受給が見込まれる場合は事前にシミュレーションをしておくことが重要です。

特定役員退職手当等や短期退職手当等は「退職金優遇の穴」みたいなものです。勤続5年以下では2分の1課税が制限されるので、受け取り方や時期を工夫する必要があります。制度の例外を理解しておけば、想定外の税負担を避けられますよ
確定申告が必要になるケース
退職金は通常、会社に「退職所得の受給に関する申告書」を提出すれば、源泉徴収によって課税が完結するため確定申告は不要です。ただし、特定の状況では自分で確定申告を行う必要があります。申告を忘れると本来受けられる控除を逃したり、納めすぎた税金が戻ってこない可能性があるため注意が必要です。
退職所得申告書を提出していない場合
退職金の支給時に「退職所得の受給に関する申告書」を会社に提出していないと、退職金に対して一律20.42%(所得税+復興特別所得税)が源泉徴収されます。この場合は退職所得控除が考慮されないため、確定申告を行って控除を適用し、納めすぎた税金を還付してもらう必要があります。
年の途中で退職し年末調整を受けていない場合
年の途中で退職し、その後に再就職していない場合は年末調整を受けられません。源泉徴収された税額が実際の所得に対して過大であることが多いため、確定申告を行うことで税金が還付されます。特に退職年の給与が前年より少ない場合は、申告によって戻る金額が大きくなる可能性があります。
所得控除を追加で受けたい場合
退職後に支払った社会保険料や国民健康保険料は「社会保険料控除」として申告できます。また、生命保険料控除、地震保険料控除、医療費控除、寄附金控除などを受けたい場合も確定申告が必要です。こうした控除を活用すれば、退職金に対する課税額をさらに減らせる可能性があります。
公的年金や年金形式で受け取る場合
退職金を年金形式で受け取る場合は「雑所得」として総合課税の対象になります。このとき、公的年金等以外の所得が年間20万円を超えると確定申告が必要です。また、公的年金等の年間収入が400万円を超える場合も申告義務があります。複数の年金を受け取っている場合は合算して判定されます。
その他のケース
・複数の勤務先から同じ年に退職金を受け取った場合
・前年や過去に退職金を受け取っており控除額の計算が特殊になる場合
・副業や配当など別の所得と組み合わせて課税が生じる場合
これらのケースも確定申告を行わなければ正しい税額計算ができないため注意が必要です。

退職金に関する確定申告は、控除をきちんと使えば納めすぎた税金が戻ってくる大事な手続きです。自分がどのケースに当てはまるのかを確認して、少しでも手取りを多くするように意識してみてくださいね
退職金の受け取り方と控除の影響
退職金は受け取り方によって課税方法が異なり、手取り額や税負担に大きな影響を与えます。老後資金の計画やライフプランを考える上で重要な選択肢となるため、それぞれの特徴を理解しておくことが必要です。
一時金として受け取る場合
退職金を一括で受け取ると「退職所得」として扱われ、退職所得控除が適用されます。控除額を差し引いた残額のさらに1/2だけが課税対象となるため、大きな優遇を受けられるのが特徴です。
メリットとしては、まとまった資金をすぐに確保でき、住宅ローンの完済や事業資金への活用、投資運用に回すといった自由度の高さがあります。一方で、一度に大きな額を受け取るため、計画的に使わなければ生活資金を早く消費してしまうリスクもあります。
年金形式で受け取る場合
退職金を年金として分割で受け取る場合は「雑所得」として総合課税の対象になります。公的年金等控除が適用され、一定額まで非課税となりますが、他の所得と合算されるため、収入次第では税率が上がり負担が大きくなる可能性もあります。
メリットは定期的に収入が得られるため生活費管理がしやすく、資金を長期にわたり安定して使える点です。デメリットは優遇度が一時金に比べて低く、総合課税によりトータルの税負担が増えるケースがあることです。
一時金と年金を組み合わせる場合
企業によっては、一時金と年金を併用して受け取る方法を選べるケースもあります。この場合、一時金部分には退職所得控除が適用され、年金部分には公的年金等控除が使えます。
控除枠を最大限活かすには、一時金を退職所得控除額に収まるように調整し、残りを年金として受け取る戦略が有効です。老後の収入バランスを整えるためにも、組み合わせ型は選択肢として有力です。
受け取り方を選ぶ際のポイント
- 住宅ローンや教育資金など大きな支出が控えている場合は一時金が有利
- 老後の生活費を計画的に確保したいなら年金方式が安定
- 税金面と生活設計を両立したい場合は一時金と年金の組み合わせが最適

退職金の受け取り方は、一時金・年金・併用のどれが正解か一律では言えません。税制優遇の仕組みと自分のライフプランを照らし合わせ、控除を最大限活かす形で選ぶことが、賢い老後資金戦略につながりますよ
今後の制度改正動向と注意点
退職金課税の見直しが議論されている背景
退職所得控除は、長期にわたり勤務した人の老後資金を守るために優遇されてきた制度です。しかし、近年は働き方の多様化や転職の一般化に伴い「長期勤続者だけが有利になる仕組みは公平性に欠けるのではないか」という議論が出ています。特に、短期で複数回転職するケースが増えていることから、現行制度のままでは世代間や労働スタイルによる不公平が広がる懸念が指摘されています。
改正が検討されているポイント
- 勤続年数に応じた控除の縮小
勤続20年以上の加算部分(70万円×超過年数)が過大だとする見方があり、今後は控除額が圧縮される可能性があります。 - 退職金と他の所得の合算課税の検討
現在は分離課税で優遇されていますが、総合課税に近い形に見直される案も過去に議論されています。実現すれば退職金に対する税負担は大きく変化する可能性があります。 - 短期勤続者への課税強化
すでに短期退職手当等は優遇対象外部分がありますが、より厳格なルールへの改正が議論される可能性もあります。 - 復興特別所得税の影響
2037年まで継続される復興特別所得税は退職金にもかかるため、実質的な税負担増につながります。制度が延長されるかどうかも今後の焦点です。
ビジネスパーソンが注意すべき点
- 制度改正は将来の退職金受取額や手取りに直結します。特に転職を視野に入れている方は、改正のタイミング次第で控除額が大きく変わる可能性があるため、常に最新情報を把握しておく必要があります。
- 企業の退職金規程も法改正の影響を受けて見直される場合があるため、在職中に制度を確認しておくことが重要です。
- 税制改正は突然実施されることもあるため、資産形成では退職金だけに依存せず、iDeCoやNISAなど他の老後資金制度との組み合わせを考えておくと安心です。

退職所得控除の制度は今後も見直しの対象になりやすい分野です。控除額の縮小や課税方法の変更が行われると、退職金の手取りが減少するリスクがあります。ですから「退職金は優遇されるもの」と固定的に考えるのではなく、常に最新の制度動向を確認しつつ、老後資金の準備を分散して行っていきましょう
| 順位 | サービス名 | ポイント | 料金 | タイプ | 代行内容 | 支払いタイミング | 支払い方法 | 対応時間 | 対応エリア | LINE対応 | 弁護士の監修 | 書類テンプレート | 追加料金なし | 返金保証 | 転職支援 | LINE公式の自動回答機能 | 分割払い対応 | 対応内容の質 | 料金の安さ | サービスの多さ | 対応時間の長さ | 総合 | 公式 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 | 退職代行トリケシ | 訴訟非対応だが、深夜でも自動チャットで疑問をすぐに解決 | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、モバイル決済、あと払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 2.93 | 5.00 | 5.00 | 3.70 | 退職代行トリケシ 公式サイト | |||||||
| 2位 | リーガルジャパン | 有給取得や書類対応に強み。LINEで簡単に退職手続きが可能 | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成 | 前払い | クレジットカード、銀行振込、モバイル決済 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 2.77 | 2.93 | 4.00 | 5.00 | 3.67 | リーガルジャパン 公式サイト | |||||||
| 3位 | 退職代行モームリ | LINEで完結&低価格。実務に強い信頼の代行サービス | 12,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、Paidy、モームリあと払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 3.77 | 4.00 | 5.00 | 3.99 | 退職代行モームリ 公式サイト | |||||||
| 4位 | 退職代行オイトマ | 交渉が必要なら頼れる一社。後払いで不安を抑えて依頼可能 | 24,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、Paidy | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.88 | 4.00 | 5.00 | 3.19 | 退職代行オイトマ 公式サイト | |||||||
| 5位 | 退職代行ニコイチ | 有給交渉に強いが、サービス範囲の確認は事前に必要 | 27,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込、モバイル決済 | 7:00〜23:30(年中無休) | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.13 | 3.00 | 4.00 | 2.50 | 退職代行ニコイチ 公式サイト | |||||||
| 6位 | 退職代行 | 法的対応が必要な方に最適。費用や連絡手段には注意が必要 | 27,500円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (成功報酬として20%+税が発生) | 4.45 | 1.00 | 1.00 | 5.00 | 2.86 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 7位 | 退職代行ローキ | 弁護士と労働組合のWサポートで、法的にも安心して退職できる | 19,800円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成、未払い給与・残業代の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料あり) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、ローキ分割払い | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 4.52 | 2.93 | 5.00 | 5.00 | 4.36 | 退職代行ローキ 公式サイト | |||||||
| 8位 | 退職代行 | 訴訟にも対応可能。コスパ重視の本格派弁護士サービス | 12,000円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | (未払い給与・未払い退職金の支払い請求、パワハラ慰謝料請求の成功報酬代として、経済的利益の22%(税込※裁判外の請求) | 4.45 | 3.77 | 2.00 | 5.00 | 3.80 | 退職代行 公式サイト | ||||||
| 9位 | 退職代行 | 法的対応も含めてLINEで完了。費用と安心のバランスが秀逸 | 25,000円~ | 弁護士事務所 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成、未払い給与・残業代の請求、慰謝料の請求、損害賠償請求への対応 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 5.00 | 1.63 | 2.50 | 5.00 | 3.53 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 10位 | 辞めるんです | 使いやすいLINE完結型。料金の明瞭さが高評価の理由 | 27,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 1.13 | 3.00 | 5.00 | 3.08 | 辞めるんです 公式サイト | |||||||
| 11位 | 退職代行プラスサービス | 費用は安いが、LINE機能やサポート体制にはやや物足りなさも | 16,280円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 3.33 | 3.00 | 5.00 | 3.30 | 退職代行プラスサービス 公式サイト | |||||||
| 12位 | 退職代行EXIT(イグジット) | 業界初の老舗ブランド。低料金が魅力だが後払いには非対応 | 20,000円~ | 民間業者 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 2.88 | 3.00 | 5.00 | 3.19 | 退職代行EXIT(イグジット) 公式サイト | |||||||
| 13位 | 退職代行サラバ(SARABA) | 費用は安めだが、支払い案内が早く安心感にやや欠ける | 24,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、未払い給与・残業代の請求 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 3.20 | 1.88 | 2.50 | 5.00 | 3.14 | 退職代行サラバ(SARABA) 公式サイト | |||||||
| 14位 | 退職代行Jobs | LINEで完結&後払い対応。気軽に相談しやすい安心設計 | 27,000円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉 | 前払い、後払い(手数料無料) | クレジットカード、銀行振込、コンビニ決済、Paidy | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.88 | 1.13 | 4.00 | 5.00 | 3.00 | 退職代行Jobs 公式サイト | |||||||
| 15位 | 退職代行 | 労組ならではの交渉力。安心して実務を任せられる体制 | 18,700円~ | 労働組合 | 退職意向の伝言、有給取得の交渉、退職書類の作成 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 8:00〜21:00 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 2.77 | 3.08 | 2.00 | 3.00 | 2.71 | 退職代行 公式サイト | |||||||
| 16位 | ネクストステージ | 費用を抑えてLINEで完結。交渉が不要な人に適したサービス | 15,000円~ | 民間業者 | 退職意思の伝言 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.00 | 3.46 | 4.00 | 5.00 | 3.37 | ネクストステージ 公式サイト | |||||||
| 17位 | やめたらええねん | LINE完結で格安。費用重視派におすすめの選択肢 | 16,500円~ | 民間業者 | 退職意思の伝言 | 前払い | クレジットカード、銀行振込 | 24時間 | 47都道府県 | (LINEのみで完結) | 1.00 | 3.31 | 4.00 | 5.00 | 3.33 | やめたらええねん 公式サイト |