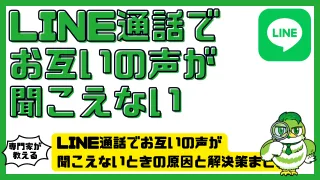本ページはプロモーションが含まれています。
目次
Manusとは?概要と注目される背景
Manus(マヌス)は、中国・北京に拠点を置くスタートアップ「Butterfly Effect」が2026年3月に正式リリースした自律型AIエージェントです。従来のAIチャットボットが「質問に答える」役割にとどまっていたのに対し、Manusはユーザーが設定した目標をもとに情報を収集・整理し、複数のタスクを自ら計画して実行できる点が特徴です。まさに「思考を行動に変えるAI」として注目を集めています。
リリース直後から、中国国内のSNSやテック系メディアで爆発的に話題となり、β版の招待コードが高額で取引されるなど、ユーザーの期待値の高さがうかがえました。その背景には、従来の生成AIに比べてタスク処理能力や外部ツールとの連携が大幅に強化されていることがあります。特に、PCを閉じてもクラウド上で作業を続ける仕組みや、リアルタイムで処理状況を可視化できる機能は、ビジネス利用において大きな利便性をもたらすと評価されています。
さらに、Manusは欧米のAIモデルに頼らず、中国発の独自技術を組み合わせたハイブリッド構成を採用しています。これにより、中国国内のみならず海外市場でも競争力を発揮する可能性があると注目され、AI業界全体に大きな影響を与えつつあります。特に、OpenAIの「DeepResearch」を上回るとされるベンチマーク結果は、多くの専門家からも驚きを持って受け止められました。

Manusは単なる会話AIではなく、ユーザーの「やりたいこと」を自律的に進めて成果に変える力を持っています。だからこそ、中国国内外で一気に注目されているのです
開発企業「Butterfly Effect」の特徴
創業者と技術的背景
Butterfly Effectは2022年に北京で設立されたスタートアップです。創業者の肖弘(シャオ・ホン)氏は、以前にブラウザ拡張型AIアシスタント「Monica」を開発した経験を持ち、そこで培った技術やユーザーインターフェースの知見がManusに継承されています。Monicaは限定的な範囲でユーザーのタスクを補助する仕組みでしたが、その実績が今回の自律型AIエージェント開発の礎となりました。
経営理念と開発方針
共同創業者の季逸超(ジー・イーチャオ)氏が掲げる理念は「思考を行動に変える」というものです。単なるテキスト生成にとどまらず、ユーザーが頭の中で描いたアイデアを実際のアクションにつなげる仕組みを強調しており、Manusの開発全体を貫くコンセプトとなっています。この発想は、AGI(汎用人工知能)を見据えた挑戦としても評価されており、競合AI企業との差別化ポイントです。
小規模ながら国際志向
Butterfly Effectは大手のような潤沢な資金や大規模な開発チームを持つわけではありません。しかし、初期段階から国際市場を視野に入れており、英語や日本語を含む多言語対応を強化。SNSを中心に海外ユーザーへの訴求も積極的に行っています。この国際志向の強さが、リリース直後に世界的な注目を集めた大きな要因といえます。
技術連携とハイブリッドモデル
同社は、自社開発だけに固執せず、AnthropicのClaude 3.5 SonnetやAlibabaのQwenといった外部の先端モデルを積極的に取り入れています。自社のエージェント設計と外部モデルをハイブリッドで統合する柔軟な姿勢により、小規模企業でありながら大規模AI企業に匹敵する性能を実現しています。
成長戦略と市場での位置づけ
Butterfly Effectの戦略は、短期的な大量導入ではなく「実用性の高いAI体験」を提供することに重点を置いています。クラウド基盤での動作やタスクの自律処理といった差別化要素を活かし、ビジネスユーザーや開発者層に信頼を築こうとしています。そのため、投資家やIT導入を検討する企業にとっても「少数精鋭の実力派スタートアップ」という位置づけで認識されています。

Butterfly Effectは小さな会社ですが、理念と技術の両面でユニークな強みを持ち、国際市場で確実に存在感を高めていることがわかります。大企業にない俊敏さと柔軟性を活かして、AI業界でどこまで飛躍できるかが注目ポイントですね
Manusの主要な特徴
自律型マルチエージェントによるタスク処理
Manusは単なる対話型AIではなく、自律的に動作するマルチエージェント構造を備えています。タスクを理解し、計画し、複数のサブAIが役割を分担して実行する仕組みになっており、人間の指示を細かく与えなくても成果物を仕上げることが可能です。例えば、情報収集AI・分析AI・レポート作成AIといった複数のエージェントが同時に動き、調査から成果物の完成までを一貫して行います。
Claude 3.5 SonnetとAlibaba Qwenのハイブリッド構造
コア部分にはAnthropicのClaude 3.5 Sonnetと、中国AlibabaのQwenが採用されています。Claudeの安定した推論能力と、Qwenの柔軟な調整性能を組み合わせることで、複雑な指示にも高い精度で対応できます。この二層構造が、Manusの自律動作を支える大きな強みです。
リアルタイム可視化機能
「Manusのコンピュータ」と呼ばれる専用画面では、AIがタスクを処理する過程をリアルタイムで確認できます。どの情報を収集し、どう分析し、どのように結論へ進んでいるのかを逐次把握できるため、ブラックボックスになりがちなAI処理を透明化しています。必要に応じて途中で介入できるので、人間とAIの協働効率も向上します。
PCを閉じても継続するクラウド実行
クラウド環境で動作するため、ユーザーがPCを閉じてもタスクはバックグラウンドで継続します。長時間を要するデータ分析やスクレイピングなども、オフライン状態のまま完了させ、終了後に結果を受け取ることができます。これは従来のローカル依存型AIツールにはない大きな利点です。
外部ツールとの高度な連携
Manus内部から直接呼び出せるツールは29種類以上あり、ブラウザ操作やExcel自動処理、Python実行、Webスクレイピングなど幅広く対応します。従来は複数のアプリを横断して行う必要があった作業を、Manusひとつで完結できるため、業務効率化に大きく寄与します。
マルチモーダル対応と学習最適化
テキストだけでなく、コード・表・画像といった多様なデータ形式を扱える点も特徴です。さらに利用履歴を学習し、ユーザーの業務フローに合わせて最適化される仕組みを備えています。エラー時には自己修正機能が働き、タスクを中断せず再実行する能力も持っています。

Manusは、人の「思考」を自動で「行動」に変える力を持ったAIです。難しいタスクを複数のAIが協力して処理し、透明性や継続性を確保しながら成果を出せるのが大きな特徴ですね。業務の効率化や新しいプロジェクトの実行を支える実践的なAIエージェントだと理解しておきましょう
外部ツールとの連携と操作性
29種類以上の外部ツールを直接操作
Manusは、クラウド上で稼働する自律型AIエージェントとして、外部ツールを呼び出して直接操作できる仕組みを備えています。現在29種類以上のツールが統合されており、Excelでの表計算やグラフ作成、Webブラウザでの自動操作、ドキュメント編集、さらにはWebスクレイピングまで対応可能です。従来は人間が手作業で行っていた複数アプリ間の切り替えを必要とせず、一つの環境の中でタスクを完結できます。
実務に直結する自動処理
代表的な機能としては、以下が挙げられます。
- ブラウザ操作:検索結果の収集や特定ページからの情報抽出を自動化
- 表計算:Excelやスプレッドシートのデータ入力・分析・グラフ化
- プログラミング:Pythonスクリプトの実行、ライブラリを用いたデータ処理
- スクレイピング:大量のWebデータを短時間で収集し、分析に利用
こうした操作は人間のクリックや入力をシミュレーションするのではなく、APIや専用モジュールを通じて実行されるため、効率性と安定性が高い点が強みです。
操作性とユーザー体験
Manusは、自然言語での指示を基盤にしているため、ユーザーは「売上データを月別にまとめてグラフ化して」と入力するだけで、外部ツールを組み合わせた処理が自動的に実行されます。作業の進行状況はリアルタイムで可視化され、必要に応じて途中で介入も可能です。
また、PCを閉じてもクラウド上で処理が継続するため、時間のかかるデータ分析やレポート作成を任せ、結果だけを後で受け取る使い方が実務に適しています。
導入効果のポイント
- 業務効率化:ルーチン作業の自動化で人間の工数削減
- データ精度の向上:人為的ミスを最小化
- 即時性:大量の情報を短時間で処理し成果物を生成
こうした外部ツールとの連携により、Manusは「一人で複数人分のアシスタント」を持つような実用性を実現しています。

外部ツール連携を使いこなすと、日常業務の自動化だけでなく、情報収集から資料作成まで一気に片付けられるんです。つまり、PCの前にずっと張り付かなくても、Manusが代わりに動いてくれる環境を作れるわけですね
OpenAIモデルとの比較とベンチマーク
GAIAベンチマークでの評価
Manusは、AIアシスタントのタスク遂行力を測る国際的な評価指標「GAIA」において、OpenAIの「DeepResearch」を上回るスコアを記録しています。レベル1の課題ではDeepResearchが74.3%の正解率にとどまる一方、Manusは86.5%を達成しました。さらに難易度が高いレベル3でも、Manusは57.7%を記録し、DeepResearchの47.6%を上回っています。特に複雑な課題を扱う際の堅実な結果が注目されています。
論理推論と外部ツール活用の強み
OpenAIモデルは言語生成や知識検索に優れていますが、Manusは「外部ツールの直接操作」と「自律的な論理推論」を組み合わせる点に強みがあります。29種類以上の外部ツールを呼び出せる仕組みにより、ブラウザ操作・Excel自動処理・Python実行・Webスクレイピングまで一気通貫でこなせます。これにより、単なる会話型AIを超えた「実行主体」としての性能がベンチマークでも評価されています。
OpenAIとの使い分けのポイント
- Manusが得意な分野
・複雑なタスクを細分化して自動完遂する業務プロセス
・長時間かかるデータ収集やWebスクレイピングなどのバックグラウンド処理
・複数ツールを横断して同時進行する業務オートメーション - OpenAIが強みを持つ分野
・幅広い知識に基づいた自然な会話やアイデア発想
・高速で安定した文章生成や翻訳タスク
・安全性や透明性の高いエコシステムでの利用
実務導入を考える上での比較視点
業務効率化を狙うならManusの「タスク自律処理」が効果的です。一方で、対話型インターフェースを中心にナレッジ活用をしたい場合には、OpenAIモデルが安心感を与えます。両者の違いを理解し、目的に応じて併用するのが実務では最適解といえます。

Manusはタスクを“自分で計画して実行する”ところに最大の強みがあります。OpenAIのモデルは会話や知識生成に秀でていますが、Manusは外部ツールを組み合わせた実務遂行力で優位性を発揮します。利用シーンに応じて両者をどう使い分けるかが、これからのAI活用のポイントですよ
料金プランと利用開始方法
料金プランの種類
Manusは、個人利用から企業導入まで幅広く対応できるよう、複数の料金体系を用意しています。基本はクレジット制で、タスクの実行ごとに消費する仕組みです。毎日または毎月付与されるクレジットがあり、不足した場合は追加購入が可能です。
- 無料プラン
月額料金はかからず、毎日300クレジットが自動付与されます。基本機能の利用が可能で、1タスクの同時実行が上限です。まず試してみたい方や軽い作業向けです。 - Basicプラン(月額19ドル/年契約16ドル)
毎月1,900クレジットに加え、毎日300クレジットが付与されます。同時に2つまでタスク実行が可能で、個人の副業や小規模利用に適しています。 - Plusプラン(月額39ドル/年契約33ドル)
毎月3,900クレジットが付与され、Basicよりも多くの作業に対応できます。個人事業主や小規模チームで継続的に使うケースに向いています。 - Proプラン(月額199ドル/年契約166ドル)
毎月19,900クレジットが利用でき、5つのタスクを同時に実行可能です。データ分析やレポート作成を日常的に任せるなど、本格利用に適したプランです。 - Teamプラン(1席あたり月額39ドル/5席以上)
1アカウントに対して19,500クレジットをチーム全体で共有できます。メンバーが複数人で業務を進める企業利用に向けられています。
利用開始方法
Manusは招待制をすでに解除しており、誰でもメールアドレスの登録だけで利用を始められます。
- 公式サイトにアクセス
右上の「Get Started」ボタンをクリックします。 - アカウント登録
メールアドレスを入力し、認証用のリンクを受け取ります。 - 初回ログイン
届いたメールのリンクからアクセスすると、自動で無料プランの利用がスタートします。 - 有料プランへアップグレード
利用量が多い場合や追加機能を使いたい場合は、アカウント設定画面からBasic、Plus、Pro、Teamプランに切り替えが可能です。クレジットの追加購入も同じ画面で行えます。
注意点
料金は為替やシステム負荷に応じて改定される可能性があります。必ず最新の情報を公式ページで確認し、利用目的に合ったプランを選ぶことが大切です。また、クレジット消費の目安を理解しておかないと、想定以上に早く残量がなくなるケースがあるため、タスクの優先度を決めて利用することをおすすめします。

Manusは無料プランでもしっかり試せますが、本格的に業務に使うなら有料プランへの移行が必須です。クレジットの仕組みや同時実行数を理解して、自分の作業量に合ったプランを選ぶことがポイントですよ
代表的な活用事例
旅行プランの自動作成
Manusは旅行の条件(行き先、日数、人数、予算など)を入力するだけで、観光名所の候補リスト、移動手段の最適化、宿泊先の比較まで自律的に調査し、旅程表やハンドブックを自動生成します。人手で行うと数時間かかる作業を短時間で仕上げられるため、旅行会社や個人利用の双方で活用されています。
株価分析と投資レポート
株式市場のリアルタイムデータやSNS上の専門家コメントを収集・整理し、トレンドやリスク要因をまとめたレポートを自動生成できます。従来のリサーチ担当者の作業を補完し、迅速に意思決定できる環境を整えることが可能です。特に短期トレードや急変動市場での情報整理に強みがあります。
企業レポートや資料作成の効率化
経理や経営企画部門では、売上比較や月次レポートを自動で作成し、グラフや図表を組み込んだ形で成果物を完成させられます。人事部門では人員配置や勤怠データを基にした分析資料も短時間で生成でき、社内業務の効率化につながります。
自己紹介サイトやLP制作
「自己紹介サイトを作ってほしい」と入力するだけで、デザイン選定、文章生成、問い合わせフォーム設置、公開までを自律的に実行します。中小企業やフリーランスにとって、専門知識がなくても短期間で高品質なサイトを持てる点が魅力です。
複数タスクの同時並行処理
市場調査・資料作成・データ集計といった複数のタスクを同時並行で進め、完成した成果物を一括で納品できます。プロジェクト単位で依頼すれば、担当者が進行を監視するだけで主要な成果物が揃うため、チームの業務効率を飛躍的に向上させられます。
教育・研修分野での利用
講義スライドや学習用の練習問題をテーマだけ指定して生成し、補足資料や参考文献リストも自動付与できます。学習者一人ひとりのレベルに合わせて教材を調整できるため、教育機関や企業研修でも活用が広がっています。

活用事例を整理すると、Manusは単なる文章生成にとどまらず「人間が手間をかけていた調査・分析・資料化の流れ」を丸ごと自動化できるのが最大の強みです。仕事でも日常生活でも、面倒な作業を任せて成果物を受け取れるのが魅力ですね
利用時の注意点とリスク
誤情報の生成リスク
Manusは高度な自律型AIですが、生成される文章やレポートには誤情報や不正確な内容が含まれる可能性があります。特に数値データや法務関連文書など、正確性が求められる場面では必ず人間のチェックを挟むことが重要です。AIの出力をそのまま鵜呑みにせず、一次情報や信頼できるデータソースと突き合わせて利用する必要があります。
データの取り扱いとプライバシー
Manusに入力した内容はサーバーに送信され、サービス改善のために解析される場合があります。企業の機密情報や個人情報を扱う場合は、情報が保存・学習に利用されるリスクを十分考慮しなければなりません。特に中国発サービスであるため、規制当局からのデータアクセスや越境データ移転に関する懸念も指摘されています。利用時には社外秘データを入力しない運用ルールを徹底することが求められます。
法的リスクとライセンス制約
Manusは外部サイトやツールを自動操作できる機能を持つため、利用者が意図せず著作権や利用規約を侵害してしまうリスクがあります。スクレイピングやデータ取得については、対象サイトの規約を必ず確認し、必要に応じて事前に許可を得ることが必要です。また、生成物自体はユーザーに権利が帰属するとされていますが、サービスを第三者に再配布することは契約上禁止されています。
サービスの安定性と依存リスク
急速に利用者が増えているため、サーバーの負荷による動作不安定や処理遅延が発生する可能性があります。特に業務プロセスを完全にManusに依存した場合、システム障害やサービス終了時に大きな業務リスクとなり得ます。重要タスクはバックアップ手段を用意しておくことが望ましいです。
利用環境における制約
Manusはクラウド上で動作するため、インターネット接続が前提となります。オフライン環境やセキュリティ制約の強い企業環境では導入が難しいケースも考えられます。また、通信が暗号化されているとはいえ、外部クラウドに依存すること自体がリスクと認識する必要があります。

Manusを安心して活用するためには「誤情報を必ず確認する」「機密情報は入力しない」「法的リスクを理解して使う」「依存しすぎない仕組みを作る」ことが大切ですよ