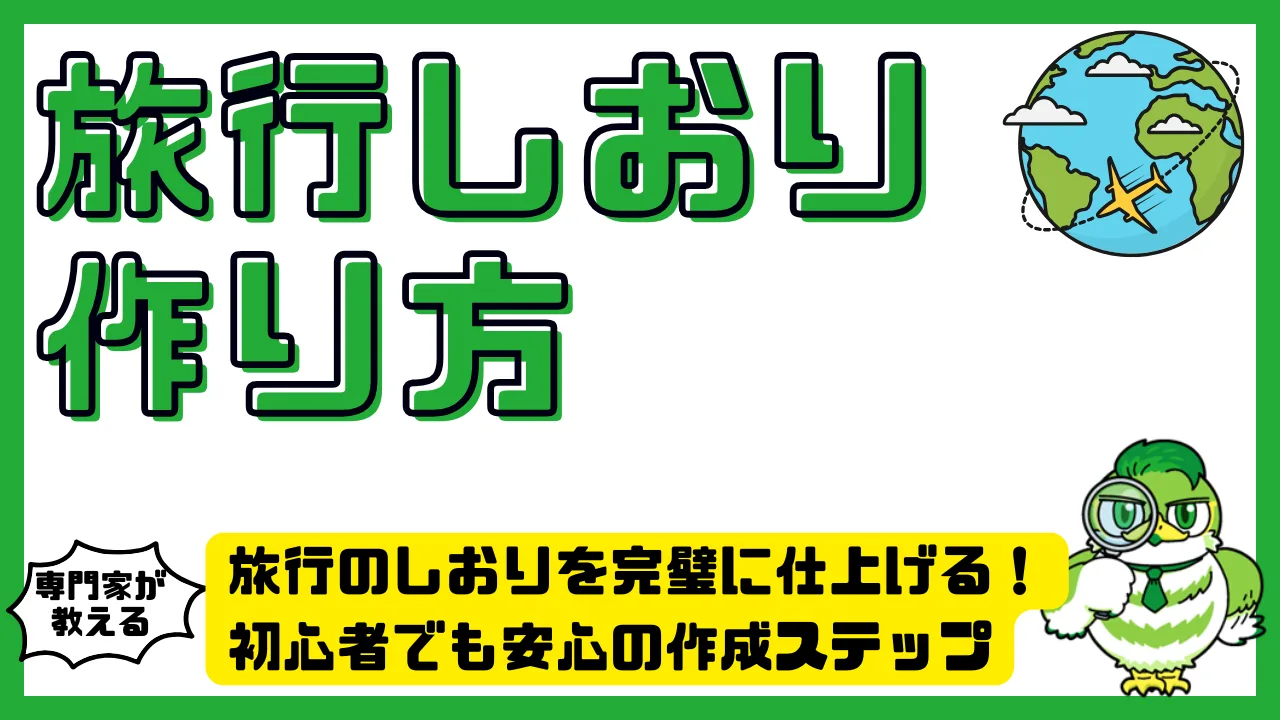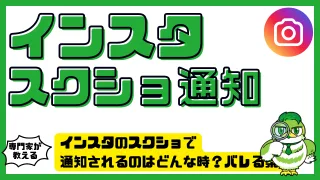本ページはプロモーションが含まれています。
目次
旅行しおりを作る前に確認すべき3つの準備
旅行しおりをスムーズに作るには、土台となる情報を事前に整理しておくことが重要です。情報が不足していると、しおり作成時に手が止まり、非効率になるだけでなく、旅先でのトラブルにもつながります。以下の3つの準備を済ませてから取り掛かるようにしましょう。
旅行の目的と人数を明確にする
まず最初に確認すべきは、旅行の「目的」と「参加人数」です。温泉でゆったりしたいのか、観光地を巡りたいのか、食べ歩きを楽しみたいのかによって、必要な情報やしおりの構成は大きく変わります。
また、参加人数によって共有の方法も変わります。少人数であれば手書きやPDF共有でも十分ですが、10人を超えるような団体旅行ではアプリやクラウドツールでのリアルタイム共有が便利です。
チェック項目:
- 旅行の目的(例:温泉・観光・食・アクティビティ)
- 参加人数とグループ構成(例:家族・友人・職場の同僚)
移動・宿泊の基本情報を整理する
次に大切なのが、移動手段と宿泊施設に関する情報の把握です。これが曖昧だと、スケジュールや集合場所、持ち物などにも影響が出てしまいます。
交通手段(電車・飛行機・レンタカーなど)の時刻や予約状況、宿泊先のチェックイン時間・連絡先・住所などを事前にリスト化しておきましょう。後から調べ直す手間を防げます。
チェック項目:
- 出発・到着の交通手段と時刻
- 宿泊施設の名前・住所・電話番号
- チェックイン/チェックアウトの時間
- 宿泊日数・部屋割り(必要に応じて)
デジタル or 手書き、作成方法を選ぶ
しおりの作成方法も事前に決めておくことで、使うツールやテンプレートをスムーズに選べます。印刷して配布する手書き・紙タイプはアナログでも安心感があり、年配の方にも好まれます。一方、スマホで見られるデジタルしおりは編集や共有が容易で、若い世代との相性が良好です。
それぞれのメリット・デメリットを比較したうえで、自分たちに合った方法を選びましょう。
チェック項目:
- 紙ベースにするかデジタルベースにするか
- 使用予定のツール(例:PowerPoint、Googleドキュメント、旅しおなど)
- 配布方法(印刷/共有リンク/QRコードなど)

これらの準備をしっかり整えることで、後工程のしおり作成が格段にスムーズになります。計画段階から丁寧に進めることで、旅行のクオリティも大きく向上します。
しおりに必ず入れておきたい基本項目一覧
旅行しおりは、参加者全員が同じ情報を共有し、安心して旅行を楽しむための「情報の地図」です。生活に不安を感じている方ほど、情報の整理や共有に悩みやストレスを抱えやすいため、しおりの構成に抜け漏れがないように以下の項目を確実に押さえておきましょう。
旅行日程(スケジュール)
旅行の開始・終了日時、日ごとの行動予定、各移動手段の時間などを、タイムライン形式でまとめます。細かすぎても読みにくくなるため、ポイントとなる時間や行動(出発・到着・チェックイン・自由時間など)を中心に整理します。目安時間を記載しておくことで、焦らず行動できるようになります。
集合場所・集合時間
最もトラブルが起こりやすいのが「集合遅れ」です。集合場所は「○○駅 東口改札前」や「羽田空港第2ターミナル 南ウィング ◯番時計台前」など、誰が読んでも迷わないように明記しましょう。必要に応じて写真付きマップやアクセス方法も併記します。
宿泊施設の情報
宿泊先の名前・住所・電話番号・チェックイン/アウト時間・朝食の有無などを記載します。あらかじめ記載しておくことで、宿までの移動やトラブル時の連絡もスムーズになります。グループ旅行の場合は「部屋割り」を記載すると混乱を防げます。
観光地・食事場所の情報
行き先のスポット名・住所・営業時間・定休日・入場料・見どころを記載しておくと、当日の移動や現地での判断がスムーズになります。おすすめメニューや予約情報があるとさらに安心です。必要に応じて服装やマナーなどの注意事項も添えると、現地での不安が軽減されます。
持ち物チェックリスト
旅行前の準備で最も効果的なのがチェックリスト形式の持ち物リストです。必需品(現金・身分証・薬など)から、天候やアクティビティに応じた持ち物(雨具・水着・登山靴など)まで記載しておくことで、うっかり忘れを防げます。特に心配性な方や初めての場所に行く方にとって、持ち物の見える化は大きな安心につながります。
緊急連絡先と注意事項
万が一の事態に備え、旅行幹事・宿泊施設・交通機関・現地の医療機関などの連絡先をまとめておきます。また、地震や交通トラブル、はぐれた場合の集合場所、体調不良時の対応フローなど、パニックを避けるための「行動指針」も記載すると安心です。
金銭・支払いに関する情報
旅行中に必要な現金の目安(入場料・交通費・食費など)や、カード支払いが可能な場所の情報も記載しておくと、予期せぬ出費への不安を減らせます。割り勘がある場合は、人数と単価をまとめて記載した一覧表やQRコード決済の利用ルールを明記しておくと便利です。
自由時間の提案・おすすめ情報
自由行動がある場合、何をすればよいのか悩む方も多いため、立ち寄りスポットやカフェ、雑貨店などの提案があると安心感につながります。旅行慣れしていない人にとっては、自由行動の時間すら「不安要素」になるため、選択肢を明示しておくことが有効です。

上記の基本項目を網羅したしおりを作成することで、旅行に不安を抱えがちな方でも、安心して旅行に参加し、楽しむ余裕が生まれます。必要な情報を一元化し、誰でも迷わず使える設計が理想です。紙で配る場合でも、デジタルで共有する場合でも、視認性・見やすさを重視しましょう。
テンプレート派におすすめの無料ツール&素材
旅行しおりをゼロから作るのが不安な方や、デザインに自信がない方には、テンプレートやアプリを使った作成方法がおすすめです。ここでは、操作が簡単で実用性の高い無料ツールや、魅力的な素材を提供するサービスを紹介します。
PowerPointの公式テンプレートを活用する
Microsoftの公式サイトでは、旅行しおり向けのテンプレートが無料で提供されています。女子旅、家族旅行、社員旅行など目的に応じたデザインが揃っており、使いたいテンプレートを選ぶだけで、完成イメージがしっかり固まります。
文字の変更や写真の差し替えも直感的にでき、完成度の高いしおりを短時間で作成可能です。PowerPointがインストールされたPC環境がある方に最適です。
Excelの「休暇プランナー」で時系列を整理する
「旅行日程を表形式で整理したい」「メンバーで予定を共有したい」という方には、Excelの「休暇プランナー」テンプレートが便利です。時間帯ごとに予定を入力でき、旅行全体の流れを可視化できます。
出発・到着時間、観光の所要時間などを一覧化できるため、段取りの確認やスケジュールの見直しにも役立ちます。
スマホで簡単に作れる旅のしおりアプリ
tabiori(タビオリ)
スケジュール管理、持ち物チェック、写真共有、チャットなどがひとつにまとまった多機能アプリです。旅行参加者全員でスケジュールを共同編集でき、紙のしおりを印刷することもできます。旅の記録をフォトブックに残す機能も魅力です。
旅しお
インストール不要のWebサービスで、スマホやPCから利用可能です。操作もシンプルで、テンプレートに従って入力するだけでしおりが完成します。LINEやメールでURLを共有するだけで共同編集が可能なので、複数人での計画にも向いています。
Funliday
行きたい場所を検索・登録し、スケジュールにドラッグ&ドロップするだけで旅程表が完成します。地図と連動してルートを自動調整する機能があり、土地勘がないエリアの旅行でも安心して使えます。
しおりす
登録・インストール不要のWebベースツール。シンプルなUIながら、カラーや項目を自由に選べ、PDF出力にも対応。旅行費の割り勘計算サービスとも連携しているため、費用の精算にも便利です。
写真やイラストが使える無料素材サイト
いらすとや
ポップで親しみやすい人物・食べ物・風景などの素材が豊富で、しおりの各ページを楽しく演出できます。
イラストAC
プロ並みのイラストが多数そろい、検索機能も使いやすいです。しおりにテーマ性を持たせたいときに重宝します。
フキダシデザイン
しおりの中にコメントや会話風のメッセージを加えたいときに便利。写真に感想を添える使い方もおすすめです。
TOWN illust
世界各地の建物や観光スポットのイラストが充実。旅行先に合わせて表紙や目次の背景に使えば、しおり全体の世界観が整います。

テンプレートや素材を上手に活用すれば、手間を減らしつつクオリティの高い旅のしおりを作成できます。時間や作業に余裕がない方、制作に不安のある方は、まずこれらのツールから試してみるのが効果的です。
初心者向け:しおり作成の手順とレイアウト設計
旅行のしおりを初めて作成する場合でも、以下の流れに沿えば迷わず完成できます。手間を減らしつつ、参加者全員が安心できるしおりを目指しましょう。
1. 用紙サイズと形式を決める
もっとも扱いやすく、印刷もしやすいのが「A4サイズを二つ折りにしたA5サイズ」。折るだけで冊子風になるため、旅行中の持ち運びにも便利です。複数ページを想定して構成するなら、ページ数が4の倍数になるよう設計すると製本しやすくなります。
2. 目次と全体構成を考える
しおりに入れたい情報をすべて書き出し、優先順位をつけて順番を決めていきます。基本的な構成は次のとおりです。
- 表紙(タイトル・旅行日・行き先・グループ名など)
- 全体スケジュール(1日目〜最終日まで)
- 宿泊施設情報
- 食事・観光予定
- 緊急連絡先・注意事項
- お土産・持ち物リスト
情報が多い場合は、見出しを分けて見やすく整理しましょう。
3. 表紙デザインとタイトルを整える
旅行のテーマや目的地に合わせて、親しみやすい表紙をデザインします。タイトルは「○○旅行しおり」「2026年 夏の北海道旅」など、内容がすぐ伝わるものにしましょう。日付を入れると後から見返すときに思い出しやすくなります。
写真やイラストを配置すると、参加者の気分も盛り上がります。
4. 項目ごとのレイアウトを決める
各ページに入れる情報は、以下のように整えると読みやすくなります。
- スケジュール:時系列順に表形式で整理。移動時間・所要時間・自由行動の有無も明記。
- 宿泊先:住所、連絡先、チェックイン・アウト時間、部屋割り一覧など。
- 緊急連絡:旅行幹事や現地ガイド、病院・警察の番号も記載。
- その他:QRコードやGoogleマップリンクを添えると便利です(スマホ閲覧向け)。
視線がスムーズに流れるよう、余白や見出しを工夫しましょう。読みやすさを優先し、フォントサイズや色使いも抑えめに整えるのがポイントです。
5. 誤字・内容の確認と印刷
内容を一通り入力したら、誤字脱字だけでなく、「時間や場所が正確か」「リンク先が開けるか」などを再チェックします。旅行に同行しない人に見せて確認してもらうのも効果的です。
印刷する場合は、人数+予備を用意しておくと安心です。デジタル版を共有する場合も、PDFにしておくと閲覧性が高まります。
6. 時間がないときはテンプレートも活用
作成に時間をかけられないときは、PowerPointの公式テンプレートや「旅しお」「tabiori」などのツールを利用すれば、デザインやレイアウトの調整が不要です。項目を埋めるだけで実用的なしおりが完成します。

スマホでの共有が前提なら、アプリやWebサービスのほうが手軽で便利です。印刷前提なら、PCでのレイアウト編集ができる形式を選びましょう。
ITを活用した共有と編集のコツ
旅行しおりを複数人で使う場合、最も重要になるのが「情報の共有」と「編集のしやすさ」です。紙媒体だけでは伝達ミスや修正の手間が大きく、特に急な予定変更には対応できません。ここでは、ITツールを活用してストレスなく共有・編集できる方法を紹介します。
Googleドキュメントやスプレッドシートでのリアルタイム編集
GoogleドキュメントやGoogleスプレッドシートは、複数人で同時編集できるのが最大の強みです。以下のような使い方が便利です。
- スケジュールや宿泊先の情報をリスト形式で整理
- 旅行メンバーに「閲覧」または「編集」権限を設定
- コメント機能で意見や変更提案を反映しやすい
- 自動保存・バージョン履歴付きで誤操作しても安心
Googleアカウントさえあればスマホでも編集可能なので、旅先での調整にも対応できます。
LINE Keepやグループトークで手軽に共有
旅行メンバー全員がLINEを利用しているなら、LINE Keepやグループトークも活用できます。
- 完成したしおりPDFをLINE Keepに保存し、誰でも閲覧可能に
- スクショや地図のリンクをグループトークで即時共有
- スケジュールの変更はそのまま通知として伝達可能
LINEは全世代で使いやすく、ITが苦手な方でも導入のハードルが低いためおすすめです。
アプリで完結できる「共有型しおり」ツールを使う
スマホアプリの中には、最初から「共有前提」で設計されているものもあります。
例:
- tabiori(タビオリ):共同編集・チャット・地図連携・写真共有に対応
- 旅しお:URLを送るだけで共同編集が可能。会員登録不要でスマホ・PC両方に対応
- Funliday:予定の入れ替えやルート提案が直感的に操作可能
これらのアプリを使えば、スマホひとつで旅の全計画を把握・更新できます。編集後にすぐ印刷も可能なため、紙とデジタルの両立も簡単です。
オンラインストレージでのファイル共有も便利
PDF形式やPowerPointで作成したしおりを、GoogleドライブやDropboxなどに保存し、共有リンクを送る方法もあります。
- 編集不可にして配布だけしたい場合に最適
- デバイスを問わずアクセス可能
- 容量が大きい画像付きしおりでもスムーズに配布可能
デジタルしおりを使うメリット
- 紛失しない:スマホやクラウドでいつでも閲覧可
- 急な予定変更に強い:その場で修正・反映できる
- 紙の無駄を省ける:環境にも配慮した旅行準備ができる
- 誰でも等しく最新情報にアクセスできる
生活の悩みを抱える人にとって、情報共有のストレスやコミュニケーションの誤解は旅の楽しさを奪う原因になります。だからこそ、誰でも使いやすく、簡単に共有・編集できるITの力をしおり作成に取り入れることが、快適な旅行の第一歩です。
以下は、生活に関して悩みがある方に向けた「旅行のしおりを完璧に仕上げる!初心者でも安心の作成ステップ&おすすめツール」の記事内セクション「ITを活用した共有と編集のコツ」の内容です。
【ITを活用した共有と編集のコツ】
1. しおりの「クラウド保存」で情報を一元管理
スマホやPC、タブレットなど複数の端末でいつでもアクセスできるように、しおりはクラウドで管理するのが基本です。以下のサービスが特におすすめです。
- Google ドライブ+Google ドキュメント
リアルタイム編集が可能で、旅行メンバーごとに閲覧・編集の権限を設定できます。旅行中でも更新が反映されるため、急な予定変更にも対応可能です。 - Dropbox Paper
画像やリンクもドラッグ&ドロップで簡単に挿入でき、コメント機能でやり取りがスムーズです。 - Notion
スケジュール、ToDoリスト、地図リンクなどを統合できるオールインワン型の情報管理ツールです。モバイルアプリでも快適に操作できます。
2. 編集ミスを防ぐための「バージョン管理」
複数人で同時に編集すると内容が混乱しやすくなります。以下の工夫でトラブルを防止できます。
- 変更履歴をオンにする(Google ドキュメント)
編集履歴が自動保存されるため、万が一の誤操作でも過去の状態に復元できます。 - 編集は1人ずつ・時間指定で実施
特定の担当者が「日程表」「持ち物」などの項目を分担して編集すると、混乱を防げます。
3. メンバーとスムーズに連携する共有設定
グループ内のITスキル差を考慮し、共有方法を工夫することが重要です。
- LINEやメールで共有URLを送付
Google ドライブやDropboxなどのURLを送るだけでメンバーは閲覧可能になります。アクセスできない人にはPDF出力して送ると安心です。 - 編集権限と閲覧権限を使い分ける
編集が必要な人だけに権限を与え、残りのメンバーには「閲覧のみ」に設定することで、誤操作を防止できます。
4. スマホで見やすいレイアウトにする工夫
外出先ではPCよりスマホでしおりを見る機会が多くなります。以下の点に注意しましょう。
- 箇条書きや表を使い、1行を短く区切る
視認性が上がり、読みやすくなります。 - 1ページ1情報のレイアウトを意識
「日程表」「宿泊先情報」「連絡先リスト」などをそれぞれ独立したページにまとめることで、必要な情報に素早くアクセスできます。
5. トラブル時のバックアップ対策
ネット環境や端末トラブルに備えて、オフラインでも閲覧できるようにしておくと安心です。
- PDFにしてスマホに保存
万が一通信できない場所でも確認でき、家族や友人に転送しやすいのも利点です。 - 紙に印刷しておく
電源が切れても使える「最後の保険」として効果的です。緊急連絡先や集合場所など最低限の情報を印刷しておくと、いざという時に役立ちます。
ITツールの利便性を活かしつつ、利用者の習熟度や旅行中のシチュエーションに応じて工夫することで、誰もが安心して使えるしおりが完成します。次に読みやすさやトラブル防止の観点から「しおりが原因で起きやすい失敗とその対策」などに進むと、さらに完成度が高まります。ご希望があれば続きも作成可能です。
しおりが原因で起きやすい失敗とその対策
旅行のしおりは便利な反面、内容や使い方によってはトラブルの元にもなり得ます。生活に不安や悩みを抱える方にとって、こうした失敗は旅行そのものの満足度を大きく下げかねません。ここでは代表的な3つの失敗例と、それぞれの具体的な対策を紹介します。
情報の抜けや誤りでスケジュールが狂う
主な原因
- 最新の営業時間や休館日を確認せずに記載
- 曖昧な移動時間や手段を記載
- 食事場所の予約漏れや定休日の見落とし
対策
- 情報源は公式サイトや地図アプリなどで必ず二重確認する
- スケジュールには「余裕時間」をあえて設けて無理のない計画にする
- しおりに「注意書き欄」を設け、天候や混雑などの変動要素を明記しておく
作成者にしか分からないレイアウトで混乱
主な原因
- 専門用語や略称を多用し、参加者が理解できない
- 情報の並び順がバラバラで、読みづらい構成
- 項目ごとの視認性が悪く、必要な情報がすぐに見つからない
対策
- 時系列に沿った見出しとレイアウトで統一感を持たせる
- 誰が読んでも理解できる言葉と説明にする
- 文字サイズや色、アイコンなどで視認性を意識し、特に集合時間や緊急連絡先は大きく強調する
紙しおりの紛失やデジタル頼みで混乱
主な原因
- 紙のしおりを持ち歩く習慣がない人が紛失する
- デジタルしおりに依存し、現地でネットに接続できず閲覧できない
- 共有方法が限定的で、参加者全員がアクセスできない
対策
- 紙とデジタルの併用を前提に作成し、両方を配布・共有する
- デジタル版はオフライン対応可能なPDF形式やアプリを選ぶ
- LINEグループやGoogleドライブなど、複数の共有手段を事前に整備する

些細なしおりのミスが、旅行全体の印象に影響することもあります。初めて幹事を務める方や不安を抱えがちな方でも、事前にこれらの落とし穴を認識し対策しておくことで、旅行の失敗リスクを大きく減らせます。情報を「誰でも使いやすい形」でまとめる意識が、安心で快適な旅の第一歩になります。
旅行後にも役立つ!しおりの保存&活用術
旅行しおりは旅のガイド役だけでなく、旅行後も「思い出」や「情報資産」として活用できます。生活に悩みがある方にとっても、心の整理や人とのつながりに役立つ活用方法を紹介します。
思い出アルバムとして保存する
旅行しおりは写真やレシート、チケットの半券などと一緒に保管することで、旅行の記憶を鮮明に残すことができます。手書きしおりの場合は旅先での感想や気づきを自由記入欄に書き加え、あなただけの旅ログとして残すと、後から見返したときに当時の気持ちを思い出しやすくなります。
写真やコメントを追加してPDF化する
スマホアプリやGoogleドキュメントで作成したしおりは、旅行後に写真やコメントを追記し、PDFとして保存するのがおすすめです。たとえば、観光スポットの感想や旅先で出会った人とのエピソードを加えることで、オリジナルの「旅の記録帳」が完成します。印刷してファイリングすれば、いつでも見返せる紙アルバムにもなります。
SNSやブログでしおりを再活用する
作成したしおりはそのままSNS投稿やブログ記事としても活用できます。旅程、使ったルート、かかった費用、訪問先の感想などを公開することで、同じ場所を訪れる人にとって有益な情報源になります。旅行中に撮った写真を加えて紹介すれば、旅の魅力をよりリアルに伝えることができます。
しおりを次回旅行の計画素材に使う
一度作ったしおりをベースに、次回の旅行計画を効率よく進めることも可能です。行った場所の所要時間や移動手段の実体験を反映すれば、より現実的でムダのない計画を立てることができます。しおりの使い回しは、旅を重ねるたびに計画力が高まる習慣にもなります。
家族や友人と共有し交流のきっかけにする
旅行しおりは、自分だけでなく一緒に行った人とのコミュニケーションツールにもなります。帰宅後に写真やコメントを追加したしおりを共有すれば、旅の振り返りや今後の旅行アイデアを話すきっかけになります。孤独感を感じやすい方でも、共通の体験を通じてつながりを持てる手段として有効です。
アナログ派にもおすすめの保管方法
紙のしおりはクリアファイルやスクラップブックに保存しておくのが便利です。マスキングテープや付箋で思い出を書き加えれば、後から追加編集も可能です。しおりを「生活の記録帳」として活用すれば、旅行だけでなく日常の気づきも大切にできます。

旅のしおりは単なるスケジュール表ではなく、自分自身と向き合う時間や大切な人とのつながりを形にするツールでもあります。旅行後の活用方法を工夫すれば、旅は終わっても楽しみは続きます。